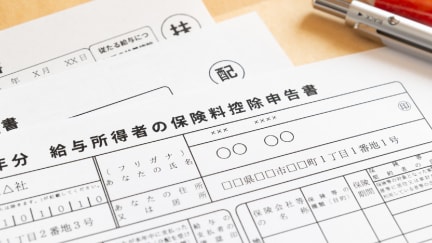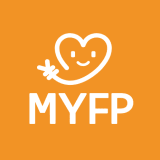新着記事
日本株マーケットアナリストだからこそ個人にお勧めしたい投資法
S&P500とTOPIXを比較
筆者は日本株のマーケットアナリストという仕事をしています。そのため日本市場の見通しや注目銘柄などを解説する機会が多いのですが、今回は、そんな私だからこそお勧めしたい投資法を紹介させてください。
同棲を始める20代カップル。2人で手取り月40万なら家賃や生活費はどのくらい?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、20代のカップル。近々同棲を計画している相談者。彼は家にこだわりたいといいますが、彼女は家賃の負担や生活費を心配しています。適正価格はどのくらいでしょうか? FPの氏家祥美氏がお答えします。
2022年のお金の使い方、節約のプロおすすめのお得情報やお金の見直しポイントは?
改めてやるべきことをチェックしよう
2020年、2021年とコロナウイルスによって、私たちが経験したことがなかった状況におかれました。リモートワークになるなど働き方が変わった人もいれば、収入が大きく左右された人もいます。また収入が変わらないまでもお金の使い方が変わった人も多いのではないでしょうか。2022年、ここで今一度、日頃のお金の使い方を考えてみましょう。
月の支出は13万!節約が苦にならない27歳独身男性「45歳で退職するにはいくら必要?」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、27歳、会社員の独身男性。節約が苦ではなく、毎月13万程度の支出で暮らす相談者。最低限の生活でいいので、45歳くらいで退職してアルバイトなどで暮らしたいと言いますが、どのくらいお金が必要でしょうか? FPの飯田道子氏がお答えします。
最大2万円「マイナポイント」もらってない人も、もらった人も追加でもらえる申請は?「上乗せ」部分も解説
マイナポイント第2弾でもらえるもの
2022年1月1日から「マイナポイント第2弾」がスタートしています。2020年に実施された「マイナポイント第1弾」でもらえたポイントは最大5000円分でしたが、今回は最大2万円分ですから、大きいですね。今回は、マイナポイント第2弾の受け取り方を解説します。第1弾を受け取った方も、まだ受け取っていない方も、ぜひもれなく受け取りましょう。
もしつらいと思ったら、会社員が休養中や退職してもらえるお金、傷病手当や家賃補助どういう申請をすればいい?
もらえる制度を確認しておこう
長い人生、思いがけず身体を壊すこともあります。そんな時には、無理をせずしっかり休養をとるのも一つの選択肢。しかし実際に休むとなると、不安になるのは身体だけではなくお金のことも。日々の生活を安心して送るためには、生活費が確保されていることも大切です。今回は、身体を壊してしまったビジネスパーソンが、勤務先を休んでいる間にもらえるお金や、退職してからもらえるお金についてお伝えします。
食べ応え抜群!具材ゴロゴロ「大根とベーコンのミルクスープ」
朝食にも!
大根とベーコンがゴロゴロ入った、旨味たっぷりのミルクスープのレシピです。食べ応え抜群で、このスープにパンを添えるだけで立派な朝食になりますよ。冷えた身体に染み渡る、寒い日におすすめのひと品です。
50歳で8000万貯めてFIRE目指す30代夫婦「第二子をもうけて住宅を購入しても達成可能?」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、30代半ばのご夫婦。FIREを目指し、運用によって50歳で8,000万円まで増やすことを目標としている相談者。第二子や住宅の購入も希望していますが、現状のプランで達成できるでしょうか? FPの伊藤亮太氏がお答えします。
ゆずの香りと酸味をたっぷり味わう「ゆずと大根の即席漬物」
まるごとゆずを使うレシピ
ゆずを丸ごと使う、大根の漬物レシピを紹介します。ゆずは皮のみを使うレシピが多いですが、今回のレシピではゆずの皮だけでなく果汁まで使い、ゆずの香りと酸味を存分に味わえるひと品です。ゆずを手に入れたらぜひ作ってみてくださいね。
「お金が貯まる夫婦」はどんな夫婦?相手の年収や貯蓄額は知っている?
仲がいい夫婦はお金が貯まる
「お金が貯まる夫婦」とは、どんな夫婦だと思いますか? 年収が高い人? それとも、節約や貯蓄にハマっている人? さて、あなたはどのように考えるでしょうか。今回、アンケート調査結果も参考にしながら、「お金が貯まる夫婦」について考えます。結婚している人も、今後結婚を考えている人も、ぜひご参考にしてみてください。
悩める販売員が最初に覚えたい3つのシーンの接客法
接客で売上を伸ばすには?
声かけすると「はっ」と驚かれる、質問しても「そうですね」とあしらわれる、商品説明しても「ふーん」で終わる……こうしたことに悩む販売員も「接客の進め方」を少し変えるだけで、お客様と楽しくコミュニケーションを取りながら売上をあげられる、と接客アドバイザーの平山枝美さんは語ります。以前はお客様とコミュニケーションを取るのが苦手だった平山さん。「接客、もうしんどい。向いてないかも……」そう思いかけたとき、尊敬していた先輩がアドバイスをくれました。「『自分がどう売りたいか?』じゃなくて、『お客様がなにをしてほしいか?どうしたら喜んでもらえるか?』を考えないと売上も伸びないよ」この言葉が、お客様の状況や気持ちを考えるきっかけになり、接客での行動や言葉づかいを見直すようになったそうです。ここでは、売り場に立ち始めたばかりで不安を感じている人や何年か接客の仕事をしているけれど自信がない人にむけて、販売員が悩みがちな3つのシーンを取り上げました。シーンごとに「嫌がられる接客」と「喜ばれる接客」の違いをイラストで解説し、お客様に押し売りをせず売上を伸ばす方法を紹介します。※本稿は『イラストでひと目でわかる
日本でFIREを実践するには?FIREの問題点「将来の公的年金が減る」を克服した具体的な方法
実現可能な道筋を考える
FIREとは、Financial Independence, Retire Earlyのそれぞれの単語をとったもので、「経済的自立と早期リタイア」のこと。「FIREは資産運用による不労所得を増やすことで経済的に自立し、早期リタイアを目指す人生戦略です。しかし、いざFIREを実現しようとすると、問題点も少なくないことが見えてきます。実はFIREにはいくつか問題があるのですが、今回は「将来の年金が減る問題を軽んじている」「子どもがいると早期リタイアは厳しい」という問題をクリアして実現するFIREについて考えていきます。
毎月赤字気味の39歳会社員「趣味は大切にしたいし仕送りも削れない」どこから改善する?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、39歳独身の会社員の方。住宅ローンを支払い、親への仕送りをしながら暮らしていますが、毎月赤字気味。将来が心配だと言いますが、趣味や楽しみは削りたくないとのこと。どこから支出改善するべきでしょうか? FPの横山光昭氏がお答えします。
今からでも遅くない!「積立投資ではじめる資産運用」 をFPが解説
イベントレポート
2021年11月18~20日、“明日から実践できる、貯める・増やすコツがここにある”をテーマに、オンラインイベント「マネーフォワード Week」が開催されました。「今からでも遅くない!積立投資ではじめる資産運用(協賛:マネックス証券)」をテーマに、株式会社Money&You 取締役でファイナンシャル・プランナーの高山一恵氏が、投資初心者に向けて資産運用の基本的な考え方について講演しました。本記事では、内容を一部抜粋・編集して紹介します。
「再就職しないとダメでしょうか?」夫に内緒で資産運用をする専業主婦の悩み
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、49歳専業主婦の女性。相談者には、会社員時代に貯めた資産があり、運用で利益を出していますが、夫には明かしていません。夫は将来を心配して再就職を促してくるけれど、相談者はもう働きたくないので悩んでいます。再就職する必要はあるのでしょうか? FPの秋山芳生氏がお答えします。
年収103万円のパート主婦がiDeCoの年末調整をした方がいい理由、修正申告方法も
諦めずにチェックしたい節税の可能性
配偶者の扶養内で年収を103万円に抑えて働いている人は多くいます。年収103万円だと、「勤務先に提出する年末調整の書類にiDeCoの掛金を記入しても節税できないから無駄」と思っていませんか?
金額よりも付き合いにこだわりローンや保険を決める夫に悩む妻「協力してお金を貯めたいのに」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、44歳、専業主婦の女性。主に夫が家計を管理していますが、唐突に高額な支出をしたり、金額よりも付き合いにこだわってローンや保険を決めてしまうことに不満を持っているといいます。どうすれば夫と協力して家計を改善できるでしょうか? 家計再生コンサルタントの横山光昭氏が運営する『マイエフピー』のFPがお答えします。
投資家が知るべき2022年のリスク要因、世界や日本で起こりうるシナリオを想定すべし
世界は今年どう動く?
2022年は大発会(最初の取引日)で日経平均が500円以上も上昇しましたが、2日後には800円以上下落するなど、年明け早々に値動きの激しい展開となっています。新しい1年が始まり、今年から投資デビューを考えていた知人はこの相場展開を見て、やはり投資は恐いと言っていました。相場の先行きを正確に予測することはできませんが、2022年に認識しておくべきリスク要因を確認しておきましょう。