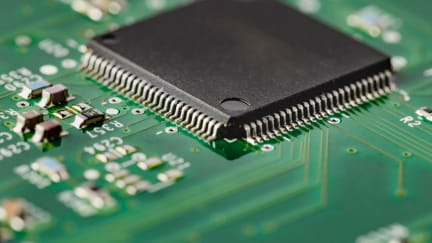新着記事
市場そのものの縮小に、中小企業はどう立ち向かうべきか(後編)
中小企業に適した「市場開拓戦略」の組み立て方
前編では、書籍の包装機器メーカーとしてナンバー1となった株式会社ダイワハイテックス(以下、同社)が、縮小する書店市場を前にどのような策をたて、取り組んでいったのかを解説した。後編の今回はその続きとして、大手包装機メーカーがしのぎを削る激戦区である「通販企業向けの発送システム」市場で、いかにして競争に打ち勝っていったのかを解説する。※本記事の前編はこちら※本記事は『ランチェスター戦略 〈圧倒的に勝つ〉経営』(福永雅文著、以下同書)より一部を抜粋・編集したものです。
2022年改正でますます便利になったiDeCo!3つの改正点と企業型DC加入者がiDeCo併用する場合の注意点
マッチング拠出かiDeCo併用、どっちを選ぶべきか
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、節税しながら老後資金を用意できるお得な制度。税制優遇の恩恵を受けながら、長期積立投資制度ができる制度として「つみたてNISA」とともに、利用者も年々増え続けており、注目されています。2022年の4月・5月・10月とiDeCoの制度が大きく改正され、ますます使いやすくなりました。今回は、iDeCoの3つの改正点と企業型DC加入者がiDeCoを併用する場合の注意点を解説します。
市場そのものの縮小に、中小企業はどう立ち向かうべきか(前編)
ランチェスター戦略の先にある、企業の生存戦略
中小企業向けの生存戦略として知られる「ランチェスター戦略」。「限られた領域における圧倒的なナンバー1の地位を確立する」というものだが、社会や市況の変化により、その領域そのものが縮小・消滅してしまうとなれば、ナンバー1企業と言えどもひとたまりもない。では、そうした企業が生き残るにはどうすればよいのか。本記事では、書籍の包装機器メーカーとしてナンバー1となった株式会社ダイワハイテックス(以下、同社)を事例とし、縮小する書店市場を前にどのような対策をとり生き残りを図ったのかについて解説する。※本記事は『ランチェスター戦略 〈圧倒的に勝つ〉経営』(福永雅文著)より一部を抜粋・編集したものです。
退職する人は必見!任意継続か国保か、保険料が安くなるのはどっち?
任意継続から国保の切り替えが可能に
会社員を辞めてフリーランスになろうと考えている人、または定年退職で仕事を辞める人など、退職してすぐに次の会社に勤めない場合には、重要な手続きが3つあります。まず、「雇用保険の手続き」で、失業給付の申請です。次の仕事が決まっていない場合には、とくに重要です。次に60歳未満の人は「年金の手続き」が必要です。第3号被保険者から、第1号被保険者へ変わります。企業年金も手続きが必要ですので、人事部などに確認してください。最後に、忘れていけないのが、「健康保険の手続き」です。会社の健康保険を継続するか、別の健康保険に入るか、どちらにしても手続きが必要です。2022年1月から少し改正があり、加入する健康保険によってはお得になります。今回は、2022年の改正を含め、退職したときの健康保険の手続きについて説明したいと思います。
トヨタやNTTが出資する新会社、次世代半導体の量産化を発表−−背景にある米国の日本に対する姿勢の変化
米中の技術覇権対立で日本企業に期待すること
政府は11月8日(火)、2022年度第2次補正予算案を閣議決定しました。総合経済対策は「物価高・円安への対応」などを重点分野に掲げ、経費として29兆861億円を確保しました。「物価高騰・賃上げへの取り組み」に7兆8,170億円、「円安を生かした地域の『稼ぐ力』の回復・強化」に3兆4863億円、「『新しい資本主義』の加速」に5兆4,956億円などが含まれています。
夫婦ともに病に倒れ、障害年金が生活費の柱に。娘の教育費や老後資金はどうなる?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、43歳、専業主婦の女性。40歳まで会社員として働いてきたが、病気になり退職することになった相談者。その一年後、夫も病気になり、治療を受けながら就労することに。障害年金等をもらい生活していますが、教育費や老後資金が不安とのこと。FPの黒田尚子氏がお答えします。
超簡単!ほったらかしの「焼き芋風」
炊飯器で美味しくできる!
さつまいもの季節、蒸気が上がった焼き芋は肌寒い季節に体も心もじんわり温まる…そんな魅力あるもの。今までグリルで焼いてみたり、オーブンで焼いてみたり、焼き芋器を使ってみたり。時間をかけるからこそじんわり甘みが引きでて美味しいものになるのだけれど、やっぱり時間がかかったり、作業が必要だったりするもの。家庭によくある調理道具を使って、そんな焼き芋に引けを取らないほど美味しく仕上がる調理法が見つかりました。
シンプルが一番!やさしいおやつ「紅茶のサブレ」
素朴な味。だけど、贅沢な味
「これは美味しいね!」僭越ながら、食べていただいた方に、大抵そう言っていただくこちらのレシピ『紅茶のサブレ』。今どきのたまごや乳は不使用!…ではないのだけれど、昔ながらの、素朴な味。だけど、贅沢な味。茶葉の香りが噛むたびに広がって、バターの香りが焼いてる時から立ち込めて。シンプルなプレーンクッキーももちろんだけど、紅茶を入れてあげると、午後のおやつタイムをちょっぴり優雅な気持ちにさせてくれます。秋の夜長のおやつにもぴったりですよ。「これ、美味しいね!」きっとそう言ってもらえるはず。
ファストリ、SMC、キーエンスに続く企業は?日本の「値がさ株」ランキング
いま「値がさ株」に注目すべき理由とは
株式の値段である株価は、数十円の銘柄から数万円の銘柄まで、企業によりさまざまです。アメリカ株は1株から買うことができますが、日本株は基本的には1単元100株単位での売買をすることになるので、「株価× 100」というのが企業への最低投資額となります。株価の水準が高い株を「値がさ株」といいますが、その値がさ株の動向に注目が集まっています。なぜいま注目されているのか、日本市場の値がさ株ランキングとともにお伝えしていきます。
112万人の資産が目減り…企業型DC、転退職時に放置して起きるデメリットとは?必要な年金の手続きをFPが解説
放置年金があるかの確認方法
転職や退職をする際に、企業型確定拠出年金(企業型DC)を「持ち運び」できることを知らず、放置されている年金資産が2021年度末で約2,600億円に上っているという報道があり、気になっている方もいるのではないでしょうか?そこで今回は、転職の際に必要な企業型DCの移管手続きや、放置されている年金資産があった場合の対処法などをお伝えします。
デジタル庁が立ち上げた、新しい組織の形「DAO」って何? 社長のいない株式会社といわれる理由と問題点
労働のあり方を変化させる可能性も秘めている
日本のデジタル庁は、政府が掲げる「デジタル社会の実現に重点計画」において「ブロックチェーン技術を基盤とするNFT(非代替性トークン)の利用等のWeb3.0の推進に向けた環境整備」が盛り込まれたことを踏まえ、今年10月からWeb3.0研究会を週次で開催しています。今月2日には第5回目となるWeb3.0研究会が開催されました。そのなかで参加者からの提案に基づいて独自のDAO(分散型自律組織)を設立する方針が発表されました。行政の立場として自らDAOに参加することによって、DAOがもつ課題や可能性を認識し、今後の研究会の議論に活かすことが目的とのことです。このニュースはデジタル庁の先進的な取り組みとしてメディアでも紹介されていますが、内容を読んで「DAOってなに?」と思われた方も少なくないでしょう。DAOはDecentralized Autonomous Organizationの略で、その日本語訳である分散型自律組織と聞いてもまったく仕組みがわかりません。そこで今回は新しい組織の形として注目されるDAOについて解説します。DAOとはどのように運営される組織なのでしょうか。また、私たちはどの
シニア人材、Z世代、リモートワーク…2030年に求められるマネジメント力とは?
MBA 2030年の基礎知識(3)
現代のビジネスパーソンにとってITリテラシーが必須となったように、求められるスキルや知識は時代によって変わっていきます。この先の時代に向け、どのようなことを身につけていくべきなのでしょうか?ビジネススクール「グロービス」による著書『MBA 2030年の基礎知識100』(PHP研究所)より、一部を抜粋・編集して2030年に求められる組織と人のマネジメントについて解説します。
PayPayとUber Eatsの組み合わせで50%還元やセブンで20%還元も!11月の注目キャンペーンまとめ
マック、サーティーワン、ドトールも
11月もたくさんのキャンペーンが開催されています。セブン-イレブンやマクドナルドなど日常的に利用するお店のものから、50%と高い還元率のものまでさまざまです。見逃せないお得なキャンペーンを厳選して紹介します。
貯蓄130万円の41歳会社員女性「親族の葬儀や自分に万が一があった場合いくら必要?」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、41歳、会社員の女性。親族の葬儀や自分に万が一のことがあった場合の資金を気にされている相談者。FPが家計状況を確認すると気になる点が…。FPの飯田道子氏がお答えします。
米国経済の最後の砦、労働市場も減速傾向に。それでも米国経済にとってチャンスといえる理由
在宅勤務による労働生産性の低下が懸念
11月4日に発表された米国の雇用統計によれば10月の非農業部門雇用者数は前の月より26万1000人増加しました。19万人強を見込んだ市場予想を上回りました。平均時給は前月比0.4%増と、前月(0.3%増)から伸びが加速しました。市場予想は0.3%増でした。ただし、雇用は強いように見えて、雇用の増加ペースは着実に鈍化しつつあります。26万1000人という増加幅は2021年以降で最小です。
AIができること、人間にしかできない仕事…テクノべート時代の考え方
MBA 2030年の基礎知識(2)
現代のビジネスパーソンにとってITリテラシーが必須となったように、求められるスキルや知識は時代によって変わっていきます。この先の時代に向け、どのようなことを身につけていくべきなのでしょうか?ビジネススクール「グロービス」による著書『MBA 2030年の基礎知識100』(PHP研究所)より、一部を抜粋・編集してテクノべートの時代に変わること・身につけるべきことについて解説します。
課税事業者になるべきか、免税事業者のままか…税理士・小島孝子氏×お笑い芸人・かじがや卓哉氏に聞く「今後取るべきインボイス制度対策」
まずは自分で試算を
個人事業主だけでなく企業の対応も問われるインボイス制度。税理士として企業の顧問や実務家へのセミナーなどを手掛ける小島孝子氏と、お笑い芸人であり税理士として事務所を開業している個人事業主の一面も持つかじがや卓哉氏に、インボイス制度がスタートしたとき、実際に取るべき個人事業主の対応策についてお伺いしました。インボイス制度はなぜ生まれたのか、インボイス制度がスタートしたらどうなるのか、3本連載でお届けします。Vol.1:インボイス制度はなぜ生まれた? どんなひとが影響を受ける? 税理士・小島孝子氏×お笑い芸人・かじがや卓哉氏に聞く2022年以降の消費税の姿Vol.2:インボイス制度によって仕事は減る? 税理士・小島孝子氏×お笑い芸人・かじがや卓哉氏に聞く「インボイスが始まった未来」小島孝子神奈川県生まれ、税理士。ミライコンサル株式会社代表取締役。1999 年早稲田大学社会科学部卒、2019 年青山学院大学会計プロフェッション研究科修了。大学在学中から地元会計事務所に勤務した後、都内税理士法人、大手税理士受験対策校講師、一般経理職に従事したのち2010 年に小島孝子税理士事務所を設立。税務や経
2030年に向けて起こるメガトレンド−−予想される新たな巨大市場とは?
MBA 2030年の基礎知識(1)
現代のビジネスパーソンにとってITリテラシーが必須となったように、求められるスキルや知識は時代によって変わっていきます。この先の時代に向け、どのようなことを身につけていくべきなのでしょうか?ビジネススクール「グロービス」による著書『MBA 2030年の基礎知識100』(PHP研究所)より、一部を抜粋・編集して2030年に向けて起こるメガトレンドについて解説します。