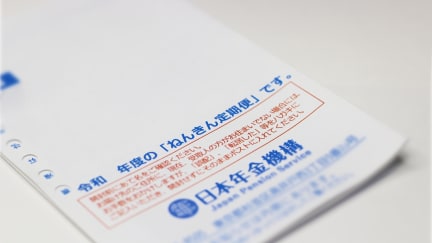「プラチナNISA」は、本当に理想的な高齢期のお金の置き場所なのか? 考えうる3つの問題点
勘違いしやすい「分配金」と「配当金」の違い
金融庁が高齢者向け「プラチナNISA」の創設を検討しています。新NISAでの購入は不適切と烙印が押された「毎月分配型」の投資信託の取り扱いを検討しているようですが、実際そこにメリットはあるのでしょうか? 今回はNISAの取り崩し方法も含め解説していきます。
iDeCoの節税メリットを失う人も。「年収103万円の壁」引き上げによる影響とは
節税メリットがなくなった人はどうすればいい?
激しい議論が交わされた「年収の壁」ですが、とりあえず税金における年収の壁については決着がつきました。次の選挙で議論は引き続き継続されるものと思います。一旦決まったことを整理した上で、現状わかる範囲でiDeCo加入者への影響を考えてみたいと思います。
払った保険料は年金額に関係がない? 改めて知っておきたい厚生年金の基本
今私たちが自己防衛としてするべきこと
2025年4月より、ねんきん定期便には事業主が負担した保険料が明記されることになりました。SNSなどで「年金給付額を多く見せようとするためにわざわざ事業主負担分を記載していないのだ」という批判があったことを受けての対応のようですが、本当にそうなのでしょうか?
NISA、iDeCo、年金…お金の知識はどのように学ぶのがいい?
お金について体系的に学ぶなら
NISAの口座開設数は、2024年9月末時点で約2,508万口座となり、実に国民の5人に1人が口座を保有しています。投資への関心が高まると同時に、お金についてしっかり学びたいという方も増えているように感じます。今回はお金の学びに関するお勧めをお伝えします。
iDeCoの受け取り方で税金は大きく変わる! 税負担を軽減する3つの方法
iDeCoの出口戦略
定年を間近に控えた方の中には、退職金と確定拠出年金を老後資金に充てようとお考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし、確定拠出年金を退職金と同じ年に受け取ると想像以上に税金が課せられ、がっかりすることがあります。「知らなかった」と後悔しないように、「受け取り方による税金の違い」を解説します。
iDeCoで50年間積み立てた場合、税金はどのくらい? シミュレーションで分かる問題点
メリットは大きいが「落とし穴」もある
改正が重ねられるiDeCoですが、加入可能期間のさらなる延長と毎月の掛金上限額の引き上げにより、いよいよ1億円超えの資産形成の可能性も出てきました。しかし、それは同時に受取り時に多額の税金を払うことを示唆しています。今回は、最大限iDeCoを利用した場合の税金を試算してみます。
「iDeCo改悪」への対策はある? 対象者が今からできることとは
これから加入を検討する方へのアドバイス
税の繰り延べ制度であるiDeCoは、受け取り時の税金対策は避けて通れない課題です。特に今回の「iDeCo改悪」の対象となってしまう方は、対策があるのであれば知りたいところでしょう。前回に引き続き、iDeCoの受け取り時の税金について詳しく解説していきます。前回記事:手取りはどれだけ減る? 「iDeCo改悪」によってどのくらい不利益を被るか
手取りはどれだけ減る? 「iDeCo改悪」によってどのくらい不利益を被るか
iDeCoの改悪ポイントとは
「iDeCo改悪」という言葉がどうも一人歩きしているようです。前回の記事で、「それほど大きな問題ではない」と指摘させていただきましたが、それでもやはりデメリットといわれると気になるのが人情です。今回は、「改悪によって」どのくらいの不利益が発生するのかを検証してみたいと思います。前回記事:それほど大きな問題ではない? 「iDeCo改悪」によって影響を受ける人、逆にメリットがある人とは
それほど大きな問題ではない? 「iDeCo改悪」によって影響を受ける人、逆にメリットがある人とは
iDeCoの活用法を改めて考える
令和7年度税制改正大綱が発表になりました。巷では受取り時の退職所得控除のルールが変更される点が「改悪だ!」といわれているiDeCoですが、今回はどんな人にとって改悪なのか、メリットが拡大する人はどんな人なのかを解説していきます。
年末年始にやっておきたい新旧【NISA】の見直し、適切なメンテナンスをする方法
ただ「ほったらかし」にしない
今年も残すところあとわずかとなりました。年末年始は長いお休みを取られる方も多いかも知れませんが、少し時間に余裕がある今だからこそやっておきたい「NISAに関する見直しのポイント」を旧NISAと新NISAに分けてご紹介します。
iDeCoの掛金拠出限度額が20,000円に引き上げ 年収600万円の場合どのくらい節税になる?
掛金増額のメリットとは
2024年12月より、iDeCoの掛金拠出限度額が12,000円から20,000円に引き上げられます。この月々8,000円の拠出額の上限引き上げは年間96,000円の控除額の増となり大きな節税効果が期待できます。今回は、対象となる方、掛金増額のメリットと留意点を解説します。
60歳、貯蓄0円からの老後資産作りは本当に可能なのか。3つのパターンを検証
お金の「三段活用」が必須
60歳代世帯における金融資産保有状況を見ると、3,000万円以上という方が20%以上いる一方で、同程度の割合で資産を保有していないと答えた方もいます。就労収入にも限界があるなか、貯蓄0円からの老後資産作りは本当に可能なのでしょうか?
扶養内を意識して働くひとにはメリットがない? 「103万円の壁」引き上げによる具体的な影響とは
手取りだけでなく、将来を考える
玉木雄一郎氏が率いる国民民主党によって「103万円の壁」が注目されています。働き控えを減らすことを目的のひとつとしていますが、そこには「壁」に対する間違った解釈もあるとも言われています。今回はこの年収の壁と将来設計について解説します。
【NISA】投資信託の運用会社が突然の業務終了…個人投資家はどのような不利益を被る?
信託報酬引き下げ合戦のデメリット
今月11日、PayPayアセットマネジメントが突然業務終了のお知らせを発表しました。NISAのつみたて投資枠でも購入できる投資信託の運用を手がけていた運用会社が業務を終えると個人投資家はどのような不利益を被るのでしょうか?
NISA、iDeCoよりも先にやるべきこととは? お金を増やすための初期設定の方法
デジタル給与払いにみる仕組み化の重要性
キャッシュレス化が進み、日常生活でも現金を扱うことが少なくなりました。利便性が高まる反面、いくら使ったのか分らない、お金の管理が不安との声もあります。今回はお金を増やすための初期設定の仕方と定期チェックについて解説します。
第1号被保険者の場合は手取りが増える? 社会保険の適用拡大により恩恵を受ける人とは
扶養のままでいることは本当にいいことか
2024年10月から、従業員数51人から100人の企業等で働くパートやアルバイトの方たちが一定の条件のもと社会保険に加入するようになります。今回は社会保険加入のメリット・デメリットをパターン別に解説します。
iDeCoや NISA に影響は? 自民党総裁選で話題「金融所得課税を強化すべき」の意味
「1億円の壁」とは
自民党の総裁選において、「金融所得課税」が話題となっているようです。これを受け、ネット上ではiDeCoや NISA にも影響が及ぶのではないかと不安な声も上がっています。今後、iDeCoや NISA で築いた財産も課税されたりするのでしょうか?
人気ファンドでNISAを始めた方にこそ知ってほしい、株価の乱高下に動じないための備えとは
他ファンドとの違いを比較検証することの大切さ
令和のブラックマンデーとも呼ばれるように、8月の株価は大きく乱高下しました。株価の行方が心配で眠れぬ夜を過ごしたという方もいらっしゃるでしょう。しかし、長期運用に株価の変動はつきものですから、今後の心構えとして今回の出来事を学びに変えていきましょう。