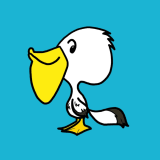検索結果
検索ワード:NISA(検索結果 1296件)
確定拠出年金3.6万人調査:運用満足度を高める要因とは?「長期継続」と「企業規模」から見る好調の背景
DC運用実感と属性の差
制度導入25年目となる本年に実施した「確定拠出年金3万6,000人調査」について、今回からテーマを分けて紹介していきます。最初のテーマは「確定拠出年金(DC)の運用はうまくいっているか?」です。前回記事:「確定拠出年金」を老後資金と見なしていない人は多い?― 3万6,000人調査でわかったDCの現在地
12月相場を読み解く4つの判断軸──アノマリー・税金・損出し・NISAや優待をどう使うか
投資家年末の行動ひとつで、“手取り”も“来年の設計”も変わる!
12月は相場の季節性、税金、損出し、NISAなど、投資判断に関わる要素が重なる特別な月です。本稿では、アノマリーの背景、税制の基本、損益通算や繰越控除の考え方、NISAと優待の位置づけまで、投資家が年末に整理したい4つの判断軸をまとめました。「この一年をどう締めくくるか」を主体的に考える一助になれば幸いです。
投資の割合が増加し、旅行は減少…2025年「冬のボーナスの使い道」は2024年と比べてどう変わった?
節約疲れをした方向けの「自分へのご褒美」のすすめ
そろそろ冬のボーナスシーズンですね。ボーナスを受け取る予定のみなさんは、使い道をもう決めていますか?今回は、この冬みんながどのようにボーナスを活用する予定なのかを、最新のアンケートデータからチェック。2024年のデータと見比べてみると、今年は変化しているポイントが4つありました。最後に注意点もお伝えしていますので、ぜひご覧ください。
年末のNISA運用は「焦り」に注意! 非課税メリットを最大化するためのポイント
焦らず整えて、来年の運用につなげよう
年末が近づくと、「今年のNISA枠が余っている」と焦りを感じる方も多いのではないでしょうか。ですが、ちょっと待ってください。非課税枠を埋めることだけを目的に、慌てて追加投資してしまうと、NISA本来のメリットを十分に活かせない可能性があります。今回は、年末に見落としがちな注意点を整理し、来年以降の運用をより効果的に進めるための方法をお伝えします。
ローン残高は3,300万円 貯めたお金で繰上げ返済か運用か、45歳既婚女性の悩み
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、45歳の既婚女性です。現在、3,300万円残っているローンを繰上げ返済するべきか、せずに運用に回すべきか、老後を見据えたうえで、どちらがよいのか悩んでいらっしゃいます。FPの飯田道子氏と検討してみましょう。
【NISAで一生モノ】株主優待と配当金も! ひと粒で2度おいしい2025年12月の欲張り銘柄3選
配当と株主優待のバランス銘柄
師走を迎え、一年の締めくくりと新たな年への期待が交錯する12月は、投資家にとって"総決算の月"です。今年最後の権利確定月として、優待・配当狙いの買いが集中しやすく、個人投資家の関心が最も高まる時期でもあります。年間の投資成績を振り返りながら、来年に向けた布石を打つには絶好のタイミング。一方、12月は株主優待実施企業が多く、選択肢が豊富なのも魅力です。今回ご紹介するのは、優待と配当の両輪で株主還元を実現する『手放したくない』銘柄です。特に、新NISAの成長投資枠を最大限活用しながら、年末年始を安心して過ごせるポートフォリオを構築するには理想的な3選。2026年に向けた相場展開は不透明ですが、長期保有で確実にリターンを積み上げられる銘柄をぜひチェックしてみてください。
【新NISA長期投資家へ】「売るべきか、売らざるべきか」株高で利益確定していい人の「たった1つの条件」
短期的な目線で高いか低いかを考える必要はない
2025年は日経平均、NYダウ、S&P500、金、ビットコインなどあらゆる資産価格が史上最高値を更新し続け、調整局面はあるものの、以前とマーケットは好調です。日経平均株価5万円を突破し、本稿執筆時点では5万円台を維持しています。しかし、マーケットに暴落はつきものです。株式市場に目を向ければ、2020年以降では、2020年2月「コロナショック」、2022年2月「ウクライナショック」、2024年8月「日本版ブラックマンデー」、2025年4月「トランプショック」と実に4回もありました。歴史的に見て、株式市場がこれだけ高い水準になっているので、「いずれ暴落するのだから、今のうちに利益確定しよう」と考えてしまう人もいるでしょう。今回は、投資で築いた資産の売り時を一緒に考えてみましょう。
「株価が大きく下落してから…」と思っても投資はできない。怖がらずに始める方法
決して割高ではない日本の株価
10月27日、日経平均株価が5万円に乗せました。4月7日、トランプ関税の発表にともなって株価が暴落した時、同平均株価は3万792円という安値をつけています。そこから半年で株価は64%の上昇したことになります。はたして、これから投資を始めるのは正しいことなのでしょうか。
節約につながる!「外食」株主優待5銘柄
食費を浮かして資産も増やす、高利回り優待を賢く選ぶ!
食費負担が増す今、外食優待は値上げの影響を打ち消す家計防衛ツールになり得ます。日常使いできる優待を「節約×資産形成」に活かすメリットや選び方を解説し、「すかいらーく」「コロワイド」など、厳選した外食優待銘柄ベスト5をご紹介。インフレ時代を賢く乗り切る戦略とは?
「確定拠出年金」を老後資金と見なしていない人は多い?― 3万6,000人調査でわかったDCの現在地
老後資金の財源として考えているものとは?
2001年にスタートした確定拠出年金(DC)は、2025年10月で25年目に入りました。2026年以降には、拠出限度額の引き上げやマッチング拠出の規制緩和など、大きな制度改正も控えています。この節目にDC制度の現在地を確認するため、3万6,000人を対象に意識調査を行いました。今回から数回にわたり、その調査で見えてきた「DCのいま」をお伝えしていきます。
2027年の法改正で「iDeCo+」が大きく変わる! 拠出可能額は企業型DC並に
企業型DCは中小企業に広がっていない?
退職金制度の有無は、人材確保において重要な判断材料となり、中小企業でも制度整備を検討する動きが広がっています。しかし、「費用負担が重い」「制度設計が難しい」という理由から導入に踏み切れない企業も少なくありません。今回は、制度改正によりメリットが拡大する「中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)」を、コストを抑えながら導入できる中小企業向けの退職金制度として紹介します。
20年の取材で見えた、お金が貯まる人の共通点「試し上手」とは?
「やってみる」だけでなく「やめてみる」こと
「お金を貯めるには、我慢するしかない」なんて思っていませんか?実は、楽しみながら貯めている人も多くいるのです。せっかくなら、楽しんでいるうちにお金が増えていったらうれしいですよね。そんな人の特徴の一つに、「試し上手」が挙げられます。貯まる人・貯まらない人それぞれに20年取材をしてきた筆者が、貯まる人の中でも、楽しく貯めている人の共通点である「試し上手」のコツについてお伝えします!
1年で消費支出が多くなるのは何月?
年末支出に備え、秋から仕込みたい家計術
秋が深まると街はイルミネーションでにぎわい始めます。ワクワクする反面、「今年の年末年始の家計をどう乗り切ろう…」とドキッとする方も多いのではないでしょうか。今から家計を整えておけば、ゆとりある年越しも夢ではありません。そこで、本コラムでは“秋から仕込む家計術”をご紹介します。
定年目前の57歳独身女性「早期退職して、趣味を仕事にしても大丈夫?」
みんなの家計相談
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、57歳の独身女性です。定年を待たずに早期退職し、趣味を仕事にしたいと考えているようです。果たして今がそのタイミングなのでしょうか。FPの氏家祥美氏と一緒に検討していきます。
積立投資の定番「ドルコスト平均法」は王道か? 非効率か?
二つの視点から自分に合った投資戦略を考える
投資の基本として語られることの多い「ドルコスト平均法」。一定額をコツコツと積み立てるシンプルな手法は、初心者にも始めやすいとされています。一方で「非効率では?」という声もあり、万能な手法ではありません。本稿では、「王道派」と「効率派」という二つの視点から向き・不向きを整理し、自分に合った投資戦略を考えるヒントをお届けします。
SNSやマスコミ情報は疑ったほうがいい。金融リテラシーの前に身につけるべきこと
美味しい話は信じない
iDeCoやNISAなどの非課税措置拡大や、折からの株高の影響を受けて、個人の資産運用熱が高まっています。これから資産運用を始める人を対象にして、金融リテラシーを身に付けてもらうためのコンテンツ制作、ならびにセミナー開催なども盛んです。が、それと同じくらい大事なのが、情報リテラシーを身に付けることです。
株式市場が好調な今、利益確定しなくていい? iDeCoで覚えておきたい「スイッチング」と「配分変更」の活用法
リスクの取り方を見直す良い機会
投資とは不思議なもので、利益が出たら出たで「そろそろ下がるかもしれないのでは」という不安に駆られてしまう方も少なくありません。今回は、iDeCoの運用時に覚えておきたい利益との向き合い方について考えていきたいと思います。
今すぐサイドFIREしたい40代独身女性。節約と投資で築いた安心資産を取り崩しても大丈夫?
みんなの家計相談
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、40代の独身女性です。サイドFIREを希望していますが、果たして実現は可能なのでしょうか?FPの黒田尚子氏と一緒に検討していきます。