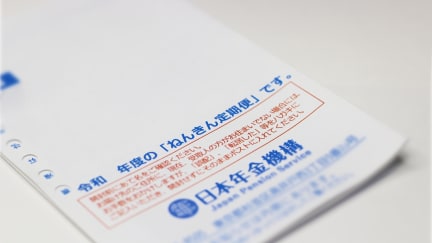検索結果
検索ワード:iDeCo(検索結果 875件)
「プラチナNISA」とは?話題の毎月分配型投資信託とそのリスク
2026年開始検討の非課税投資制度、新NISAと異なる点は?
「プラチナNISA」は2026年開始が検討されており、65歳以上の高齢者を対象とした新たな非課税投資制度です。毎月分配型の投資信託が非課税になる点が特徴ですが、注意すべき点も……。本記事では、制度の詳細からリスク、投資の際のチェックポイントまで、金融アナリストの視点から詳しく解説します。
退職・転職・働き方の変更で年金はどう変わる? 会社員が知っておくべき年金の基本
老後不安を解消するために今からできること
ニュースで年金についての議論が報じられるたびに、「将来、本当に年金はもらえるのだろうか?」と、不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。日本の年金制度は、現役世代が支払った保険料を仕送りのように高齢者などの年金給付に充てる世代と世代の支え合いの考え方で運営されています。老後の不安を解消するために大切なことは、制度を正しく理解し、老後に向けた備えを始めることです。今回は、会社員が知っておくべき年金の基本と将来に備えるためのポイントをファイナンシャルプランナーが解説します。
初任給の使い方は意外と重要! 家計管理の基本「50-30-20ルール」を知っていますか?
初任給の使い道と貯蓄のポイント
新社会人にとって、初任給はこれからの人生設計の第一歩となる大切なお金です。初めての給与をどう使うかによって、将来の家計管理の土台が築かれます。この大切な一歩目で、浪費癖がついてしまうと、改善するのはなかなか難しいものです。自分の収入にあった計画を立て、無駄遣いを防ぎながらも、明るい未来へ繋がる家計管理を目指しましょう。
iDeCoの節税メリットを失う人も。「年収103万円の壁」引き上げによる影響とは
節税メリットがなくなった人はどうすればいい?
激しい議論が交わされた「年収の壁」ですが、とりあえず税金における年収の壁については決着がつきました。次の選挙で議論は引き続き継続されるものと思います。一旦決まったことを整理した上で、現状わかる範囲でiDeCo加入者への影響を考えてみたいと思います。
払った保険料は年金額に関係がない? 改めて知っておきたい厚生年金の基本
今私たちが自己防衛としてするべきこと
2025年4月より、ねんきん定期便には事業主が負担した保険料が明記されることになりました。SNSなどで「年金給付額を多く見せようとするためにわざわざ事業主負担分を記載していないのだ」という批判があったことを受けての対応のようですが、本当にそうなのでしょうか?
NISA、iDeCo、年金…お金の知識はどのように学ぶのがいい?
お金について体系的に学ぶなら
NISAの口座開設数は、2024年9月末時点で約2,508万口座となり、実に国民の5人に1人が口座を保有しています。投資への関心が高まると同時に、お金についてしっかり学びたいという方も増えているように感じます。今回はお金の学びに関するお勧めをお伝えします。
iDeCo以外にある?老後の資産形成の選択肢とそれぞれのメリット・デメリット
FPは何を選ぶ?
税制優遇の恩恵を受けながら、老後の自分年金を作る制度として注目されているiDeCoですが、2024年末に「iDeCo」改悪が話題になりました。iDeCoと退職金を受け取る場合のルールが変更になり、受取時に税負担が重くなるように改悪されました。そこで、iDeCo以外の老後の資産形成の方法に注目が集まっているようです。今回は、iDeCoも含めた老後の資産形成の手段として考えられる商品のメリット・デメリットを一緒に見ていきたいと思います。
iDeCoの受け取り方で税金は大きく変わる! 税負担を軽減する3つの方法
iDeCoの出口戦略
定年を間近に控えた方の中には、退職金と確定拠出年金を老後資金に充てようとお考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし、確定拠出年金を退職金と同じ年に受け取ると想像以上に税金が課せられ、がっかりすることがあります。「知らなかった」と後悔しないように、「受け取り方による税金の違い」を解説します。
「長期・積立・分散」の3本柱が強い理由と資産形成に差をつける“4本目の柱”
長期投資の鍵は「低コスト」
「資産形成」の必要性を感じる方が増えていますね。NISAやiDeCoなどの制度を活用する人も増えた一方で投資を含めた資産形成の難しさを感じたり、資産を増やすために始めたはずが減らしてしまったと悔やんでいる方の声も届きます。では資産形成のための投資を成功させるためには何が必要なのでしょうか?答えは投資の基本原則である「長期・積立・分散」 の三本柱です。この考え方を正しく理解して実践することが安定的に資産を増やすことにつながると言われています。さらに今回はプラスアルファで「低コスト」の考え方も取り入れて、より堅実に資産を構築する方法を考えていきたいと思います。
iDeCoで50年間積み立てた場合、税金はどのくらい? シミュレーションで分かる問題点
メリットは大きいが「落とし穴」もある
改正が重ねられるiDeCoですが、加入可能期間のさらなる延長と毎月の掛金上限額の引き上げにより、いよいよ1億円超えの資産形成の可能性も出てきました。しかし、それは同時に受取り時に多額の税金を払うことを示唆しています。今回は、最大限iDeCoを利用した場合の税金を試算してみます。
【初めての投資】NISAとiDeCoで迷ったら、どっちがいい?
NISAとiDeCoの違いとは
これまで投資を避けてきた人も、世の中でたくさんの情報に触れるようになって「投資をしてみようかな」と考えている人も多いのでは?そんな投資未経験の人からよく聞かれるのが「NISAとiDeCo、どちらを始めるのがいい?」という質問です。あなたはどちらだと思うでしょうか。考え方を一緒に見ていきましょう。
退職所得控除改正で話題の『iDeCo改悪』~影響と対応策を解説~
実際に影響を受ける一部の人々とは…
2025年度税制改正で、確定拠出年金(DC/iDeCo)の一時金受取に関する制度が変更となります。退職金との受取間隔が5年から10年に延長され、SNSでは"iDeCo改悪"と話題に。しかし、実際に影響を受けるのは65歳定年企業に勤める一部の人々に限られます。本記事では、改正の影響と対応策について解説します。
「iDeCo改悪」への対策はある? 対象者が今からできることとは
これから加入を検討する方へのアドバイス
税の繰り延べ制度であるiDeCoは、受け取り時の税金対策は避けて通れない課題です。特に今回の「iDeCo改悪」の対象となってしまう方は、対策があるのであれば知りたいところでしょう。前回に引き続き、iDeCoの受け取り時の税金について詳しく解説していきます。前回記事:手取りはどれだけ減る? 「iDeCo改悪」によってどのくらい不利益を被るか
手取りはどれだけ減る? 「iDeCo改悪」によってどのくらい不利益を被るか
iDeCoの改悪ポイントとは
「iDeCo改悪」という言葉がどうも一人歩きしているようです。前回の記事で、「それほど大きな問題ではない」と指摘させていただきましたが、それでもやはりデメリットといわれると気になるのが人情です。今回は、「改悪によって」どのくらいの不利益が発生するのかを検証してみたいと思います。前回記事:それほど大きな問題ではない? 「iDeCo改悪」によって影響を受ける人、逆にメリットがある人とは
「ねんきん定期便の年金額では暮らしていけない」56歳女性のライフプラン再設計
ねんきん定期便から始める老後資金準備
会社員のAさん(56歳)はねんきん定期便を見て、この年金額では老後の生活費には足りないことに気がつきました。「このままで老後資金は大丈夫なのかを確認したい、何か対策が必要であれば始めたい」とFPである筆者のもとに相談に来られました。
投資信託の運用会社が倒産すると保有ファンドはどうなる?
投信の誤解⑭
投資信託を設定・運用している投資信託会社は本当に倒産しないのでしょうか。NISAやiDeCoなど、税制メリットを受けられる制度が充実し、長期投資を始めてみようと考える人が増えているだけに、この点をしっかり考える必要がありそうです。
社会保険料改定、年末調整、ふるさと納税…2025年下半期の【お金のイベントカレンダー】
子育て世帯の「生命保険料控除」拡充の可能性も
2025年の下半期は家計を整える大切な時期です。年初に立てた貯蓄や家計計画を振り返ったとき、「予定通りに進んでいる!」という方もいれば、「計画からずれてしまった…」という方もいるかもしれません。特に7月以降は、夏休みやシルバーウイークなどイベントが多く、出費が増えがちな時期。先々のことをイメージして、月ごとに使う金額をしっかり予算立てしておくことが重要です。この記事では、後半の家計管理に役立つポイントをわかりやすくまとめました。
「103万円の壁」、iDeCo掛金限度額の引き上げ…2025年上半期の【お金のイベントカレンダー】
税制改正により「103万円」の壁が引き上げられる可能性
2025年は、引き続き物価高が家計を直撃する年になりそうです。2024年の値上げ品目数は1万2520品目と過去3年で最少だったものの、2025年1月からはパックご飯やパン、酒類・飲料など、飲食料品3933品目の値上げが予定されています。物価高の背景には、原材料費の高騰に加え、物流費や人件費の増加があります。一方で、賢く節約や資産形成を進められるチャンスもある年です。2025年上半期には、家計に関するさまざまなイベントや注意点があります。本記事では、上半期のお金に関するポイントをわかりやすくまとめました。家計防衛のヒントとしてぜひご活用ください。