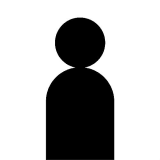はじめに
2025年10月27日、日経平均株価は史上初めて5万円の大台を突破しました。足元の日経平均株価の急上昇を支えていたのは、半導体関連の3銘柄に集中していたことが日経新聞の報道で明らかになっています。ただ、この3銘柄は株価の単価が高い、いわゆる「値がさ株」で、1単位を購入するのに200万~300万円超かかるため、個人投資家には手が出しづらいでしょう。
裏を返せば、この3銘柄をはじめとする日経平均の急上昇を主導してきた半導体関連株を除けば、「まだ株価に上値余地がある銘柄が少なくない」とも考えることができます。そこで注目したいのが、「これから株式相場を牽引する業種やセクターはどこか」という点。ここでは、その牽引役にふさわしい「サナエノミクス」関連の注目3テーマを紹介しましょう。
日経平均高値更新も、“評価不足”の銘柄が続出か
日経新聞によると、日経平均が4万円から4万5000円に上昇した6月27日から9月18日までの期間、ソフトバンクグループ、アドバンテスト、東京エレクトロンの値がさ半導体関連3銘柄の日経平均への寄与度は計51%だったそうです。同様に、4万5000円から5万1000円まで上昇した9月18日から10月29日までの期間では、この3銘柄の寄与度の合計は実に76%まで上昇。要は、この期間の日経平均の上昇の過半が、この3銘柄の上昇に支えられてきたということです。もはや、225銘柄から構成される「日経平均株価」というより、「半導体平均株価」と呼んだほうが適切かもしれません。
半導体関連の株価が今後も上昇を続けるかどうかは、誰にもわかりません。ただ、もし日本株が今後も上昇を続けるとしたら、半導体関連以外の銘柄に上昇余地が残っているといえそうです。それは、日本を代表する企業、トヨタ自動車の株価推移を見ればわかりやすいでしょう。同社の株価は2024年3月に高値3891円を付けていますが、2025年10月28日につけた年初来高値は3221円。この間、日経平均は3万円台半ばから5万円超まで急上昇したにもかかわらず、トヨタの株価はいまだ2024年の高値にさえ届かない水準にとどまっているのです。
確かに、同社の純利益は2024年3月期をピークに減少しましたが、決して業績が悪いわけではなく、2025年度上半期の世界販売台数は526万台と、過去最高を更新しました。トランプ関税の悪影響があったとしても、日経平均が1万円以上も上昇しているのに2024年の高値にさえ遠く届かない水準にとどまっているのは、やはり不自然でしょう。今後も全体相場が暴落することなく上昇を続けるとすれば、大きく株価の水準が引き上がる業種やセクターが出てくることが予想されます。その有力候補は、やはり「国策=サナエノミクス」の追い風を受ける業種・セクターでしょう。
前置きが長くなりましたが、ここから「国策に売りなし」の相場格言に当てはまる、有望相場テーマをチェックしていきましょう。
造船関連の穴株的な銘柄が人気化?
【防衛(+造船)】
有望相場テーマの筆頭といえるのが、石破内閣時代から引き継がれているテーマ「防衛」です。防衛費については、先の岸田政権時に「2027年度に対GDP比2.0%まで引き上げる」目標が定められていましたが、高市首相は、目標達成時期を2年前倒しして、2025年度中に2.0%まで引き上げる方針です。2024年度が1.6%なので、わずか1年で0.4%引き上げられることになります。パーセンテージにすると大きくは見えませんが、日本の2024年度の名目GDPが616兆9095円だったので、0.4%=約2兆5000億円の増額です。決して小規模ではありません。
「防衛関連」といえば、まず三菱重工、川崎重工が浮上します。この2社は、護衛艦や潜水艦、輸送機や哨戒機などを手掛けており、納入金額が突出して大きいのが現状です。ほかにも管制システムや航空機エンジン、弾薬など、さまざまな企業が自衛隊に製品を納入していますが、規模が大きい企業が多く、防衛費の増額が売上高に与える影響はさほど大きくないのが難点かもしれません。また、株式市場では「防衛関連銘柄」として物色され、すでに株価が上昇している銘柄が多いのもポイント。株式投資用語でいう「手あかがついた」状態であるため、上値余地がどれだけあるか判断が難しいところです。
個人的に注目しているのが、防衛関連の中でも「造船」です。造船業は、1990年代には世界シェアの4割近くを占めるなど、日本の主力産業のひとつでした。ところが、2000年代以降は中国と韓国企業に押され、シェアは1割程度まで急減。それにともなって、株価が低迷する企業が続出しました。しかし、足元では政府が「日本の造船業の復活」を掲げ、造船ドックの建設・整備の支援を表明するなど、造船ブームが巻き起こっています。
また、2023年の『防衛生産基盤強化法』の施行によって、防衛省が発注する装備品の想定営業利益率が、8%から15%に引き上げられているのもポイント。要は、海上自衛隊向けに納入する船舶や、船舶に搭載するエンジンや計器、バルブなどの装備品の利益率が上がっているわけです。これまで株価が低迷していた分、船舶関連銘柄の上値余地は大きいと考えられます。すでに株価が大きく上昇している関連銘柄も見受けられますが、今後は銘柄のすそ野が広がり、主要な銘柄以外まで人気化する公算があるでしょう。いわゆる「穴株」狙いがハマるセクターといえそうです。