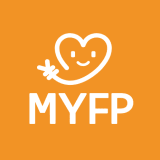新着記事
学資保険が負担で貯められない共働き夫婦。貯蓄残高50万円の理由が未来を左右する
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、2人の子をもつ共働き夫婦の妻(39歳)。子どもの教育費が心配で学資保険を多めにかけていますが、それが負担になって車の購入費が貯まらないそうです。家計に問題はあるのでしょうか? FPの氏家祥美氏がお答えします。 2歳と4歳の子をもつ会社員夫婦(私39歳、夫40歳)です。子どもの教育費が心配で、学資保険に毎月5万と、かなりの額をかけています。また、車の購入資金として600万円貯めたいのですが、なかなか貯まりません。家計を見直したいと思い、7月から固定費を削減し始めたところです。今の家計状況で学費と車代を賄えますか?夫の手取り月収は28~34万円で、夜勤がない今は28万円。10月から再開予定です。【相談者プロフィール】・女性、39歳、会社員、既婚・同居家族について: 夫/40歳、会社員、手取り月収28~34万円(夜勤がない今は28万円。10月から再開予定) 子ども2人/2歳、4歳・住居の形態:持ち家(戸建て)・毎月の世帯の手取り金額:39~44万円・
2022年度に廃止される「年金手帳」、そもそもの役割や持っている手帳はどうなる?今後の対応は
年金手帳廃止の背景
公的年金の加入者に国から配られる年金手帳。年金手帳には、大切な自分の年金に関する情報が記載されているのですが……実は、2022年4月に廃止されることになりました。すでに年金手帳を持っている方は、今後どうなるのでしょうか。また、2022年4月以降に公的年金に加入する方はどうするのでしょうか。今回は、年金手帳廃止の背景と、今後の対応について紹介します。
ジメジメした天気は株価にも影響?湿度と不快指数で秋の株式相場を予測する
秋雨前線に台風…秋晴れにはまだ遠く
秋の長雨の季節になりました。夏の猛暑を引き起こした太平洋高気圧の勢力が弱まる一方、大陸にある冷たい高気圧の勢力が強まって、2つの勢力の境目にできた秋雨前線が日本列島に停滞します。これが秋雨の原因になります。前線が弱まる10月半ばの“秋晴れ“の頃までは、台風の上陸の時期とも重なり”ぐずついた天気“になりがちです。そんな天候と株式市場の間には深い関係があることは、以前から、この連載でも取り上げてきました。「梅雨入りが早いと株式市場は上がる?下がる?統計から見えた意外な結果”」では、梅雨入りが早い年の6月相場は株価が安くなる傾向にあることを紹介しました。梅雨入りが早ければそれだけ、6月は雨模様の天気の日が増えます。 “雨の日には株価が下がりやすい”という統計結果が出ているのです。このような天気と株価の関係は行動経済学という学問で裏付けられています。行動経済学を平たく言うと、人間の行動はその時の気分に左右されるため、株式を買ったりする投資も気分の影響を受けてしまうということです。雨の日には投資家が憂鬱な気分になり株式市場で悲観的な見方が強まるため、株安につながりやすいということです。今回は雨と
住宅価格は上昇しているが、実は賃貸に住んでいる人も得をしている?
今の家賃と住み続けている家賃を比較すると…
現在まで、首都圏のマンションを筆頭に住宅の価格は上昇してきており、数年前に住宅を買った人は、価格上昇の恩恵を受けています。では、持ち家の価格上昇の恩恵を受けていない賃貸派の人は損をしているのでしょうか。
ポン酢にだしを加えてほどよい酸味!「鶏むね肉お浸し」
漬け込むだけでおいしい
さっぱりしたものが食べたいときは市販のポン酢が大活躍します。だしを加えて少し酸味を抑えたおひたしで食べやすい一品です。
ローンを組んでから月7万以上の赤字家計に「教育費や老後資金を貯められる?」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、45歳、専業主婦の女性。住宅ローンを組んでから、全然貯金ができていないことに気づいたという相談者。パートで働くことを考えていますが、そのほかにやるべきことは? 家計再生コンサルタントの横山光昭氏が運営する『マイエフピー』のFPがお答えします。 子どもが2人いる専業主婦です。家計を預かり、今までなんとなくやってきました。最近、相続で受け取った800万円のうち500万円を頭金に入れ、マンションを購入し、住宅ローンを組むことになりました。そこでお金の面をいろいろ見ているうちに、全然、貯金ができていないことに気が付きました。それに気が付くと、このまま住宅ローンを支払いながら、教育費や老後資金などを貯めていけるのか、不安になってしまいました。住宅ローンの支払いが始まってから、収支は赤字だと思います。子どもが幼稚園に入ったら、パートなどに出て家計を助けられたらとは思っているのですが、そのほかやるべきことを知り、家計を黒字に改善できるようにしていきたいです。
初めての相続対策。相続税、生前贈与、遺書…キホンを知って早めの準備を
「争族」にならないように
誰しも、やがては土に還るのが運命だと分かってはいても、近しい家族を失った時の悲しみは、立ち直るまでに相当の時間を要するものです。そんな心模様とは裏腹に、「相続」に必要な各種手続きや「相続税」を納める期限は、思いの他すぐにやってきてしまうのが現実です。そんな負担を少しでも軽減させるため、「終活」という言葉が今では一般的になってきました。2018年7月、およそ40年ぶりに相続に関する法律が大きく改正されました。多くは2019年7月から施行されてます。相続に関する法律は非常に複雑で、自分に当てはまるのがどんなパターンなのか、調べるだけでも一苦労です。「相続」と聞いただけで敬遠されそうな対策のうち、多くの人に関係するであろう主要な項目から、まずは何から始めれば良いか?のポイントを解説していきます。
8割以上がパスワード使いまわし、セキュリティより利便性優先 。 「脱パスワード」で安全確保を
パスワードに頼らないセキュリティ確保
COVID-19パンデミックの影響で、企業も消費者もデジタル化が急速に進み、サイバー攻撃に遭う危険性も高まっています。一方、IBMの調査によると、80%以上がパスワードを使いまわしているなど依然セキュリティ懸念は高いままでした。今後もオンラインサービス利用は続くと考えると、パスワードに頼らないセキュリティ確保への期待が増しています。
「暗号資産はハッキングのリスクが…」という人に知ってほしい、最新の暗号資産ハッキング対策
ポリネットワークとリキッドの事例を解説
暗号資産(仮想通貨)について調べていると「ハッキングにより〇〇億円が流出!」なんてびっくりなニュースを見かけます。実際に2018年には国内の暗号資産取引所が相次いでハッキング被害に遭いました。私たちの日常では考えられないほどの大金がほんの一瞬でインターネットの闇に消えていったわけです。なかなか暗号資産投資に踏み切れない人のなかには、当時のイメージをそのままに暗号資産は危ないと考えている人も多いかと思います。ハッキング事件をきっかけに暗号資産投資をやめてしまった人もいることでしょう。確かに今でも暗号資産のハッキング事件は毎年のように起きています。つい最近も、暗号資産がハッキングによって奪われる事件が発生しました。ところが、攻撃を受けた先の顧客資産のほとんどが犯人の手にわたることなく守られました。なぜ被害を防ぐことができたのでしょうか。今回は8月に起きたポリネットワークとリキッド、2つのサービスに対するハッキング事件をもとに、現在の暗号資産ハッキング対策について解説します。
「楽天経済圏」と「PayPay経済圏」サービスを徹底比較!自分にあったものはどっち?
楽天経済圏 VS PayPay経済圏【第3回】
「楽天経済圏」と「PayPay経済圏」のポイントアップについて解説してきました。第1回 「楽天経済圏」とは?“最新版”ポイントを増やすコツ第2回 「PayPay経済圏」を徹底解説!ポイントを倍増させるには?今回は、それぞれの経済圏の主力サービスも比較することでそれぞれの経済圏の魅力を考えていきます。
60歳自営業。年金は夫婦で年68万、住宅ローン残債2300万。投資か返済どちらを優先?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、60歳・自営業の男性。年金額は70歳から夫婦で年68万円、住宅ローン残債は2,300万円で残り19年という状況の中、老後資金作りのための投資信託購入かローンの繰り上げ返済、どちらを優先すべき? FPの秋山芳生氏がお答えします。 住宅ローンの繰り上げ返済をすべきか、老後の自分年金のための投資信託購入を優先すべきか悩んでおります。子ども3人を、中学から大学まで私立に通わせたのと、仕事の業績悪化などで貯蓄はありませんでした。2年ほど前から業績回復、収入が安定したため、毎月地元信金へ2万円・小規模企業共済に4万円・つみたてNISA夫婦満額、特定口座の株式投資信託を含め計15万円で、合計21万円を毎月貯蓄しております。その他、個人年金が昨年末から入ることになり、終身で5年5%逓増(ていぞう)型で年間、60歳40万円・65歳48万円・70歳58万円……と夫婦でもらえます。この年金は69歳で仕事を辞めるまで普通預金に蓄えておくつもりです。公的年金は、未加入期
ジュニアNISAを始めるべき?養育費が続くか心配なシングルマザーの悩み
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、32歳・シングルマザーの会社員。養育費が続くかなど、将来に金銭的不安のある相談者。子どものためにジュニアNISAを始めるべきか悩んでいます。FPの渡邊裕介氏がお答えします。 シングルマザーです。子どものためにジュニアNISAを始めるべきか悩んでいます。学資保険には加入していません。自分の老後も不安ですが、自分にもしものことがあった時に、ちゃんと子どもにお金が残るかも心配です。養育費ももらっていますが、支払いが滞る可能性もありますし……。また、今は実家で親と同居させてもらっていますが、いずれは家を借りるか買うかして出たいと考えています。今の生活はお金の面では楽な反面、保育園との関係で通勤が大変だったり、子どもが大きくなった時に手狭になりそうなので、考えてしまいます。実家からはなるべく離れたくないので、そうなると家賃相場は(管理費・駐車場込で)2LDKで10万くらいです。※編集部注 相談文は一部割愛させていただきました。【相談者プロフィール】・女性
「PayPay経済圏」を徹底解説!ポイントを倍増させるには?
楽天経済圏 VS PayPay経済圏【第2回】
ソフトバンクグループ傘下のZホールディングスは、主力のYahoo!JAPAN事業に加え、2021年3月に株式交換により8000万人以上が利用するといわれるLINEを完全子会社化しました。そして、Yahoo!JAPANが元々展開していたQRコード決済サービスPayPayの名の元に金融サービスをブランド統合しはじめています。このYahooグループとLINEの金融サービスやポイントプログラムはPayPay経済圏とも呼ばれ注目を集めています。
日本は165か国中何位?世界の2021年SDGs通信簿が公開、16項目の進捗度も
日本の及第点は16項目のうち3項目のみ
国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は8月9日、産業革命前と比べた世界の気温上昇が2021~2040年に1.5度に達するとの予測を公表しました。2018年の報告書で想定した2030~2052年より10年ほど早まりました。IPCCは人間活動の温暖化への影響は「疑う余地がない」と断定。産業革命前は半世紀に1回だった極端な猛暑は、1.5度の気温上昇で9倍、2度で14倍に増えると予測しています。強烈な熱帯低気圧の発生率は1.5度の上昇で1.5倍、農業に被害を及ぼす干ばつの発生率は2倍に拡大する予想です。気候変動リスクをきちんと受け止め、対策を急ぐ必要性が高まっています。10月末からの第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)の議論への注目度が増しています。
「楽天経済圏」とは?“最新版”ポイントを増やすコツ
【第1回】「楽天経済圏 」VS 「PayPay経済圏」を徹底比較
楽天のポイントを活用できるサービス群は「楽天経済圏」と呼ばれ、楽天の提供する銀行やクレジットカード、携帯電話、インターネット通信、証券等様々なサービスを利用することで、SPU(スーパーポイントアッププログラム)という圧倒的にポイントが貯まる仕組みが提供されます。非常にお得なポイントプログラムですが、この1年で楽天経済圏の改悪が縦続いており、「このまま楽天経済圏を利用するかどうか悩む」という声も聞こえてきます。一方でソフトバンクグループ傘下のZホールディングスの金融サービスやポイントプログラムも「PayPay経済圏」とも呼ばれ注目を集めています。圧倒的なポイントの仕組み持つ楽天経済圏か、新た動きをみせるPayPay経済圏か、どちらを使うべきなのか徹底比較していきたいと思います。今回は「楽天経済圏」の解説です。
「無理なく出せるリフォーム代はいくら?」再雇用で働くかどうかで資金に700万の差が!
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、45歳・会社員の女性。夫と中学生の子ども2人と暮らす相談者。リフォームを予定していますが、ローンを組まずに出せる資金はいくらでしょうか? FPの三澤恭子氏がお答えします。 リフォーム費用はどれくらいが妥当な金額でしょうか。45歳・会社員、51歳の夫と、15歳の双子の子どもたちと4人暮らしです。現在、築22年のマンションに住んでいます。2年後くらいにリフォームをしたいと思っています。住宅ローンがまだ残っているため、リフォームローンは考えていません。教育資金や老後資金を考慮すると、我が家が現金で無理なく支出できるのはどれくらいなのか知りたいです。子ども2人は、一人は私立中学・私立高校・私立文系、もう一人は公立中学校・公立高校・国公立大学を予定しています。自宅から通える大学を想定しています。2台保有している車も、10年以上になってきているため、数年のうちに買い替えたいと思っています。【相談者プロフィール】・45歳、会社員、既婚・同居家族について:夫(
日本株の転機は近い?過去の値動きパターンから反転時期を読む
9月に向け重要日柄が集中
新型コロナウイルス感染の拡大に歯止めが掛からないなか、トヨタの9月大幅減産の方針が伝わるなど、頼みの企業業績にも不透明感が浮上しています。海外でもコロナ禍からの経済正常化で先行した欧米や中国などで景気スローダウン懸念が意識される場面が増え、「世界の景気敏感株」とされる日本株への逆風も止みません。一方で、好調な企業業績を背景とした割安感は一段と際立つ状況にあり、日経平均ベースの予想PER(株価収益率)は12倍台、PBR(純資産倍率)も1.1倍台とかなりの悪材料を先行して織り込んだとも見られる水準に低下しています。きっかけ次第で大幅な水準訂正になる可能性も小さくないと考えます。今後9月に向けては、そうした転換を促すかもしれないいくつかの重要日柄が集中します。日経平均株価3万円超えの2月高値から約半年を経過し、株式需給の面でも信用期日絡みのポジション整理が一巡しつつあります。9月後半には自民党総裁選が行われる見通しで、その後の総選挙を見据えた経済対策への期待も高まりやすい時期に当たります。
お受験目指すシングルマザー「月14万の教育費を捻出するために固定費を下げたい」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、35歳・シングルマザーの会社員。子どもの私立小学校入学を目指している相談者。高騰する教育費を捻出するために、他の固定費を下げたいといいます。想定した進路のままで教育資金はもつでしょうか? FPの坂本綾子氏がお答えします。 35歳シングルマザー(会社員/正社員)ですが、子どもをできれば私立小~私立大に入れたいと考えています。教育費を捻出するために他の固定費を下げたいのですが、何から着手すればよいでしょうか。また、老後資金をためるにはどれくらいの額を準備をすればよいでしょうか。子どもはいわゆるお受験対策塾などに通っており、現在教育費が月10万円ほど平均でかかっております(講習があるとさらに上がる時もあります)。現在、年中でその程度なので、来年年長になったら教育費は受験費用など含めて年額200万ほど必要なのではと想定しています。元夫からの援助は養育費月5万円(18歳の誕生日まで)のみです。もし私立に入学できた場合は義務教育の間は私が費用を負担するつも