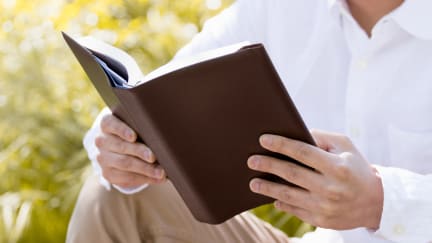検索結果
検索ワード:iDeCo(検索結果 875件)
企業型DC×マッチング拠出とiDeCo、併用するならどちらが有利? 迷わないための4つのポイント
将来の年金資産に差がつく活用法
企業型DCには、資産形成をより進める仕組みとして「マッチング拠出」があります。マッチング拠出の有無は企業ごとに異なります。導入されていない場合や利用しない場合は、iDeCo(個人型確定拠出年金)を併用する選択肢もあります。では、どちらを選ぶのが資産形成において有利なのでしょうか? それぞれの制度の違い、選び方のポイントについて解説します。さらに、2024年12月の制度改正による変更点や、今後の見通しについてもお伝えします。
夫のセミリタイアを叶えたい31歳女性「2人の子育てとマイホームを実現するにはあといくら必要?」
みんなの家計相談
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、第一子が生まれたばかりの31歳の女性。現在、30歳のご主人と共働きだそうですが、ご主人が40歳になるタイミングでセミリタイアを計画中といいます。それでもマイホームは購入できるのかという相談です。FPの氏家祥美氏がお答えします。
金融庁が公表した「プログレスレポート2025」、そこに書かれた個人投資家が見逃せない3つのこと
金融庁の役割とは
金融庁が「プログレスレポート2025」を公表しました。このレポートは、2020年以降毎年発表されるもので、資産運用機関が顧客本位の運用体制をきちんと行っているのかを点検・評価しています。今回はそのレポートから一部抜粋してご紹介します。
確認しないと損することも。住民税決定通知書のチェックポイントと来年に向けた節税アクション
見逃せない重要ポイント
毎年5月から6月にかけて手元に届く「住民税決定通知書」。見慣れない言葉が並び、つい確認を後回しにしてしまう方も多いのではないでしょうか。しかし、この通知書にはご自身の収入や納める税金がどう決まったのかが記されており、家計管理や節税を考える上で大切なヒントが詰まっています。今回の記事では、次の3つのポイントに絞って解説します。住民税決定通知書の基本的な役割と確認すべきポイント来年度の住民税負担を減らすために、今からできる具体的な節税策住民税決定通知書の内容に疑問や誤りなどを見つけた時の対処法住民税決定通知書への理解を深め、家計や将来設計に役立てていきましょう。
個人向け国債、固定5年に100万円分投資したら満期にはいくらになる?
固定5年の個人向け国債が向いている人とは
マイナス金利の解除もあって、このところ金利が上昇している「個人向け国債」に注目が集まっています。元本保証があって、一度購入すればあとは持っているだけで預金よりお金が増やせるとあれば、ぜひ検討してみたいと思いますよね。では、個人向け国債の「固定5年」に100万円分投資したら、利子はいくらもらえて、満期にはいくらになっているのでしょうか。個人向け国債の金利の推移とともに、チェックしてみましょう。
新NISAスタートから一年半、積立設定後はほったらかしのままで大丈夫? NGなパターンとは
資産見直しのポイント
新NISAのスタートからはや一年半。この間、低コストのインデックスファンド「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」(愛称「オルカン」)や「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」に投資し、「長期・積立・分散投資」を実践しはじめた人も多いでしょう。ただ問題は「長期」の部分。2025年の市場は波乱含みの展開で、4月には暴落も経験しました。そのため「積立設定をしてからその後何もしていないけれど、ほったらかしのままでいいのか不安」という声も耳にします。今回は、新NISAスタートから一年半の今こそ考えておきたい資産見直しのポイント・投資先の商品選びのポイントを紹介します。
掛金の大幅引き上げ、70歳まで延長…新しい【iDeCo】はどう変わる?
ますます老後の資産作りで重要になる
年金改正法が成立し、いよいよiDeCoの「新しい形」が現実のものとなりました。掛金は大幅に引き上げられ、加入可能期間も70歳までとなります。とはいえ、資産が大きくなればそれだけ受取時の課税が重くなる可能性もあるので、その活用方法は人によって異なりそうです。2024年末の税制大綱の発表からずいぶんと時間が経過しましたが、6月13日にやっと年金改正法が成立しました。今回の改正について、メディアでは基礎年金の給付水準の底上げや遺族年金制度の変更点に注目が集まっているようですが、確定拠出年金については「大幅な拡大」であり、老後資金専用口座の魅力がさらに高まったともいえる内容です。今回の改正のキーワードは「穴埋め」と「そのまま継続」の二つです。「穴埋め」とは、掛金の上限を企業年金とiDeCoとの合算で管理するということです。ここは少し面倒ではありますが、第二号被保険者にとってはとても重要な意味を持つので詳しくお伝えします。
眠っている資金があったら一時払終身保険を選ぶのはあり? 加入のメリットとは
一時払終身保険の仕組み
保険を使っての資産形成のひとつに一時払終身保険があります。積立利率が低迷する前は、3年間預ければ、元本を超えた解約返戻金が受け取れる商品も存在しました。長く続く低金利で影を潜めていましたが、近年、有効活用できる商品も登場しています。加入のメリットと気をつけることをお伝えします。
早期退職して人生をガラッと変えたい55歳男性「転職すると収入は下がるが、生涯年収は増やしたい」FPの回答は?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、55歳の男性。60歳での定年退職を前に会社の「早期退職制度」を利用し、現在お勤めの製造業を退職し、フリーランスとして、仕事をしていきたいという相談です。FPの岡田真治氏がお答えします。
年収1億円の人の年金はいくらになる?
年金の仕組みを知る
年収1億円という高所得者層は、多くの人にとって成功と豊かさの象徴かもしれません。収入が多い分、税金や社会保険料の負担も小さくないのが現実です。「年収が高く多くの負担をしているのだから、将来受け取れる年金も多いはず」と想像されるのではないでしょうか。しかし、日本の公的年金制度は、必ずしも収入の高さがそのまま将来の年金額に直結するわけではありません。実は、制度には一定の「上限」が設けられており、年収1億円という高所得の方であっても、期待するほどの年金額にはならないケースがほとんどなのです。この記事では、年収1億円の人が将来受け取れる年金額を具体的に考察し、公的年金制度のポイントと、豊かな老後を迎えるための準備について解説します。
楽天証券iDeCoの商品除外を延期に これからとるべき行動は?
対応が不十分だった点とは
楽天証券がiDeCo加入者へ向けて、先日発表した商品除外については延期する旨のメールを発信しました。商品除外の発表から一転して詳細は改めてとのご案内に、戸惑いの声が届いております。この状況を整理し、これからとるべき行動を考えていきましょう。
初期設定のままは要注意! 老後資金に差がつく【企業型DC】の使い方
制度と運用の基本を確認
企業型確定拠出年金(企業型DC)をよくわからないまま続けていませんか? 加入から何年も経っているのに、自分がどんな制度に入っているのか、運用状況はどうなっているのかを把握していない方は多くいらっしゃいます。企業型DCは「自分の老後資金」を左右する大事な仕組みです。本記事では、企業型DC制度の基本から、将来に向けた見直しのヒントまでをわかりやすく解説します。
「トランプ相場」の乱高下にドキッ。投資初心者が手を出さない方がいい投資とは?
初心者が注意すべき投資と取り組むべきこと
「早く資産を増やしたい」 投資を始める際、多くの方が抱く期待ではないでしょうか。特に近年、将来への備えや資産形成への関心が高まる中で、投資の世界に足を踏み入れる方は増えています。しかし、期待先行で始めてしまうと、大切な資産を大きく減らしてしまう可能性が潜んでいます。投資は将来の資産形成において有効な手段となり得ますが、同時に注意すべき点も多く存在します。投資を始めたばかりの方や、これから始めようと考えている方が、特に注意すべき投資について、その理由とともに解説していきます。
投資初心者こそ気をつけたい、株価の暴落時にやってはいけない行動とは?
暴落を経験した今、見直すべきこと
今年から新NISAを始めた人にとって最初の洗礼になった、トランプ政権による株価暴落。自分が積み立てたお金が一気にマイナスになってしまって、投資を続けるべきか迷っている人が多いかもしれません。中には、「やっぱり投資は自分には早かった」と思ってやめてしまう人もいるかもしれません。では、今回のような暴落した時、どのように考えればいいのか、正しい行動は何なのかについて、FPが解説します。
楽天証券でiDeCoを利用している方は要注意! 9本の投資信託が除外でどうなる?
除外された投資信託のパフォーマンスは?
楽天証券は、5月15日に同社のiDeCoラインナップから、9本の投資信託を除外する旨を発表しました。いきなりの発表に、戸惑ったり、驚いたりしている方も少なくないようです。今回は、除外とはなにか、これからどうしたら良いのかなどを解説します。
100万円を倍の200万円に増やすには? 「72の法則」から考える投資戦略
手元資金を2倍に増やすには
今手元に100万円あったら、どうやって増やしますか?貯蓄から投資へと意識が変化しつつある昨今、資産形成は人生における重要なテーマの一つといえるでしょう。今回は100万円を倍の200万円に増やすときに知っておきたい「72の法則」やリスクとリターンの関係性、投資の制度をお伝えします。あなたの投資戦略の参考にしてください。
高配当銘柄が人気? NISAにおける買付の傾向とは
NISA口座開設数の伸びは鈍化しているか
岸田政権時の2022年11月に「資産所得倍増プラン」を公表し、「貯蓄から投資へ」をスローガンに掲げました。「資産所得倍増プラン」は、日本の個人金融資産2000兆円のうち、半分以上が預貯金や現金で保有されている状況を打破するために、個人の貯蓄を投資にシフトすることを奨励する政策です。このプランでは、NISAの拡充やiDeCoの改革を行い、一部の投資に対して税制優遇を実施しています。具体的には2022年から5年間で買い付け額を28兆円から56兆円へと倍増させるとしていました。しかし、2025年2月時点で目標としていた56兆円を超え、当初目標から3年弱も早く達成しています。日本証券業協会が公表したデータによると、NISA制度が始まった2014年からの累計買付額が2024年末に全金融機関で52.7兆円、2025年は3月末までに5兆1405億円の買い付けがありました。
東京証券取引所が株式の最低投資金額を10万円程度に引き下げ
個人投資家への影響と注目点は?
東京証券取引所が株式の最低投資金額を10万円程度に引き下げる方針を発表。これにより個人投資家は少ない資金で投資しやすくなります。政府の「資産所得倍増プラン」とも連動し、若年層や投資初心者の市場参入拡大が期待されます。本記事では、最低投資金額引き下げのメリット・デメリット、個人投資家が注目すべき点を解説します。