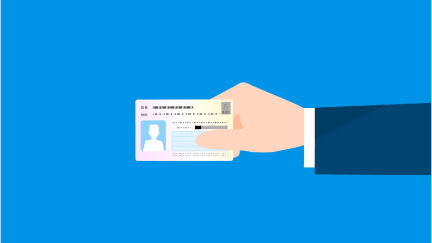新着記事
自分の時間を作りたい40歳会社員。年収を700万から500万に減らしたら年金はいくら減る?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、40歳、会社員の女性。長時間労働がつらく、もっと自分の時間を作れる仕事に転職しようとしている相談者。現在の年収は700万円。年収500万円くらいになった場合、将来の年金はどの程度減るのでしょうか? FPの井内義典氏がお答えします。
歩くだけでお金が稼げる「STEPN」が暴落ーー暗号資産は投機なのか?
Dappsの可能性とリスク
暗号資産は単に値動きを見て売買するだけだ、と思っている方も少なくないでしょう。暗号資産を取引所だけで取引していると、そのような局所的な目になってしまうかもしれません。しかし、実際には「Dapps(Decentralized Applicatiion)」と呼ばれる分散型アプリがブロックチェーン上に数多く作られていて、そのなかで暗号資産は様々な形で活用されています。最近では分散型金融(DeFi)やノンファンジブルトークン(NFT)が注目されるなかで、暗号資産の数が2万以上にまで増えていますが、それとともにDappsの数もまた1万以上に増えています。このように話してもDappsを触ったことがない方が大半だと思います。現状、国内の取引所ではDappsへのアクセスに対応していません。では、私たちはどのようにしてDappsを利用することができるのでしょうか。以下では、運動して稼ぐことができるMove2Earnアプリとして注目されている「ステップン(STEPN)」というDappsを例に、その使い方や注意点について解説していきます。
離婚したら年金はどうなる?配偶者に知られず確認できる「年金記録」で見るべきポイント
50歳からの賢い住宅購入(2)
アラフィフ世代が住宅購入を考える際、ローン返済の資金として年金を考慮に入れることでしょう。そこで、公認会計士でコラムニストの千日太郎 氏の著書『初めて買う人・住み替える人 独身からファミリーまで 50歳からの賢い住宅購入』(同文舘出版)より、一部を抜粋・編集して年金の受給額について解説します。編注:初出時に書名に誤りがありました。
NTT、三菱UFJ、トヨタも…自社株買い、株価への影響と投資家の注意点
高配当企業の株価動向
5月16日に配信した「オリックスにJT、マルハニチロも…株主優待の潮目、廃止増加の背景とは」の記事の中で、株主優待の廃止の代わりに増配や自社株買いを行う企業が増加するとお伝えしましました。株主優待を2024年には廃止するとしたオリックス(8591)も自社株買いと増配を発表した企業の一つです。株主優待の廃止を嫌気し、発表直後の株価は下落しましたが、その後の同社株は堅調に推移しています。今回の決算時において、オリックスに限らず、自社株買いや増配の発表が目立ちました。そこで自社株買いのメリット、デメリットを始め、自社株買いの規模や現在の株価動向を振り返り。また、高配当企業の株価動向などをお伝えしたいと思います。
マイナンバーカードを申請してみた。申請や受け取り、カード利用時の注意点は?
実際にやってみたら
証明写真を撮ったときに、データで写真を受け取った筆者。まだマイナンバーの申請をしていない事を思い出し、WEBから申請をしてみることに。実際にマイナンバーの申請をしてみて、気づいたことやポイントについてまとめます。これからマイナンバーカードを作ろうと考えている方は参考にしてみてください。※市区町村によってはステップが異なる場合があります。
さっぱり!香りを存分に味わえる「ニラぬた」
ちりめんじゃこと一緒に調味料と和えるだけ
旬のお野菜1品を使ったレシピ。一年中お野菜が出回る昨今、こんなお野菜が今は旬なのだということを感じていただければうれしいです。今回は、ニラを使った使い切りレシピを紹介します。「ニラぬた」は、ニラをさっとゆでて、ちりめんじゃこと一緒に調味料と和えるだけ。爽やかな酸味と程よい塩分で、さっぱりと頂けます。炒め物もいいですが、たまにはこんなさっぱりとした食べ方もいいですね。マンネリになりがちなニラの新しい食べ方、試してみませんか?
アラフィフ世代の住宅購入、購入できる家の上限額がわかる計算式とは?
50歳からの賢い住宅購入(1)
定年延長や廃止、再就職など年齢を重ねてからも収入を得る手段が増えたことで、老後を考え40代後半から50代前半のタイミングで家の購入を検討する方もいるでしょう。そこで、公認会計士でコラムニストの千日太郎 氏の著書『初めて買う人・住み替える人 独身からファミリーまで 50歳からの賢い住宅購入』(同文舘出版)より、一部を抜粋・編集してアラフィフ世代の住宅購入について解説します。
扶養「106万円の壁」を超えるとどうなる? 外れて働く意外と大きなメリット
保険料の負担をなくすか、年金を増額か
パートタイマーで社会保険の扶養に入っている人も多いでしょうが、社会保険で近年「106万円の壁」という言葉が登場しています。この「106万円の壁」を超え、厚生年金・健康保険に加入したほうが良いのでしょうか。
43歳主婦、脱サラ夫は経営赤字、愛犬の治療費は年200万円。赤字家計をどう乗り切る?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、43歳、会社員・主婦の女性。夫が昨年企業したものの、赤字で自分の給与も出ない状況のなか、愛犬が病気にかかり、治療費が年間200万円かかることになったといいます。蓄えを切り崩して生活していますが、このピンチを乗り切る知恵は? FPの氏家祥美氏がお答えします。
混ぜて冷やすだけ!ココアパウダーで作る「濃厚チョコプリン」
シンプルな材料で
甘いチョコプリンで一息つきましょう。チョコといっても、材料はココアパウダーと牛乳とお砂糖とゼラチン。それなのに濃厚で口どけのよいプリンが仕上がります。
FXの利益が吹き飛ぶ「ショック相場」を回避する方法、意識すべき相場の転換点とは
2つの代表例から考える
FX取引の典型的な失敗例として、コツコツと積み上げてきた利益が、ある日突然ドカンと消失してしまうケース「コツコツドカン!」(第7回参照)があります。これに陥らないためには、自分が取引している相場の「上がっている理由」「下がるリスク」など、ある程度は理解することが大切です。今回は、どうしたら「ドカン!」を回避できるか、深掘りしていきたいと思います。
個別銘柄選びにも役立つ、日本経済の先行きがいち早くわかる情報ソースとは
足元の景気を知る方法
いま日本の景気がどうなっているのかーーそれは、半歩先読みが必要な株式投資において、とても大事な情報ですよね。私たちが生活をして消費をすることなどが企業の決算につながっているので、今どういったことに人気があるのか、どういった分野が調子が良いのかを知ることができたら、個別銘柄選びにも役立つと思います。今回は景気の先取り、どの分野が活況なのかを早く掴むことができる情報ソースをご紹介します。答えから言いますね。それは内閣府が発表している「景気ウォッチャー調査」です。景気ウォッチャー調査は身近かつ、日本経済の状況を最も早く把握できる敏感な経済指標と言えます。
二郎系と町中華、儲かるのはどっち?ラーメン屋会計士に聞く「商売のからくり」
なぜ生き残っていけるのか
どこの商店街にもある老舗の町中華。行列ができるわけでもなく、グルメサイトのスコアが高いわけでもないのに、もう何十年もそこで営業し続けている。飲食店業界の激しい競争の中で、なぜ生き残っていけるのでしょうか。それは、町中華には町中華ならではの「強み」があるからです。公認会計士・税理士兼「ドラゴンラーメン」(八戸市)店主の石動龍氏が、「業態別・ラーメン屋の儲けのからくり」を解説します。※本稿は『会計の基本と儲け方はラーメン屋が教えてくれる』の一部を再編集しています。
「属性の違い」から考える、ビジネスでSNSを成果につなげるポイント
お金に困らない人が学んでいること(3)
国が副業や兼業の促進に力を入れるなど、いまや「人類総経営者時代」と言っても過言ではありません。そこで、ビジネス書作家・岡崎 かつひろ( @zakihalz )氏の著書『お金に困らない人が学んでいること』(すばる舎)より、一部を抜粋・編集して成果を出すためのマインドを紹介します。
ポイントの使い方で2倍の差も! 失敗しないポイ活の秘訣とは
覚えておきたい還元率と割引率の違い
「ポイント使ってください」これ、もったいないかも。世の中には色んなポイントが存在しますが、同じように1ポイント1円でお買い物に充当できるものでも、その利用価値は大きく異なります。1ポイントが2円の価値に倍増するものや、実は1ポイント1円の価値に満たないものなど。知らないと損する、ポイントとの正しい付き合い方を解説します。
2300万の住宅ローンを組んだ42歳会社員と3000万の奨学金返済がある彼。将来に不安がよぎる
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、42歳、会社員の女性。結婚を考えている37歳の学生の彼との老後の生活に不安があるという相談者。相談者には2,300万円の住宅ローンが、彼には推定3,000万円の奨学金の返済があります。住宅ローンと奨学金を返して老後を乗り切れるでしょうか? FPの三澤恭子氏がお答えします。
マイナンバーってそもそも何?人に知られたらNG?通知カードのままではできないこと
マイナンバーカードでしかできないことは
マイナンバー制度が始まったのは、2015年のこと。日本国内に住民票を持つ人に、12ケタのマイナンバー(=個人番号)がつき、その年の10月から、通知カードが送られてきました。それ以来、年月を経てもなお、マイナンバーとは何なのかいまひとつわからない、という人も多いようです。そのため、マイナンバーカードの申請をしないままにしていることも。今回は、マイナンバーとはそもそも何のための番号なのか、そしてマイナンバーカードの役割、通知カードのままではできないことについてお伝えします。
現場で成果をあげていた多くの営業マンは、なぜ出世すると成果を出せなくなるのか?
お金に困らない人が学んでいること(2)
情報過多の現代社会で、成功している人はどのように知識をインプットしているのでしょうか?そこで、ビジネス書作家・岡崎 かつひろ( @zakihalz )氏の著書『お金に困らない人が学んでいること』(すばる舎)より、一部を抜粋・編集して成果に繋がる「インプット」の技術を紹介します。