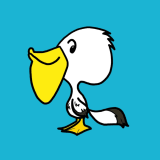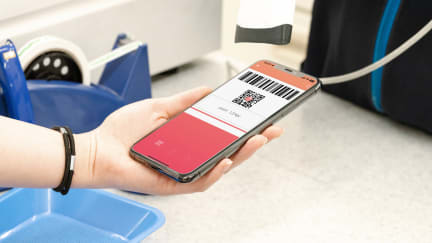新着記事
株主優待と配当金も! ひと粒で2度おいしい11月の【欲張り銘柄】3選
株主優待と配当金のダブル恩恵
もう11月ですね! 季節の変わり目、心地よい風が吹き始めるこの時期は、投資においても新たなチャンスが広がっています。3月決算企業の中間決算発表のピークを迎えるのも11月初旬ということでマーケットは一喜一憂しながらあらゆるニュースを消化していきます。個人的には思わぬ安値で買えるチャンスもあるので買いたい銘柄をしっかりウォッチしておきたいと思っていますさて、本題です。今回も株主優待実施企業が少ない11月ですが、配当金と株主優待のバランスが良い銘柄を3つ紹介させていただきます。
住宅ローン、返済比率20%でも赤字に転落…住宅購入を進める前に知っておくべき予算の立て方
住宅ローン借入可能額の落とし穴
住宅購入を予定しているAさん(39歳)。住宅メーカーへ相談する際、どれくらいの予算を想定すればいいのかを相談しに、ファイナンシャルプランナーの筆者のもとに相談に来られました。住宅ローンの借入額がいくら位までであれば、無理なく返済できるのかが気になっているそうです。Aさんのご家庭の家計状況と今後の対策についてみていきましょう。
11月権利確定の【配当利回り】ランキング、4.5%超えの1位はあの企業
日本の高配当銘柄の配当金を積み立てるスタイルが人気
日本の高配当銘柄を選んで、配当金で安定収入をコツコツ積み立てることを目指して投資するスタイルが投資家から人気です。高配当銘柄への投資は、収益の安定性とリスクの分散を求める投資家にとって魅力的といえます。今回は、2023年11月2日(木)現在のデータをもとに、11月権利確定銘柄の配当利回りトップ5を紹介します(中間配当が11月でも、中間配当が出ていない企業は除いています)。
超PayPay祭でランチタイム10%還元、都内のお寿司30%還元も。11月の注目キャンペーンまとめ
ファミマで10%還元も
超PayPay祭を開催するPayPayを筆頭に、11月もたくさんのキャンペーンが発表されています。中でも注目度の高いキャンペーンを厳選して解説します。
知っておきたい年末調整の仕組み、どのような所得控除が受けられる?
所得控除と税額控除の違いとは
会社員なら、毎年11月に会社から年末調整の用紙が配布されます。年末調整とは一体どのような仕組みなのか知らないまま提出している人も多いのではないでしょうか?今回は年末調整の仕組みと、年末調整で受けられる所得控除の内容について解説します。
コロナで株価が3分の1になったJINS、復活の兆しも気になるのは上場を控える強力なライバル
斜陽産業のメガネ業界、その行方は?
わたしが、株式投資でいちばん最初に手応えを感じたのは、ジンズHD(3046)の売買でした。株式投資をはじめてまもない2012年頃、原宿でJINSの路面店を見かけました。それまでメガネといえば、数万円レベルの高級品で、作るのにも時間がかかるちょっとお堅いイメージの商品でしたが、その原宿の店舗は、Tシャツで若者が接客する非常にカジュアルなものでした。また、フレーム+レンズで2,980円といったとてもリーズナブルな価格で、数時間でメガネができるという手軽さは、メガネ業界の常識を覆すものでした。さらに、それまでは、視力の弱い人だけをターゲットにしていたメガネ業界ですが、JiNSは、パソコンのブルーライトから眼を守る”PCメガネ”という新しいカテゴリーメガネを提案し、視力が弱くない人までもメガネユーザーにしてしまう大革命を起こしたのです。そんな変化を好機ととらえ、ジンズ株を購入し、1年で3倍近くの利益を取ることができました。あのときの興奮は今でもはっきりと覚えています。その後、同様のビジネスモデルが蔓延し、メガネ業界は競争激化で、当社の業績も低迷します。またコロナ禍では、外出控えによる需要の落ち
NISA口座の金融機関変更、どんな人がするべき?
新NISAスタートに向けて早めに行動しよう
2024年から始まる新NISA制度。新しいスタートに備えて今一度自身の資産状況について整理し、考え直したい人もいるのではないでしょうか。今回は、NISA口座の金融機関変更について、どんな人が金融機関変更を検討すべきかや、変更する際の注意点について解説します。
よゐこ有野、お金の専門家の影響で変わったこと「貯金も大事やけど…」
学級委員が授業を総復習
お笑い芸人・よゐこの有野晋哉さんが、毎月さまざまな専門家をゲストに迎えて、お金の知識を身に付けてきた「お金の知りたいを解決!お金の学園〜学級委員・よゐこ有野晋哉〜」。今回で一旦、連載を休載するにあたり、有野さんに今までの授業を振り返ってもらいました。
定年で企業型DCの加入資格を喪失、その後も働くならiDeCoに加入したほうがいい?
60歳からのiDeCo活用法
企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入資格を60歳までとしている会社が多いようです。しかし、60歳以降も働いている場合は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入を検討したいもの。今回は働き方別iDeCoの活用法と受取り方を解説します。
話題の【所得税4万円定額減税】は支離滅裂?首相所信表明演説から読み解く今後の日本経済
将来増税するのであれば本末転倒?
臨時国会が10月20日に召集されました。岸田総理大臣は所信表明演説の中で、今後3年間程度は持続的な賃上げや設備投資を拡大するための政策に集中すると述べました。また国内の経済の現状について、今年のような高い水準の賃上げや設備投資の動きが続くのであれば、「成長型経済」が可能だという考えを話し、経済対策として「供給力の強化」と「国民への還元」の二つを掲げました。「供給力の強化」は企業への賃上げを促す減税制度の強化や、戦略物資への大型の投資減税などを挙げています。注目される「国民への還元」については、税収の増収分の一部を還元できればと考えている、と語りました。
「最寄駅は自転車15分で不便…」マンションを住み替えたい共働き4人一家 教育費との両立は成り立つ?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、38歳、共働き4人家族の女性。中古マンションを購入したけれど、利便性が悪く住み替えを考えていますが、教育費も含めいくら貯めたらいいかわからないと言います。FPの横田健一氏がお答えします。
50代、会社でのゴールが見えてきました。そのときあなたはどうしますか?
定年準備の心構え
50歳前半までは、仕事への意欲も充分あり、バリバリと仕事ができる時期でもあります。そして、役職としても部下を指導する立場になっているのではないかと思います。ところが50代中盤、つまり定年が近づいてくるころには、会社での自分のゴールが見えてきます。つまり、自分はこの会社で「どのくらいのポジション(役職)まで行けるのか」が見えてくるのです。それは会社から見た「自分への評価」でもあります。それが、ハッキリするのが「役職定年」かもしれません。何年後かに訪れる定年時のポジションも、だいたい予想がつきます。ここで役員になれなかったら、あと数年で定年、そして再雇用ということです。再雇用といっても、半数以上の人が70歳まで働く時代なので、もし、あなたが55歳だとすると就労期間は15年以上、平均余命までは28年以上残されています。さて、50代。この会社での自分の先が見えてきました。そのときあなたはどうしますか?
せっかくの投資が残念なことに…【新NISA】でハイリターンを求めて犯しがちなミス6選
自由度が増した分難易度もアップしている点に注意!
投資は、経済的に豊かな未来を形作る一つの手段です。来年から始まる新NISAは現行のNISAに比べて非課税保有期間が無期限となることや、投資可能期間も恒久化するなどメリットが大きく増えました。新NISAを利用して資産を増やし、将来の資金計画を立てようと考えている方も多いのではないでしょうか。今回は、新NISAにおいて初心者がするべきことや、犯しがちなミスについて説明します。
「10%ポイント付与」と「10%割引」はどっちがお得?
ポイントの落とし穴
「これって、どっちがお得なんだろう?」そう思うことはありませんか? ふだん買い物をするうえで、ちょっと気になる、アレとコレのお得度の違い。頭に入れておくと、何かと役立つかもしれません。ぜひチェックしていきましょう!
「ネットへの書き込みが名誉毀損と言われ…」和解金、適正な額は?
訴訟に発展した場合の流れも解説
インターネット上では、SNSや掲示板、ネットニュースのコメント欄など、誰でも自由に自分の意見を書き込める場が増えました。しかし、書き込みの中には「こんなことを書いていいのか?」と、目を疑いたくなるようなコメントも見受けられます。最近は、ダイレクトメール機能を利用して、直接メッセージを送るケースもあります。今回は、インターネット上の書き込みについて、弁護士の観点から解説していきます。
「値上げしない」宣言のサイゼリヤがストップ高! 驚きの好決算の秘密とは
国内事業はお荷物
おもな小売企業の決算がひと通り出揃いました。全体的には、悪くないといった印象ですが、ひときわ好調が目立ったのは、比較的お値段控えめの”庶民の味方”企業でした。ドラッグストアはおおむね全体的に好調でしたし、ユニクロを展開するファーストリテイリングも過去最高益の着地でした。値上げ疲れで節約志向が顕著に見える結果です。そんな中、頑なに値上げを拒んだサイゼリヤ(7581)が、驚きの好決算で注目を集めました。前回の第3四半期決算後に、この連載で取り上げたときは、他社が値上げして、消費者はそれを受け入れつつあるのに、値上げをしないサイゼリヤは大丈夫? 通期予想に対する進捗率もあまりよくなく、予想値未達の心配も、とやや懐疑的な記事でした。まずは2023年8月期の決算を見てみましょう。
ドリンクチケットの特典も。意外と機能が充実している保険会社の健康増進アプリ4選
アプリごとにユニークな特徴
みなさんは、健康に良いことを何かやっていますか?筆者も、スポーツクラブに入会していますが、仕事が忙しくなり、もう何ヶ月も行っていません。それでも月額会費だけは引き落とされていて、なんてもったいないことでしょう…。やはりスポーツなど健康を維持するために、もっとも重要なのは継続することです。今回は、保険会社が提供する健康増進アプリを使って、運動を継続する方法について考えたいと思います(継続が苦手な筆者も一緒に考えます…)。
退職金で資産運用はすべき?老後生活にゆとりをもたらすために知っておくべき3つの注意点
資産寿命を延ばし、人生100年時代を生き抜く
「老後の生活を営むにあたり、これまで形成してきた資産が尽きるまでの期間」を資産寿命といいますが、この言葉をはじめて聞いた方もいらっしゃるかもしれません。長寿化が進む中、いかに資産寿命を延ばすかは、安心して老後を過ごすために考えておきたいことです。退職金での資産運用は、この資産寿命を延ばす考え方に繋がります。今回は、退職金での資産運用について、メリット・デメリットや注意点を解説します。