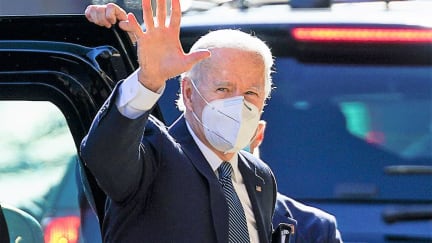むしろコロナ第6波が来なかったら株安?世界で感染拡大でも日本株が下がらなかった理由
株価には企業業績と政策が重要
世界で新型コロナウイルスの感染が再び拡大しています。欧州では感染再拡大を受け、オーストリアで全国的なロックダウン(食料品や薬局などを除いた店舗の営業停止、罰則付きの外出制限)、オランダで飲食店の営業時間短縮、ドイツではワクチン非接種者の店舗立ち入り禁止などが決定されています。米国でも屋内のマスク着用が強く推奨されており、感染の動向次第では行動制限のさらなる強化も想定されます。さらに、11月からはオミクロン型の感染が世界各国で急拡大しています。日本は外国人の入国を基本的に停止していますが、すでに50を超える国で感染が確認されていることから水際対策で長期にわたって流入を防ぐことは困難と見られ、今後国内での感染拡大を想定する必要があります。日本では夏場のデルタ型による感染第5波が収束して以降、感染者数は極めて低水準となっていますが、オミクロン型や次なる変異ウイルスが発生することで第6波が到来する可能性は十分残ります。今回は、感染第6波が来た場合の株式市場への影響について考察します。<文:ファンドマネージャー 山崎慧>
Go To トラベルは年明け再開?予算追加なしでも経済効果は7.1兆円の驚くべき効果
観光産業立て直しへ待ったなし
11月10日、衆参両院の本会議で岸田氏が改めて首相に選出され、第二次岸田内閣が発足しました。岸田首相は同日夜に記者会見を行い、世帯主960万円の所得制限を設けたうえでの18歳以下への10万円給付や、健康保険証や銀行口座との紐づけを条件とした最大2万円相当のマイナポイント付与などに加え、Go To トラベル事業を再開する方針も示しました。一部報道では再開時期は年明けとなる見込みです。今回はこのGo To トラベル事業が今後の日本経済に与える効果について考察してみます。<文:ファンドマネージャー 山崎慧>
米国の債務上限問題って何?法案が成立しても一安心…とはならない基本的メカニズムを解説
過去の事例と市場の動きを分析
10月7日、米国政府債務の上限を短期的に引き上げることで与野党が合意し、法案成立が見込まれます。しかし、これで問題が解決したわけではありません。このままでは数ヵ月後に同じ事態に陥ることになります。今回は、株価にも影響を与える米国の債務上限問題について解説します。<文:ファンドマネージャー 山崎慧>
宿泊・飲食産業はもうもたない…内部留保はほぼ枯渇、財務面から見る業界の深刻度
終わりの見えない自粛が日本の文化を蝕む
新型コロナウイルスの日本の新規感染者、重症者はこのところ減少傾向にあります。一方、9月12日に期限を迎える緊急事態宣言は感染者数の「高止まり」を理由に9月30日まで延長される見込みです。2021年は緊急事態宣言のみならず、まん延防止等重点措置のもとで営業時間短縮に加え酒類提供も過料の罰則付きで命令されており、特に東京都では緊急事態宣言とまん延防止等重点措置のいずれも発出されていなかった期間は年初と3月から4月にかけてのわずか3週間ほどとなっています。経済再開に積極的な姿勢を示していた菅首相は自民党総裁選の立候補を見送っており、次期首相の方針によっては緊急事態宣言のさらなる延長や冬場にかけての再発出の可能性も十分想定されます。<文:ファンドマネージャー 山崎慧>
デルタ型の猛威で中国「ゼロコロナ戦略」に暗雲、日本株に及ぶ中国リスクとは
日本株への逆風続く
新型コロナウイルスのデルタ型の感染が世界的に広がっています。ワクチン接種で先行する米国や英国では、感染者数は増加しているものの死者数の増加ペースが抑制されていることから、行動制限を緩める動きが続いています。ワクチン接種数が1億回を超え、接種完了率が40%に近づきつつある日本でも、感染の拡大と比較して死者の増加は抑えられています。一方、ワクチン接種が遅れているその他のアジア諸国では感染、死者ともに増加傾向が続いています。これまでアジアでは感染者、死者ともに欧米対比で低い状況が続いていました。しかし今局面では、直近で世界の新規感染者のおよそ2割、死者の3割ほどをアジアが占めるに至っています。こうした中、フィリピンではこれまでで最も厳格なロックダウンが実施されている他、マレーシアやタイなどでもロックダウンが強化されています。コロナの封じ込めを目指してきたオーストラリアでもロックダウンが繰り返されていますが、政権の方針は徐々にワクチン接種の加速へと転換されてきています。<文:ファンドマネージャー 山崎慧>
米国の景気・金融政策は転換点だが株高は続く?データから読む“有望な投資先”
ISM製造業指数、金融政策、株価の関係を検証
新型コロナウイルスの新規感染者数は国内では再拡大が懸念されていますが、世界全体でみると鈍化の傾向にあり、変異株の動向を注視しつつ各地で経済再開の動きが進んでいます。特に米国では世界に先駆けて景気が回復し、代表的な企業景況感であるISM製造業指数は3月に64.7まで上昇しました。これは実に1983年以来の高水準です。ただ、その後のISM製造業指数は5月61.2、6月60.6と、横ばい圏での推移となっています。その他の経済指標も高止まりはしているものの、さらなる加速は見込みにくい状況です。<文:ファンドマネージャー 山崎慧>
10代以下のコロナ死者数0人なのに自殺者数は24年ぶり水準に急増、若者世代の負担を考える
すり減る日本社会の持続性
4月23日に発出された緊急事態宣言は、6月20日までまたも延長されました。その前の緊急事態宣言は1月8日から3月21日、4月5日からはまん延防止等重点措置がとられたことを考えると、今年はほとんどの期間で非常事態が日常となっています。この異常な日常が日本の様々な面に影響を及ぼしていることは周知のことですが、今回は特に深刻と思われる若い世代への影響について考えます。<文:ファンドマネージャー 山崎慧>
競馬ファンも唸る「ウマ娘」、ゲーム収益にとどまらない爆発的ヒットの理由
配信開始から5日で100万DL、約2ヶ月で600万DLを突破
サイバーエージェント(4751)は4月28日に1~3月期の決算を発表し、前年同期比で売上高が+26.6%、営業利益が2.1倍と非常に好調な業績が示されました。<文:ファンドマネージャー 山崎慧>
バイデン大統領のインフラ投資案は予想外に小型化、株価への影響は?
2兆ドルだが公約の4年ではなく8年
バイデン大統領は3月31日に「アメリカンジョブズプラン」という総額2兆ドルあまりのインフラ投資計画を発表しました。期間は8年間としています。今回は、政策の主な内容について解説します。<文:ファンドマネージャー 山崎慧>
1都3県はまだ緊急事態宣言下…延長にかかる国民一人あたりの負担金額は?
リバウンド阻止を理由に緊急事態宣言延長
政府は3月5日、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県に発令している緊急事態宣言を21日まで2週間再延長すると発表しました。これにより、飲食店の時短営業、外出・イベント・施設利用の制限が続くことになります。新型コロナウイルスの新規感染者数は全国で1,000人、東京で300人程度まで減少し、重症者数も全国で400人程度、東京で50人程度まで減少しています。政府は、感染や医療提供の状況を示す6つの指標がステージ3(感染急増)相当に下がることを緊急事態宣言解除の目安としており、東京都を含めた全地点で6つすべての解除基準をクリアしている状況となっていますが、菅首相は「リバウンドの阻止」を理由に緊急事態宣言の延長を決定しました。目標達成後にゴールポストを動かした印象が強い決定ですが、世論調査ではおおむね8割が今回の緊急事態宣言の延長を支持しており、民意に従った結果とも言えます。一方、緊急事態宣言の延長によって経済的な損失は拡大します。今回は、1都3県の緊急事態宣言延長により発生する、追加支出や経済的損失を試算してみます。<文:ファンドマネージャー 山崎慧>
トランプ大統領より攻撃的なバイデン政権の議会運営、株価に水を差すリスクは?
超党派の合意をはやくもあきらめ
米国のバイデン大統領は、就任に合わせて総額1.9兆ドルのという景気対策を発表しました。その名も「アメリカンレスキュープラン」です。このプランをめぐり、バイデン政権の攻撃的とも言える議会運営方針が見えてきました。<文:ファンドマネージャー 山崎慧>
増税は不可避!?米両院を手にしたバイデン政権の景気対策、株価への影響を考察する
本当に大型財政政策は出るのか
米国では1月5日にジョージア州で上院議員選挙2議席の決選投票が行われ、2議席とも民主党が勝利しました。これで、大統領、下院に続き、上院も民主党が支配(50対50にハリス副大統領を加える)することになります。翌1月6日には、トランプ現大統領支持者による米国議会議事堂への乱入事件が起こりました。米国内では混乱が続いていますが、バイデン氏は正式に次期大統領に選出されました。株式市場は上昇を続けており、背景にはバイデン政権による追加の景気対策が早い段階で打たれるとの期待感があります。<文:ファンドマネージャー 山崎慧>
コロナ禍で家計負担が増える!? 高齢者医療費負担引き上げに児童手当削減…期待外れの第三次補正予算案
早急な医療体制の強化を
政府は2020年度第3次補正予算案を近日中に閣議決定する見込みです。2021年度当初予算案と合わせた15ヵ月予算となるもので、主な政策は以下の通りです。<文:ファンドマネージャー 山崎慧>
日本の財政政策は世界トップクラス、日本経済回復の支えとなる第三次補正予算に期待
Go Toも景気回復に寄与
日本の7~9月期の実質GDPは前期比年率+21.4%と、現系列で過去最高の成長となりました。全国的な緊急事態宣言などを受けて4~6月期の実質GDP成長率は前期比年率-29%と、これまでの史上最悪だったリーマンショック時(-18%)を大きく更新する落ち込みとなりましたが、そこから急回復を遂げています。<文:ファンドマネージャー 山崎慧>
バイデン民主党完全勝利なら株暴落も!?米大統領選に市場関係者が身構える理由
党内左派の勢いに警戒
11月3日に米大統領選挙が実施されます。民主党は、2016年に共和党が勝利したミシガン、オハイオ、ウィスコンシンなどのいわゆるラストベルトや、トランプ大統領の在住地であるフロリダなどの接戦州でいずれも選挙戦を有利に進めており、賭けサイトではバイデン候補の勝利確率が70%を上回っています。バイデン候補が勝利した場合、株式市場にはどのような影響があると考えられるのでしょうか。
株価上昇でも家計は苦しい…アベノミクスとは何だったのか
憲政史上最長政権の経済政策を振り返る
日本憲政史上最長となる7年8ヵ月の安倍政権の実績で最も議論が分かれるのは経済政策、いわゆるアベノミクスの評価でしょう。今回は第二次安倍政権発足(2012年12月26日)直後の2013年1月から新型コロナウイルス禍前の2019年12月までの7年間を対象に、アベノミクスの総括的検証を行いたいと思います。
経済的死者を減らせ!新型コロナで深刻すぎる日本経済の重症度
新型コロナウイルスでGDPは最悪の落ち込み
日本の新型コロナウイルス新規感染者数は5月対比で高水準が続いており、第二波が懸念されています。一方、感染再拡大からおよそ2ヵ月が経った8月中旬でも重症者数は抑えられており、政府も「医療提供体制はひっ迫した状況ではない(安倍首相)」と繰り返しています。結果として死者数の増加は緩やかで、引き続き他国対比で被害の抑え込みに成功しています。しかし、経済の落ち込みは深刻です。
世界経済「史上最大のV字回復」へ向かうが、日本は出遅れ懸念
「Withコロナ」でどう経済と両立
新型コロナウイルスの感染拡大ペースの鈍化を受け、各国で徐々に経済活動が再開されています。感染再拡大を防ぐ規制が完全には撤廃されない中、経済はV字型でなくL字型の弱い回復にとどまるとの見方が一般的です。しかし、実際の経済データは各国でL字型でなくV字型の回復を見せています。感染拡大が最初に始まった中国では、4〜6月期の実質GDP成長率が季節調整済み前期比+11.5%と、統計開始以来過去最大の伸びとなりました。水準で見ると1〜3月期の落ち込み(同▲10.0%)をわずか1期で全戻しするV字回復となっています。