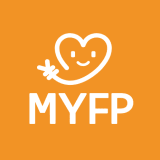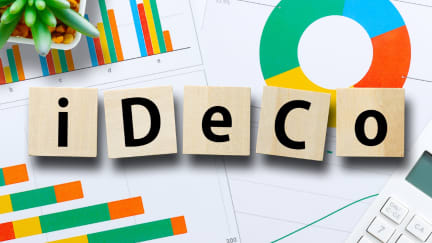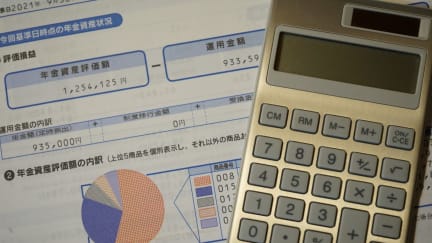60歳以上の「iDeCo」新規加入は、受け取れない期間に要注意。2022年改正で見落としがちなポイント
確定拠出年金制度の改正を解説!
日本では、2001年からスタートした確定拠出年金制度(iDeCo、企業型DC)。加入者数は年々増加の一途を辿り、私的年金としての認知も上がってきました。およそ20年の歳月を経て、徐々に制度が整えられてきた中で、今年2022年に大きな改正が行われます。その改正は、利用者側にとってメリットとなる改正ではあるものの、注意をしておかなければいけないポイントがあります。今回は、その中でも見落としがちなポイントに絞って解説します。
「年金が少なそうで不安」50代自営業夫婦が老後資金作りのためにやるべきことは?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、52歳と51歳の、ともに自営業のご夫婦。教育費もそろそろ払い終えるタイミングで、自分たちの老後資金を貯めようと考え始めた相談者。自営業の人が老後の備えのためにやるべきことは? FPの横山光昭氏がお答えします。
自己投資や交際費で赤字の40代ライター。フリーランスが老後資金を貯めるベストな方法は?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、44歳のフリーライターの女性。そろそろ老後資金を準備しようと考えていますが、自己投資や交際費・被服費などが多く、毎月赤字に。どの支出も下げるのは難しいと言います。資産形成へのステップは? 家計再生コンサルタントの横山光昭氏が運営する『マイエフピー』のFPがお答えします。
50歳以上は「iDeCo」に新規加入するべきか?改正で増えたメリットと注意点
「第二の退職金」をつくる
老後の資産形成の最強の仕組みと呼ばれる「iDeCo」ですが、50歳以上の方からは加入を躊躇する声がこれまで多く聞かれました。しかし令和4年の改正で、ますます魅力が増したことをご存じでしょうか?今回は、50歳からのiDeCo新規加入について解説します。
老後破綻の危機に気づかず車購入を考える43歳独身会社員。40年ローンが引き金に
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、43歳会社員の女性。購入したマンションに一人暮らしの相談者。住宅ローンの負担を重く感じながらも車の購入を検討しており、さらにローンを増やすことに不安を感じています。ところが家計には様々な問題点が…。FPの秋山芳生氏がお答えします。
「始め方や詐欺にあわないためには、どうしたらいいの?」馬渕磨理子が投資の大原則を解説
具体的な4つの投資方法
経済アナリストの馬渕磨理子です。資産運用の必要性を感じ、投資を始めようと思ったものの「どうやってはじめたらいいの?」と思っている方もいらっしゃるでしょう。講演などをしていると、20代の方からは「投資詐欺にあわないためにはどうしたらいいの?」という質問も多く受けます。今回は投資をどうやって始めたらいいのか、投資の大原則、いくらから投資を始めることができるのかお話しします。
「掛金はいくらが適正?」iDeCoを始める時によくある4つの質問
気を付けたいポイントを解説
未来の自分に向けた仕送りのために活用したいのが、節税しながら自分年金を創る仕組み「iDeCo」です。預金だけではダメな時代、資産形成は一日でも早く取り組むのが吉といえるでしょう。国の制度であるiDeCoは金融機関を通じて申込みますが、気を付けたいポイントがいくつかあります。今回はiDeCoについて、よくある質問を解説していきます。
商品から選ぶのは間違っている?積立投資、資産配分と運用商品を決めるまでの手順とは
投資信託の選び方と重要ポイント
積立投資について「どの運用商品を買ったら良いのか」 という質問は、個別相談のなかでも最も多い質問のひとつです。近年では、運用商品が充実してきているため、選ぶのに悩んでしまうことでしょう。この記事では、自分にあった積立投資が実践できるように運用商品、主に投資信託(投信)を選ぶまでのプロセスを解説します。
「iDeCo」の制度変更で影響ある3つのポイント、メリットあるのはどんな人?
制度開始から20年
確定拠出年金は、アメリカ人の老後の資産形成を力強く後押しした401kという制度を模して、2001年に日本版401kとして始まりました。個人型と企業型の2つの種類がありますが、制度開始から20年の月日を経て、どんどん使いやすく、またメリットも拡大しています。今回は2022年の変更点から、特に皆さんに影響のある3つのポイントをお伝えします。
会社員とフリーランスで社会保障はどう違う?独立する前に知っておきたい、年金や保険の格差対策
ご自身やご家族のために
会社組織に所属せず、個人で業務を請け負い事業を行うフリーランスという働き方があり、近年注目されています。そんなフリーランスの立場になる前に、理解しておく必要があることに会社員との社会保障面での違いがあります。今回は、フリーランスの方の社会保障について解説していきます。
毎月家計が4万円の赤字…将来に備えるならNISAかiDeCo?投資を始める前にやることは?36歳個人事業主の悩み
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、36歳独身、個人事業主の女性。外出自粛の影響もあり、将来を真剣に考え出した相談者。貯金は120万ほどで家計も赤字気味ですが、将来に備えて投資を始めたいといいます。投資の選び方、始め方は? 家計再生コンサルタントの横山光昭氏が運営する『マイエフピー』のFPがお答えします。
そもそも「NISA」「iDeCo」って何?年収500万円の場合、税制メリットはいくらあるのか
税制優遇の特典付き投資術
初めまして、ファイナンシャルプランナーの山中 伸枝です。「資産形成」について話題になることが増えました。その際に「NISA」と「iDeCo」という制度がよく紹介されているかと思いますが、「私には関係ないや」とスルーしてしまっていませんか?たくさん情報がある中、自分にとって必要なものとそうではないものを精査するのは大変ですが、国が発信する情報は特別です。そこには後回しにしてはいけない理由があります。
60歳で「企業型DCの加入者資格喪失」の通知、定年後はどうするのがベター?
考えておきたい3つの選択肢
2022年4月から個人型や企業型を含め確定拠出年金の改正が続きます。今回は改正前に60歳で定年を迎えられた方からの相談事例をもとに、確定拠出年金の改正ポイントについてお伝えさせていただきます。
先の収入が読めない37歳自営業。優先はiDeCo?NISAは「つみたて」か「一般」か?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、最近投資を始めたばかりという37歳フリーランスの方。先々まで現在と同じ収入を得られる保障がないため、iDeCoやNISAをどのようなバランスで運用していけばよいのかわからないといいます。自営業者の上手な将来への備え方は? FPの伊藤亮太氏がお答えします。
「ドル建て終身保険」に向いている人そうでない人、リスクを理解して活用する場合の方法は?
自分にあっている?
前回「ドル建て終身保険」の仕組みと特徴から考えられる、メリットとデメリットについて解説を行いました。「ドル建て終身保険」は、リスクやデメリットばかりではありません。かといって、誰もがいつでも有効に活用できるか?といえば、決してそうではない商品です。この「ドル建て終身保険」に向いている人と、そうでない人の特徴を整理して、具体的な活用方法を解説します。
26歳独身会社員「将来海外で働きたいけどiDeCoや資産運用はどうすればいい?」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、26歳会社員の女性。今後海外で働きたいという希望があり、結婚するかどうかはわからないという相談者。つみたてNISAを始めたばかりで、iDeCoを始めるべきか迷っていると言いますが、判断の基準は? FPの伊藤亮太氏がお答えします。
年金月6万、老後資金2200万の59歳独身女性。今からどれくらい資金を増やせる?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、自営業の59歳独身女性。老後資金は2,200万円、年金は月額6万円という相談者。老後資金を増やしたいといいますが、今からでも打てる対策はあるのでしょうか。また、どれくらい老後資金を増やすことができるでしょうか? FPの秋山芳生氏がお答えします。
ローン返済にiDeCoに…娘の学費まで貯金が回らない会社経営夫婦。どこを見直せばいい?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、夫婦で会社を経営する37歳の女性。マイホームを購入してから、ローン返済やiDeCoの積み立てのために、娘の学費まで貯金が回らないといいます。どこから改善すればよいでしょうか? また老後の備えは十分でしょうか。家計再生コンサルタントの横山光昭氏が運営する『マイエフピー』のFPがお答えします。