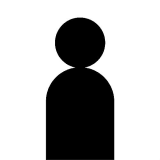はじめに
2025年3月3日、トヨタ自動車が“会社史上初”となる株主優待制度の導入を発表し、業界を驚かせました。株主優待を廃止する企業がある中、日本の自動車メーカーの巨人であるトヨタが、なぜこのタイミングで株主優待の導入を決めたのでしょうか。ここでは、昨今のトヨタを取り巻く状況や経営環境の変化などから、トヨタの株主優待新設の理由を考察します。
優待導入企業数は減少から再び増加傾向へ
冒頭で紹介したように、トヨタ自動車が1937年8月の会社設立以来、初となる株主優待制度の導入を2025年3月3日に発表しました。この発表を受けてマーケットは騒然としたものの、翌日の4日の株価は一度も前日の終値を上回ることなく、前日比マイナス42円(1.5%安)で大引け。ただ、4日は日経平均株価が一時1000円近く値下がりするなど急落したため、それが機関投資家の参加者が多いトヨタ自動車の株価に影響したものと思われます。
株主優待は個人投資家の人気が高く、優待新設・廃止のニュースが出れば、それだけで株価が大きく上下するケースが少なからず見受けられます。筆者が過去にマネー誌の編集をしていた時分、株主優待はいわば“鉄板ネタ”。定期的に特集が組まれていました。当時も優待を導入している企業は千数百社に上り、優待品の写真の掲載許可取得や優待リスト作成のために、幾日も徹夜作業したものです。
そんな大人気の株主優待制度ですが、導入企業数は2019年の1532社をピークに、2022年には1473社まで減っていました。新型コロナの感染拡大による業績悪化のほか、東証による市場改革の一環で「資本コストの向上」への意識が高まったことなどが、導入企業減少の要因として挙げられています。普段からマネー系の記事に目を通す人なら、「株主優待の導入企業が減っている」といった内容の記事を目にしたことがあるのではないでしょうか。
しかし、2023年から導入企業は再び増加に転換。2024年末には1,530社、全上場企業の33.9%が株主優待制度を導入しており、導入企業数で7年ぶりに過去最高の数字を更新しました(野村インベスター・リレーションズ調べ)。日本経済が新型コロナによる景気悪化や約30年続いたデフレ経済から脱却し、“金利ある世界”の中で再成長に向けてリスタートを切る――トヨタ自動車は、このような経済環境の中で株主優待を開始したことになります。
優待導入は「長期でトヨタ株を保有してもらう」目的
気になるのは、「なぜこのタイミングでトヨタが株主優待の導入を決めたのか」です。トヨタ自動車の株主優待の内容は以下の通り。
・継続保有期間1年以上で1,000円相当の電子マネー贈呈
・継続保有期間3年以上で3,000円相当の電子マネー贈呈
・継続保有期間5年以上は、1000株保有で3万円相当の電子マネー贈呈
・その他、抽選でモータースポーツの観戦チケットや関連グッズを贈呈
トヨタの株価は3月21日現在で2844.5円なので、100株を保有するには28万4,450円が必要になります。「2年未満の保有で1000円の電子マネー」は、リアルマネーに換算すると利回り(「優待利回り」)は0.35%。優待利回りで4%を超える銘柄も少なからずある(3月24日現在のYahoo!ファイナンスの「株主優待利回りランキング」で157社)ことを考えると、0.35という数字はかなり低い水準です。
「5年以上の1000株保有で3万円」だと優待利回りは1%に上がります(それでも“高利回り”とはいえませんが)。トヨタの自社サイトでは、株主優待制度導入の目的を「より多くの投資家に当社株式を“長期にわたって”保有してもらうこと」としており、優待の内容もそれを反映したものになっているといえるでしょう。
中には、株主優待をもらう権利が発生する「権利確定日」の直前に買い、権利確定日が過ぎたら即座に売る、いわゆる「優待取り」の手法を用いる個人投資家も存在します。トヨタは株主優待を導入するにあたって、こうした「優待取り」の手法を避け、長期で株式を保有してもらうために、このような「継続保有で優待内容拡充」の方式を採用したと思われます。