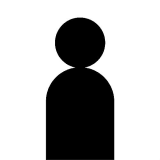はじめに
バブル崩壊以降と東証の市場改革で持ち合い解消の流れが加速
トヨタが株主優待制度を導入した理由の1つに、前述した「東証の市場改革」が大きく影響していると考えられます。日本では、1980年代後半のバブル期に「政策保有株」と呼ばれる、関係が深い企業や銀行などの金融機関と株式を相互に保有しあう「株式の持ち合い」が常態化していました。経営の安定化や他社による敵対的買収を防ぐことを主な目的に、「あなたの会社の株式を保有する代わりにあなたたちも私たちの株を保有してください」という日本独自の企業文化があったのです。
しかし、バブル崩壊によって「少数株主の意向が反映しづらい」「株主資本を効率的に使えない」といった「株式持ち合いによるデメリット」がフォーカスされるようになり、1990年代以降は株式の持ち合いを解消する動きが出始めます。東証も市場改革の一環で株式持ち合いを解消するよう企業への圧力を強めており、2023年には持ち合い株の解消によって資本効率の改善や経営の自由度が増すことを狙ったETF(上場投資信託)まで誕生しました。
大手外資系証券の推計によると、2024年3月末時点で企業や金融機関が保有する持ち合い株の残高は約60兆円に上るとのこと。持ち合いは徐々に減っているとはいえ、まだ解消にはほど遠い状況です。運用会社の担当者からは「持ち合い株の解消には少なくとも5年以上の時間が必要」との声も聞かれます。
個人投資家を「安定株主」へ
こうした流れを背景に、トヨタグループでも持ち合い株を解消する動きが加速しています。トヨタグループは、グループ本家にあたる豊田自動織機のほか、自動車部品国内最大手のデンソー、同じく自動車部品大手のアイシン、合成樹脂メーカーの豊田合成、総合商社の豊田通商など、複数の大手企業が上場中。2023年、トヨタグループはこうした株式持ち合いの解消を進めることを表明します。
翌2024年7月には、三菱UFJフィナンシャル・グループと三井住友フィナンシャル・グループに加え、大手損保会社も保有するトヨタ株の売却を打ち出しました。その時点で、その2行と損保会社が保有するトヨタ株の総額は3兆円超。これに対して、トヨタ自身も同月に8000億円超の自社株のTOB(株式公開買い付け)を発表し、同年9月にはその取得枠を1兆2000億円まで拡大しました。今後、取得枠をさらに追加する可能性もあるようです。
もっとも、いくら世界のトヨタとはいえ、すべての株式持ち合いを解消するためには、1社の資金力だけでは限界があります。また、今後も持ち合い株の売却が進めば、それを狙ってトヨタ株を買い集め、トヨタグループへの影響力を強めようとする外資企業が出てくる可能性も十分考えられます。
そこで、トヨタが触手を伸ばしたのが「株主優待制度」。これまで、トヨタは業績拡大による株価の上昇や株式の配当、自社株買いを株主還元策としてきました。しかし、持ち合い株解消の潮流や、ホンダと日産自動車の経営統合失敗にも見られるような、自動車メーカーを取り巻く経営環境の変化に対応するには、安定した資本構造と経営基盤が不可欠です。トヨタは「新NISA(少額投資非課税制度)も始まったことだし、個人投資家を安定株主に取り込もう」と考え、株主優待制度の導入に踏み切った――という構図なら、読者の皆さんも腑に落ちるのではないでしょうか。
投資管理もマネーフォワード MEで完結!複数の証券口座から配当・ポートフォリオを瞬時に見える化[by MoneyForward HOME]