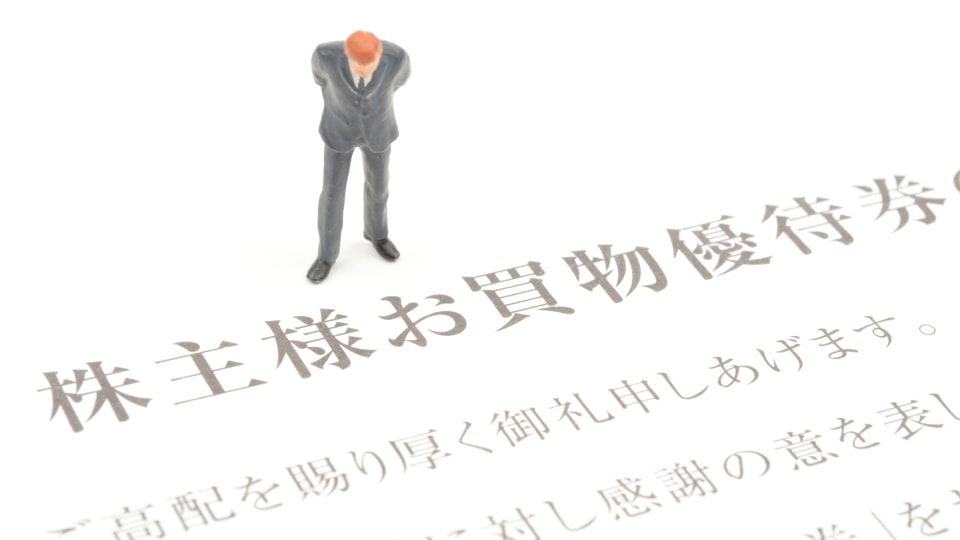はじめに
新NISA普及に伴い個人投資家の裾野が広がり、株主優待への関心も高まっています。こうした中、日本証券業協会は2024年10月から株主優待に関する学術的な研究結果をもとに、優待の意義や効果を検討する「株主優待の意義に関する研究会」を設置し、意見交換が進められてきました。本研究会は、2024年11月から2025年2月にかけて4回の会合が開催されました。研究者、実務や法律に精通した有識者、個人投資家の立場からのプレゼンテーションを基に、株主優待の現状および意義や効果について議論され、結果が4月16日に公表されました。 その内容は、かなり興味深いものとなっています。
株主優待の現状とその効果
株主優待とは、企業が自社の株を購入した株主に向けて、自社商品やサービスなどの「優待品」を贈る制度です。日本で株主優待が始まった背景については、中元・歳暮などの贈答文化や株主総会でのお土産の制度化など諸説あります。株主優待は任意の制度であるため、すべての企業が実施しているわけではありません。株主優待の実施状況をみると、データを遡ることができる1992年には、株主優待実施企業は251社(全上場企業の9.5%)でした。2019年には過去最高の1532社(全上場企業の37.2%)が採用しています。
その後、コロナ禍に伴う業績悪化や優待コストの重さ、コーポレートガバナンス・コードの浸透により、株主還元の手段として配当を重視する海外投資家の圧力が強まり、株主優待を廃止する企業が増加しました。しかし、足元で株主優待を導入する企業が増加しています。2022年9月末時点では、1473社まで減少しましたが、2024年9月末時点で1494社、全上場企業の約3分の1が株主優待を実施しています。
増えた理由としては、新NISAの開始や企業に対して政策保有株の解消を求められている点が挙げられます。個人投資家は株主優待の拡充により株式を長く保有する傾向があるためです。長期保有優遇型の株主優待を導入している企業は2024年9月末時点で612社あり、株主優待実施企業の4割を超えています。
株主優待がもたらす効果も同時に公表されています。まず、株主優待導入によって株主数が大幅に増加しています。東証が掲げる上場維持基準にも株主数はあり、プライム市場の株主数の基準は800人となっています。次に、上場企業における株主優待制度の有無とボラティリティの関係をみると、ボラティリティは優待有企業の方が低いという結果でした。また、株主優待制度の有無とPERの関係をみると、PERは優待有企業の方が高い結果となっています。株主優待導入・廃止発表後の株価動向をみると、株主優待制度を導入した企業と廃止した企業では2割程度のバリュエーションの違いが見られました。