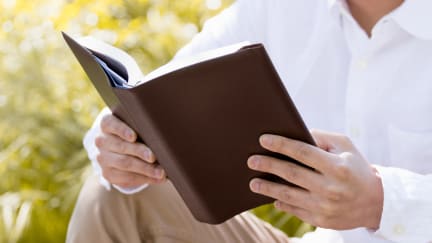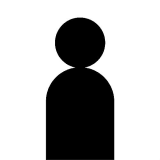所得制限なし! 東京都民・私立高校生家庭の「授業料軽減助成金(都の制度)」の申請のポイントは?
申請は30〜40分程度かかる可能性も
前回の記事では、「国の制度」の就学支援金の申請のポイントについてお伝えしました。本記事では「東京都の制度」である「授業料軽減助成金(都民対象)」の申請のポイントについてお伝えしていきます。締切が2025年7月31日(木)ですので、期日は迫っています。また、システム操作には30~40分程度かかる場合もあります。時間に余裕をもって申請しましょう。「国の制度」とは、事前に準備するものがまったく異なりますので、目を通していただき、スムーズに進めるためのポイントを押さえましょう。特に間違いやすいポイント、わかりづらいポイントを「★要注意ポイント!」の印をつけましたので、事前にチェックしてから申請いただくとスムーズかと思います。
役職定年で給料が半分に? 50代後半のための「今から」行動に移せる具体策3点
セカンドライフの準備を始めよう
「役職定年で給料が半分になるらしい…」同じ会社の先輩方から話を伺い不安になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際その年齢が迫っている方はより切実です。収入減が予想される場合は「生活防衛」のための準備と対策をあらかじめ講じることが非常に重要になります。役職定年での収入減の実態や、この変化を乗り越え、その後の人生を物心ともに豊かに送るための方法を解説していきます。役職定年後も安心して暮らすために、不安を希望に変える生活設計をしていきましょう。
せっかくのイベントが子どもの発熱でキャンセル…「チケットガード」は使える?
行けなかった後悔、高くついていませんか?
楽しみにしていたライブ、舞台、スポーツ観戦、子どもとのレジャーイベント。その日を心待ちにしていたのに、当日になって急な発熱やケガ、交通トラブルで泣く泣く行けなくなったという経験、あなたにもありませんか?しかも、多くのチケットはキャンセルや払い戻しができないため、数千円〜数万円もの出費が無駄になってしまい、心にもお財布にも大きなダメージとなります。そんな「もしも」のときに頼れるのが、チケット代を守るサービス「チケットガード」です。この記事では、チケットガードの仕組み・補償内容・メリットとデメリットを解説します。入っておけばよかった…と後悔しないために、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
資産運用の初心者注目! 元本割れしない金融商品「個人向け国債」の上手な使い方ガイド
Sponsored by 財務省
資産運用の重要性が広く認知されてきています。一方で、資産運用に関心はあるけれど、なかなか一歩を踏み出せずに悩んでいる人もいることでしょう。資産運用のはじめの一歩を踏み出すのにためらってしまう――そんな人に知ってほしいのが「個人向け国債」です。個人向け国債を購入すると、半年ごとに利子が受け取れ、満期に元本が戻ってきます。元本割れがないため、資産運用が初めての方にぴったりの商品です。ただし、金融商品を購入する際は、商品のことをよく理解することが大切です。個人向け国債の特徴や活用方法を学んでいきましょう。
夫のセミリタイアを叶えたい31歳女性「2人の子育てとマイホームを実現するにはあといくら必要?」
みんなの家計相談
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、第一子が生まれたばかりの31歳の女性。現在、30歳のご主人と共働きだそうですが、ご主人が40歳になるタイミングでセミリタイアを計画中といいます。それでもマイホームは購入できるのかという相談です。FPの氏家祥美氏がお答えします。
夏のボーナスの使い道に異変? 「節約疲れ」の処方箋とは
心地よいお金との付き合い方
この夏、ボーナスが支給された人も多いでしょう。ここ数年、支給平均額は上昇傾向にあり、昨年よりも増えたという人もいるかもしれません。東証プライム上場企業の全産業のデータを見ると、今夏のボーナスの平均額は86万2928円で、前年比3.8%の増加(※一般社団法人 労務行政研究所 2025年5月8日発表)。昨年(前年比同4.6%増)に続いて上昇しています。では、この夏ボーナスは、みんなはどんなものに使う予定でしょうか。アンケート結果を見ていきましょう。さらに、「節約疲れ」を感じている人へのヒントもご紹介します。
子どもも“物価高”を感じている。家族で考えるお金の価値とモノの選び方
日常で育もう! モノを「選ぶ目」
「この前は100円だったのに、今日は120円?なんでー!?」スーパーのアイスコーナーで、そんな声を上げたのは小学3年生の娘。日々の暮らしの中で、子どもたちは意外としっかり「値段の変化」を感じ取っているんだなと、驚いた瞬間でした。「物価上昇」という言葉を聞くと、難しそうな経済用語に思えるかもしれません。でも、毎日の買い物や食卓の中にある“身近な変化”なのです。「物の値段が変わるってどういうこと?」「お金の価値ってどう決まるの?」そんな疑問に、親子で一緒に向き合ってみる時間を、夏休みにこそつくってみませんか? 3人の子育て真っ最中のFPが実体験をもとにお伝えします。
社会保険の加入対象の拡大には、大きく分けて3つある? どんな人が対象になるのか
年収の壁を超えて働くメリットとは
2025年6月13日に成立した年金制度改正法は、年金に関するさまざまな変更が盛り込まれていることから、ニュースなどでも大きく報じられました。なかでも「社会保険の加入対象の拡大」は、これまで「106万円の壁」の扶養の範囲で働いているパート・アルバイトの人に大きな影響のある改正ですが、内容があまりわかっていない人もいるかもしれません。今回は、年金制度改正法によって社会保険の加入対象が今後どのように拡大するのか、紹介します。
公立小学校の学習費は年間約33万円! 新生活で増える支出、家計のバランスはどう整える?
夏休み前の今こそ見直す家計の負担
新生活が始まり数ヶ月、入学準備がひと段落したと思ったのも束の間、「想像以上にお金がかかっている気がする」と感じていませんか?入学準備などの初期費用に加え、学用品の追加購入や習い事、食費など、じわじわと支出が膨らみやすい時期です。さらに、夏休みを前に昼食代や、預かり保育等の費用の増加など、今までにない支出を実感するタイミングでもあります。こうした支出の変化を早めにキャッチしておくことが、今後の家計の安心につながります。本記事では、子どもが小学校に入学したばかりの筆者が、実体験をもとに小学校生活で増えやすい支出の具体例と整え方についてお伝えします。
「月々1万円台で新車に乗れる」 残価設定型クレジットは本当にお得? カーリースやローンとの違いとは
家計に合ったマイカープランの立て方
「月々1万円台で新車に乗れる」「頭金なし・ボーナス払いなしでOK」そんな広告を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか?このような支払いを可能にしているのが「残価設定型クレジット(通称:残クレ)」と呼ばれる仕組みです。初期費用を抑えながら新車に乗れるという手軽さから、残価設定型クレジットは車の購入方法として広く利用されるようになっています。しかし車の購入は、日常生活における大きな支出のひとつであるため、「月々の支払いの安さ」だけに目を向けるのではなく、仕組みや注意点を理解し、自分のライフスタイルや家計に合っているかどうかを慎重に見極めることが大切です。今回はFPの視点から、残価設定型クレジットの基本的な仕組み、注意点、そして他の購入方法との違いについて解説していきます。
「ボーナス」で将来の備えをしすぎないほうがいい? FPが伝える上手な使い方
4つの視点で考える
「ボーナスが出たけど、何に使うのがいい?」そう思った事はありませんか?ボーナスは、月収だけでは難しい大きな出費を後押ししてくれるお金です。一方で、景気や業績によって増減する「変動型の収入」であることも忘れてはいけません。家計全体の設計(ボーナスをどう位置づけるか)と、使い道のバランス(何にどう使うか)の両方を意識する事が大切です。本記事では、ボーナスの使い道を整理する4つの視点、ライフステージごとのバランスの考え方、ボーナスをあてにしすぎない家計設計の基本を解説します。
「あれ?今月の手取りが減ってる…なんで?」新卒2年目に手取りが減る理由
お金の流れを見直す機会に
社会人生活も板についてきた新卒2年目に気づく、手取り額の減少。実は、“ある税金“の支払いが始まることが関係しています。1年目にはなかった支払いが、6月から突然始まることで、月々の手取りに影響が出てくるのです。今回は、給与から引かれるお金の仕組みや2年目の手取りがどの程度変わるか、そして手取り減の対策についてお伝えします。
価格高騰の中でコメ代はどう節約する? 「古いお米」をおいしく食べる方法とは
おいしく食べる4つの方法
依然としてコメ価格の高騰が続いています。スーパーでのコメ平均価格は、2025年4月25日から5月4日分で5キロあたり19円値下がりしたものの、翌週からはまた連続で上がり続け、前年同月比で約2倍の価格で推移しています。農林水産省の発表では、3月に落札された備蓄米で小売や外食に届いている量は全体の10%前後であり、残りの90%については未だ集荷業者や卸業者から出ていない状態とのことです。そこで新たな策として出たのが、備蓄米の「競争入札」ではなく、政府が売り渡し先や価格を決める「随意契約」で放出すること。日々ニュースを賑わせているのでご存じの方も多いことでしょう。このような状況の中で、食費を節約する方法と、古いお米をおいしく食べる方法をご紹介します。
料理、家事、エンタメ…節約アドバイザーがあえて節約しないところとは?
支払い方法の工夫まで
先日のこと、本連載の編集担当の方と話をしているときに「節約アドバイザーの方でもお金をかけるところ、節約しないところってあるんですか?」と聞かれました。確かに筆者の中でも「これは多少の支出があっても、買う価値はある」と考えるカテゴリーがあります。そこで今回は、自分語りになってしまいますが、筆者がお金をかけているものについてご紹介します。支出というのは、その人のライフスタイルや価値観で大きく変わってきますので、あくまでも筆者の例として参考になさってください。
5月病でお財布の紐が緩む?「ストレス散財」を防ぐ方法
衝動的にお金を使わないための工夫とは?
新年度を迎え、何かと慌ただしかった4月が終わり、気分が沈みがちになる「5月病」を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、この時期、お金の使い方にも変化が現れることがあるのです。この衝動的な「ストレス散財」は、家計の負担になるだけでなく、自己嫌悪やさらなるストレスの原因にもなりかねません。そこで今回は、5月病によるストレス散財の原因を探り、無駄遣いを防ぐための具体的な対策を紹介します。
5月連休中の遠出計画はちょっと待った? 夏ごろまでにガソリン価格は1リットル=140円以下まで下がるかも!
なぜ下がると予想できる?
昨今の物価の上昇が国民の生活を直撃しています。最近では、特にお米の値上がりについて、政府が備蓄米を放出したにも関わらず、流通など構造的な問題で値段が下がらないことがテレビの報道番組などで盛んに取り上げられていて、気にされている方も多いのではないでしょうか。もうひとつ、人々の生活に密着しているモノとして挙げられるのがガソリン。ここでは、その「ガソリンの価格」について、今後の動向を考察します。
「家電の延長保証」加入する?しない?判断するための4つのポイント
点検・清掃がセットになった延長保証サービスも
家電を購入する際に「せっかくだから長く使える良いものを買いたい!」という人も少なくはないはずですが、長い間使う際に気になるのは故障です。そんな故障に伴う突然の出費に備えることができるのが”延長保証”です。今回は、「延長保証に加入するべきか判断するための4つのポイント」をご紹介します。
初任給の使い方は意外と重要! 家計管理の基本「50-30-20ルール」を知っていますか?
初任給の使い道と貯蓄のポイント
新社会人にとって、初任給はこれからの人生設計の第一歩となる大切なお金です。初めての給与をどう使うかによって、将来の家計管理の土台が築かれます。この大切な一歩目で、浪費癖がついてしまうと、改善するのはなかなか難しいものです。自分の収入にあった計画を立て、無駄遣いを防ぎながらも、明るい未来へ繋がる家計管理を目指しましょう。