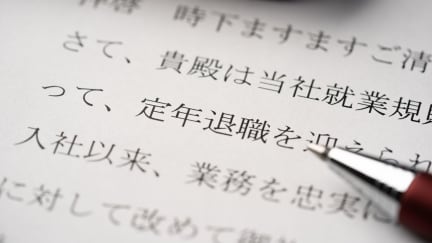企業型DCで考えたいマッチング拠出とiDeCoの併用、選択のポイントをFPが解説
春は各種変更届けのタイミング
企業型確定拠出年金(DC)が導入されている会社も多くなっていますが、特に春はさまざまな変更の申請があったり、転入・転出もあったりと忙しい時期でもあります。今回は、特に質問も多いマッチング拠出とiDeCo併用における選択のポイントを解説します。
「趣味は貯金」1000万貯めた30歳独身女性が次に狙うインフレ下の資産運用
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、30歳、会社員の女性。30歳にして1,000万円を貯めた貯金上手の相談者が次に考えているのは、「インフレ下の資産運用」について。どんな手段が考えられるでしょうか。FPの伊藤亮太氏がお答えします。
プロ投資家にはない個人投資家のメリット、プロは意外と柔軟な投資判断ができない?
金融アナリストが考える個人投資家の強み
個人投資家には、プロの投資家にはないメリットや強みが存在します。今回はプロに負けない、個人投資家ならではのメリット、強みについてお伝えいたします。
海外居住者でもiDeCoを活用できる?ただし、受けられなくなるメリットも
日本を離れる方にお勧めの制度と注意点
WBCでの侍たちの活躍に日本中が歓喜した記憶は新しいですが、スポーツに限らずたくさんの日本人が海外で活躍しています。今回は日本を離れ、海外で活躍する方たちにお勧めしたい国の制度と、注意点をご紹介します。
手に汗握らない金額で始める、分散投資…投資を始める人が押さえるべき5箇条
「投資で大やけど」の可能性を減らそう
大学入学や社会人になる、転職するなど新年度をきっかけに新たな生活が始まる方も多いでしょう。そして、新たな生活をきっかけに投資デビューする予定の方もいらっしゃるかもしれません。今回はそうした方向けに、投資を始める上でぜひ押さえていただきたい基礎となる5つのポイントをご紹介します。
年金のギモン、繰上げと繰下げはどちらを選ぶべき?よゐこ有野「破綻してもらえなくなるって聞くけど…」
資産運用と家計(4)
お笑い芸人・よゐこの有野晋哉さんが、毎月さまざまな専門家をゲストに迎えて、お金の知識を身に付けていく「お金の知りたいを解決!お金の学園〜学級委員・よゐこ有野晋哉〜」。2023年3月はファイナンシャルプランナーの岩城みずほ先生に、資産運用と家計について、弁護士でタレントの三輪記子さんと一緒に伺いました。今回は、「公的年金制度」について伺いました。「年金は破綻する」と言われているのは、本当なのでしょうか?
iDeCoとの併用も可能になった企業型確定拠出年金、メリットと見落としがちなデメリット
FPが掛金の拠出スタイルごとに解説
iDeCoの兄貴分ともいえる企業型確定拠出年金(企業型DC)。加入者も多いのですが、意外に内容を理解した上で活用しているという方は少ないようです。企業拠出に加えて個人が掛金を上乗せできる仕組みも整ってきましたので、今一度制度を確認しましょう。
それiDeCoとNISAのほうがメリットありますよ−−FPが出会った勘違い事例3つ
貯金や保険を使った時との違い
iDeCoとNISAの認知度も高まり、ご自身でも活用しようという方が増えてきました。さまざまな活用法がありますが、用途が限定的だと勘違いしていて、「それ、iDeCoやNISAを使ったほうがメリットありますよ!」というケースも。ファイナンシャルプランナーの筆者が、実際に出会った事例を3つ、具体的な金額を交えて紹介します。
定年間際の59歳会社員が退職金の手取りを増やす方法は?
自分の退職金がいくらなのか、どう受け取るのか
「高齢者の金融リテラシー調査2019」(フィデリティ投信)によると、約7割の人が退職金の金額を直前まで知らなかった、という驚きの事実があります。今回は退職間際の人が退職金を受け取る前にチェックしておきたい退職金の手取りを増やす方法についてお伝えします。
iDeCoとNISAで損してしまうケースとは?FPが解説する税金の優遇制度の注意点
税制優遇を正しく理解する
「税金がお得になる!」と評判のNISAとiDeCoですが、実際にそのお得さの確認をしているでしょうか? 特にiDeCoは、働き方や掛金の拠出の方法によって、税金のメリットの受け方が異なりますので、自分の場合はどうなのか、確認していきましょう。
投資をしていて【確定申告】した方がお得になるのはどんな人?知っておきたい「総合課税」のルール
税理士が投資と税の基本を解説
税金が増えるのに、将来もらえる年金が減っていく……お金に対する不安をあおる報道が続くなか、NISAやiDeCoを活かして、投資や節税に関心を寄せるようになった方も多いのではないでしょうか。でも、「税金やお金のこともよくわからないのに、投資も始めてしまいパニック状態になっています」ですって?なんて……嘆かわしい!情報や知識も得ずに投資や税と向き合っていると、お得な手続きを逃してしまうこともありますよ。今回は投資の税について、お笑い芸人で現役の税理士である税理士りーなが解説します。
iDeCo「障害給付」で注意すべきポイント、老齢給付と異なる点は?
障害年金との違いも解説
iDeCoの給付には「老齢給付」「死亡給付」「障害給付」の3つがありますが、老齢給付以外はあまり情報がないのが現状です。前回は加入者が死亡した場合の取り扱いについて解説しましたので、今回は障害を負った場合について見ていきます。
iDeCoとNISA、初心者が始めるならどっち? よゐこ有野「やろうって気持ちになった」
資産形成の制度(4)
お笑い芸人・よゐこの有野晋哉さんが、毎月さまざまなお金の専門家をゲストに迎えて、投資や資産形成についての知識を身に付けていく「お金の知りたいを解決!お金の学園〜学級委員・よゐこ有野晋哉〜」。2023年1月はファイナンシャルプランナーの山中伸枝先生に、資産形成の制度について、タレントで元「アイドリング!!!」14号の酒井瞳さんと一緒に学びます。今回は、NISAと並ぶもう1つの税制優遇制度「iDeCo」について伺いました。まだ資産運用を始めていない2人はNISAとiDeCo、どちらを選ぶべきなのでしょうか?
約6000本もある投資信託はどう選べばよい? 選び方のキホンと気になる疑問をお金のプロが解説
投資信託選びの5つのポイント
投資家が出したお金をまとめて、プロが代わりに運用してくれる投資信託は、長期・積立・分散投資が簡単にできるうえ、つみたてNISA・iDeCoといった節税に役立つ制度でも利用される金融商品です。でも、投資信託ならどれでもいいのかというと、そんなことはありません。今回は、「投資信託の選び方のキホン」を紹介します。
「月5万円以上」貯蓄ができる会社員向け、おすすめ投資戦略をお金のプロが解説
つみたてNISA、iDeCoの次は?
お金を増やす方法はいろいろありますが、資産形成期、特に貯蓄に回せるお金が少ない時期は選択肢が限られてきます。優先順位は概ねつみたてNISA・iDeCoとなるので、貯蓄金額に回せるお金が月5万円であれば、預貯金・つみたてNISA・iDeCoの配分で終わってしまいがちです。以前の記事で、月5万円投資する場合の投資のロードマップを詳しく紹介しましたが、今回は、月5万円以上に貯蓄ができる場合や、すでにある程度余裕資金がある場合の投資戦略を考えていきたいと思います。
「夫が亡くなったらiDeCoはどうなる?」法定相続人とは違う、死亡一時金の受取人の順位
請求の手続き方法をFPが解説
iDeCoに関する質問で意外と多いのが、加入中の万が一の取り扱いについてです。iDeCoは、老後のために積み立てを行う口座ですが、老後に至る前に加入者本人が亡くなったら、積み立ててきたお金はどうなるのだろうか、という疑問にお答えしていきます。
扶養を外れたフリーランス妻55歳、iDeCoと国民年金基金どちらがベター?(後編)
最終的に選んだ結果は?
扶養期間が長い妻は、老後の公的年金だけでは心もとないのが現実です。54歳で扶養を外れた妻が、自分年金を作るベターな選択について相談事例を元にお伝えします。本記事は前回から続いて後編となります。
扶養を外れたフリーランス妻55歳、iDeCoと国民年金基金どちらがベター?(前編)
実際の受取額をシミュレーションしてみたら…
扶養期間が長い妻は、老後の公的年金だけでは心もとないのが現実です。今回は54歳で扶養を外れた妻が、自分年金を作るベターな選択について相談事例を元にお伝えします。