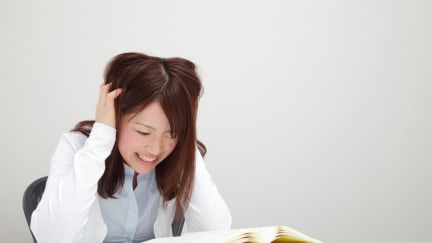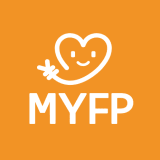ねんきん定期便をチェックせず「放置」で起こりうる“3つの不都合なコト”
最悪は、年金額の減少につながる
ねんきん定期便をチェックしていますか? 老後の収入の大部分を占めるものは何かというと、公的年金。にもかかわらず、受け取れる年金額をつかんでいない人が多いです。ファイナンシャルプランナーの高伊茂が、ねんきん定期便をチェックしていないと起こりうる“不都合なコト”と、”最低限チェックしたいコト”をご案内します。
38歳独身、介護の可能性あり。これからの住まいは賃貸or購入?貯蓄法は?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、38歳、会社員の女性。以前はあるだけお金を使っていたけれど、コロナを機に貯蓄体質になったという相談者。今はマンションの購入とつみたてNISAとiDeCoを検討中とのこと。相談者に合ったマネープランは? FPの横田健一氏がお答えします。38歳独身女性。持病あり、結婚の予定なし、マンション購入or賃貸と今後の投資・貯蓄法についての悩みです。お金に関する悩みは常にあったものの、あるだけ使う(衣服や旅行など)という生活をしてきました。ただ、これからの人生を考えると、下記のような条件からお金の不安は大きく、かつコロナで生活費を抑えるということが初めてできており、貯蓄が増えたことから、これを定着させて確かなものにしていきたいと思っています。ここ1年ほどで家計簿アプリをつけたことで、ブラックボックスだった資産や出費が可視化できたことも非常に大きく、自然と出費を以前よりは抑えられています。【現状の懸念】・独身(結婚の予定なし)・難病持病あり(保険は今以上には入
「不安で仕方がない」共働き夫婦の教育・住居・老後の資金計画をFPが見直し!
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、33歳、会社員の女性。今年第一子を出産した相談者。今後時短勤務で収入が減るなか、教育・住居・老後の資金計画に無理がないか不安で仕方がないといいますが…。FPの鈴木さや子氏がお答えします。今年頭に第一子を出産しました。そこで過去の記事なども参考に資金計画を立ててみましたが、今後時短勤務になって収入が減ること、教育費の増加、リフォームや親の老後を考えると不安で仕方ありません。計画に無理がないか確認していただけないでしょうか。子どもはできるだけ早いうちにもう1人希望しており、2人目を産んだ後は時短勤務を希望しています。上の子が小学校に上がるタイミングで義実家をリフォームして同居する予定です。リフォームには立地などの条件から2,000〜3,000万はかかると知り合いの業者さんには言われました。夫の退職後は在宅もしくは近場の職場でパートとして働き夫婦の時間を大切にしていけたらと考えています。・教育資金一人につき公立大学理系自宅外通学に必要な金額を用意した
給料は変わらないはずなのに手取りが下がった…健康保険料、厚生年金保険料、チェックすべき給料明細
社会保険料が変わったことが原因の可能性
振り込まれた給料が、先月より大きく減っている! 残業時間は先月と変わっていないのになぜ?と思われた方があるのではないでしょうか。その理由は、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が変わったことが原因の可能性が大です。社会保険料は、給料の額に連動して上下しますが、その計算は原則年1回しか行われません。つまり残業時間が毎月大きく変動するとしても、1回決まった保険料は1年間同じです。その変更時期が毎年9月分の社会保険料からとなっているのです。今回は社会保険料の計算と、給料明細のチェックポイントをお伝えします。
女性の退職や再就職で一生涯の手取り収入はいくら変わる?
老後の年金額はいくら増えるの?
結婚や出産、子どもの成長、介護などをきっかけに、働き方を見直す女性は多いでしょう。しかし、退職や再就職で「一生涯の収入」がいくら変わるかまで意識したことはありますか? 例えば年100万円の違いは30年間だと3,000万円にもなりますし、厚生年金に加入して働けば老後の年金受給額も増えます。収入が増えれば、その分子どもの教育費や家族でのレジャー費などにお金を使うことができます。働くモチベーションを上げるためにも、働き方を変えるとどのくらい収入が変わるのかを理解しておきましょう。
私たちが定年を迎える頃、退職金はもらえるの?
私的年金など、自ら備えを始めよう
将来の老後の生活に思いを巡らせたとき、資金面でその中心的な役割を担うのは退職金です。日本企業では、古くから終身雇用のもと、若いころの賃金を低く抑える代わりに多額の退職金を用意するという報酬制度を整えてきました。退職金制度にはさまざまな役割があります。働く人にとってみれば、定年後も豊かに暮らすためには退職金は欠かせません。また、企業としても、報酬の支払いを定年退職時まで留保しておくことで、それを社員が熱心に働くためのインセンティブとすることができるのです。拙著「統計で考える働き方の未来―高齢者が働き続ける国へ」(ちくま新書)では、労働の実態、高齢化や格差など日本社会の現状、賃金や社会保障制度の変遷等を統計データから分析することで、これからの日本人の働き方を考えています。その中では、退職金の過去から現在に至る趨勢を分析しています。今回は、著書の内容をもとに、退職金の現在の状況を確認し、その将来を予想していきましょう。
退職金がなく老後資金作りに焦る36歳「支出を限界まで絞って投資に回したい」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、36歳、会社員の男性。会社に退職金制度がないため老後資金のために投資を始めたという相談者。老後が不安なため、支出をできるだけ絞って投資に回したいといいますが…。家計再生コンサルタントの横山光昭氏がお答えします。もっと投資にお金を回したいと思っています。投資のために、支出をさらに削りたいのですが、どのように絞るとよいでしょうか。現在も結構がんばっているのですが、まだ絞りたいです。自分が勤める会社は退職金制度がなく、自力で人よりも多く老後資金を作らなくてはいけません。今まではあまり貯金しようとも思わず、ほとんど貯めていませんでした。ですが、年金が減るとか、老後破綻などの話を聞くうちにだんだんと将来が不安に思え、老後資金を今からしっかり作らなくてはと思ったのです。そのため1年ほど前からiDeCoを始めています。貯金よりもかなり利回りがよく、効率が良いと感じました。このままいけば貯金をするよりも、投資で老後資金がしっかりできるのではないかと自信が持てた
外貨建て年金保険に加入を検討する41歳独身女性。メリット・デメリットは?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、41歳、公務員の女性。外貨建て年金保険に加入を検討していますが、ベストな選択か迷いがあるそうです。改善点はあるのでしょうか? FPの鈴木さや子氏がお答えします。外貨建て保険で70歳から年2万ドルもらえるように計画しています。しかし、年金の免除申請期間が長かったことや、奨学金返済800万(育英会の借金は優良な投資だと思っています)に加えて、突発的な浪費癖もあり、今のプランが正解なのか不安があります。ガン家系ということもあり、健康保険も入るべきとは思いつつ、決めきれずにずるずると40 歳を超えてしまいました。ベストな選択が出来ているかどうか、改善点はどこか、プロの見立てを教えていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。【相談者プロフィール】女性、41、準公務員、未婚子どもの人数:なし同居家族について:なし住居の形態:賃貸毎月の世帯の手取り金額:32万円年間の世帯の手取りボーナス額:140万円毎月の世帯の支出の目安:22【毎月の支出の内訳】住
子どもをインターナショナルスクールに入れて留学もさせたいが、いくらかかる?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、33歳会社員の女性。現在第一子を妊娠中の相談者。子どもには可能な限り海外で活躍できるような教育をしてあげたいが、どのくらい費用がかかるのか心配とのこと。FPの山本節子氏がお答えします。子どもの教育費について相談させてください。夫婦とも産まれる子どもに、可能な範囲で教育を受けさせたいと考えております。今年結婚をし、現在第一子を妊娠中で、今後授かれたら子どもは二人を希望しています(できれば3年以内)。子ども一人あたり、どの位の金額を教育費としてかけれるものか検討がつかず悩んでおります。主人は将来海外でも活躍出来るように、可能なら早いうちからインターナショナルスクールに通わせたり、海外の学校に入れたい希望があるようですが、私自身は高額なため無理ではないかと思っています。私としては、家族の生活や老後の生活が無理なく送れる範囲で教育費をかけたいと思っています。家計をみて頂き、アドバイスを頂けましたら幸いです。以下、家計の補足や今後の支出の予定などを箇条書
iDeCo改正で何が変わる?59歳の人が後悔しないために知っておくべきこと
2022年5月よりiDeCoの加入年齢が65歳未満に
いまiDeCoの加入期間(掛け金を積み立てできる期間)は60歳までになります。加入期間が10年あれば60歳から老後の給付金として受け取ることができるわけです。しかし、現在加入中の59歳の人は、60歳で給付金を受け取ってしまうと後悔することになるかもしれません。2022年5月よりiDeCoの加入年齢が65歳未満に改正される点も考慮しつつ、「59歳で退職、企業型確定拠出年金をどうしたらいい?」といった悩みにファイナンシャルプランナーが答えます。
9月から厚生年金保険料が値上げ、影響あるのはどんな人?
報酬月額の平均が32等級に該当する場合
9月から厚生年金保険料が値上げになることはご存じでしょうか?新型コロナウィルスの感染拡大の影響で勤務時間の短縮や残業代がなくなり家計が厳しい人もいると思います。このような状況下で厚生年金保険料の負担が増えるのはどんなケースなのか?正しく理解しておきましょう。
ひろゆき「2つの“おいしい制度”も知らず、投資などするな」
「ラクの達人」が教えるお金の増やし方
「2ちゃんねる」など、日本のインターネット文化黎明期をリードしてきた「ひろゆき」さん。「投資で一発狙いたい」という人に、ある節税制度の名前を聞くと、「知らない」と答える人もいるという。「国が税的に“おいしい制度”を用意しているのに、その存在すら知らないなら、投資なんてしないほうがいい」と「ひろゆき」さんが語る、その制度とは何か? 前回に続き、彼の「お金」や「成功」の哲学を、著書『1%の努力』(ダイヤモンド社)から一部抜粋して紹介します。<撮影:榊智朗>
41歳、初めての自活へ「iDeCoとつみたてNISA拠出後手取り月13万」どんな未来図に?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、41歳、パート・アルバイトの女性。これまで家族のケアに時間を費やしてきたけれど、これからは実家を出て自活をはじめたいと言います。FPの鈴木さや子氏がお答えします。問題行動のある家族の対応に心身を削ってきました。やっと相応の支援に繋がり比較的落ち着いてきたので、もう自分を優先して実家を出る方針です。実家を出て行き詰らないか、賃貸か購入か、積立金額、全部悩んでいます。私は身体が弱く、手段を考えるも収入をなかなか増やせません。無理をして何度も身体を壊し、でもペースを守れば割と健康を維持できています。社会保険のあるパートをしています。自活が厳しい収入とはいえ、家族がストレスで安心して家にいられず、睡眠もままなりません。身体が資本、心身を壊してはどうしようもないとも痛感しています。その分貯蓄・運用はしてきました。現在、iDeCoとつみたてNISAを全額賭けています。収入に見合いませんが預金の一部を積立に回したいのと、時期的に今多めで後で調整するのはアリか
コロナ禍で生活が厳しくなって…年金の繰上げ受給をしても大丈夫?残念な結果にならないために
2022年に改訂後は、繰上げ受給の好機なのか?
コロナ禍で、生活費に困っている人が急増しました。失業者も増えています。また、夏のボーナスも大幅減になり、たぶん冬のボーナスはもっと期待できないかも。この状態が続くとかなり生活が厳しくなってきます。そのため、年金の繰上げ受給の相談も増えてきているそうです。本当に生活ができないという状態ならば、繰上げ受給はやむを得ない事もありますが、年金の受給額が減ってしまい総額でみると損になることが多いので、くれぐれもよく考えた方がいいでしょう。とくに、会社に勤めている人は、注意が必要です。せっかく繰上げ受給をしたのに、その年金が支給停止になる場合もあります。しっかりと繰上げ受給について知ってください。コロナ禍で、さらに残念な年金の受け取りにならないようにしてください。
老後資金2300万が1年で200万減!定年後の家計をどう立て直す?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、再雇用で働く61歳男性。相談者の定年後、貯めていた老後資金が1年間で200万ほど減ってしまい、家計を改善したいとのこと。家計再生コンサルタントの横山光昭氏が運営する『マイエフピー』のFPがお答えします。定年後の支出が多くなっており、老後資金が予定以上に減ってしまいました。80代、90代に生活していけるのか、不安です。60歳で定年を迎え、今は再雇用で働いています。今の手取り収入は約18万円。当初の予定では、手取り月収に老後資金から5万円を補てんし、毎月23万円で生活費を収めたいと考えていました。住宅ローンは完済していますし、無理はないと思ったのです。65歳まで勤めたら年金受給が始まります。始めの1年は私一人の年金ですが、翌年には妻の年金も加わり、月にして約23万円の年金収入になります。毎月23万円の生活費に収められたら、老後資金は減ることなく、介護や医療費、旅行代などに回せると思っていたのです。ですが、私が再雇用で働き始めた後、妻が「家計簿も定年
年金制度が確定給付から確定拠出年金に変更!定年まであと10年弱でどう運用する?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、51歳、会社員の女性。会社の年金制度が確定給付から確定拠出年金に変更になり、どう運用すればよいのかお悩みとのこと。FPの坂本綾子氏がお答えします。会社員です。勤め先の年金制度がかわり、確定給付→確定拠出年金に変わります。勤続30年定年まで、あと10年切る段階でまとまった大金について、年金制度移換金としてその運用方を自分で決めなければなりません。このコロナ禍短期的に、また定年見据えた中で、どうすべきでしょうか?株式市場も実態経済とリンクしていないような回復ぶりに、一旦定期預金的なものに全額振り向け、徐々に債権株式にスイッチして、半額位を運用に回すことをイメージしております。【相談者プロフィール】女性、51歳、会社員同居家族について:両親、子ども2人(20歳、22歳)住居の形態:親の家で同居毎月の世帯の手取り金額:50万円ボーナスの有無:なし毎月の世帯の支出の目安:40万円【毎月の支出の内訳】住居費:15万円食費:10万円水道光熱費:なし教育費:1
個人型確定拠出年金「iDeCo」の賢い使い方、損しがちな勘違いとは?
FPの知っておきたいお金のこと
「個人型確定拠出年金はしていないけど、かわりに個人年金保険はやっています。」「会社に企業型確定拠出年金はあるけど、やっていません。代わりに米ドル建ての変額終身保険はやっています。毎月2万円です。」FPとして家計相談やライフプランの相談を受けてきて、本当にこういった声を多く聞きます。2001年に日本版401kとして確定拠出年金が日本にはじまってから、もうすぐ20年。今回は知ってとくするお金の制度として「個人型確定拠出年金」について解説します。
会社員は“税金弱者”、税理士が教える「節税」と「税制優遇制度」
別居の親も「扶養」できる
確定申告する機会がほとんどない会社員は「税金弱者」になりやすい、と「税理士YouTuberチャンネル!!」のヒロ税理士(田淵宏明)さんはいいます。しかし、会社員でもできる節税があります。有効活用できる制度もあります。その内容を聞きました。