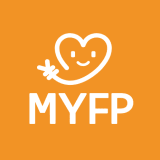4月から定年70歳延長に改正、社会保険や公的年金、お金の面で生活に影響する?
改正高年齢者雇用安定法について解説!
2021年4月からの改正高年齢者雇用安定法の施行を受けて、企業には従業員に70歳まで働く機会を確保する努力義務が生じることになりました。この改正で定年廃止や、70歳までの定年引上げ、再雇用を拡大するなど、上場会社でも「生涯現役」へと舵を切りはじめました。改正法では、少子高齢化で人口が減少していく中、働く意欲がある高齢者に活躍できる環境を整備することを目的としています。いったい改正高年齢者雇用安定法の施行で、私たちの生活にどのような影響があるのでしょうか。働き方が変わることによって、他の社会保険の制度や公的年金にどのような関わりが出てくるのか見ていきます。
働かなければ老後破綻!?私たちが“生涯現役”を迫られる理由
稼ぐべき額は意外と多くない
「老後に2000万円の資産の取り崩しが必要である」という金融庁の報告書が波紋を広げたことは、記憶に新しいでしょう。人生の3大支出が教育資金、住宅資金、老後資金と言われるように、多額の資金が必要とされる老後資金に関して、多くの人は不安に駆られます。人々が老後資金に対して漠然とした不安を抱く一方で、老後に実際にどれくらいの支出があって、どれくらいの収入を稼げばいいのかということはあまり認識されていないのではないでしょうか。拙著「統計で考える働き方の未来―高齢者が働き続ける国へ 」(ちくま新書)では、年金世帯の家計収支をもとに、実際にどれくらいの金額を稼げばいいのか提示しています。ここでは、その内容をもとに、年金世帯の家計収支を分析していきましょう。
年金受給開始まであと3年の61歳シングル「資産2200万円で老後は大丈夫?」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、61歳独身の会社員の方。現在再雇用で勤務中の相談者。悔いのない人生のために、来年退職を予定しているといいますが、老後資金は大丈夫でしょうか? また、いずれお母様の介護が必要になった場合はできる限り在宅で行いたいとのことです。FPの飯田道子氏がお答えします。 老後を迎える独身者です。令和2年3月に60歳で定年退職し、同じ職場に再雇用され2年目を迎えます。仕事中心の生活のなかでやり残してきたことがあり、後悔のない人生にしたいという気持ちが日に日に強くなり、来年3月で退職を考えています。気持ちは強いのですが、年金受給開始まで3年残っており、私の預貯金で老後が大丈夫か不安です。現在の収入からも貯蓄は続けており、月収入の余りは貯金と株購入に当て、ボーナスは現在はほぼ全額貯金しています。コロナ禍がなければ年20万ほどは旅行などで使うはずでした。現在預貯金で約1,600万、投資の内訳としては約500万を投資信託で運用し、その半分はNISA枠を当てています。残
確定拠出年金の受け取り方で老後生活が変わる!勤続19年58歳夫と53歳パート妻の場合
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、53歳、パートの女性。夫の退職まであと2年。企業型確定拠出年金に加入しており、受け取り方法が一時金、年金、併用と選べる中で、どのように受け取ったらよいかとお悩みです。FPの坂本綾子氏がお答えします。 主人が60歳定年まであと2年です。退職金は一時金と年金401Kの併用が選べます。一時金は500万程度、401Kは1,000万程度の予定ですが、勤続年数が19年の為、一時金の非課税枠が少なく、受給方法をどうしたら良いか教えてください。定年後はそのまま嘱託で働く予定で年収300万程度です。60歳から個人年金が5年(年120万)と10年(年58万)が貰えます。公的年金は65歳から月18万弱です。高校1年の息子の教育費は別に用意するとして、60歳からの生活費は35万程度に抑えたいと考えています。【相談者プロフィール】・女性、53歳、パート・アルバイト、既婚・同居家族について:夫58歳、子ども16歳・住居の形態:持ち家(戸建て、千葉県)・毎月の世帯の手取り金
「つみたてNISA」と「iDeCo」のどちらを選ぶべき?長期投資で一番大切なこと
つみたてNISAとiDeCoのメリット
「つみたてNISAとiDeCoのどちらをやった方がいいの?」と思っている方は結構多いのではないでしょうか。いきなり冒頭から結論を言ってしまい申し訳ありませんが、基本的には両方やった方が良いと思います。ただ、「資金的に両方はちょっと……」という方もいるでしょう。両者とも同じ非課税制度ですが、中身は全く別物なので、違いを把握したうえで、自分にとって使い勝手の良い方を選ぶようにしてください。
老後破綻にならないために公的年金でやりくりするコツ、「減らない財布」を作るには?
余裕資金と公的年金で安泰
使ってもお金が「減らない財布」を手に入れたいと思いませんか? もしも、それがあれば、老後はまさに安泰ですね。じつは、老後生活における「減らない財布」というのがあります。それが「公的年金」なのです。偶数月には、2ヵ月分の年金が金融機関の口座に振り込まれます。これは、生きている限り一生涯続きます。まさに公的年金というのは、「減らない財布」と言えるのではないでしょうか。しかし、残念ながら年金の受給額だけでは生活費としては少ないと感じる人が多いのではありませんか?ところが、考え方を変えるだけで、老後破綻にならない「減らない財布」を持つことができるのです。
66歳、貯金300万「老後資金を増やすために投資を始めたい」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、66歳、パートの女性。現在貯金が300万円ほどという相談者。リフォームなど、今後も出費が見込まれるなか、投資をして老後資金を増やしたいと言いますが……。家計再生コンサルタントの横山光昭氏が運営する『マイエフピー』のFPがお答えします。 これからの老後資金について相談させてください。現在66歳で、老人保健施設で働いています。子どもはみんな独立し、一人暮らしです。毎月の手取り収入は約17万円。マンションのローンも完済していますし、それで暮らすことができていたのですが、65歳になり月に約8万円の年金を受け取るようになったら、その分支出が増えたようです。貯金を増やすことを期待していたのに、この1年、全く増えることがありません。今の貯金は300万円ほど。マンションを中古で購入したので、もう少しでリフォームが必要になると思いますし、90歳、100歳と生きることになったら、老後資金が足りないと思います。その時に子どもの世話になるなどは、申し訳なくて考えられま
40歳独身、手取り年収410万「住まいを購入して老後資金も確保したい」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、40歳、公務員の女性。現在、宿舎住まいの相談者。ずっと宿舎に住めるかわからないため、住宅購入を検討しています。いくらくらいの物件なら老後資金もしっかり確保できるのでしょうか。FPの渡邊裕介氏がお答えします。 いくら位のマンションを購入するべきか相談したいです。公務員(医療職)で宿舎にいるため家賃が安くその分貯金にまわすことが出来ています。ただし、今後は公務員としての身分が保証されるかわかりません。また収入も減少する可能性があります(合併や買収の可能性があるため)。そこで、今のうちに住宅購入を検討した方がいいかと思いました。30代で現在の仕事に就職したため年金も少ないのではないかと気になります(20代は国民年金のみ、30代より厚生年金に加入)。老後の資金をある程度残せる住宅購入をしたいです。シングルですので1〜2LDKで2,000~3,000万あたりを検討しています。ご助言をよろしくお願いします。【相談者プロフィール】・女性、40歳、公務員、独身
「年金」繰下げ受給は“税金・社会保険料が高くなるから損”という間違い
繰下げ受給の「損」「得」について
老後の生活費というのは、年金の受給額で大きく変わってきます。約5割以上の人が、年金の収入だけで暮らしています。残りの人は、年金以外にも収入があると言うことです。とはいっても、残りの人たちも収入の内訳をみると、総収入の約8割が年金です。つまり老後の生活には、年金の受給額が、大変重要だということになります。そうであれば、年金の受給額を少しでも増やしておきたいですね。そこで、考えられるのが「繰下げ受給」です。しかしながら、一部のネットや雑誌で、「年金を繰下げ受給すると損になる!」という内容の記事を見かけます。その根拠となるのが、「年金を繰下げ受給すると税金や社会保険料が上がって損になる」と言うことです。さてそれは、本当でしょうか?今回は繰下げ受給の「損」「得」について考えましょう。
アラサーカップルの不安「出産で給与が減っても60歳2000万を達成できる?」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、28歳、会社員の女性。婚約者とともに、60歳2,000万円を目標にコツコツ積み立て投資を行っているという相談者。今後もし、出産・育児のために給与が減っても目標を達成できるか知りたいとのこと。FPの秋山芳生氏がお答えします。 老後の資金形成のために、つみたてNISA3万3,333円/月とiDeCo¥5,000円/月をコツコツ積み立てしています。60歳のときに2,000万円を目標に、まだ20代のためリスクを取って国内・海外株式中心に年率5%程度の運用で行っています。年齢が上がるにつれて、ローリスク商品に入れ替えていこうと思っています。今は自分の給与から積み立て出来ていますが、今後出産・育児により給与が減り、出費が増えて積み立てが出来なくなる可能性があります。一時的に積立をやめた場合であっても、目標達成できるか知りたいです。また何年間であれば、積み立てをストップしても問題ないか教えてください。 【相談者プロフィール】・女性、28歳、会社員、既婚・同居
企業型確定拠出年金、会社をやめたらどうなる?iDeCoとの違いは?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、25歳、会社員の女性。会社の確定拠出年金に入っている相談者。もし会社をやめた場合にどうなるのか、iDeCoのほうがいいのか、また、何十年と続けていけるかも心配だそうです。FPの秋山芳生氏がお答えします。 20代会社員です。会社の福利厚生で拠出型企業年金保険に入ったのですが、あとから会社を辞めると中途解約をしなければならず、元本割れのリスクがあることに気づきました。今のところ会社を辞める予定はありませんが、正直何十年と続けていけるかわかりません。今すぐやめてiDeCoに切り替えた方がいいでしょうか?【相談者プロフィール】・女性、25歳、会社員、独身・同居家族について:父:会社員・住居の形態:親の家で同居・毎月の世帯の手取り金額:15万円・ボーナスの有無:なし・毎月の世帯の支出の目安:10万円【毎月の支出の内訳】・住居費:2万円・食費:2万円・通信費:3,000円・お小遣い:5万3,000円・その他:5,000円【資産状況】・毎月の貯蓄額:2万円・
あと1年で年金を受け取る人が事前に準備すべきこと、知らないともらえる額が変わる場合も
損をしないために知っておこう
来年から年金の受け取りとなった人は、しみじみするかもしれませんが、手続きはきちんとしなくてはいけません。とはいえ、初めてのことなので何をすればいいのかわからない人も多いと思います。年金は請求しないと受け取れませんが、それに加えて事前に理解して対処しておくことで、受け取る年金額が変わることもあります。今回はあと1年で年金を受け取ることができる人向けに、何を準備しておかなくてはいけないのか、何を決めなくてはいけないのかなど、損しないために知っておくべきことをお伝えします。
30代独身「つみたてNISAと毎月の貯金の比率はどれくらいが理想?」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は36歳、会社員の女性。上手に資産形成していくには、つみたてNISAと毎月の貯金をどれくらいの比率で積み立てていけばいいのか知りたいとのこと。FPの高山一惠氏がお答えします。 毎月2万円ずつ、つみたてNISAと積み立て貯金に入金していますが、つみたてNISAを上限いっぱいにして積み立て貯金を減らしても大丈夫なのかを知りたいです。また、個人年金保険も気になっているのですが、始めた方がいいのかなど、アドバイスをお願いします。【相談者プロフィール】・女性、36歳、会社員、独身・住居の形態:賃貸・毎月の世帯の手取り金額:17万円・年間の世帯の手取りボーナス額:40万円・毎月の世帯の支出の目安:15万円【毎月の支出の内訳】・住居費:5万3,000円・食費:2万円・水道光熱費:1万円・教育費:5,000円・保険料:6,000円・通信費:7,000円・車両費:5,000円・お小遣い:3万円【資産状況】・毎月の貯蓄額:4万2,000円・ボーナスからの年間貯蓄額:2
昨年スタートの「高等教育の無償化」。対象になる収支バランスを知りたい
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、58歳、会社員の男性。50歳の時に娘を授かったという相談者。「高等教育無償化」の対象となるための収支のバランスが知りたいといいます。60歳からはアルバイトとして働きながら、年金の繰り上げ受給もしつつ生計を立てる予定です。FPの三澤恭子氏がお答えします。50歳のとき娘を授かりました。60歳で一応の定年を迎え、そこからは70歳まで同じ会社でアルバイトになります。働く日数と収入は一年ごとにフレキシブルに選択でき、手取り年50万から250万までです。家内は専業主婦で(これは譲れません)、娘に寄り添って教育しているので算国理とも2学年上の課程が終わっています。なので、塾は大学まで不要です。公立を念頭に、住民税非課税で「高等教育の無償化」を利用するため繰り上げて年金をもらいつつ、やり繰りする上でどう収入と支出を組み合わせるのが良いでしょうか。持病があり、60歳以降はなるべく勤務量を減らしたいです。子が独立したら月15万もあれば暮らせます。【相談者プロフィー
義父母と同居の妻「家の維持費や教育費で老後資金が貯められない」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、47歳、会社員の女性。義父母と夫、高校生と大学生の子どもと暮らす相談者。教育費や自宅の維持費、車の購入費などの特別費で出費がかさみ、老後費用を貯められないそうです。FPの氏家祥美氏がお答えします。老後のためにお金を貯めたいのですが、なかなか貯められません。夫が自営業で退職金もなく、将来は国民年金です。私はパートから正社員に転職して一年未満です。義父母と同居しているので、将来は介護が必要になり、私が仕事を辞めなければいけないかもしれません。子どもの大学費用は学資保険で準備していますが、それ以外の貯金が少ないです。定期的に車の購入や、家の修繕、子ども資金で、まとまったお金が出ていくためです。将来子ども達が独立しても、子どもの助けは借りられません。借入金はありませんが、毎月の出費が多く、貯金が貯められません。持ち家の建坪が大きく、光熱費が高いです。自営業のため、保険費も高いです。今後、老後資金としてどのような準備をしておけばよろしいでしょうか。将来に
退職一時金を受け取るとiDeCo受け取りは課税対象になってしまうの?定年前後で気をつけたいこと
退職所得控除の確認を
定年前後のお金の悩み、今回は退職金とiDeCoの税金のかかり方についてお伝えします。「会社からの退職金を60歳で受け取り税金の控除を受けた場合、61歳で受け取るiDeCoは課税対象となってしまうのでしょうか? だとしたらiDeCoの掛け金を減らした方がいいのでしょうか」と悩まれている相談について、考えていきます。
60代で知っておくと「得する手続き」とは?年金、健康保険、雇用保険ですべきこと
手間を惜しまずしっかりと
60代というのは、定年退職の時期でもあり、年金などの支給が始まる年代でもあります。このため、この時期には、さまざまな手続きが必要になってきます。これらの手続きは、会社任せでなく、自ら行わなくてはいけないことが多いのです。しかし、手続きは面倒だからと言って、後回しにしてはいけません。それぞれに期限があります。手続きが遅れたから、「損」をすることだってあります。逆に手続きをすることで、「得」になることもあるのです。60代で行う手続きで定年退職に関することを含めて「得」をする手続きについてまとめてみます。
早期退職金1200万が数年で半分に。完全リタイア後の生活が不安な62歳
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、62歳、再雇用で働く独身の方。50代で早期退職し、退職金1,200万をもらったけれど、半分ほどまで使ってしまったという相談者。現在も貯金から補填する生活を送っており、完全リタイアした70歳以降の生活が不安だと言います。家計再生コンサルタントの横山光昭氏が運営する『マイエフピー』のFPがお答えします。 再雇用で働いている62歳です。80歳、90歳まで生きるとすると老後資金が足りなくなると思うので、どのようにやりくりしていけばよいかを教えてください。50代で早期退職をし、退職金を1,200万円ほどもらいました。まだ若かったのでほしいものがたくさんあり、そのお金で高級時計やバッグを買いました。また旅行にも行ったりして、残ったのが690万円ほど。その後は、60歳を過ぎても長く働ける今の会社に再就職しました。60歳以後は再雇用として、委託社員の扱いで働き、給与は50代より3割ほど減って手取り20万円半ばほどです。毎月は赤字でなんとか暮らしており、貯金を増