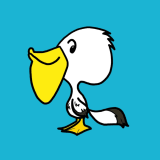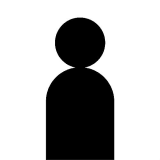新着記事
【NISAで一生モノ】株主優待と配当金も!ひと粒で2度おいしい2026年1月の欲張り銘柄3選
配当と株主優待のバランス銘柄
「一年の計は元旦にあり」と言いますが、投資の世界では「一年の計は『1月の銘柄選び』にあり」かもしれません。新NISAの成長投資枠を活用するなら、株価の変動に一喜一憂せず、「持っているだけで嬉しい」と思える銘柄をポートフォリオの土台に据えるのが王道です。配当金という「実益」と、優待品という「楽しみ」の両輪があれば、長期保有のモチベーションはぐっと高まります。今回は、安定感抜群の配当銘柄から、生活を豊かにする優待、そして2026年だけの特別な「お楽しみ」を用意している銘柄まで、バラエティ豊かな3社をご紹介します。 新しい年の投資初め(ぞめ)として、あなたの資産に彩りを加えてみませんか?
子ども向けNISA構想をきっかけに考える、子どもの将来のための投資
「お金を残す」よりも「選択肢を残す」ために、親ができること
子どものための投資は「増やすこと」より「選択肢を残すこと」が重要です。新NISAや子ども向けNISA構想が注目される一方、教育費をすべて投資で賄うのは現実的ではありません。資金の役割を分け、家族全体で資産設計と金融教育を考える視点が求められます。新NISA・子ども向けNISA構想を踏まえ、親として考えたい投資の向き合い方を解説しました。
国際観光旅客税の引き上げ、「106万円の壁」撤廃…2026年下半期の【お金のイベントカレンダー】
手取りに直結の変化が続く
1年の中でも、下半期がはじまる時期の6月末~7月にかけてはボーナス時期真っ盛り。まとまった収入で財布の紐が緩みがちなタイミングです。また、それ以降は夏休みやシルバーウィークなどの大型レジャーが重なり、出費がかさむ時期でもあります。年初に下半期のイベントをイメージし、今のうちから月ごとの予算をしっかり立てておくことで、後半戦で焦ることなく過ごすことができるでしょう。結果、「準備しておいてよかった!」と実感できるはずです。ここでは、2026年後半の家計管理に役立つポイントと、押さえておきたいお金のイベントをみていきましょう。
子どものお年玉、親が管理していると課税対象になる可能性も…「名義預金」とみなされないために注意すべきこと
お年玉や児童手当はどう管理する?
子どもの名義で口座を作り、「いつかこの子のために」とお年玉や児童手当をコツコツ貯めている親は少なくありません。その思いはとても愛情深いものですが、実はその貯め方や管理の仕方によっては、税金面で問題になることがあります。一方で、ルールを正しく理解しておけば、将来の資産づくりだけでなく、子どもの金融教育にもつなげることができます。今回は、未成年への贈与や名義預金の考え方を整理しながら、家庭でできる金融教育についてもお伝えします。
「178万円の壁」への引き上げ、住宅ローン控除の延長、出産費用の保険適用…2026年上半期の【お金のイベントカレンダー】
家計に大きな影響を与える制度改正が続く
2026年は、長引く物価高にどう立ち向かうかが家計の命運を分ける年になります。2025年(令和7年)11月分の消費者物価指数では、総合指数が前年同月比で2.9%上昇、生鮮食品およびエネルギーを除く指数も3.0%上昇しており、生活のあらゆる場面でお金の重みが変わっていることを示しています。こうした「インフレ時代」を生き抜くには、社会の動きを先読みし、攻めと守りの両面から家計を整えることが不可欠です。今回は、2026年上半期に予定されている制度変更や家計の重要トピックを時系列でまとめました。新しい1年の資産を守り育てるためのヒントとしてぜひご活用ください。
「国策に売りなし」2026年の主役株20テーマから5つを厳選! 有望相場の本命を探る(前編)
国策を追う
2025年、日経平均株価は1月の3万9000円台から、11月には5万2636円まで大幅に上昇しました。1月から4月にかけては、「トランプ関税」の影響で3万円ギリギリの水準まで下落したものの、そこから「半導体関連株」を中心に急反発。上場来高値の更新を続けました。2026年は、どのようなテーマが注目されるでしょうか。ここでは、2026年注目の2つのテーマを深掘り。後編では、3つのテーマに加えて、株式相場が抱えるリスクなどについて検証します。後編:株価数倍の「スター銘柄」候補は? 防衛・サイバー・半導体特需に潜む「2026年の主役」を探す
退職金・DB・DCの「手取り」を最大化する受け取り方とは? 知っておきたい税金の仕組み
賢い税制活用と老後資金の考え方
定年が近づくにつれ、退職金の使い道をあれこれ考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、退職金にかかる税金の仕組みを知らないとせっかくの計画も台無しになってしまいます。今回は退職一時金、DB(確定給付企業年金)、DC(企業型確定拠出年金)と複雑化する退職金と税金について整理します。
2026年「午尻下がり」にどう備える? 来年の戦略として注目したい「高配当ETF」
相場の転換期に備える投資術
2025年も残すところあと4日となりました。この1年を振り返ると、金融市場は活況を呈しました。先週にはS&P500とニューヨークダウが過去最高値を更新。日経平均株価も2024年末から約25%上昇し、3年連続の2桁プラスという力強い足取りで終えようとしています。年後半はゴールド(金)を筆頭に、銀、プラチナ、パラジウムといった商品市況も高騰しました。投資信託の上昇率でも、ゴールド関連ファンドが1位となっています。しかし、2026年を目前に控え、投資家は少し気を引き締める必要があるかもしれません。
火災保険は建物だけで十分?
実は見落とされがちな家財の補償
火災保険の相談をしていると、「火災保険は建物だけでいいですよね?家財はいりませんよね?」という質問をよくいただきます。家財保険は日常生活に溶け込んだ持ち物の保険なので、普段はあまり意識されず、必要性を感じにくい人が多いようです。しかし実際には、災害や事故のあと、生活を立て直すために欠かせない補償でもあります。今回は、家財保険が必要な理由や、補償金額の目安を詳しく解説します。
「お金=見えない数字」になっていない? キャッシュレス世代の子どもに“価値の重み”を教える、家庭での解決策
週に1回の「アナログ習慣」
ある日、子どもたちのおままごとの様子を見て、筆者は思わず笑ってしまいました。「お支払い方法は?」「PayPayで!」「ではこちらのQRコードを読み取ってください」スマホ操作を誘導する流れまで完璧で、まるで本物の店員とお客さんのようです。思えば、私たち大人も現金を使う機会がめっきり減りました。スーパーやカフェ、コンビニでもスマホをかざせば支払い完了。財布の中身を確認することも、硬貨を数えることもほとんどありません。子どもたちにとっても「お金を払う=スマホをかざす」という感覚が当たり前になりつつあります。そして今、そんな“現金に触れない世代”の子どもたちにとって、どうすれば「お金の価値を感じる力=金銭感覚」を育てられるのかが、親世代にとって新しい課題となっています。
あなたの老後に2000万円は必要? 平均ではなく「わが家はいくら必要か」を考える
暮らしから必要額を考える
老後資金について、2019年にいわゆる「老後2000万円問題」が大きく話題になりました。夫婦世帯が年金だけで暮らした場合、長期的にみると生活費が不足する可能性がある、という内容です。ただ、この話題から時間が経ったことで、「とりあえず2000万円必要」「なんとなく不安」といった形で、数字だけが記憶に残っているケースも少なくありません。しかし、老後資金は、住まい・働き方・家族構成・健康状態・暮らし方など、それぞれの前提によって必要額が大きく変わります。老後資金は「平均いくらか」ではなく、「わが家はどのくらい備えると、安心して暮らし続けられるか」という視点で考えることが大切です。本記事では、今の暮らしから必要額を考えるための視点を整理します。
なぜ今「ダウの犬」なのか? 配当と安定性を重視する王道戦略の注目10銘柄
高配当よりも“続く配当”を重視する、安定志向の考え方
短期的な値動きに振り回されず、配当と安定性を重視した投資を考えたい局面が続いています。そうした視点で改めて確認したい戦略が「ダウの犬」です。ダウ平均30銘柄の中から配当利回りの高い10銘柄を選び、1年間保有するというシンプルな戦略をもとに、本稿では2025年時点の予想配当利回りから各銘柄の特徴と位置づけを整理します。
12月で健康保険証が廃止に! まだ対応していない人はどうすればいい?
マイナ保険証への切り替え完全ガイド
12月2日以降、「病院で保険証が使えなかった」「窓口でマイナ保険証を出すように言われた」という声がSNS上で急増しています。中には「知らなかった」「まさか本当に使えなくなるとは思わなかった」という困惑の声も少なくありません。これは、2024年12月2日から従来の健康保険証の新規発行が停止され、2025年12月1日をもって完全に廃止されたことによる制度変更です。つまり現在、これまでの健康保険証では医療機関での受診ができず、マイナンバーカードを保険証として利用する「マイナ保険証」、または「資格確認書」が必要です。「保険証がない=医療を受けられない」というわけではありませんが、手続きが済んでいない人は早急な対応が必要です。特に気温も冷え込んで体調を崩しやすいこの時期、いざという時に慌てないよう、今のうちに準備を整えておきましょう。
年収が高いのに貯まらない人、年収が低くても貯まる人「貯まる家計」の3条件
「貯まる家計」の本当の条件
「年収が高いのに貯まらない」「年収が低くても堅実に貯めている」。家計調査を見ると、年収1000万円でも貯蓄ゼロ世帯が存在する一方、年収300万円台でも数千万円以上の金融資産を持つ家庭もあります。違いを生むのは、収入額ではなく支出と負債の構造です。年収では測れない家計を整えることこそ、豊かさへの第一歩です。金融資産が少ない家計のパターン3つと、貯まる家計になる3つの条件をお伝えします。
冬の「光熱費」と「カビ」を同時に撃退! 今すぐできる窓の断熱&換気術
暖房代を上げずに暖かく
この時期は「暖房をつけても部屋が暖まらない」「窓の結露がひどくてカビが心配」といった、冬の家事に関する悩みがある人もいるのではないでしょうか。本格的な冬を迎え、光熱費の請求額が跳ね上がりやすい時期です。そこで今回は、暖房の設定温度を上げることなく、家の冷え込みを根本的に解消し、さらに冬特有の悩みである結露やカビを同時に予防する、実践的な対策を解説します。
クレジットカードは有料、無料どう選ぶ? 年会費ありのカードを選ぶなら確認したい4つのポイント
「持つ・持たない」の判断基準
キャッシュレス化の拡大とともに、クレジットカードは“支払い手段”から“お得を生むツール”へと進化しています。最近では、年会費を払ってでも持つ価値がある「高付加価値カード」の人気が高まっています。とはいえ、「無料カードでも十分?」「有料カードで元が取れる?」と悩む声も少なくありません。この記事では、有料カードを選ぶための条件や判断のコツ、無料カードとの違いを具体的なカード事例とともに解説します。
高級腕時計が好調な「シチズン」と「セイコー」の株価が急上昇、なぜ2社は伸びている?
どちらが割安といえるか
デフレ時代が長く続いた日本でも、ここ数年でインフレ時代へと突入しつつあることを痛感するようになりました。数ヶ月単位で物価が上昇していく中、賃金上昇のスピードは追いつかず、必然的に節約志向が強まります。外食を控えたり、サブスクを見直したりする動きが広まる中、じつは高級腕時計の需要は堅調です。国内2大時計メーカー、セイコーグループ(8050)と、シチズン時計(7762)の株価もここにきて急上昇しており、注目が集まっています。高級腕時計には手が届かなくとも、投資家としてその恩恵には預かりたい。となるとどちらが魅力的でしょう?
60代前半、「お金のため」だけでは続かない——定年後も満足して働く人の共通点
セカンドキャリアの準備をしていますか?
「何歳まで働けば安心ですか?」「いくらあれば老後は大丈夫ですか?」そんなご相談を受ける機会が増えています。仕事・健康・人間関係など、あらゆる面で変化が訪れる60代前半。定年後研究所の最新調査によると、この時期は仕事満足度が大きく下がる一方、人生満足度を高く保つ人には共通点があることがわかりました。今回は、FPとして多くの相談を受ける立場から、定年後をどう働き、どう生きるかを考えるヒントをお伝えします。