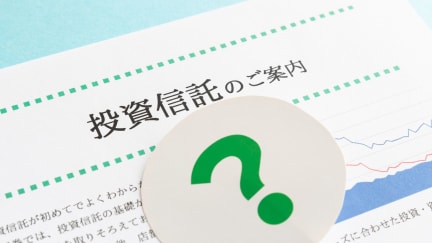この春新登場!金融アナリストが注目するETFと投資信託3選
各社が次々とリリース!
2024年に新NISAがスタートし、各社が次々と魅力的でユニークな投資信託やETFをリリースしています。またコスト面でも熾烈な争いが起こっているようです。投資家としては良い選択肢が増えていくのはありがたいことですね。今回はこの春に新規上場、新規設定されるETFや投資信託で皆様にぜひ知っていただきたい商品を3つご紹介いたします。
みんな【新NISA】で何を買っている?成長投資枠の人気銘柄も予測
口座数は約1400万件に!
2024年3月に日本証券業協会(日証協)から、NISA口座の開設及び利用状況が公表されました。日証協が大手証券10社(大手5社、ネット5社)を対象に2月末時点の状況を集計したものです。証券会社10社(大手5社・ネット5社)の2024年2月末時点のNISA口座数は約1400万口座となっています。2024年2月におけるNISA口座の新規開設件数は53万件であり、2023年1~3月におけるNISA口座増加数(1か月平均)18万件と比較 すると、約2.9倍に増加しています。 2024年1~2月における買付額(1か月平均)は、成長投資枠1.5兆円、つみたて投資枠2700億円であり、2023年1~3月における買付額(1か月平均)と比較すると、成長投資枠で約3.3倍、つみたて投資枠で約3倍に増加しています。
金融アナリストが教える!新年度から始める資産形成のスタートアップガイド
安定した利益を出すための基礎知識
新年度がスタートしましたね!新たなことにトライされる方も多いのではないでしょうか。また将来を見据えてこの機会に投資を含む資産形成のスタートを切る方もいらっしゃるかもしれません。大学生でも新NISAが活用できることもあり学生投資家も増えているようです。今回は少額から始められる投資による資産形成の方法や投資の基本、将来のための準備などを紹介します。投資初心者が長期的に安定したパフォーマンスを出すための投資方法として、まず、「定期積立投資とドルコスト平均法」と「インデックスファンドへの投資」という方法が挙げられます。
【新NISA高配当株投資】暴落や下落相場に負けない、配当生活を続けるための技術
株の売却を考える3つのタイミング
新NISAで高配当株投資を行えば、税金が一切かからずに、「配当金」という形で不労所得が入ってくる仕組みをつくることができます。もちろん、値上がりして売却した場合の利益も非課税です。目下、日本株も米国株も好調をキープしていますが、ときに暴落が起こるのもまた相場です。過去には、ITバブルの崩壊、リーマンショック、コロナショックなど暴落相場があったことも事実です。今後も大きな暴落や下落相場が来ることもあるでしょう。そんな時、新NISAで高配当株投資を行っている場合は、どう乗り越えていけば良いのでしょうか。一緒に考えていきたいと思います。
騰落率、分配金利回り…投資信託の収益率を示す数字は?
金利のしくみ(10)
今さらの話で恐縮ですが、2024年から新NISAがスタートしました。特に資産形成層の方は、つみたて投資枠を活用して投資信託を積み立ててこうなどと考えているのではないでしょうか。その投資信託の収益率を示す数字について解説します。
すべての人がオルカンに投資すべきではない? 【新NISA】の投資戦略
オルカンはリスク許容度が高い人向けの商品である
新NISAのスタートで投資信託に個人マネーが流入しています。なかでも人気を集めている投資信託が、三菱UFJアセットマネジメントが運用している「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」(オルカン)です。ただ、中には「新NISAではオルカンを買っておけばOK」などと言われ、とりあえず買っている人もいるのでは。本当にオルカンだけで大丈夫なのでしょうか。そもそもすべての人にとってオルカンが良いのか、という問題もあります。今回は、オルカンの人気の背景、オルカンは誰にでもおすすめできる商品なのかを、新NISAの投資戦略とともに一緒に考えてみましょう。
【新NISA】一般口座、特定口座どちらを選べばいい? NISA口座開設でつまずきやすいポイント4つ
意外と大きな関門「口座開設」と「入金」
新NISAを始めてみようと思ったものの…意外とつまずくことが多いのが、口座開設です。「言葉が難解で、どうしたらいいかわからない」「何を選べばいいかわからず、先に進めない」という声もよく聞きます。そこで、NISA口座を開設する際によくあるつまずきポイント4つと、そのクリア法を解説します。
今をときめくハイテク株に投資したい人にぴったりのETFと投資信託4選
新NISAにも対応!
ハイテク株とはハイテクノロジー企業やテクノロジー関連企業の株式を指します。これらの企業は、最新の技術やイノベーションを活用して商品やサービスを提供しており、成長性や収益性が期待されることから、投資家の注目を集めています。
「とりあえず」継続雇用ではない暮らし方、老後をどこまでイメージして準備したら良いのか
老後は、これまでできなかったことに取り組める時間である
NISAやiDeCoといった税制優遇制度を老後資金用に活用している方も多いかと思いますが、そもそも老後をどこまで具体的にイメージして準備したら良いのでしょうか? 今回は海外のリタイアメント事情も踏まえ考えてみたいと思います。
新NISA【成長投資枠】で個別株銘柄選びの参考にしたいETF3選
チャートチェックの技術も紹介
個別株の銘柄選び、何から選ぶのか迷いますよね。雑誌、SNS、YouTubeなど今は情報がたくさん溢れていて、欲しい情報がすぐに手に入る良い時代であると同時に、自分で情報の良し悪しを見分ける力も必要とされています。今回は銘柄を選ぶ前にやっておくべきこと、そして具体的な銘柄の簡単な選び方の一つの方法をお伝えします。
高配当株式ファンドへの投資で気をつけるべきことは? チェックしておきたい5つのポイント
保有コストの高さには要注意
2023年12月12日に設定・運用が開始された「SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」が投資家の人気を集めています。SBIグローバルアセットマネジメントのリリースによると、設定後わずか36営業日で純資産総額が400億円を突破。これは2023年以降の主要ネット販売会社販売ファンドで最速とのことです。新NISAでは無期限で非課税の運用ができることから、高配当株に人気が集まっています。そんな高配当株に手軽で分散投資できる高配当株ファンドへの投資で気をつけるべきことをお伝えします。
SBI、楽天、マネックス…新NISAで自分に合った口座はどう選ぶ?
絶対外せない3つのポイント
2024年にスタートした新NISAは、大きな盛り上がりを見せています。日本経済新聞によると、2024年1月の新NISA口座経由の購入額は1.8兆円。旧NISAの3倍ペースだというのですから驚きです。そんな新NISAを始めるには、金融機関に口座開設する必要があります。しかし、新NISAは1人1口座のルール。新NISAができる金融機関はたくさんあるので「どこでスタートするのがいい?」と悩んでしまう方もいるでしょう。今回は、自分に合った新NISA口座の選び方を一緒に見ていきましょう
【新NISA】定年前後はどんな投資商品を選ぶのがいい? 確定拠出年金とNISAの出口の違い
出口を見越した商品選びが重要
新NISAの登場で、いよいよ日本人の行動が「貯蓄から投資」へ大きく変容している様を感じられるようになりました。投資は時間を味方につけるのが鉄則ですが、今回はそろそろ老後を考える定年前後の方の投資商品選びをお伝えしたいと思います。
新NISA成長投資枠で買える銘柄も!少額から投資できてリターンに期待できるアメリカの最強ETF3選
経費率の低コストも魅力
日経平均株価が史上最高値を34年ぶりに更新しました。 私は直近で東京、大阪、名古屋、豊橋、仙台など対面セミナーで登壇させていただいていますが、投資への関心の高まりを肌で感じています。その中で、「せっかく投資をするなら全世界株式(オール・カントリー)やS&P500だけではもったいないでしょうか…?」というご意見もよく耳にします。そこで今回は、少額から投資できる低コストな米国ETFを3つご紹介します!
【新NISA】を利用して不動産オーナーになれる? もうひとつの投資先「REIT」とは
NISAならではのメリット
新しいNISAは、これまでの一般NISAとつみたてNISAを合体させた形になったことから、投資のバリエーションがかなり増えたといえます。今回はNISAを利用して不動産に投資する方法をご紹介します。
【新NISA】毎月いくら積立するべき? 家計簿なしで積立額を決める方法
新NISA活用のファーストステップ
2024年からスタートした新NISA。この機に投資を始める人からよく出るのが、「毎月いくら積立するべきでしょうか?」という質問です。そこで、「これまで毎月いくら貯金ができていたかわかりますか?」と尋ねるのですが、「よくわかっていません」と答えが返ってくることが珍しくありません。積立投資を始めるためには、まず初めに、現在の収入や支出、貯蓄の金額を把握することが大切です。そこでこのコラムでは、家計簿をつけていない人でも家計状況を確認できる方法を紹介します。その確認結果をもとに、新NISAの積立額を決めていきましょう。
【新NISA】オルカン以外の選択肢は何がある? 成長投資枠の使い道
ETFや日本の株式が選択肢のひとつ
新しいNISAが始まり、月々ムリのない金額で投資信託の積立を開始された方も多いようです。一方、年間投資枠360万円を使い切りたいとおっしゃる方も少なくなく、今回は「成長投資枠」をどう使うのかについて解説していきたいと思います。
【新NISA】楽天証券でお得に投資をする方法まとめ
クレカ積立は年会費無料のカードに軍配
投資をするときに、楽天証券を利用している方は多いでしょう。楽天証券は2023年12月には国内証券会社単体で1,000万口座を突破した、ネット証券最大手の一角です。そんな楽天証券での投資をお得にするにはどうすればいいのでしょうか。楽天証券で新NISAを利用することを想定して紹介します。