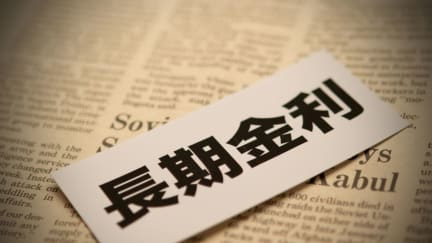FRB利下げ決定、さらなる株高の始まりか?2025年金融相場の行方
投資家は歴史に学び、利下げ局面でのリスクを見極める
FRB(米連邦準備制度理事会)は9月のFOMCで利下げを決定し、年内さらに2回の追加利下げが想定されています。インフレの沈静化や景気減速の兆しを踏まえた「政策転換点」ともいえる今回の判断。投資家にとっては株式市場への影響をどう見極めるかが最大のテーマです。本記事では、過去の利下げ局面を振り返りつつ、2025年の金融相場に潜むリスクとチャンスを探ります。
長期金利が1.6%を突破、今後も上がる?
なぜ国債を売る動きが強まっているのか
8月20日、日本の長期金利である10年物国債の利回りが1.6%を超えました。債券市場では国債を売る動きが強まっています。なぜ国債を売る動きが強まっているのか、長期金利の上昇は、どのような影響を及ぼすのでしょうか。
住宅ローン、銀行口座、資産運用の見直し…金利が上がった時に私たちがするべき5つのこと
金利上昇の恩恵を最大限受けるには
日銀は2024年12月の利上げを見送りましたが、2025年は政策金利0.75%を視野に入れているといわれています。しかし、金利が上がった時に、自分の生活にどう影響を受けるかわからない人も多いと思います。今回は金利が上がった時にやっておくべきことをいくつかお伝えします。
利上げで株価はどうなる?いまさら聞けない金利・為替・株価の関係
専門用語なしで解説!
金利、為替、株価は相互に関係しており、どれか一つが動くと他の二つにも影響を与えます。投資家はこの関係を理解していると、金利が下がる局面で株を買う、為替が円安になるタイミングで輸出企業に投資する、といった判断が可能となるなど、理に適った投資タイミングを掴むことができます。また逆に、金利が上がりそうな時に株式を減らし、安全資産にシフトするなど、効果的で戦略的なリスク管理が可能になると考えられます。そこで金利、為替、株価について3週連続で解説していきます。
マイナス金利が解除されたから…だけではない、金利の知識が必要な理由
金利のしくみ(最終回)
12回にわたって続けてきた「金利のしくみ」も、これが最終回です。今回は、どうして金利の知識が必要なのかについて、お話します。
「変動金利」「固定金利」それぞれ有利になるのはどんな時?
金利のしくみ(9)
お金の貸し借りを行っている期間中、市場金利の動向に応じて適用利率が見直されるか、あくまでも約定した時点の適用金利が継続されるかによって、「変動金利」と「固定金利」に分かれます。
最終利回り、所有期間利回りとは? 債券には4種類の利回りがある(パート2)
金利のしくみ(8)
債券には4種類の「利回り」があります。前回はこのうち「利率」と「応募者利回り」、「直接利回り」について解説しました。今回は、「最終利回り」と「所有期間利回り」ついて考えてみましょう。パート1:「応募者利回り、直接利回りとは? 債券にある4種類の利回り(パート1)
「複利効果」とは何か? 単利と複利の違いを構造的に理解してみよう
複利効果の正体
よく「複利効果」という言葉を目にすると思います。なぜこのような効果が生じるのかを、単利との違いは何なのか、などについて解説します。
住宅ローンを借り換えた方がいい3つの目安とは? 行動に移す際の注意点も解説
変動金利の住宅ローンは借り換えすべきか
日本では低金利が長い間続いています。住宅購入時に住宅ローンを選んだときには、あまりよく考えずに金利が低いものを選んだという人は少なくないでしょう。しかし、2022年12月に日銀が金融政策に修正を加えてから、2023年7月、11月と徐々に金利固定型の金利が上昇してくると、変動型を選んでいる場合は、将来の金利上昇が心配になっている人が増えています。また、住宅ローンを契約した時よりも今の金利が低い変動型のローン場合には、ローンを借り換えると有利なるのではないか思うこともあるでしょう。今回は、住宅ローンの借り換えにあたり、事前に知っておきたい注意すべきことを確認していきましょう。
あなたは答えられますか? 実はまったく異なる概念「利率」と「利回り」の違い
金利のしくみ(4)
利率と利回り。何となく同じもののように見えて、でもなぜ言い方が違うのか、不思議に思う方もいらっしゃるでしょう。でも、両者はまったく異なる概念なのです。
住宅ローン、固定金利と変動金利はどのような影響を受ける? 【長期金利】のしくみ
金利のしくみ(3)
前回、期間1年未満のお金の貸し借りに適用される「短期金利」について解説しました。今回は1年以上のお金の貸し借りに適用される「長期金利」です。前回記事: 預金や住宅ローンに影響はある?知っておきたい【短期金利】のしくみ
預金や住宅ローンに影響はある? 知っておきたい【短期金利】のしくみ
金利のしくみ(2)
金利には「短期金利」と「長期金利」があります。預金や住宅ローンの金利は、短期金利や長期金利の動きに左右されます。その違いはどこにあるのか、経済にどのような影響を及ぼすのかなどについて解説します。まずは短期金利をとり上げます。
長期金利の上限「1%をめど」に引き上げ、私たちの生活にどのような影響がある?
多くの人には短期金利の方が重要?
日本銀行が10月末に開催された金融政策決定会合にて大規模な金融緩和策を修正したことにより、日本の長期金利が上昇しています。ニュースを見ていると、日銀が金融政策を修正したことや、長期金利が上昇したことは目にする機会が増えたかと思いますが、それが具体的に私たちの生活にどのような影響を及ぼすのかを理解できていますか?今回は日銀の金融政策の修正や、それに伴う金利の上昇が生活に及ぼす影響を解説していきます。
なぜ「金利」は動く? 日本にようやく金利が生まれてきた背景
金利のしくみ(1)
日本は長年にわたって「金利」がありませんでした。1990年代に入ってから景気が悪化し、さらに物価が持続的に下落するデフレ経済に、長年の間、苦しめられたからです。それがここに来て、ようやく金利が顕在化してきました。今回から何回にわたって続けられるか分かりませんが、金利の基本について考えていきたいと思います。
日本株相場も下落…アメリカ政策金利の据え置きは市場にどのような影響を与えた?
米国株式市場は大幅続落
市場の注目を集めた9月のFOMC(米連邦公開市場委員会)は大方の予想通り、政策金利の指標であるFFレート(フェデラルファンド金利)の誘導目標を5.25~5.50%で据え置きました。しかし、同時に発表された経済見通しではFOMC参加者によるFFレートの予想中央値は2023年末時点で5.6%。今回は利上げを見送ったものの、年末まであと1回の利上げを示唆しています。FOMCは年内にあと2回、開催が予定されています。10月31日~11月1日、12月12~13日の残り2会合のどちらかで、利上げを行うことが適切と考えているFOMCメンバーが半数以上いるという結果がドットチャートで示されました。ここから市場はFRB(米連邦準備制度理事会)が利上げに固執する強固な姿勢を読み取りました。
住宅ローンの繰り上げ返済をするべき?事前に確認したい5つのこと
完済時期も要注意
例えばボーナスや、中途退職した際の退職金など、まとまったお金が入ったときに「住宅ローンの繰り上げ返済をしようかな…」と思うことがありませんか?「今は金利が低いから、あまり効果がないのだろうか」「いや、それでも大きなローンを抱え続けるより、少し軽くなったほうがよいのでは」と迷う人も多いかも。そこで、繰り上げ返済の検討をする際に、確認したいポイントを5つお伝えします。
日経平均が約33年ぶりに高値を更新したのはなぜ? 金利、企業業績、それ以外に考えられる要因
バフェット、PBR改善要請の影響か
日経平均がバブル崩壊後の高値を更新しました。その後も買いの勢いは衰えず3万1000円の大台も越え、1990年7月以来、約33年ぶりの水準まで上昇しました。日本株が急伸した背景として様々な要因を指摘できますが、まずはもっとも基本的なことを確認しましょう。
金利上昇によって不動産投資は終焉を迎えるか?日本の恵まれていた環境が変わりつつある背景を解説
金利上昇と不動産投資の関係性
もふもふ不動産のもふです。足元では金利上昇が見えてきており、「不動産の価格が下落するのか?」「不動産投資はもう終わりなのか?」といった質問をいただくことが増えました。不動産投資は、銀行融資がとても大切です。そのため借り入れの金利が上昇することによって、返済の金額が増えることにより、手元に残るお金=キャッシュフローが減少してしまいます。家賃収入を当てにしている不動産投資家にとっては、とても大きな影響です。不動産の価格がどうなるのか−−予想するのは不可能なのですが、個人的な予想としては、下記のように考えています。金利上昇したら一時的に不動産の価格が下落するが、その後インフレで不動産の価格は上がっていく不動産投資が終焉することはなく、時代に合わせた投資手法になっていく今回は、これら私の個人的な見解について、解説させていただきます。