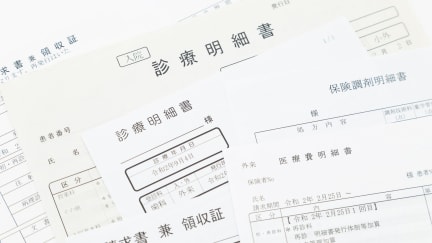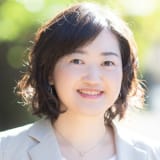都内で暮らす50代独身女性の平均年収や貯蓄額、生活費はいくら?【2023年版】
平均貯蓄額は高いものの…
50代は、自分自身の定年後にひかえるセカンドライフが視野に入ってくるとともに、親の介護が現実的になってくる人も多く、ライフスタイルの軌道修正の必要性が増してくる頃です。会社員の場合は50代半ばが収入のピークになる場合が多いのですが、60歳以降のことを考えて、暮らしをコンパクトにしていく方向での見直しを意識する人が増えていきます。そんな50代の都内で暮らす独身女性の、平均年収や貯蓄額、生活費はいくらくらいなのでしょうか。データをもとに見ていきたいと思います。
止まらない食品の値上げ…。着実に食費を減らせる5つの処方箋
買う・作るときのひと工夫がカギ
食品の値上げラッシュが続くなか、本気で食費の見直しをはじめる人も多いでしょう。代表的な節約法としては外食の頻度や予算を下げることが挙げられますが、もともと自炊中心の人だと、その効果は限定的です。そこで今回は、着実に食費を減らせる買い物やご飯づくりのコツを5つ紹介します。
都内で暮らす50代独身男性の平均年収や貯蓄額、生活費はいくら?【2023年版】
貯蓄ゼロが39.6%
キャリアを積み収入も安定、お金も時間も自由に使えるイメージの50代独身男性。一人暮らしが長ければ、生活にまつわる身のまわりのこともお手の物、自分なりのライフスタイルもできあがっているでしょう。そんな50代にとって、普段の暮らしに不自由を感じることはないかもしれません。しかし、定年退職の年齢が近づくにつれ、老後の心配が増えてくるのではないでしょうか。今回は、東京都内で暮らす50代独身男性の収入、貯蓄、生活費についてデータで見ていくとともに、老後への備えを考えます。
確定申告後に医療費の領収書がごっそり出てきた…訂正はできる?
申告期限に要注意
確定申告で医療費控除の適用を受けて、すでに還付金も受け取っている場合に、そのあとで、場合によっては数年たってから、申告漏れの医療費の領収書がごっそり見つかることもあります。「確定申告後に領収書がでてきてしまった」場合に、確定申告のやり直しが可能か、そしてその際の留意点についてお伝えしましょう。
その保険不要かも。結婚・出産・定年退職…ライフイベント別に保険を見直すポイントをFPが解説
ポイントをチェックし保険を考える
よく「保険はライフイベントごとに見直しましょう」と言われます。「見直し=加入し直す」と考えられがちです。これはある意味正しくもあり、誤りでもあります。見直すことは決して加入し直すことばかりではなく、加入中の保険が、ライフスタイルに合っているかどうかを見極めることが大切です。今回は、ライフイベントに対し適切な保険に加入しているか、その見極めるポイントについて解説いたします。
35歳会社員「妻に秘密の借金、子どもが生まれる前に返済したい」FPの回答は?
Vol.1:妻にバレずに借金を返済せよ
30代を迎えると昇進・転職、結婚、出産など、様々なライフイベントに直面するひとが多いはずです。この時期は「お金」にしっかりと向き合うタイミングでもあります。「貯蓄もしているし、余剰資金でNISAやiDeCoもばっちりです!」なんてひともいれば、「資産運用をまったくしていない…」「貯金がない…」「借金があります!」など状況はひとそれぞれ。本連載「30代から始める、まったく0から貯金し投資ができるまでの道」では、主人公の金前すすむさんの家計改善から貯金、そして投資までを、お金のプロのアドバイスを基に進めていく企画です。何やら「妻には知られていない借金がある」という、金前すすむさん。はたして借金を返済して、将来に向けて資産運用を始めることはできるのでしょうか。
もしお金のプロが新社会人だったら…。初任給22万、一人暮らしの投資戦略を考えてみた
金融資産への投資だけが投資ではない
4月より新社会人となる方、おめでとうございます。学生時代とはまた違う新しい環境で、充実した毎日を過ごされることと思います。そんな新社会人のうちから、お金を増やすために考えたいのが投資戦略です。今回は、初任給22万円・都内近郊在住の一人暮らしの新社会人を想定して、投資用のお金をどう捻出するか、どんな投資をするのかという投資戦略を考えてみました。
「お金持ちになるにはどうしたらいいの?」と子供に聞かれたら?お金の学びになる答え方をFP解説
お金持ちになるための3つのポイントとは?
子どももお金持ちに憧れるもの。将来の夢を聞かれて「お金持ち!」と答える子どももいます。けれど「お金持ち」とはどういう人のことかと尋ねると、あまりわかっていないようです。お金をたくさん稼ぐだけでは、お金持ちにはなれません。稼いだお金を、上手に使い、上手に貯めることが必要です。登場するのはFPママとFPパパ、そして息子のヒロの3人です。※本稿は、頼藤太希・高山一恵著 『11歳から親子で考えるお金の教科書』(日経BP)の一部を再編集したものです。
大切な服が傷むことも…衣替えのNG行為と正しいしまい方
使いがちな圧縮袋も要注意
日本全国的に例年よりも早く春がきた今年。「まだ寒くなるかも」と冬物を残しつつ春物を引っ張り出して着はじめ、きちんと衣替えをしないままにズルズルときてしまっているかたも多いのではないでしょうか。そのままにしておくと、大切な服を傷めてしまうことにもなりかねません。そこで今回は衣替えのNG行為と正しいしまい方をご紹介します。
都内で暮らす40代独身女性の平均年収や貯蓄額、生活費はいくら?【2023年版】
30代から賃金は大きく増えていない
2022年6月の東京都の世論調査によれば、東京都に住む40代女性にとって、今後の生活の不安は、自分や家族の健康・病気、自分の老後が上位をしめています。仕事やプライベートが充実しているように見える40代ですが、今後のことを考えると不安が大きいようです。40代は、老後の不安が徐々に現実的になってくる時期。今のままでいいのか、悩みの多い年代なのかもしれません。そんな時期を、多くの人はどのように乗り越えているのでしょうか。今回は、東京都内で暮らす、40代独身女性の年収、貯蓄、生活費の平均について見ていきます。そして、悩みを抱えつつも、しっかり暮らす40代の姿を追ってみたいと思います。
「借金がいくらあるかわからない」リボ払いに苦しむ5人家族の主婦。カード地獄を抜け出すには?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、45歳、専業主婦の女性。生活費の支出が多く、クレジットカードの分割払いやリボ払いを多用してしまい、借入がどれほどあるかわからない状況とのこと。この状況から抜け出す道は? FPの秋山芳生氏がお答えします。
冷蔵庫、電子レンジ、掃除機…新生活に向けての家電選びで気をつけたいこと
単機能か高機能か
新婚生活から一人暮らしまで、新しい生活を始める方々は家電の購入、または買い替えを検討しているでしょう。では選ぶ際に何を気をつけるべきでしょうか。
都内で暮らす40代独身男性の平均年収や貯蓄額、生活費はいくら?【2023年版】
1ヶ月の貯蓄額は〇〇円
学校を卒業してから順調にキャリアを積んできた40代の独身男性は、人間的な魅力に加えて経済的にも余裕があり、仕事でもプライベートでも一目おかれる存在になっているのではないでしょうか。独身にこだわっているつもりではないのに、気づけば40代、という独身男性にとって、今後のライフプラン、マネープランをふと考えてしまうこともあるでしょう。将来を考えるにはまず現状の整理から。それには、平均的な数字を知っておくことも役に立ちます。今回は、40代独身男性が東京で暮らしている場合、年収や貯蓄額、生活費はどのくらいかかっているのか、見ていきたいと思います。
がんになったらすべてを保障してくれるわけではない?知っておきたいがん保険の保障範囲
合併症は保障されない保険も
がん保険の契約件数は、2527万件(生命保険協会調べ2020年度)で、かなり多くの方が契約をしています。そもそも「がん保険」とは、どんな保険でしょうか?「がん保険」とは、「医療保険」の一種ですが、がんという病気しか保障しない保険です。逆にいうと「がん」になったときには保障してくれますが、がん以外の保障はありません。では、「がん」になったら、すべてを保障してくれるのでしょうか?じつは、そうでもありません。どんな「がん」に対して保障してくれるのか? または、どんな場合には「保障」してくれないのか? 再度確認してみましょう。
自分は残業しない−−管理職の宣言は職場にどんな影響を与えたのか?
言いにくいことが言えるようになる伝え方(3)
自分の「思い」を伝える際、表現しきれないこともあれば、相手が違った形で受け止めてしまう場合もあります。臨床心理学者・平木典子 氏の著書『言いにくいことが言えるようになる伝え方 自分も相手も大切にするアサーション』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)より、一部を抜粋・編集してアサーティブに思いを伝える方法を紹介します。
いきなり「できません」と伝えるのはNG!依頼を断るときのテクニック
言いにくいことが言えるようになる伝え方(2)
同じ言葉でも、バックグラウンドが違えば異なる意味を持つこともあります。理解してもらえると思っていた発言に、否定的な反応を返されるということもあるかもしれません。臨床心理学者・平木典子 氏の著書『言いにくいことが言えるようになる伝え方 自分も相手も大切にするアサーション』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)より、一部を抜粋・編集して依頼を断るコミュニケーションについて解説します。
「意見を変えるのは無責任」は間違い?コミュニケーションを円滑にするスキルとは
言いにくいことが言えるようになる伝え方(1)
自分の言いたいことを大切にして表現すると同時に、相手が伝えたいことも大切にして理解しようとするコミュニケーションスキル、アサーションをご存知でしょうか?臨床心理学者・平木典子 氏の著書『言いにくいことが言えるようになる伝え方 自分も相手も大切にするアサーション』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)より、一部を抜粋・編集してアサーションの実践方法について解説します。
家計簿をつけるうえで一番避けたいこととは? 正しいつけ方をFPが解説
細かくつければいいわけではない
「家計簿をつけているものの、なかなか支出が減らない」、「家計簿のつけ方が間違っているのかも」という悩みをお持ちの方もおられるのではないでしょうか。家計簿は単に支出の内容を記載すればいいものではありません。収入に対してどのくらいの支出があるのか、支出を減らすにはどこから手をつけたらいいのかのヒントを得る手段として上手に活用することが大切です。今回は家計簿のつけ方や、支出を減らすための家計簿の活用方法について解説します。