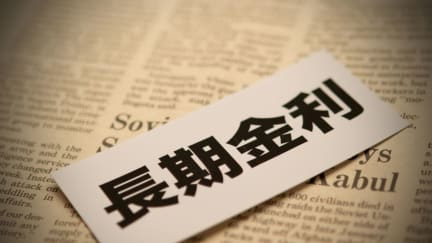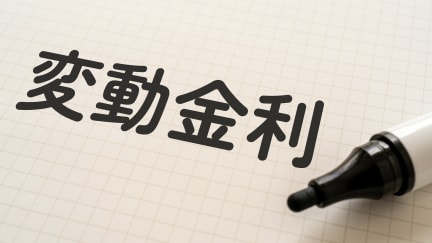42歳一人暮らし、950万円の住宅を購入予定「修繕費などのコストが心配…暮らしを現状維持して老後資産を増やせる?」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、42歳、一人暮らしの会社員の女性。950万円の中古住宅の購入を考えているけれど、購入後のコストや老後資産が心配とのこと。FPの飯田道子氏がお答えします。
金利上昇リスクへの備えは大丈夫?【変動金利型住宅ローン】を検討している人が確認するべき5つのポイント
低金利にとらわれすぎずに全体で判断するヒント
固定金利型と変動金利型の金利差が大きく推移する中、変動金利型住宅ローンが注目されています。ただし、金利上昇観測も高まってきていますから、これから変動金利型住宅ローンを検討するなら金利変動リスクにしっかりと備えておきたいところです。これから変動金利型住宅ローンを検討する場合、踏まえておきたいチェックポイントを5つ解説します。
新NISA、定額減税、住宅ローン減税優遇…2024年上半期の見逃せない【お金のイベントカレンダー】
2024年は例年よりも盛沢山
2023年は、2020年から約3年続いたコロナ禍の影響や、ウクライナ戦争による物価高などもあり「家計管理が大変だった…」という方、「自分なりの節約術を確立し、家計は順調」という方、それぞれ思うことがあるのではないでしょうか。2024年のお金のイベントは、例年よりも盛沢山。節税で家計収支が楽になったり、資産をより効率よく増やせたりするでしょう。今回は、上半期のお金のイベントをわかりやすくまとめました。
住宅ローンを借り換えた方がいい3つの目安とは? 行動に移す際の注意点も解説
変動金利の住宅ローンは借り換えすべきか
日本では低金利が長い間続いています。住宅購入時に住宅ローンを選んだときには、あまりよく考えずに金利が低いものを選んだという人は少なくないでしょう。しかし、2022年12月に日銀が金融政策に修正を加えてから、2023年7月、11月と徐々に金利固定型の金利が上昇してくると、変動型を選んでいる場合は、将来の金利上昇が心配になっている人が増えています。また、住宅ローンを契約した時よりも今の金利が低い変動型のローン場合には、ローンを借り換えると有利なるのではないか思うこともあるでしょう。今回は、住宅ローンの借り換えにあたり、事前に知っておきたい注意すべきことを確認していきましょう。
住宅ローン、固定金利と変動金利はどのような影響を受ける? 【長期金利】のしくみ
金利のしくみ(3)
前回、期間1年未満のお金の貸し借りに適用される「短期金利」について解説しました。今回は1年以上のお金の貸し借りに適用される「長期金利」です。前回記事: 預金や住宅ローンに影響はある?知っておきたい【短期金利】のしくみ
貯金1,000万円、世帯年収1000万円の20代夫婦「7,000万円の住宅購入は妥当ですか?」
無理な住宅購入はその他のライフイベントにも影響大
人生の三大支出と言われている住宅費。どれだけお金をかけるかは悩むところです。ファイナンシャルプランナーの筆者の元に住宅購入を控えているご夫婦が相談に来られました。毎月のローン返済額について専門家の意見を聞きたいそうです。ご家庭の家計状況と住宅購入の適正額についてみていきましょう。
変動金利型住宅ローンを契約した人は必見!金利上昇の影響が大きい人の特徴3つ
注意点と対策をFPが解説
10月31日、日銀は長期金利の上限のめどを1%とすることなどを決定、大手三行は10年固定金利型住宅ローンの基準金利を引き上げました。日本の金利は低い水準にありますし、短期金利に大きな動きはありませんが、変動金利型住宅ローンを利用する方は、来年以降の基準金利は上がることを想定したご家庭の対策を確認しておきましょう。とはいえ、なかなか重い腰が上がらない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は変動金利型住宅ローンを利用している方のうち、金利上昇への備えを早めにすすめておきたい方の特徴を3つ挙げ解説します。
「夫が働けなくなった時に住宅ローンの返済が続くのが心配…」どうすればいい?
団体信用生命保険、福利厚生制度、そして…
住宅ローンの借り入れをしている方は、万が一働けなくなったらどうしようと頭をよぎったことはないでしょうか。夫婦の場合、働き方や金融資産など状況によって対処方法は変わってきますが、どのように考えていくのが良いのかを解説します。
預金や住宅ローンに影響はある? 知っておきたい【短期金利】のしくみ
金利のしくみ(2)
金利には「短期金利」と「長期金利」があります。預金や住宅ローンの金利は、短期金利や長期金利の動きに左右されます。その違いはどこにあるのか、経済にどのような影響を及ぼすのかなどについて解説します。まずは短期金利をとり上げます。
45歳でマンションを購入した独身女性 完済は80歳「老後資金を確保できるか不安」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、45歳会社員の女性。73歳の母との同居を視野に入れ、34年ローンで新築マンションを購入した相談者。ローンを返済しつつ老後資金を確保できるか不安だといいます。FPの渡邊裕介氏がお答えします。
住宅ローン、返済比率20%でも赤字に転落…住宅購入を進める前に知っておくべき予算の立て方
住宅ローン借入可能額の落とし穴
住宅購入を予定しているAさん(39歳)。住宅メーカーへ相談する際、どれくらいの予算を想定すればいいのかを相談しに、ファイナンシャルプランナーの筆者のもとに相談に来られました。住宅ローンの借入額がいくら位までであれば、無理なく返済できるのかが気になっているそうです。Aさんのご家庭の家計状況と今後の対策についてみていきましょう。
「高利回りのマンション投資」を実現するためにチェックしておくべき2つのポイント
必要なのは「リスクの理解」
首都圏を中心に、都市部の不動産は高騰しています。投資家向けのビルやマンションも、表面利回りが5%を下回る不動産も珍しくない市況です。そんな中、「せっかく不動産投資をする以上、もっと高収益・高利回りな物件にチャレンジしたい!」と考え、例えば利回り10%以上に絞って不動産情報を収集している方や、競売物件情報にアンテナを張っている方も少なくないと思います。そして、高利回りな不動産の情報をたくさん集めていくと、一つの傾向が見えてきます。それは、ほぼ例外なく「古い」ということです。これは、減価償却が進み、純粋な資産価値が低下している不動産である以上、「築浅な不動産に比べて、築古の不動産は売買価格が安くなる」のは当然の流れともいえます。一方、不動産投資においては、築年数の進行による賃料の下落は、売買価格の下落に比べて緩やかであることが多く、その結果、高利回りな築古物件が生まれやすくなっている側面もあるのです。実際に、投資用マンションの情報サイトを眺めると、利回り30%を超えるようなマンションが公開されていることもあります。それでは、このような高利回りの築古不動産、特に居住用の区分マンション(分譲タ
長期金利10年ぶり高水準で「変動金利型住宅ローンに不安…」FPが教える5つのポイント
今後の返済計画が家計を左右する?
10月4日(水)、日本の長期金利は大きく上昇し、一時10年ぶりの高水準となりました。背景にはアメリカでの長期金利の上昇を受け、日本でも長期金利の上昇圧力が強まっていることがあります。食費や光熱費、ガソリン代などあらゆる物の値上がりも続く中、変動金利型住宅ローンを契約されている方の中には、漠然とした不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。このようなタイミングだからこそ知っておきたい、変動金利型住宅ローンのポイント5つを解説します。
住宅ローン、夫婦で組むと「返済負担を減らせる」はウソ?契約前に確認しておきたい4つのポイント
夫婦で住宅ローンを組む3つの方法
夫婦共働きはもちろん、大黒柱は妻、という家庭も珍しくなくなってきました。夫婦それぞれに安定した収入があるなら、マイホームを取得する際、夫婦2人で住宅ローンを組むこともできますが、方法は複数あり、それぞれに注意点もあります。夫婦で住宅ローンを組む3つの方法と、契約前に確認したいチェックポイントを確認していきましょう。
住宅ローン、総返済額は【変動金利】と【固定金利】でどれだけ変わる?
変動金利に向いていない人の特徴とは
「フラット35」が、2023年8月の金利を公表しました。最頻金利は年1.72%(借入期間:21年以上35年以下、融資率9割以下の場合)で2ヵ月連続で低下したものの、年0.3%台からという依然低い水準で推移する変動金利型と比較すると、高い水準です。これから住宅ローンを契約される方は、変動金利型の低い金利を活かすプランに一考の価値があるでしょう。変動金利型を検討するにあたり、知っておきたい変動金利型の利用に注意が必要な人の特徴について解説します。
低金利で住宅ローン控除もあるなか、住宅ローンで頭金を減らすとどんな影響があるのか?
頭金を出すメリット・デメリット
マイホームの取得時に必要となる頭金の金額は、住宅ローンの借入金額に影響を与えます。マイホーム取得相談の際、どれくらい出せばいいのか、といった質問を筆者もよくお受けしますから、気になる方は少なくないようです。頭金を減らすことは、賢い資産活用となるのでしょうか?今回は、頭金を出すメリットデメリットについて解説します。
住宅ローン、金利が下がるならネット銀行などに借り換えるべき?
見えている数字以外に考えるべきこと
ファイナンシャルプランナーの筆者のもとに、会社員で38歳の女性が相談にいらっしゃいました。一昨年に住宅ローンを組んで新築の家を購入したのですが、ネットで調べてみると、住宅ローン金利の低さに借り換えをした方が、返済額を減らせるのではないか、とお悩みのようです。住宅購入の契約が進んでいくなか、住宅ローンを借りる金融機関や条件について検討する間もなく、契約に間に合わせるためには地元の銀行を選択するしかなく、「ネット銀行などもっと低い金利で住宅ローンを組むことができたのではないか」と、ずっと気になっていたそうです。
産休に入る26歳女性「子供は2人欲しく、3500万の家も購入したい。このままの貯め方では無理?」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は現在妊娠中の26歳会社員の女性。将来、子供を二人持ち、3,500万円の家を購入することを希望していますが、貯蓄計画に不安があるようです。FPの菅原直子氏がお答えします。