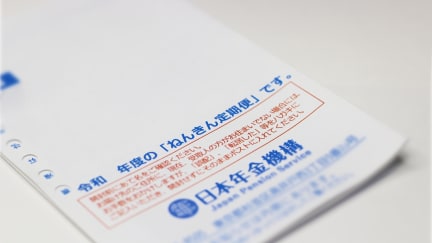「年金は目減りする」は誤解?令和8年度の改定から読み解く“年金の真実”
正しい知識で老後不安を解消
「年金は目減りする」「年金はもらえなくなる」そうおっしゃる方が少なくありません。だからこそ、老後のために自助努力が必要と投資に励もうとするのですが、本当に公的年金はあてにならないのでしょうか?今回は1月23日に発表された令和8年度の年金額改定を基に年金を解説していきます。
企業型確定拠出年金(企業型DC)、定年時に「損をしない」受け取り方とは?
受け取り方で税金はどのくらい変わるのか
「確定拠出年金は受け取り時に課税される」という認識が高まってきています。正しい理解はとても重要ですが、課税を嫌って利用しないのではなく老後資金として最大限に活用するという視点で様々な受け取りのオプションを知ることも大切です。今回は特に定年で退職金と企業型DCを受け取る際の税金と、受け取り方のオプションについて解説します。受け取り時の選択肢について理解を深めていただけるとうれしいです。
賞与制の会社から年俸制の会社への転職で年金が減る? 転職前に確認すべき「3つの数字」
高収入層ほど影響が出る可能性も
「年棒制に変わると、損することはあるのだろうか」——賞与ありの会社から、年棒制・賞与なしの会社への転職を考える50代も少なくありません。年収は同じでも、支給形態の違いで厚生年金や社会保険料の計算方法が変わり、将来の年金額や各種給付に差が生じる場合があります。転職後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、知っておきたい「3つの数字」を解説します。
知らないと損する!年金制度改革の5つのポイントをFPが解説
働き方も老後設計も変わる最新制度の全容
2025年5月16日、年金制度改革法が国会に提出され、6月13日に成立しました。少子高齢化の加速、働き方や家族の形が多様化し、従来の制度ではカバーしきれない課題が増えていたためです。この改正により、自分の働き方やライフスタイルを主体的に選択する力が、さらに求められるようになります。今回は、将来後悔しない選択ができるようになるために、2025年の年金制度改正のポイントを分かりやすく解説していきます。
年金「繰り下げ受給」で得する人、損する人--あなたのベストを見つける3つのステップ
ベストな年金戦略
65歳から年金を受け取るか、それとも手取りが減っても早く受け取る「繰上げ受給」にするか、はたまた、年金額が増える「繰下げ受給」をするか…。数字だけを見ると「遅らせるほど得」と感じますが、そこには「何歳まで生きるか」「増えた分に見合った手取りになるか」といった現実的なハードルが潜んでいます。この記事では、その判断基準と“自分のベスト”を見極めるためのヒントをお伝えします。制度を使いこなす視点で、ベストな年金戦略を描いてみてください。
「私的年金の見直し」iDeCoの加入期間や掛金額はどう変わる?
改正はいつから?
公的年金だけでは、老後の生活費をまかなうことが難しいのが実情です。それをカバーするために、公的年金の上乗せを作れる「私的年金」の制度が用意されています。2025年6月に成立した「年金制度改正法」には、私的年金の制度改正も盛り込まれています。今回の改正によって、私的年金を使って老後資金をより手厚く用意できるようになります。今回は、年金制度改正法の改正内容のひとつ、私的年金の見直しを紹介します。
高所得者にとっては改悪ではない? 厚生年金の標準報酬月額「段階的引き上げ」で保険料が増えるのはどんな人か
影響がない人とは?
会社員・公務員の方が納める厚生年金保険料は、毎月の給与から天引きされています。2025年6月に成立した「年金制度改正法」には、厚生年金保険料にかかわる「標準報酬月額」の上限の段階的な引き上げが盛り込まれています。これによって厚生年金保険料が増えてしまう人が出てくるといったら、気になる方も多いでしょう。今回は、今後の標準報酬月額引き上げのポイントを紹介します。
遺族年金制度の見直しは改悪ではない? 5年間の「有期給付」になる人とは
改正後も、遺族年金の金額だけで生活するのは難しい
家計を支える人が亡くなったときに、遺族の収入の支えになるのが「遺族年金」です。2025年6月に成立した「年金制度改正法」には、遺族年金の見直しが盛り込まれています。これを受けて、遺族年金の制度は2028年4月から段階的に変わっていく予定です。今回は、今後の遺族年金の見直しのポイントを紹介します。
在職老齢年金制度の見直しで年金額が増える人はどのくらいいる?
見直しはなぜ行われたか
2025年6月13日に成立した年金制度改正法の改正内容のひとつに「在職老齢年金の見直し」があります。これによって、もらえる年金額がこれまでより増える人がいます。年金は老後の収入の柱となるお金ですから、増えるのは嬉しいですよね。今回は、年金制度改正法の改正内容のひとつ、在職老齢年金の見直しについて紹介します。
年収1億円の人の年金はいくらになる?
年金の仕組みを知る
年収1億円という高所得者層は、多くの人にとって成功と豊かさの象徴かもしれません。収入が多い分、税金や社会保険料の負担も小さくないのが現実です。「年収が高く多くの負担をしているのだから、将来受け取れる年金も多いはず」と想像されるのではないでしょうか。しかし、日本の公的年金制度は、必ずしも収入の高さがそのまま将来の年金額に直結するわけではありません。実は、制度には一定の「上限」が設けられており、年収1億円という高所得の方であっても、期待するほどの年金額にはならないケースがほとんどなのです。この記事では、年収1億円の人が将来受け取れる年金額を具体的に考察し、公的年金制度のポイントと、豊かな老後を迎えるための準備について解説します。
「定年退職して業務委託で働きます。退職金を年金受け取りすれば経費と相殺できますか?」
退職金の賢い使い方と起業に向けたお金の整理法
60歳で定年退職するAさんは、継続雇用ではなく、知人の会社で業務委託として働く道を選びました。手元の退職金の一部を年金形式で受け取り、起業の経費と相殺できると考えていましたが...。
退職・転職・働き方の変更で年金はどう変わる? 会社員が知っておくべき年金の基本
老後不安を解消するために今からできること
ニュースで年金についての議論が報じられるたびに、「将来、本当に年金はもらえるのだろうか?」と、不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。日本の年金制度は、現役世代が支払った保険料を仕送りのように高齢者などの年金給付に充てる世代と世代の支え合いの考え方で運営されています。老後の不安を解消するために大切なことは、制度を正しく理解し、老後に向けた備えを始めることです。今回は、会社員が知っておくべき年金の基本と将来に備えるためのポイントをファイナンシャルプランナーが解説します。
払った保険料は年金額に関係がない? 改めて知っておきたい厚生年金の基本
今私たちが自己防衛としてするべきこと
2025年4月より、ねんきん定期便には事業主が負担した保険料が明記されることになりました。SNSなどで「年金給付額を多く見せようとするためにわざわざ事業主負担分を記載していないのだ」という批判があったことを受けての対応のようですが、本当にそうなのでしょうか?
贅沢ではないが貧困でもない? 年金生活者のリアルな実態
年金暮らしを愉しく過ごすためにできること
年金で暮らしている人たちはどのような暮らしをしているのでしょうか? 総務省「家計調査 世帯収支編」を見ると、年金生活者の暮らしぶりがわかります。今回の記事は、総務省「家計調査 世帯収支編」の「65歳以上の者がいる世帯(世帯主が65歳以上、無職世帯)」のデータを使って、年金生活者の暮らしぶりを読み解いていきたいと思います。
「ねんきん定期便の年金額では暮らしていけない」56歳女性のライフプラン再設計
ねんきん定期便から始める老後資金準備
会社員のAさん(56歳)はねんきん定期便を見て、この年金額では老後の生活費には足りないことに気がつきました。「このままで老後資金は大丈夫なのかを確認したい、何か対策が必要であれば始めたい」とFPである筆者のもとに相談に来られました。
50-60代夫婦に大きく影響! 遺族年金に関わる年金繰下げ問題が改正の方向へ
あまり報道されていない見直し案とは
年に一度送られてくるねんきん定期便。受け取りを65歳より遅らせると金額が増える「繰下げ受給」の仕組みを周知する目的もあり、50歳以上に届くねんきん定期便には70歳/75歳の見込額が記載されています。老後資金に不安がある人にとって、繰下げは対策の一つとして有効ですが、現行制度では繰下げをしたくてもできない人がおり、改正の方向へ進んでいます。
年金を繰り上げ受給して新NISAで運用するのは得なのか?「70歳繰り下げ受給」を上回るために必要な運用利回りは
「収益率の順序リスク」にも注意が必要
SNSをはじめネット上では、「60歳で年金を受け取って新NISA投資に回したほうがよい」という意見が散見されます。実際、直近20年間のS&P500の運用利回りは円ベースで年9%前後なので、こういった意見が出てくるのも仕方がないのかもしれません。年金は原則65歳から受け取り開始ですが、60歳~64歳で受給する「繰り上げ受給」、66歳〜75歳で受給する「繰り下げ受給」を選択することができます。繰り上げ受給は、1カ月早めるごとに0.4%ずつ受給率が減少し、60歳受給は受給率76%(24%減額)となります。繰り下げ受給は、1カ月繰り下げるごとに0.7%ずつ受給率が増加し、75歳受給は受給率184%(84%増額)となります。一度、受給を開始すると、途中でこの増減率を変更することはできません。繰り下げ受給は、年金を増額するための運用リスクを一切取ることなく、増やせるのが大きなメリットです。繰り下げによる増額分を超えるには、どれくらいリスクを取れば良いのでしょうか。一緒に考えていきたいと思います。
年金は繰上げて早くもらった方が得ですか?
最初は得だが…
年金は繰上げて早くもらった方が得なのでは?という話はよく耳にします。実際に私の周りでも、繰上げ受給をしている人が何人もいます。では、いったいどのくらいの人が繰上げ受給をしているのでしょうか?厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況 (令和4年)」によると、2022年に国民年金を繰上げ受給している人は、約26%の160万人ほどです。また、厚生年金を繰り上げている人は約0.7%の約21万人です。それに対して、国民年金を繰下げしている人は、約2%の12万人で、厚生年金を繰り下げている人は、約1.3%の約37万人です。年金の繰上げ受給と繰下げ受給とでは、繰上げ受給をしている人の方が圧倒的に多いことがわかります。では、年金の繰上げ受給は正解なのでしょうか?