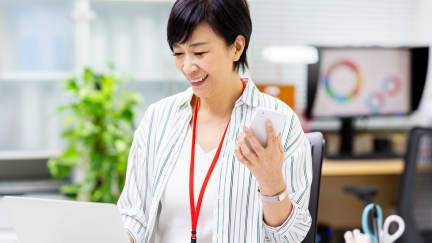20代から定年まで、どんなプランで資産形成をしていくのが理想?
お金は目的別に3つに分けて貯めよう
老若男女世代を超えて、マネーに関するお悩みで一番多いのが「老後資金の不安」です。そこで、今回は、将来に備えて、20代から定年となる60代まで、どのような考え方で資産形成をしていけば良いのか、各年代の資産形成のポイントを交えながら解説します。
夫の退職金を住宅ローン返済にあてた58歳パート女性「手元に現金がなく、万一のときに不安…」
夫が定年後、妻の公的保障はどうなる?
ファイナンシャルプランナーの筆者のもとに、パートで58歳の女性が相談にいらっしゃいました。昨年、夫が定年退職となり退職金を住宅ローンの返済にあてたところ、手元にほとんど現金が残らなかったそうです。さらには、退職後に夫が加入していた生命保険を解約したため、老後のお金が不安になったというご相談でした。
「お墓はいらない」といっても死後どの程度お金がかかる?
コロナ後、変わる葬儀費用
200万円は必要といわれた葬儀費用。コロナ禍で葬儀のスタイルがだいぶ変わりました。死後の整理費用に、準備しておくべき資金、準備する方法を解説します。
相続してしまうと「一生手放せない負動産」に…。売買が強制却下される意外な不動産とは?
知られていない、不動産取引の”例外”
日本では、不動産は自由売買が原則とされています。つまり、「売り手」と「買い手」が話し合って、不動産の売買金額や取引条件さえ固まれば、たとえ家族や隣人といった第三者が「その売買はやめた方がいい!」「その売買は許さない!」といった反対意見があったとしても、その売買は成立して、買い手の名義に所有者を変更することができます。しかし、その中で唯一、売り手と買い手の間では売買が成立しているのに、その売買は「許さない」として手続き途中で却下されるケースがあります。その不動産とは、田んぼは畑などの「農地」です。ちなみに、この場合、「交渉次第でなんとかなる」といった甘いものではなく、それを覆すことも難しい、厳しいものなのです。意外と知られていない、「自由売買を許さない」特殊なケース。そして、これは思いのほか身近な不動産であり、農地の売却処分に困っている不動産所有者がたくさんいます。今回は、なぜこのような不思議なルールがあるのか、そして、もしも自分がこれに該当して売却処分に苦しむことになってしまったとき、その対策はあるのかを見ていきたいと思います。
知っておきたい 「180万円の壁」。60歳パート主婦「夫の健康保険の扶養に入れますか?」
年金の受取額を確認することが重要
シニア世代の就業者は増えていますが、60歳以降も働き続ける女性は多いと実感しています。働く理由には経済的不安もあるでしょうが、健康増進、社会や人とのつながりを持つためでもあるようです。今回はパートで働く主婦の方々から質問されることが多い健康保険の扶養についてお伝えします。
よゐこ有野、相続で揉めるケースに驚き「莫大な遺産があって、じゃないんだ」
終活を考える(4)
お笑い芸人・よゐこの有野晋哉さんが、毎月さまざまな専門家をゲストに迎えて、お金の知識を身に付けていく「お金の知りたいを解決!お金の学園〜学級委員・よゐこ有野晋哉〜」。2023年7月は社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーの井戸美枝先生に、終活について伺いました。今回は、「相続と遺言」について。遺言書とエンディングノートの違い、ご存知ですか?
「死ぬまでにお金を使い切る」難題。残す資産をコントロールするためにできることとは
収入と支出のバランスが重要
日本の金融資産は約2000兆円あります。そのほぼ6割を60歳以上の人が保有しています。多くの資産を高齢者が持っているのがわかりますね。でも死んでしまったら、その資産は相続財産になります。MUFG資産形成研究所の「退職前後世代が経験した資産承継に関する実態調査(2020年)」のデータによると、親から相続した平均金額は3273万円です。中央値では1600万円です。つまり、老後には2000万円以上必要だと言われている一方で、2000万円近く残している人が多いのです。もしかすると2000万円貯めたものの、「減るのが恐くて使えなかった」ということもあるのではないでしょうか。「死ぬまでに、自分のお金は全部使い切る」のが理想ですが、これがなかなか難しいのです。今回は、「死ぬまでに自分のお金を使い切る」という難題に挑戦してみようと思います。
よゐこ有野「いやらしいわぁって…」親への【終活】の切り出し方に四苦八苦
終活を考える(3)
お笑い芸人・よゐこの有野晋哉さんが、毎月さまざまな専門家をゲストに迎えて、お金の知識を身に付けていく「お金の知りたいを解決!お金の学園〜学級委員・よゐこ有野晋哉〜」。2023年7月は社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーの井戸美枝先生に、終活について伺いました。今回は、「終活の切り出し方」について。スムーズに話を進めるには、どのように切り出すのがよいのでしょうか?
相続した不要な「負動産」を売るために実践すべき、たった2つのこと
実は、負動産の買い手は多い
相続で引き継いだ山林や農地、親が生前に住んでいた空き家など、「思い出は詰まっているけれど、今は何も使っていない」不動産は、意外と多くの人にとって身近な財産の一つです。これらの不動産は、使っていなくとも固定資産税の支払いや、草木の除草伐採などの維持管理が避けられず、様々なリスクが年々積みあがっていく、資産価値よりも負債の大きい「負動産」と化していることも少なくありません。そして、負動産がかかえる問題は、負債的要素をもっていることだけでなく、「売りたくても売れない」という、八方塞がりに近い側面も持ち合わせています。しかし、実際にはそんな悲観する必要はありません。負動産を売却処分したいと思ったときに、見落とされがちな「2つのこと」を実践することで、誰でも負動産問題から卒業することができるようになります。今回は、その「2つのこと」について見ていきたいと思います。
よゐこ有野、終活の現実を知りショック「結構な金額…」
終活を考える(2)
お笑い芸人・よゐこの有野晋哉さんが、毎月さまざまな専門家をゲストに迎えて、お金の知識を身に付けていく「お金の知りたいを解決!お金の学園〜学級委員・よゐこ有野晋哉〜」。2023年7月は社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーの井戸美枝先生に、終活について伺いました。今回は、「終活で整理しておくべきこと」について。4つあるそうですが、何かわかりますか?
60~65歳は年金生活を「幸せ」か「苦しい」ものにするかの分かれ道。老後を安泰に過ごすためにやるべきこと
資産運用よりも大切なこと
60歳の定年を迎えて、その後は再雇用。その再雇用も65歳には終わるのが一般的です。65歳からは年金生活とシミュレーションしているのではないでしょうか。これがもっとも多いパターンでしょう。だからこそ、60歳から65歳までの暮らし方がとても重要になってくるのです。この時期の生活・暮らし方が、その後の年金生活を幸せなものにする、それとも苦しいものにするかの分かれ目になるといってもいいでしょう。では、この再雇用の期間は、どんな生活・暮らし方をすれば、幸せな年金生活が過ごせるのかを考えてみましょう。
よゐこ有野、日本の健康寿命を知りショック「嫌ですね…」
終活を考える(1)
お笑い芸人・よゐこの有野晋哉さんが、毎月さまざまな専門家をゲストに迎えて、お金の知識を身に付けていく「お金の知りたいを解決!お金の学園〜学級委員・よゐこ有野晋哉〜」。2023年7月は社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーの井戸美枝先生に、終活について伺いました。
「老後に受けとるお金」どんなものに税金、社会保険料がかかる? 手取りを減らさないために考えておきたいこと
年金以外の税金、社会保険がかかる収入に注意
老後に受けとる年金には税金や社会保険料がかかります。また、年金以外の収入があれば、税金や社会保険料がかかるケースもあります。老後の収入のどんなものに税金や社会保険料がかかるのか、また、収入が増えることによる影響について解説していきます。
44歳シングルマザー「働かなくなった時の老後資金が足りるか不安」お金のプロのアドバイスは?
安心のセカンドライフを過ごす方法
厚生労働省が発表した、「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果」によると、ひとり親世帯の平均年収は母子世帯の平均年収が373万円、父子世帯が606万円。子どものいる世帯全体の平均年収が814万円なので、母子世帯の平均年収は、子どものいる世帯の平均年収の半分以下となり、収入の差が浮き彫りになりました。ファイナンシャルプランナーの筆者のもとに、小学生の子どもを育てる、40代のシングルマザーの方が、子どもが独立し、ご自身も退職した後、お金の不安なく安心した老後を過ごせるか不安だ、とご相談にいらっしゃいました。
老後資金、受け取り方で損することも!税理士が明かす税金をおさえるポイント
政府は退職金の課税ルール見直しを検討
政府が退職金の課税ルールの見直しを検討しています。「退職なんてまだ先だし、自分には関係ない」ですって? なんて……嘆かわしい!退職金など、老後資金に対する税金の制度は、「老後に取り崩すためのお金だから税金を安くしておこう」ということで、とても優遇されています。正しく理解することで、大きく節税できるチャンスが広がるのです。今回も、お笑い芸人で本物の税理士である税理士りーなと一緒に楽しく学び、老後資金がすり減らないようにしっかり対策しましょう。
ローリスク・ハイリターン商品、毎月分配型の投資信託…「退職金でやってはいけない投資」4選
都合の良い投資は存在しない
生きている間にまとまったお金を得られるライフイベントといえば、定年退職時の退職金や相続で得られる財産などでしょう。特に老後の支えとなるのは退職金の存在です。しかし、年々退職金の金額が少なくなってきているというデータがありますので、投資でさらに増やして、老後の生活の不安を減らしたいと考えて、投資をスタートさせる方は少なくありません。人生100年時代と言われる今、老後は長いので、資産寿命を延ばすためにも資産運用することは良いことです。でも中には、退職金ではやってはいけない投資があります。いくつか紹介します。
夫47歳・妻44歳で子供を授かった夫婦「今から5000万円の住宅を買っても教育費や老後資金は大丈夫?」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、48歳で、1歳の子供をもつ会社員の男性。賃貸暮らしの不安から、マイホーム購入を予定している相談者。5,000万円の物件が気になっているようですが、教育費や老後資金を考えた時、購入可能でしょうか。FPの鈴木さや子氏がお答えします。
貯蓄額を増やすだけではNG? 老後資金の不安が減る“貯蓄以外“の4つの備え
老後は複数の柱で支えよう
家計相談を受けていると、老後が不安で“貯蓄”に励む若者によく出会います。老後資金の備えとして、貯蓄や資産運用が有効な方法であることは間違いありません。ただ、貯蓄額を増やすことがすべてだと思っていると、老後に対する不安は増してしまいます。そこでこの記事ではあえて、“貯蓄以外”で老後生活の支えになる4つの方法を紹介します。老後が不安な人は、貯蓄や資産運用とあわせて取り組んでみてください。