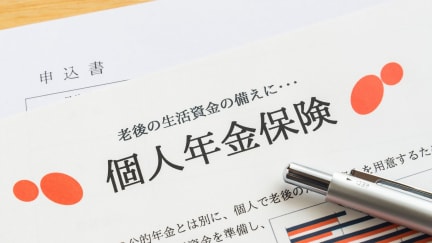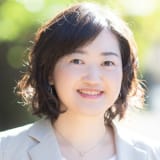投資信託や株式の値上がり益を狙わない、キャッシュフローを増やす投資戦略
老後のお金の考え方①
老後の資産形成というと、投資信託や株式を購入し、その値上がり益を狙うというイメージが先に立ちますが、そうではなく、キャッシュフローを増やすという視点を持つと、別の資産形成ができるかも知れません。
人生の中でも「もっとも幸せな働き方」ができるのは定年後。それを実現するために捨てるべきものとは?
ひとのために働くことが幸福感を高める
「定年」には、どういうイメージを持っていますか?「定年後の働き方」についていろいろと考えたいと思っているけど、本音は「何をどう考えればいいのか、今ひとつよくわかっていない」という人が多いかも知れません。「再雇用が決まっているので、定年になっても、あまり変わらないのでは?」と、なんとなく流されながら定年を迎える人のなんと多いことか!(これは何人もの、定年前の人にインタビューした感想です)。ところが実際には、定年前と後では、大きく違うのです。収入や仕事における役職などによる違いだけではありません。働くことの意義や意識、価値観、生き方まで変わっていくのです。リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」によると、仕事の満足度は定年後の方が満足している人が多いのです。人生の中でも「もっとも幸せな働き方」ができるのは定年後なのです。では、どうして定年後に「もっとも幸せな働き方」ができるのか、についてお話しをしてみます。
相続手続きの書類と負担を減らせる!「法定相続情報一覧図」って?
取得方法や疑問点を行政書士が解説
「法定相続情報一覧図」を活用すれば、相続手続きの際、戸籍等の書類を提出する必要がなくなり、負担が軽くなります。どんな場合に有効なのか、作成の仕方や注意点を、行政書士が解説します。
まとまった資金があるシニア世代が本当にやるべき投資とは?
60歳資産運用(3)
現役で働く若い世代が行う投資と、リタイアを見据えたシニア世代が行う投資では、そのスタンスは大きく変わってきます。そこで、CFPでシニア投資コンサルタント・西崎努 氏の著書『60歳を過ぎたらやってはいけない資産運用』(アスコム)より、一部を抜粋・編集してシニア世代の投資との向き合い方について解説します。
シニア世代や投資初心者が不要な金融商品やサービスを見抜くためのポイントとは?
60歳資産運用(2)
金融消費や金融サービスにはさまざまな種類があり、その特性やリスクとリターンもバラバラです。それらの中から、自身にあったものを選ぶには、どうすればいいのでしょうか?そこで、CFPでシニア投資コンサルタント・西崎努 氏の著書『60歳を過ぎたらやってはいけない資産運用』(アスコム)より、一部を抜粋・編集して不要な金融商品やサービスを見抜くポイントについて解説します。
まとまった資産があるがゆえのリスクとは? シニア世代が考えたい資産形成と資産運用の違い
60歳資産運用(1)
リタイヤが視野に入る60歳は、資産運用においても大きな分かれ道を迎えます。そこで、CFPでシニア投資コンサルタント・西崎努 氏の著書『60歳を過ぎたらやってはいけない資産運用』(アスコム)より、一部を抜粋・編集して資産形成と資産運用の違いについて解説します。
65歳から介護保険料が大幅増で驚きの事例も…介護保険の仕組みを解説
地域によって保険料に大きな差
65歳の誕生日を迎えると、健康保険証の様な紙の介護被保険者証が届きます。介護保険があることは認識しているものの、受けられる介護サービスや、支払わなければならない介護保険料について、くわしく知っているひとは多くないでしょう。65歳を境にサービスの内容も保険料の負担額も大きく変わります。老後のライフプランに影響を与える介護保険について検証します。
iDeCoで掛金の引き落としがストップする7つの理由、チェックすべきポイントは?
放置すると不利益を被ることに
iDeCoは、転職で公的年金の被保険者区分に変更が生じた場合や、企業年金の有無に変化が生じた場合など、金融機関と年金機構の登録情報に不整合が生じると、iDeCoの掛金の引き落としがストップしてしまうことがあります。通知が来た際に慌てないよう、その対処方法を理解しておきましょう。
年金生活への移行時期60代の生き方が、老後生活を決めるワケ
働く意義が変わる
「60代の生き方が、その後の老後生活を決定づける」なんていわれても、ピンッとこないかもしれません。「なぜ?」と思ってしまいますね。しかし、60代というのは、現役生活から年金生活への大切な移行時期にあたります。人生が大きく変わっていくターニングポイントといっていいでしょう。この時期をどのように過ごすか、そしてどうやって過ごしたかが、その後の生活を決めるといってもいい大事な時期なのです。(60歳以降も働いている人は、現役といえますが、ここでいう現役生活というのは、一般的に収入が多くある時期として便宜的に使っています。また年金生活というのも、収入の多くが年金になっている時期を便宜的に使っています)
個人年金保険とiDeCo、つみたてNISAはどう違う? それぞれで積立を行なうメリット・デメリットを解説
税制優遇も大きな違い
ひと昔前に比べて、積立方法が増えてきました。企業型確定拠出年金(企業型DC)と個人型確定拠出年金(個人型DC)が2001年に始まり、2017年1月には個人型DCの加入者が拡充されiDeCoの愛称で、公務員や主婦も加入できるようになりました。さらに翌年の2018年1月からつみたてNISAが開始しました。そのため「保険での積立か、iDeCoを始めたほうが良いか」と筆者のもとにも多くご質問が寄せられます。今回は、個人年金保険との比較について解説します。2022年11月の法令に基づき執筆しております。
将来、年金はいくらもらえる? 何歳から受け取るのが正解? 繰り上げ・繰り下げの損益分岐点は何歳か
税金・社会保険料の天引きに注意
老後の大切な収入である「年金」は、老若男女関係なく誰もが気になる関心事です。将来、自分は年金はいくらもらえるのか、年金の金額を大きく左右する繰り上げ受給・繰り下げ受給とは何なのか、はたして年金は何歳から受け取るのが良いのかなど、気になることが盛り沢山なのが、年金です。今回は、自分は年金がいくらもらえるのかの目安や、年金の繰り上げ受給・繰り下げ受給の仕組み、繰り上げ・繰り下げの損益分岐点を解説していきます。
一時金、年金、併用…iDeCoはどのように受け取るのが正解か? 出口戦略をお金のプロが解説
退職金と同タイミングで受け取るときは要注意
iDeCoはいつから始めればいいのかというと、いつでもOKです。長期の積み立てになるので、始める時期はそれほど気にする必要はありません。しかし、早いに越したことはありません。なぜなら早く始めれば、より長期で積み立てることができ、その分金額も多くなるからです。では、iDeCoの受け取りは、どうすればいいのでしょうか?iDeCoは、60歳から75歳までの間に受け取ることができ、「一時金」「年金」「一時金と年金の併用」の3つの受け取り方から選ぶことができます。つまり、タイミングや受け取り方法を自分で選択できるのです。では、受け取るタイミングと受け取り方は、どう選べばもっとも有利になるのでしょうか?今回は、iDeCoの出口戦略、受け取り方について解説をしてみましょう。
免許返納と運転継続、比べてみたらどちらがお得? 年間費用を試算してみた
返納時期はライフスタイルに合わせて
65歳定年を迎えた後、免許を返納するかどうか悩まれるひとがたくさんいます。通勤の足として、子どもの送迎や買物など、自動車が必要不可欠な地域の場合、免許返納は大きな決断といえます。自動車を運転し続けるくらしと、免許返納し自動車のないくらしとの経済的な比較を踏まえ考えます。
加入しすぎた保険はどう見直すべき?覚えておきたい社会保障制度をFPが解説
金融庁が公的保険を解説するサイトを開設
会社員の橘恵美さん(仮名・33歳)は、1年ほど前に「病気やケガで仕事ができなくなったらどうしよう」「大病をして医療費がたくさんかかったらどうしよう」と、さまざまな心配をするあまり、保険ショップに相談に行き、定期の死亡保険、医療保険、就業不能保険と複数の保険に加入しました。貯蓄性の保険も勧められましたが、保険料が高かったので諦めたそうです。その結果、毎月の保険料負担が大きく、老後に備えての貯蓄ができず、ますます不安が大きくなっているというのです。つみたてNISAも開設してはいるけど、投資に回す余裕がなく、中身はからっぽだそう。新しいNISA制度が議論される中で、「本当にこれで良いのだろうか?」と、恵美さんはファイナンシャルプランナーの私のところにご相談にこられました。
子に中学受験をさせたいが、働き続ける自信がない42歳共働き妻。仕事を辞めたら?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、42歳、会社員の女性。43歳の夫と共働きの相談者。子どもの中学受験を考え始めましたが、体力的に仕事を続ける自信がないとのこと。妻が仕事を辞めたら家計はどうなるのでしょうか? FPの坂本綾子氏がお答えします。
浪費癖があり貯蓄が苦手な50代夫婦「余裕のある老後を送りたいけど不安になってきた」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、56歳、会社員の女性。若い頃から浪費癖が治らず、貯蓄が苦手だという相談者。家計をチェックしたFPが指摘する「今すぐやったほうがいいこと」とは? FPの氏家祥美氏がお答えします。
貯蓄130万円の41歳会社員女性「親族の葬儀や自分に万が一があった場合いくら必要?」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、41歳、会社員の女性。親族の葬儀や自分に万が一のことがあった場合の資金を気にされている相談者。FPが家計状況を確認すると気になる点が…。FPの飯田道子氏がお答えします。
元本確保型を選んで塩漬けのiDeCo、運用商品はどう変更すればよいのか?
運用商品変更で覚えておきたい2つの技
iDeCoをはじめてみたものの、どの商品を選べばよいか分からずそのままになっている、あるいは、結局なじみのある元本確保型商品にして放置している、という方は少なくないのではないでしょうか?今回は、その後の手続きについて具体的に解説します。