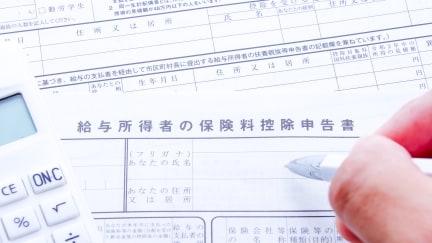結局「年収の壁」はどう変わった? 2025年改正での変更点まとめ
結局、いくらまで働くのが正解?
パート・アルバイトとして働く多くの人が直面しているのが、複雑すぎる「年収の壁」。2025年、「年収の壁」に大きな制度改革があり、壁はより複雑に。そんな中、あなたの働き方は“損をしない”選択ができているでしょうか。知らないままでは、気づかぬうちに手取りが大きく減ってしまうかもしれません。今回は、結局「年収の壁」がどのように変わったのか解説します。
【年末調整】保険料控除でいくら戻ってくる? 10月から届く「保険料控除証明書」活用ガイド
確定申告で迷わないための提出ステップ
10月に入ると、自宅に「保険料控除証明書」が届き始めます。これは、その年に支払った保険料を証明する書類で、年末調整や確定申告で提出することで所得税や住民税を軽減できる大切なものです。本記事では、控除証明書の種類や年末調整・確定申告での提出手順を整理し、還付の目安についてもわかりやすく紹介します。届いたときに迷わず対応できるよう、基本をしっかり押さえていきましょう。
気づかないうちに保障が消えていた…保険の「失効リスク」を避けるには?
契約中の保険も「失効」に注意!
民間の保険に入っている方の多くは、「自動引き落としだから大丈夫」「契約しておけば安心」と考えているのではないでしょうか。ところが、何らかの事情で支払いが滞ると、保険契約が途中で効力を失う「失効」という事態が起こり得ます。解約した覚えがないのに保障がなくなり、いざというときに給付が受けられないのは大きなリスクです。今回は、失効リスクを避けるために知っておきたい注意点や思わぬ失効を防ぐための支払い方法について紹介します。
「思ったより住民税が高かった…」そんな方が来年度に向けて今すぐできる節税アクション
来年の住民税を減らすために、今年やるべきこと
住民税の決定通知書を手にして、「思ったより住民税が高い...」と驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。住民税は前年の所得をもとに計算されるため、今年どのように行動するかが、来年度の税額を左右します。この記事では、医療費控除やiDeCo、ふるさと納税など、身近で実践しやすい節税策を中心に、来年度の住民税を賢く抑えるための具体的なアクションをご紹介します。今日から始められる節税の工夫を通じて、家計の負担を軽減し、将来への備えを一歩進めていきましょう。
確認しないと損することも。住民税決定通知書のチェックポイントと来年に向けた節税アクション
見逃せない重要ポイント
毎年5月から6月にかけて手元に届く「住民税決定通知書」。見慣れない言葉が並び、つい確認を後回しにしてしまう方も多いのではないでしょうか。しかし、この通知書にはご自身の収入や納める税金がどう決まったのかが記されており、家計管理や節税を考える上で大切なヒントが詰まっています。今回の記事では、次の3つのポイントに絞って解説します。住民税決定通知書の基本的な役割と確認すべきポイント来年度の住民税負担を減らすために、今からできる具体的な節税策住民税決定通知書の内容に疑問や誤りなどを見つけた時の対処法住民税決定通知書への理解を深め、家計や将来設計に役立てていきましょう。
パート・フリーランス・個人事業主…扶養内で働く3つの選択肢、あなたにあった働き方は?
本当にパート一択?
ただでさえ分かりにくい“扶養”の仕組み。「パートで働く場合でも混乱しやすいのに、働き方を変えたらどうなるの?」と思う方も多いでしょう。働き方が多様化してきた中で、パート以外の働き方も注目されるようになってきています。しかし、扶養内で働きたい場合、働き方を変えて扶養状態が維持できるのか、それとも仕組みや条件が変わり維持できなくなるのかは気になるところです。今回は、パート以外の働き方としてフリーランスと個人事業主で働く場合、扶養状態が維持できるのかどうかを検証していきます。その上で、それぞれの働き方のメリット・デメリットを比較し、あなたにあった働き方が選べるように判断基準をまとめました。
個人事業主が今こそやっておくべき「確定申告」が楽になる仕組み化
クラウド会計ソフトの活用法
2025年の確定申告の期間が終わりました。経費等の入力作業が多い個人事業主の方からは、毎年溜め込まずにもっとこまめにやっておけばよかった…と思うものの、結局締切間近に焦ってしまう、という声を聞きます。来年こそは繰り返さないで済むように、個人事業主の方に向けて確定申告の準備を楽にするクラウド会計ソフトの自動化について解説します。
確定申告をギリギリで終えた人が今すぐやるべき3つのこと
後悔しないために今すぐ見直し&修正を
「ギリギリに準備を始めたけれど、なんとか申告期限までに確定申告が終わった!」とホッと一息ついている方も多いのではないでしょうか?初めての確定申告だと、慣れない申告作業は大変です。そのような中、ギリギリでも申告期限内に終わらせたことは本当に素晴らしいことですが、「とりあえず申告できたから大丈夫」と安心していませんか? 実は、慌てて仕上げたことで、申告ミスしてしまっている可能性もあるのです。今回は、確定申告をギリギリで終えたけれど十分な確認をしないまま申告してしまった方に向けて、提出後にチェックしておくポイントや修正が必要になった場合の対応を解説します。また、来年は余裕を持って申告できるようになるためのポイントもお伝えするので、いつもギリギリの申告になってしまうという方も是非参考にしてみてください。
副業収入がどのくらいあると確定申告が必要になる? 申告漏れを防ぐための判断基準を解説
収入の種類や働き方によって変わる基準
「パートをしながら副業を始めたけど、私って確定申告したほうがいいのかな」と迷う方もこの時期は多いのではないでしょうか。特に、副業の収入がどのくらいあると確定申告が必要になるのか、基準がよく分からないという方も多いと思います。確定申告が必要なのかどうか判断しにくい理由のひとつに、「年末調整」と「確定申告」の違いが分かりづらい点があります。パートなどの給与収入の場合、会社で年末調整してもらえるため自分で確定申告をする機会はほとんどありません。そのため、副業で収入を得ても確定申告が必要だということを知らずに過ごし、追徴課税などのペナルティを受ける可能性が高くなってしまうのです。そのような事態にならないように、この記事では、副業の種類ごとに「確定申告が必要なのかどうか」の判断基準を分かりやすく解説します。
年末調整だけじゃ足りない?会社員も確定申告すべきケースとは
おさえておきたいポイントをFPが解説
会社員は、毎年12月に年末調整が行われ、所得税の計算や控除の適用が自動的に処理されています。そのため確定申告は必要ないと思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、年末調整だけでは適用できない特定の条件や控除に該当した際には、会社員でも確定申告の義務が発生する、あるいは確定申告することで税金が戻ってくることがあります。今回は、会社員でも確定申告すべき主なケースについてFPが解説していきます。
医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらを選択するほうがお得?
一番所得が多い人が申告しよう
税金の計算のもとになる所得を差し引く「所得控除」のひとつに、「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」があります。どちらも、かかった医療費などを確定申告することで税金が安くなる制度ですが、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。では、どちらを選択するほうがお得なのでしょうか?今回は、医療費控除とセルフメディケーション税制のしくみと、どちらを選択するほうがお得なのか、ポイントを紹介します。
学生バイトの年収の壁が123万円や150万円に? 扶養控除をおさらい
働き損を防ぐポイント
2024年は「103万円の壁」が大きな話題になりました。今回は、政府与党の2025年度税制改正案の内容をもとに、高校生や大学生、大学院生などの子どもの働き方について、親子で把握しておきたい内容をまとめました。
開業届を出すと扶養から外れる? 個人事業主として働く場合に気をつけたいこと
開業届の提出で変わる社会保険の扶養
働き方が多様化する中、子どもとの時間を大切にしながら、やりがいのある仕事に挑戦したいと考える方が増えてきています。その中で、パートから在宅で働くことを検討する方も多いのではないでしょうか。個人事業主として在宅ワークを始めるのであれば、「開業届」を提出する必要があります。しかし、扶養内で働いていた状態から、在宅ワークを始めていこうと考えている場合は注意が必要です。この記事では、個人事業主の場合の扶養条件が開業届の提出とどのように関係しているのか、また後悔しない開業方法について解説します。
副業している40代会社員「私の確定申告の仕方は合っていますか?」
会社員が副業するならおさえておくべきポイントをFPが解説
多様な働き方が認められるようになり、会社員で副業収入を得ている人も増加傾向にあります。副業で収入が増えることは、生活にゆとりをもたらしてくれますが、確定申告についてはおさえておくべきポイントになります。今回は副業で収入を得ている45歳会社員を事例に、会社での年末調整との兼ね合いや確定申告の方法についてファイナンシャルプランナーが解説します。
会社員が副業でいくら稼ぐと確定申告が必要?
副業収入の判断基準や注意点を解説
副業を始める会社員が増えている昨今。副業による収入がある場合、確定申告が必要かどうか迷う方も多いのではないでしょうか。本業に加えて副業から収入を得ることは家計の助けになるだけでなく、新たなスキルを習得できる良い機会でもあります。しかし、副業収入には税金がかかる場合があり、適切な知識を身に付けておくことが、副業をする上でも非常に有益です。今回は、会社員が副業収入を得た場合に確定申告が必要になるケースや注意点についてファイナンシャルプランナーが解説します。
控除可能な範囲を超えるとただの支出になる…? 住宅ローン控除、iDeCo、ふるさと納税、税制優遇制度を併用する場合の優先順位
お得に活用できる最適なバランスとは
将来に対する不安や、老後への備えの必要性が訴えられる中、「お金を増やす」ことが注目されがちですが、「お金を守る」ことも大事な視点です。「お金を守る」ためにできることのひとつが、税負担を軽減することです。そのために利用できる代表的な税制優遇制度として、住宅ローン控除、iDeCo、ふるさと納税があります。これらの制度は併用が可能ですが、そのバランスに頭を悩ませている方も少なくありません。それぞれの制度の活用バランスは人によって異なりますが、「今年こそお得に活用したい!」と思っている方は是非この記事を参考にしてくださいね。
【年末調整】iDeCoは所得控除を受けられる?いくら戻って来る?
申告を忘れた場合に取り返す方法
年末が近づいてくると勤め先で行われる年末調整。条件に当てはまる人は、所得控除の手続きをすることで所得税や住民税を安くできます。iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)を利用している場合、いくら所得控除を受けられるのでしょうか。その結果、税金はいくら安くできるのでしょうか。
個人事業主・フリーランスが知っておきたい【確定申告】の負担を一気に減らすための3つの事前準備
青色申告をスムーズに行うことが節税への第一歩
個人で働く方にとって大きな負担となるのが「確定申告」ではないでしょうか。毎年、3月になると「申告期限に間に合わない!」「事前準備をちゃんとしておけばよかった……」といった声を聞きます。とはいえ、何から準備を始めればいいのかがわからない方も多いのではないでしょうか。本記事では、初めての確定申告を来年に控え、今から不安を感じている個人事業主・フリーランスの方に向けて、これだけは押さえてほしい3つの事前準備を解説します。最初に仕組みをしっかりと作っておけば、確定申告の負担は一気に減らせます。