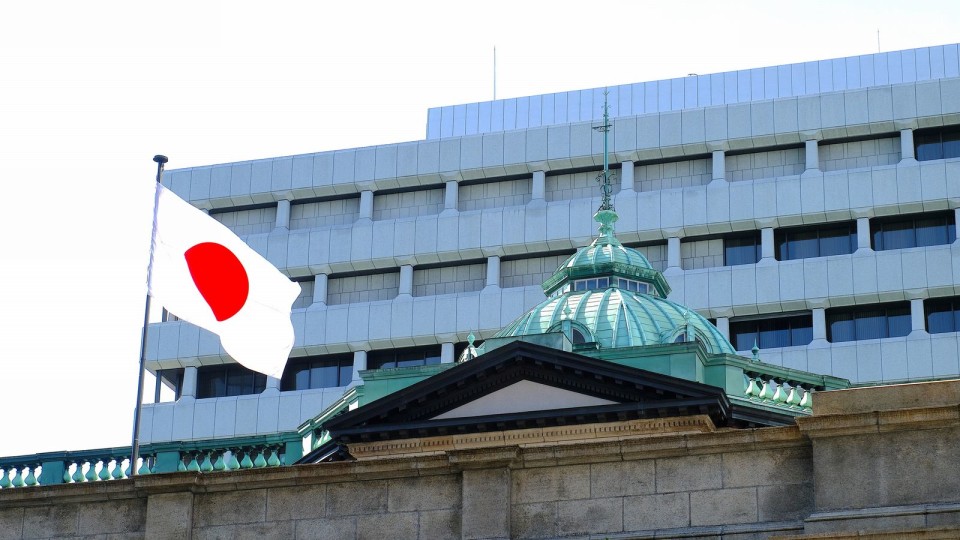はじめに
米ドルは、11月10日(木)に発表された米10月CPI(消費者物価指数)をきっかけに、一時140円を割れるまでの急落となりました。
10月に、1990年以来、約32年ぶりの150円を越える米ドル高・円安となった時には、「新たな円安時代」においてまだまだ通過点のような論調も少なくありませんでしたが、ちょっとムードが変わったのではないでしょうか。しかも、それは日銀の金融緩和が不変の中で起こったということも、じつは重要だったのではないかと考えます。
今回は、記録的な「超円安」が展開する中で広がった、日銀の金融緩和が主因だといった指摘、構造的な円安なのでまだまだ続くといった考え方などは、やはり「間違い」だったのではないかといった視点で再検証してみたいと思います。
なぜ米ドルは急落したのか?
私は、前回の記事で、「歴史的円安が展開しているのは日銀が金融緩和を続けているためで、それが変わらないと円安も変わらない」といった考え方は違うと述べました。
実際、日銀の金融緩和は変わっていませんが、上述のように11月10日(木)の米CPI発表をきっかけに、米ドル/円は146円台から、ほんの2営業日で138円台まで米ドル急落、円急騰となったわけです(図表1参照)。

では、なぜ日銀の金融緩和が変わらない中でも円安から急に円急騰となったのか。これについて、私はそもそも日銀の金融政策を反映する金利で、今回の円安は全く説明できない、今回の米ドル高・円安は米国の金融政策を反映する米金利と連動してきたため、米金利次第で米ドル高・円安が変わる可能性もあるとの見方を示しましたが、少なくともこれまでのところ、そんな見方は正しかったと言えるのではないでしょうか(図表2、3参照)。


つまり、日本の金利は大きく変わらない中でも、CPI発表を受けて米金利が比較的大きく低下すると、10月には150円を越えるまで上昇していた米ドル/円は、一転して140円を割れるまで米ドル急落・円急騰となったわけです。