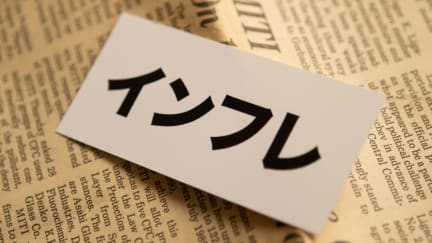シリコンバレー銀行の経営破綻はどんな影響があるのか?下落局面で考えたい投資戦略
リーマン・ショックとの違いは
2023年3月10日(金)にアメリカの地方銀行「シリコンバレー銀行(SVB)」が経営破綻したことを受け、この3月13日週は株安が進行しました。株価が下落することに恐怖を覚える方も多いと思いますが、こうした下落局面ではどのような投資戦略をとるべきなのか−−SVBショックから相場の下落局面での立ち振る舞い方を考えていきたいと思います。
東日本大震災から12年、課題を残しながら進む原発再稼働への動き
官民の動きからも現実味
2011年3月11日(金)14時46分に発生した東日本大震災から、早くも12年の年月が経過しようとしています。震源は三陸沖の宮城県牡鹿半島の東南東130km付近、マグニチュードは9.0でした。日本国内観測史上最大規模で世界でも4番目の規模の地震でした。津波による大きな被害があった岩手、宮城、福島3県を中心に死者、行方不明、震災関連死は約2万2,000人にも上ります。当時、皆さんはどこで何をなさっていましたか?
業績悪化で従業員を解雇しているのに、なぜ株価があがるのか?
日本人の感覚では理解しづらい投資の常識・非常識
コロナショック後の回復局面から、インフレ長期化による景気減速懸念へとシフトしていくなかで、昨年2022年くらいから、米大手のITや金融、メーカーやサービス業など幅広い業種において、従業員を解雇する動きを伝えるニュースが目立つようになり、業績回復期待などで株価が上昇するケースもありました。そこで今回は、従業員の解雇によって株価が上昇する現象など、日本人の感覚としてはなじみのなさそうな投資の常識・非常識の一部を解説します。
投資信託や銘柄にも直結する【インフレ】を見極めるための5つの指標
経済指標をおさえるメリットとは
今回は、投資信託や銘柄にも直結する、注目すべきインフレ関連の経済指標について紹介します。インフレ関連の経済指標をおさえることで、3つのメリットが考えられます。
東日本大震災から12年、現在までの市場の推移と資産形成において覚えておくべきこと
投資家が学ぶべき教訓
2011年3月11日(金)、前週の米雇用統計の影響もあり株価が軟調に推移するなか、14時46分、東日本大震災が発生しました。当時、筆者は日経225先物の買いポジションを保有していたものの、大引け(取引時間の終了、当時は15時10分)が迫るなか、地震が恐くて取引どころではなかった記憶があります。資産形成の重要なポイントとして、長期・積立・分散があげられますが、長期で投資を行っていくなかで、天災や戦争など、自分の力ではどうすることもできないことが発生する可能性もあります。
放置されてきた【PBR1倍割れ企業】に東証がメス−−日本市場はどう変わるのか?
背景に「物言う株主」の存在も
今年に入り、東証が開催している「市場区分の見直しに関するフォローアップ会議」の資料が話題を呼んでいます。2023年1月10日(火)と1月25日(水)、両日の資料で中長期的な企業価値向上に向けた取り組みの動機付けと題し、上場会社の資本コストや株価・時価総額への意識改革やリテラシー向上を促し、改善に向けた取り組みを促進すると掲げました。具体策として、継続的にPBRが1倍を割れている会社には、開示を強く要請します。実施時期は今年の春からとしており、早急に企業側にプレッシャーを与えたように感じます。
為替アナリストが「円安151円の更新は2030年以降になる」と考える理由とは
為替アナリストが「円安151円の更新は2030年以降になる」と考える理由とは
一時1米ドル=130円を割れる米ドル安・円高となりましたが、2月に入ると130円を大きく上回る米ドル高・円安に戻してきました。「円安復活で、ひょっとしたら2022年10月に記録した151円の更新に向かう可能性もあるのか!?」と、思う方はさすがにいないでしょうか。そうですね、さすがにそれは無理だと思います。あの151円の円安を更新するのは、早くても5~6年以上先、「早くて」そうなので、普通なら2030年以降の話になるのではないかと考えます。しかし、この円安も思っている以上に進むかもしれません。
テンバガー(10倍株)になりやすい条件とは?金融アナリストが注意点とあわせて解説
2021年・2022年のテンバガーも
「テンバガー」という言葉をご存知でしょうか?テンバガーとは、英語で10のtenと、野球の俗語で「塁打」を意味するbaggerをあわせた言葉で、10倍以上の株価成長を見せる銘柄のことを指します。皆様のなかには、テンバガーの銘柄を持って、利確した経験がある方もいらっしゃるかもしれません。テンバガー銘柄を予想できれば10万円が100万円に、100万円は1,000万円になります。一攫千金が狙えるということで夢が膨らみますが、テンバガーの予想はプロでも難しいと言われます。今回は2021年、2022年にテンバガーとなった日本の銘柄と、テンバガーになりやすい条件について、私なりの考えをまとめてみましたのでお伝えします。相場の値動きを知るだけでも知見が溜まっていくと考え、毎回恒例の一週間の相場まとめもありますので、どうぞ最後までお付き合いください。
FRBの金融政策、米国景気、日銀総裁の交代…今後の日本経済に大きな影響を与える4つの要因とその影響
投資で知っておくべきこと
3月決算企業の決算発表が終了しました。全体としては下方修正が相次いだかなり厳しい決算と言えそうです。
「物価上昇は続くも鈍化していく」日銀は日本の経済や物価の先行きをどのように見ているのか
日銀総裁人事に注目が集まる
日銀総裁人事に注目が集まっています。日本経済新聞が6日の早朝に「日銀次期総裁、雨宮副総裁に打診 政府・与党が最終調整」という記事を配信しましたが、雨宮氏が固辞したということで、黒田総裁の後任として経済学者の植田和男氏を候補とする人事案が国会で提示されました。黒田総裁は4月8日に2期10年の任期を終えるため、まだ現体制で1か月以上運営をするわけですが、現時点で日銀は日本の経済や物価についてどのような見解を持っているのでしょうか。日銀が公表する「展望レポート」から読み解きましょう。
日本電産、住友化学、村田製作所…グローバル企業の下方修正。上場企業の業績は本当に厳しいのか?
株式市場はどう受け止めたか
2022年度第3四半期の決算発表が一巡しました。改めて今回の決算を振り返ってみましょう。
医療、介護、事業承継…「2025年問題」の恩恵を受ける企業は?
アナリストが投資家目線で紐解く
「2025年問題」というのをご存知ですか?団塊の世代が2025年に、75歳以上の後期高齢者となることによって、日本の人口の年齢別比率が変化し、全人口の4人に1人が高齢者という超高齢化社会を迎えるということを指します。団塊の世代は昭和22(1947)年から昭和24(1949)年に生まれた方々で、総務省が発表した「統計からみた我が国の高齢者」によると、団塊の世代を含む75歳以上人口は1,871万人(総人口に占める割合は14.9%)で、80歳以上人口は1160万人(同9.2%)とのことです。超高齢化社会を迎えることによって、社会や私たちの生活に問題が出てくることも予想されます。
新設される「こども家庭庁」への違和感−−本当に危機的状況の少子化を乗り切れるのか?
足りないと感じる“働き手”の優遇策
「こども家庭庁」が2023年4月に発足します。政府が社会全体でこどもの成長を後押しするために創設しました。こどもの最善の利益を第一として、こどもの視点に立った当事者目線の政策を強力に進めていくことを目指しています。最重要コンセプトとして「こどもまんなか社会の実現」を掲げています。
FX予想「できること」「できないこと」の見極め、米ドル急騰の「雇用統計ショック」は想定内だったのか?
ポイントは為替相場の「行き過ぎ」
2022年10月にかけて展開した「止まらない円安」から、11月以降は「止まらない円高」に一変しました。ところが、2月3日(金)の米雇用統計発表をきっかけに、その流れは大きく米ドル高・円安へ戻す動きとなりました。この「雇用統計大相場」にどう対処すべきだったのか−−今回はFXトレードにおいて不可欠である相場の予想について、「できること」「できないこと」をどう見極めるべきか、説明したいと思います。
2月に権利確定する「配当利回りランキング」トップ5銘柄
配当+優待で家計を助ける
投資で得られる利益は大きく分けるとインカムゲイン(Income Gain)とキャピタルゲイン(Capital Gain)に分けられます。インカムゲインは株の配当や不動産の家賃収入などの資産を保有していることで得られる利益のことを指し、キャピタルゲインは資産の価値が買った時より上がり、売却によって得られる利益のことを指します。投資をする際には、どちらの利益を狙って投資をするのかを考えて、投資先を選択するとよいのではないでしょうか。この記事を読んでくださっている方は、配当収入を重視した投資に興味のある方だと思いますが、配当収入を狙う上で「配当利回り」は調べる必要があります。
オリエンタルランドにサイバーエージェントも…進む株主優待の二極化、拡充・新設する企業は?
株主優待の背景にある“日本らしさ”
サイバーエージェント(4751)が1月25日(水)に株主優待を新設すると発表しました。昨年、サッカーワールドカップを無料配信して話題を呼んだ、子会社にあたる「ABEMA」のプレミアム利用料の無料クーポン券を付与します。100株以上の株式保有者に対して3ヵ月分の無料クーポン、500株以上の株式保有者には12ヵ月分の無料クーポンを進呈する内容です。株主に優待制度を通じてサービスの理解を深めてもらい、中長期的に株式保有をしてほしいとの思いから株主優待の導入が決定した、と発表しています。月額960円の利用料金×12ヵ月分(500株以上保有)=11,520円分の優待となります。SNSでの反応はさまざまですが、概ね好評のようです。
世界10大リスクと日本が受ける影響とは?リスク1位の関連銘柄も
Z世代、水問題などもランク入り
米国の大手調査会社であるユーラシア・グループが毎年、年初に1年のリスクについてまとめていることをご存知でしょうか? 投資業界では有名だと思うのですが、一般的にはあまりニュースで見ることがないように思います。投資では“対処”がとても大切なので対処力を高めるためにリスクを知り、リスクが現実のものになってしまった時に上がりやすい銘柄を押さえておくことも戦略の一つですし、投資をしていなくても、私たちを取り巻く環境でどのようなリスクがあるのかを知っていることは大切だと思います。今回は米国の調査会社ユーラシア・グループが1月3日(火)に発表した2023年の世界の10大リスクとリスク1位の関連銘柄、加えてユーラシア・グループが挙げている日本が受ける影響ついても紹介します。
好調のサイゼリヤ、冴えない無印良品、ユニクロ…。小売業全体は好調でも差がでた要因
日本経済復活の起爆剤はいかに
3月末決算企業の第3四半期の決算発表が本格化しています。市場では米国や欧州などの景気減速を背景に、製造業を中心に通期の業績予想の下方修正が増えるのではないかとの懸念が出ているようです。