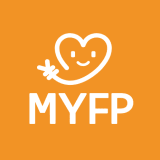返済に追われる生活…教育費の準備が間に合わなかった家計の行く末
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、貯金ゼロ、教育ローンの返済に追われる47歳の専業主婦。住宅ローンの返済も保険の契約者貸し付けに頼ります。子どもが独立するのを機に家計を立て直したいといいますが……。FPの横山光昭氏がお答えします。貯金がありません。子どもたちの学費のために今まで教育ローンをたくさん組んでしまいました。住宅ローンもあと16年残っています。ボーナス払いも使いながら返済していますが、この8年ほどはボーナスが出ておらず、保険の契約者貸し付けを使ってなんとか支払っています。老後の準備もしなくてはいけないので、ローン返済に追われる生活をなんとかしたいと思っています。自分もしばらくはフルタイムで働き、ローンの早期返済を目指していましたが、体調を崩したため今は専業主婦をしています。そろそろまたパートででも働きたいと思っているのですが、忙しくしてまた体調を崩すことがないようにと夫に言われており、まだ働き先を見つけることができていません。子ども2人が春から社会人となり、独立するので
働く主婦たちが「子育てとの両立で利用したいサービス」、断トツの1位は?
育児の負担は家庭によって様々だけれども
小泉進次郎環境大臣の育休取得は賛否両論を巻き起こしました。論争が起きるということは、男性の育児がまだまだ社会に浸透していないことの裏返しとも言えます。日本では、育児は女性がするものという認識が根強く残っていると感じます。その呪縛がある限り、子育ての負荷は女性の方に重くのしかかりがちです。仕事と家庭の両立を希望する“働く主婦”にとっては、子育ての負荷が減らないままでは、働けば働くほど心身を疲弊させてしまうことになります。では、どんなサービスがあれば働く主婦は助かるのか。純粋にサービス自体のニーズを探るため、金銭面での負担は考慮しないという条件で調査してみました。
手取り月40万の共働き夫婦「今の収入で子育てできますか?」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、低収入であるため将来の見通しが立たないという30代の共働き夫婦。子どもやマイホームが欲しいけれど、収入面で不安があり、なかなか踏み出せないといいます。FPの氏家祥美氏がお答えします。低収入であるため、将来の見通しが立ちません。子どもをもうけて生活できるのか、老後の費用が足りるのか不安です。結婚7年目、地方で共働きの夫婦です。お互い正社員ですが、二人とも田舎の中小企業勤めであり、給与・賞与の額が低く、また退職金も出るかどうかわからない状況です。結婚当初、お互いの手取りを考えたとき、子どもや持ち家を考えることは難しいかもしれないと思っていましたが、貯金が1000万円を超えたことで、もしかすると、それらの夢に挑戦してもいいのではないかとも思うようになりました。ただ、もし子どもを授かれたとしても、産休や育休、場合によっては私が仕事を辞めることになる可能性も考えなければならないとなると、収入が半減することになるため、やはり無理なのかなとも思います。年齢が
保険料に旅行費用、どれも必要で何を削ればいいのかわからない
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、住宅購入や2人目の子どもがほしいと悩んでいる34歳の主婦。旅行費用や保険料が高いと感じているものの、どれも必要な気がして、何を削ったらいいのかわからないといいます。FPの飯田道子氏がお答えします。戸建ての家を購入するか、もっと広い家に引っ越したいと思っていますが、金銭的に厳しいのかなと感じています。また、子どもがもう一人ほしいとも思いますが、子どもの将来にかかる費用を考えると躊躇してしまいます。旅行が大好きで、3ヵ月に1回は近場に、1年に1回は遠出をします。また1年に1回北海道へ帰省もするので、貯蓄はしているものの、旅費として使うお金も意外と多いです(年60万円ほど)。教育費や車の購入費(維持費含む)、子どもをもう1人授かった場合のお金など、大きくかかる出費については、毎月積み立てています。また、生命保険料が高いような気はしていますが、どれを削ったらいいのかわかりません。内訳は以下の通りです(どちらもがん家系のため、がん保険は外せません)。・火
核家族率の高い「浦安市」、子育て支援は充実している?
「孤育て」を救うサポート体制とは
東京に隣接する利便性から人気が高く、ベッドタウンとして発展している千葉県浦安市。同市もフィンランドのネウボラを参考に「切れ目のない支援」を行なっています。市の特徴としては、人口流動が大きく、高齢化率が低くて若い世代が多いこと。また18歳未満の子どもを養育する子育て家庭の核家族率は、平成27年は95.7%。祖父母が身近にいない、相談できる友人・知人もおらず「孤育て」に陥りがちな家庭の多さが浮かび上がります。そんな浦安市で、子育て家庭の孤立や不安を軽減するために行われているサポートの実態に迫ります。
37歳共働き夫婦「子ども3人を私立の小中高大一貫校に入れたい」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、もう1人子どもがほしいという高収入の37歳共働き夫婦。2人の子どもに加えて、授かれたら3人目も小中高大一貫の私立小学校に進学させたいといいますが……。マネーフォワードから生まれたお金の相談窓口『mirai talk』のFP秋山芳生氏がお答えします。現在子どもが2人おり、2人とも小中高大一貫の私立小学校に入れようと考えております。長男はすでに幼児教育の塾(月額4.8万円)に通っております。この状況で2年後にもう1人子どもを作りたいと考えていて、その子も同じように私立小学校に入れるとした場合、金銭的に実現可能か教えていただけないでしょうか。なお、住宅ローン残高が3700万円あり、年間4~6回は国内・海外旅行(1回あたり20~50万円かかります)に行っております。また幅広く投資をしていて毎月配当金があります。 <相談者プロフィール>・男性、37歳、既婚(妻:37歳、会社員、育休中)・子ども2人:4歳、1歳・職業:会社員(コンサル)・居住形態:持ち家(
子育てファミリーに朗報、「ファン付きウエア」がベビー用品に進出の衝撃
空調服とエルゴベビーがタッグ
子育て中のファミリーの大きな悩みの1つといえば、子どもの温度調節ではないでしょうか。冬場の保温はもちろん、夏場の猛暑をどうしのぐかは、多くの家庭で悩みの種となっています。そんな課題を解決する一助となりそうな新商品が、今年の春夏シーズンに登場することになりました。炎天下の工事現場で働く人の必需品「ファン付きウエア」を製造するアパレルメーカー・空調服が、ファン付きのベビー用品を売り出すことがわかったのです。育児用品で高い認知度を誇る「エルゴベビー」の販売会社とタッグを組んだという新商品は、どのような物なのでしょうか。2月7日まで東京都内で開かれている内覧会を取材しました。
「家計見直せ夫」に地道に立ち向かう、家庭内金銭バトル
お金と男と女の人生ルポ vol.23
結婚すれば夫婦ふたりで家計をやりくりしていくのは当然のこと。日本では妻が家計を握っているケースも多いのですが、夫が生活費として一定の額を毎月、妻に渡す方法をとっている家もあるようです。
共働きワンオペ育児がつらい…やりがいのある仕事を手放してもいい?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、仕事のやりがいはあるものの、フルタイム勤務がつらいという34歳の共働き主婦。パートに切り替えたいといいますが、いまのような貯蓄ができなくなることが不安だといいます。FPの鈴木さや子氏がお答えします。 体力的にも、気力的にも、子育て環境的にも、フルタイム共働きがキツイです……。いまの職場では法人営業部に所属していて部下が数名おり、責任もやりがいもあります。ただ、持ち帰りの仕事も多く、残業もあるため、子どもとの時間がなかなか取れません。パートに切り替えたいとも思いますが、妻の給与が半分または3分の1になった場合、いまのような貯蓄はできず、子どもの教育費や老後など、将来の家計的に大丈夫なのか漠然とした不安に駆られます。夫は泊まりや研修も多いので、ほぼワンオペ育児になります。夫の仕事ぶりを尊敬しておりますので、夫側の働き方を変更することは考えていません。〈相談者プロフィール〉・女性、34歳、既婚(夫:34歳、会社員)・子ども2人:9歳、2歳・職業:会社
子どもにはお金の教育をしたい 、親子で始められる投資ってないですか?
まずは金融機関に口座を作ってみよう
2019年には「老後生活費2000万円」と話題になりましたが、人生100年時代には、人生設計を考えて、それに伴いお金についても学ぶことが必要です。子どもたちはまさに人生を100年かけて駆け抜けていこうとしています。そのためには経済的な裏付けが不可欠です。経済設計を学ぶにあたり、投資という方法を知ることで、社会や経済の仕組みにも興味を持ち、理解することができます。しかし、親がお金に対して深く考えずに生きてきたとしたら、いざ子どもにお金の教育をしたいと考えたときに、親である自分ではとてもできないかもしれないとあきらめていませんか。そもそも、学校では教わってこなかったお金のこと、無理はありません。そこで、親子で投資を始めてみたらいいのではないかと考えます。
30代共働き・夫婦別財布「出産・育児で妻の収入が減るのが不安」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、妻の方が収入が高いという夫婦別財布の30代共働き主婦。この先、出産や育児で妻の収入が下がることを考えると、漠然と不安だといいます。FPの三澤恭子氏がお答えします。夫婦共働きで、財布は別です。それぞれ月5万円ずつ、夫婦の共通口座に貯蓄しています。貯蓄と生活費を出し合って残ったお金は、お小遣いとしてそれぞれが管理しています。いまは夫よりも給与が高いですが、今後子育てや老後を考えると、私の収入が下がることも予想されるので漠然と不安です。そんなに無駄遣いをしているとは思いませんが、このままでいいのかアドバイスがほしいです。よろしくお願いします。〈相談者プロフィール〉・女性、31歳、既婚(夫:31歳、会社員)、子どもなし・職業:会社員・居住形態:賃貸・毎月の手取り金額:49万円(夫:21万円、妻:28万円)・年間の手取りボーナス額:120万円・毎月の世帯の支出目安:約39万円【支出の内訳】・住居費:8.5万円・食費:5万円・水道光熱費:1.3万円・教育費
子どもが大学生の頃には年金生活…教育費と老後資金の準備法
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、介護が終わり、これから子どもを授かりたいという共働き夫婦。ただ、もし子どもを授かることができたとしても、大学に通う頃には、夫は年金生活に入っています。教育資金と老後資金はどう準備したらよいのでしょうか。家計再生コンサルタントの横山光昭氏が運営する『マイエフピー』のFPがお答えします。義母を看取り、介護が終わったので、ようやく夫婦の時間を持てるようになりました。これから5年以内にできれば子どもを2人もうけ、10年以内に今の家(介護のために中古物件を購入し住宅ローン支払い中)をリフォームしたいと考えています。夫は再婚で、あと10年ほど養育費の支払いがあります。ですが、それ以外のお金は家計に入れてくれていて、私の収入と合わせて生活しています。支出もできるだけ抑える努力はしていて、毎月5万円ずつ積立貯金をし、余剰金も5万円ほど出せてはいますが、貯金可能額としてはこれで精いっぱいです。この先、子どもを授かった場合、子どもが大学に通う頃、夫は年金生活です。
亡くなった夫が残した手紙に…行き場のない後悔を抱えて過ごす46歳女性
お金と男と女の人生ルポ vol.20
男女の関係がうまくいくかどうかは、縁とタイミングだとよく言われます。恋人同士にしろ夫婦にしろ、ほんのちょっとしたズレが関係を変えることがあるのではないでしょうか。アユミさん(仮名=46歳)は、今でも気持ちの持って行き場がないことがあると話してくれました。
子どもの"家計力"を養うチャンス!効果的なおこづかいの渡し方とは?
定額それとも必要な都度?お年玉はどうする?
みなさんは子どもにおこづかいを渡していますか?たとえ毎月決まった金額のおこづかいをあげていない家庭でも、必要な物を買うお金やお年玉など、子どもがお金を手にする機会は少なくないはずです。大人になると誰もが少なからず家計を管理しますが、学校ではお金の上手な使い方や管理の方法を学ぶ機会はほとんどありません。「おこづかい」は、子どもにとってお金について学ぶ貴重なチャンスなのです。そこで今回は、おこづかいを通して将来役立つ家計力を育てるコツを紹介します。
夫亡き後、未成年の子どもがいるとマイホームを売却するのに時間がかかる理由
相続人の権利は未成年の子どもにも平等
不慮の事故で亡くなった夫。遺された妻は悲しみに暮れる暇もなく、ひとりで3人の子どもを養っていかなければなりません。妻は、夫が遺してくれたマイホームを売却する決心をしますが、マイホームの名義を亡くなった夫から相続人である妻に変えるのは簡単なことではありませんでした。なぜなら、未成年の子どもたちにも相続権があるからです。自分が亡くなった後に大切な家族が困らないように、子どもが生まれたら、自分名義の住宅を購入をしたら、遺言書の作成をしておいた方がいいといいます。
お年玉口座を開くのに、今ならネット銀行に預けるべき?
15歳未満でも口座が持てるネット銀行を探してみよう
お年玉の預け先はどうしていますか?子ども用の口座を銀行につくっている親も多いと思います。わが家では、親があらかじめつくった子ども用の口座もありましたが、ある程度の年齢になったら、子ども自身に口座をつくらせてその後は管理も任せるようにしてきました。銀行には、店舗を持ついわゆる馴染みのある銀行のほかに、ネット銀行という存在もあります。ネット銀行はわざわざ銀行の店舗に出向かなくてもコンビニなどで手軽にお金の入出金ができる便利な面を持っています。2019年は消費税増税もあり、キャッシュレス元年とも呼べるような年でした。お金の預け先もこれからどんどん多様化されていくことでしょう。そこで、お年玉の預け先の選択肢にネット銀行を取り入れてみましょう。
私立中学進学と1億円の住宅購入、高収入家庭の皮算用
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、夫が総合商社に勤める高収入世帯の20代夫婦。現在は海外に住んでいますが、帰国後は子どもを私立中学に通わせ、1億円近い住宅を購入したいといいますが……。FPの黒田尚子氏がお答えします。住宅購入資金と十分な教育資金を確保したく、ご相談しました。できればもう1人子どもが欲しいのですが、中学から私立に入れることを考えると金銭的に不安があります。3人目はあきらめるべきでしょうか。3人の子どもを中学から私立に通わせ、理想に近い住宅(1億~8000万円程度)を購入するためには、どのように計画を立てていけば実現できますか。現在は夫が海外駐在中のため、日本で勤めていたときよりも給料が増え、年間500万円程度貯金ができていますが、数年後に帰国した際は給料が下がり貯金のペースが落ちることが予想されます。ただ今後も数回、海外駐在がある予定です。第一子が3歳を過ぎたタイミングで、私も前職と同程度(手取り年350万円ほど)稼げる正社員として再就職をして家計を助けたいのです
なぜ主婦層の7割は、就職氷河期世代支援に期待しないのか?
“今更感がある”、“もう中年”の声も
政府は就職氷河期世代の人たちを支援し、3年で30万人の正規雇用者を増やす目標を掲げています。就職氷河期世代支援プログラムの概要には、支援対象について以下のように記されています。「支援対象としては、正規雇用を希望していながら不本意に非正規雇用で働く者(少なくとも50万人)、就業を希望しながら様々な事情により求職活動をしていない長期無業者、社会とのつながりを作り、社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする者など、100万人程度と見込む」上記にある100万人の対象者への支援は必要だと思います。しかしながら、就職氷河期世代に生まれたために辛い思いをした層を支援するにあたって、「30万人の正規雇用者を増やす」ことは、果たして適切な目標だと言えるのでしょうか?