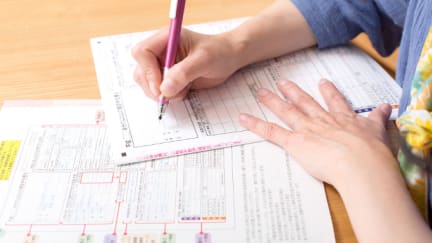脱税者を取り締まる税務調査とは?お金の隠し場所と使い道
第1回:税務署はどうやって不正を見抜くのか?
青汁王子や銀座の高級クラブのママによる脱税事案が、最近各種メディアで取り上げられました。脱税という言葉そのものはよく耳にするので、なんとなく身近なものに感じている人がいると思います。一方で、脱税とは一体何なのか? 誰がどうやって見抜いているのか? 自分の周りや、自分の身にも起こりうる話なのか? 具体的に質問されると、うまく答えることができない人が多いのではないでしょうか。今回は、知っているようで知らない「税務署の不正の見抜き方」について、3回にわたってお話していきたいと思います。
住宅ローン控除利用中にふるさと納税はいくらまで大丈夫?
医療費控除やiDeCoにも注意!
住宅ローン減税とふるさと納税の両方を行う場合、いくらまでなら損をしないか?気になる人も多いことでしょう。今回は、住宅ローン控除を利用している方がふるさと納税を利用する際に気をつけたいことをお話しします。
男性の育休で収入は…育児休業給付金で「実質9割カバー」は可能?
男性育休の特別制度や育休中の就労なども活用を
あなたは「子どもが産まれたら夫婦で協力して子育てしたい」と思いませんか?厚生労働省「平成29年度雇用均等基本調査」 によると、男性の育児休業(以下「育休」)取得率は徐々に高くなっているものの、平成29年度は5.14%であり女性の83.2%に比べるとかなり低い数字といえます。男性が育休取得に踏み切れない理由は、職場の雰囲気や仕事の調整以外にも「減収」が思い浮かぶことでしょう。しかし実は、育休制度をよく理解して利用することで育休中の減収は最小限に抑えることができます。今回は、減収の備えとなる育児休業給付金のほか、男性育休の特別制度や育休中の就労条件など、男性の育休取得を応援するお役立ち情報をご紹介します。
収入の4割を占める住宅ローン、借り換えを検討すべき?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、25歳の時に都心の1LDKマンションを購入した30歳の未婚男性。月8万円の住宅ローンの返済が重すぎて貯蓄もままならないといいます。ローンの借り換えをして負担を減らした方がいいのでしょうか。FPの横山光昭氏がお答えします。東京で一人暮らしをはじめ、25歳の時に都心で1LDKのマンションを購入しました。5年間、住宅ローンの支払いを続けているのですが、毎月その返済でいっぱいいっぱいで、貯蓄がまったく増えません。購入時は、結婚したら売ればいいか程度に考えていたのですが、30歳になった今、結婚するような相手もおらず、このまま一人なのかもしれないと思っています。婚活もしているのですが、なかなか実らず、あきらめモードとなってきています。今は住宅ローン控除を受けているところですが、金利が低いので、住宅ローンの借り換えをしたほうが後々のためにはよいのかなと考えています。借り換えをしたほうがよいでしょうか?〈相談者プロフィール〉・男性、30歳、未婚・職業:会社員・
消費税10%で変わる?増税前に知っておきたい住宅価格への影響
書類作成と手続き、少しの手間で大きな減税
8%から10%へ、2019年10月から消費税増税が予定されています。これまで3%、5%、8%と消費税率はじわじわと上がってきたわけですが、そのたびに、増税前の駆け込み消費などが話題となってきました。大きな買い物ほど、消費税アップの影響を受けることになります。では、住宅購入の場合はどうでしょうか。住宅ローン控除の変更点とあわせて確認したいと思います。
確定申告すると「得する」会社員ってどんな人?
会社員に認められている必要経費とは
会社員は勤め先に年末調整をしてもらえます。そのため、基本的には確定申告をしなくてもいいことになっています。しかし、会社員でも、給与から天引きされた源泉税等や予定納税額が、年間の所得に基づいて計算した税額よりも多い場合は、税金を納めすぎていることになるので、確定申告をすれば税金が戻ってきます。この申告手続のことを、特に「還付申告」といいます。今回の記事では、確定申告をする必要のない会社員でも、確定申告をすることで税金が戻ってくるケースについて、そして還付申告のやり方についてお話します。
ワンストップ納税し忘れた!ふるさと納税の確定申告はどうすればいい?
ふるさと納税したときの確定申告のしかた
ふるさと納税は、返礼品が送られるだけでなく、所得税・住民税の減税を受けることができるのも大きな魅力です。会社員や公務員はワンストップ特例制度を活用すると、確定申告が不要で、翌年の住民税負担が減り、手取りが増えます。けれども、「ワンストップ特例の申請書を出し忘れた」、「知らない間に6つ以上の自治体にふるさと納税してしまっていた」など、ワンストップ特例制度が使えない人は、翌年以降5年以内に確定申告する必要があります。今回は、会社員や公務員がふるさと納税をしたときの、確定申告のしかたについて具体的にお伝えします。
どっちがお得?医療費控除とセルフメディケーション税制
確定申告のひと手間で税金を減らそう
「この1年、病院に行く回数や市販薬を買う機会が多かった」という方は、1年間にかかった医療費がいくらになるのかを確認してみましょう。「医療費控除」もしくは「セルフメディケーション税制」を利用することができれば、支払った税金の一部が還ってくる可能性があります。今回は、2つの制度の仕組みや特徴を紹介します。
期間延長、住宅ローン控除は消費税10%でどう変わる?
今年の税制改正は“消費税率引き上げ対策”
前回の記事では、2019年度の税制改正のテーマは“消費税率引き上げ対策”であるとお伝えしました。今回は、“消費税率引き上げ対策”のうちのひとつである「住宅ローン控除」の改正についてお話していきたいと思います。そもそも住宅ローン控除とは何かを解説してから、改正の内容を紹介します。
育休中は正社員の妻を扶養に!「配偶者特別控除」の活用法
節税効果だけでなく保育料が安くなる可能性も
正社員の妻でも育休中の間は「配偶者控除」「配偶者特別控除」を活用して税金が低くなるかもしれないことをご存知でしょうか?配偶者(妻)が正社員や年収が高い場合「税金の控除は関係ない」と思いがちですが、育休中など年収が低い場合は、控除対象になる可能性があります。さらには、復帰後の保育料も安くなる可能性もあります。今回は、育休中の子育て世帯がチェックしておきたい「配偶者控除」「配偶者特別控除」について、ご紹介します。
被災地に代わり他の自治体が寄付を集める、ふるさと納税の意外な活用法
ふるさと納税のことをもっと知ろう
平成最後の今年の漢字が「災」に決まりました。2018年は、地震や台風などの自然災害が次々に日本列島を襲った年。困ったときはお互いさまということで、被災地を応援しようと、いろんな形でいろんな人が被災地支援を行う姿を目にするようになりました。実はふるさと納税はいま、被災地支援の一手段として一般的になりつつあるということをご存知でしょうか。今回の記事がふるさと納税シリーズの最後となります。ふるさと納税をもっと楽しめるようなテーマとして、[1]ふるさと納税によくある失敗談と、[2]ふるさと納税のちょっと意外な活用法について取り上げたいと思います。
ふるさと納税で損をしないために、知っておきたい税金のこと
ふるさと納税のことをもっと知ろう
街にクリスマスの音楽が流れ、イルミネーションが綺麗に輝く時期は同時に、ふるさと納税のラストスパートの時期でもあります。会社員の方は12月にボーナスが支給されると年間の収入金額がほぼ確定しますし、自営業の方も12月に入れば年内の収入がだいたいわかるかと思います。これから、ふるさと納税の最終的な調整をするという方も多いでしょう。今回は、ふるさと納税シリーズの第三弾として、ふるさと納税の肝となる「税金」についてのお話をしていきたいと思います。
5つのステップでできる!ふるさと納税の手続きと注意点
ふるさと納税のことをもっと知ろう
「今年のふるさと納税、どこにした?」――みなさんの職場やご家庭で、そんな会話が聞こえる時期となってきました。早いもので2018年も残すところあと1ヵ月。毎年ふるさと納税をしている方は、そろそろラストスパートをかける頃かと思います。もしかすると、12月の1ヵ月だけでふるさと納税を終わらせるという方もいらっしゃるかもしれません。そこで今回は、ふるさと納税シリーズの第二弾として、ふるさと納税の手続きはどうすればよいのか、どういう基準で寄附する自治体を選んだらいいのか、手続きをする上での注意点についてお伝えしたいと思います。
多くの人が見落としている「ふるさと納税」本当の魅力
利用率No.1サイトで賢く選択
2018年も残りわずか。毎年、年末になるとにぎわうのが「ふるさと納税」の駆け込み需要です。ふるさと納税という言葉自体は今や認知度が90%を超えるものの、実際に行っている方は15%という話もあります。あと一歩が踏み出せていない理由として「具体的なメリットがわからない」「手順がわからず面倒だ」という声を耳にします。そこで今回は、ふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を企画・運営する、トラストバンクの広報・田中絵里香さんにインタビュー。ふるさと納税の手順やメリット、ふるさとチョイスの活用法など、これから初めてふるさと納税を行う方、行ったことはあるけれど今年のお礼の品を迷っている方にとって必読のお話を聞きました。※サブタイトルの「利用率」は2018年10月11日~12日 調査委託先:マクロミル
利用者激増!10年目を迎える「ふるさと納税」はどんな制度?
ふるさと納税のことをもっと知ろう
あなたにとって、「ふるさと」とはどこですか? そこは、必ずしも生まれ育った土地ではないかもしれません。ふるさと納税の“ふるさと”も、それと同じように、必ずしも生まれ育った土地ではない場所を包含する概念になっています。今年、ふるさと納税の制度は、スタートしてからちょうど10年という節目を迎えました。制度を利用しているかどうかはさておくとしても、ふるさと納税という言葉を聞いたことがないという人はいないくらい、ふるさと納税は全国的に浸透しています。ふるさと納税シリーズ第一弾は、ふるさと納税の制度趣旨と概要、見直しの動向についてお伝えいたします。(※なお、本シリーズでは特に断りのない限り、個人のふるさと納税を前提としています)
ふるさと納税をするときの具体的なやり方解説
初心者のためのふるさと納税
年末が近づき、話題になるのが「ふるさと納税」。ここ数年、お得度もアップし、ふるさと納税を利用する人が増えています。前回、実は簡単「ふるさと納税」、税金が安くなるのはどういう仕組み?を紹介しました。実際、次はどうすればいいのか、具体的な手順を紹介します。
実は簡単「ふるさと納税」、税金が安くなるのはどういう仕組み?
初心者のためのふるさと納税
たとえば、○○市に2万円寄付をする→もともと自分が納めなければならなかった税金が1万8,000円少なくなる→寄付先から肉や魚、米や酒、果物などの返戻品がもらえる。上手に寄付すれば自分の持ち出しは2,000円だけ。ふるさと納税を簡単に言うとこうなります。ここ数年、使いやすくお得度がアップしたため、ふるさと納税をする人が急増しています。一方、この制度を推し進めていた総務省が、返戻品競争の過熱ぶりに待ったをかけ、返戻品を寄付金額の3割以下にするよう要請したり、見直しをしていない自治体名を公表したり……と改正の動きも出ています。あらためて今回は話題の「ふるさと納税」の基本的な仕組みとやり方、注意点などを取り上げましょう。
プレ定年夫婦が税金を払わずに資産形成できる方法
夫婦2人で1,600万円の非課税の隠し口座を活用しよう
いま50代夫婦が最も気になることは、老後のお金ではないでしょうか?正面から取り組むのは怖いので目を背けたくなるところではありますが、50代は人生100年時代の折り返し地点、お金や夫婦関係・人生を見直すラストチャンスと言えます。