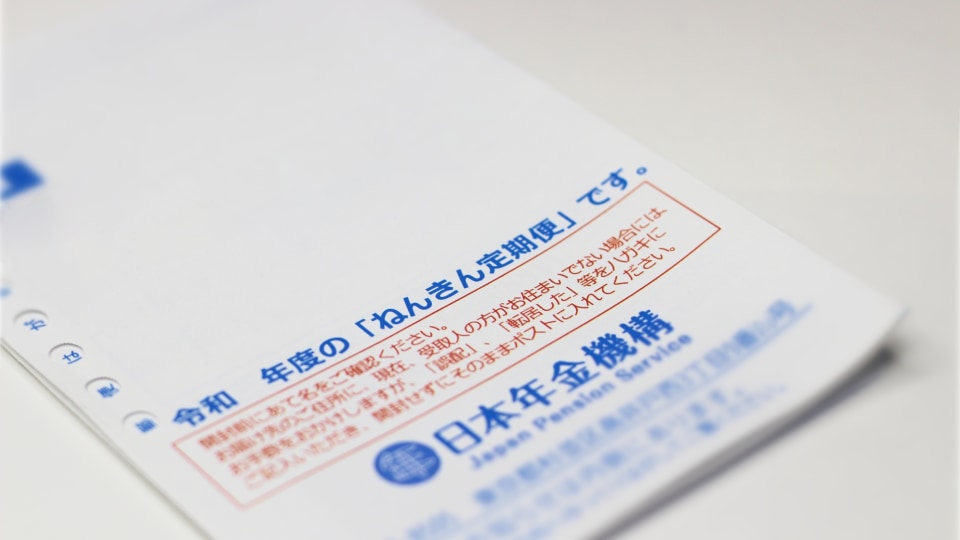はじめに
2025年4月より、ねんきん定期便には事業主が負担した保険料が明記されることになりました。SNSなどで「年金給付額を多く見せようとするためにわざわざ事業主負担分を記載していないのだ」という批判があったことを受けての対応のようですが、本当にそうなのでしょうか?
厚生年金保険料はどう決まる?
会社員は毎月給与から厚生年金保険料が天引きされます。この料率は、平成29年9月に最後の引き上げが終了し、以降18.3%に固定されています。会社員の社会保険料は労使折半ですから、実際は会社員自身が9.15%を負担し、事業主が9.15%を負担します。
この料率は報酬に対してかけられるため、賃上げや昇級などで報酬が上がると毎月負担する保険料の金額も上がります。ただし、月の報酬は4月から6月までの3ヶ月間の手当などを含む総額を平均し、さらに定められた金額の幅に従って32等級に分けられるので、原則年間を通して一定です。
月の平均報酬が93,000円未満だと標準報酬月額は1等級、88,000円となり、その9.15%である8,052円が本人が負担する厚生年金保険料、そして同額の8,052円が事業主が負担する厚生年金保険料です。
2等級は、月の平均報酬が93,000円以上101,000円未満、標準報酬月額は98,000円です。先ほどと同様、この標準報酬月額に9.15%の料率がかけられますので、本人負担の保険料は8,967円、事業主負担も8,967円です。
標準報酬月額には上限があり、月の平均報酬が635,000円以上は32等級となり、標準報酬月額は650,000円として計算されます。従って、月の平均報酬が80万円であったとしても等級は32等級なので、負担する厚生年金保険料は65万円の9.15%、すなわち59,475円となります。この額は、実際の平均報酬80万円の7.43%となります。
このように会社員が負担する保険料は、単純に給与の額に料率がかけられるわけではないので、負担率が人により若干異なることになります。一方、賞与は支給された賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てた額を標準賞与額とし、そこに保険料率をかけます。ただし標準賞与額には1ヶ月あたり150万円という上限が定められています。
つまり、賞与が50万円の場合の自己負担保険料は、9.15%なので45,750円、賞与が180万円の場合の自己負担保険料は、150万円に9,15%をかけるので137,250円(実質負担率7.625%)になるのです。
事業主が負担する保険料は、上記で示した会社員本人が負担した保険料と同額となりますので、今回の見直しにより、ねんきん定期便にその額が記載されることは、改めて年金の仕組みの理解を深めるためには良いことなのではないかと思います。
将来の年金額はどのように決まっている?
では、将来受け取る老齢厚生年金の額はどのように計算されるのでしょうか? 実は、払った保険料がいくらなのかということは、受取り額にはまったく関係ありません。将来の年金額は以下の計算式で求められます。
平成15年3月以前の厚生年金加入期間については、平均標準報酬月額に1000分の7.125を掛けて計算します。また平成15年4月以降の厚生年金加入期間については、平均標準報酬額に1000分の5.481を掛けて計算します。
平成15年3月までは、賞与は将来の年金額に算入されませんでした。しかしその後は算入されるようになったので、平均標準報酬額はと標準報酬月額と標準賞与額の総額を対象とする加入期間で割ったものとなります。
平成15年4月以降の入社の方を考えてみましょう。現時点で勤続20年、この間の平均標準報酬額は40万円と仮定します。平成29年までは厚生年金保険料率は上昇し続けていたので、実際はそこまで高くはありませんが、この20年間で負担した保険料は40万円x9.15%x20年x12ヶ月=8,784,000円となります。
この20年間の加入で約束された将来の老齢厚生年金の額は、40万円x5.481/1000x20年x12ヶ月≒530,000円となります(実際は、物価や賃金の変動に合わせて「再評価率」を乗じるのでさらに複雑な計算になりますが、今回は割愛します)。
この数字を出すと、多くの方は880万円ものお金を払って年金はたったの53万円かと思うかも知れませんが、厚生年金保険料には国民年金保険料も含まれているので、国民年金も受け取ります。
仮に年金加入期間が20年、会社員として厚生年金保険料を負担したその金額の一部が国民年金保険料として支払われているとすれば、この間で将来約束される老齢基礎年金は、(令和7年度老齢基礎年金満額831,696円x20年/40年=)415,848円となります。
つまり、約880万円負担した保険料によって得られる年金額は約95万円です。つまり、65歳から年金を受給すると、払込保険料分を回収するまで9.3年かかります。日本人の平均寿命は、男性が81.09年、女性が87.14年ですから、75歳で元をとりその後の年金は利息部分と考えることもできるかも知れません。