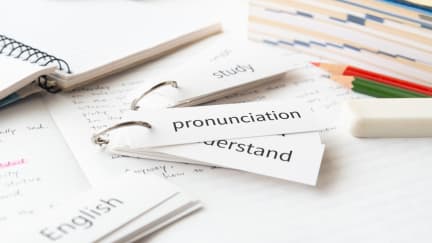「ネガティブな感情」は自分を知るためのツール?不安や焦りとうまく付き合う方法
感情はコントロールしなくていい
ただでさえ変化が激しく先が見えづらい世の中なのに、新型コロナウィルスの感染拡大によって、ますます不安やストレスを感じることが増えました。不安は心をざわつかせ、ときにはネガティブな感情の連鎖に陥ります。そして、あまりにもネガティブな自分に嫌気がさして、「不安な気持ちを抑える方法があればいいのに」と考えてしまいます。ところが、心理カウンセラーでベストセラーの著書を持つ石原加受子さんによると、不安や怒りのようなネガティブな感情は、抑えたり、コントロールしたりすべきものではないそうです。石原さんはネガティブな感情を「自分を守るための貴重な情報」ととらえて、次のように述べています。感情によって、自分に何が起こっているのかがわかります。とくにネガティブな感情であれば、それによって、自分のどこに問題があるのかを探り当てることができます。感情は自分の問題点を見つけ出すツールなのですから、「感情を抑えたり、コントロールする」というのははっきり言うと間違っているのです。(『感情はコントロールしなくていい』p15より)では、たとえば「不安」という感情とはどう付き合えばいいのでしょうか。石原さんの著書『感情は
ZoomやGoogle Meetで使える「オンラインセールスのトーク術」
対面で行う従来のセールストークとはここが違う!
アフターコロナを見据え、出勤や勤務体系、オフィスの新しい在り方が模索されています。当然、営業活動もその一つ。従来の「アポを取り付けて相手方に出向いて対面で行う」というスタイルが、今後はZoomやGoogle Meetなどのオンライン会議システムを用いた商談にとって代わるとみられています。営業コンサルタントの横山信弘氏は、従来の「担当と会う→雑談でアイスブレイク→セールス後、相手方の社内検討を経て諸条件のすり合わせ」というフローから頭を切り替えなければならないと説きます。そのコツを「before→after形式」で書いた横山氏の著書『簡単だけど、一瞬で心をつかむ77のルール セールストーク力の基本』からpickupしてみてみましょう。※本記事は同書の一部を抜粋・編集したものです
元敏腕刑事が教える「隠し事を暴く」3つのテクニック
まずは自分から心を開くこと
被疑者が隠している事実を心から完全に反省し真実を言わせることを、刑事の世界では「完落ち」と言います。被疑者といえども、人には誰にでも言いたくないことがあり、それに対して刑事は言いたくないことを言わせなければならない立場にあります。ですから、取調べにおいて大切なのは、人と人との心の触れ合いです。そういった意味で、刑事は「コミュニケーションの専門家」と言えます。さまざまな職種や立場の方と接し、相手の心理を読んで、言いたくないことを聞き出すというスキルは、世の中の幅広い職業に活かせるのではないでしょうか。詐欺や横領、贈収賄、選挙違反などの事件で2000人以上の取調べを担当してきた元敏腕刑事であり、『元知能犯担当刑事が教える ウソや隠し事を暴く全技術』の著者・森透匡さんが、会社の部下や同僚、交際相手の隠し事を暴く方法を解説します。※本記事は同書の一部を抜粋・編集したものです
テレワークは朝1時間で9割決まる!生産性を上げてメリハリがつく「モーニングルーティン」のすすめ
「意思が弱い」と自分を責めないで
新型コロナウイルスの影響で不要不急の外出を控えるなか、テレワーク、時差通勤、遠隔教育 を始める人が増えました。テレワークによって「通勤時間がなくなりストレスが減った」という意見もある一方で、・メリハリをつけるのが難しくリフレッシュできない・「やろう!」と思っていたことはたくさんあるのに、ついダラダラして進まない・家族と一緒の部屋で仕事をしているので集中力が続かない・不安感からついTVやSNSでコロナ関連のニュースを見てしまい、仕事が止まるなどといった悩みもよく聞きます。今まで「通勤」「対面での仕事」「職場で同僚と一緒にデスクで仕事を頑張る」という、ある意味「意思」や「やる気」を出さなくても良い「強制力」によって、仕事の生産性を上げてきました。その強制力が急になくなり、自分でなんとか頑張らないと回らない状態に放り出されてしまったのが今なのです。そこで、朝活の第一人者であり『「朝1時間」ですべてが変わるモーニングルーティン』の著者・池田千恵さんに、テレワークでも生産性を落とさないタスク管理の習慣について聞いてみました。
書類選考で落ちる履歴書・職務経歴書にありがちな特徴とは?
ネット記事ではあまり見ない「応募書類に何を書いたらいけないか」のポイント
何らかの理由で退職して再就職をめざすなら、履歴書や職務経歴書を書かねばなりません。そのとき「”なぜ同業他社ではなく、その会社を選んだか“を書く」「自分の能力でどう貢献できるかを書く」などと言われますが、みなさんが本当に知りたいのはそんな当たり前の事ではなく「どこに気を付ければ”書類落ち“しないのか」ではないでしょうか。『それでも書類選考で落とされない履歴書・職務経歴書の書き方』(中園久美子著)を参考に、「落とされる履歴書・職務経歴書の特徴」を2つ、紹介します。
メンタリストに学ぶ「大勢の前でも緊張しない唯一の方法」
「ありのままで」が大事
大勢を前にしてスピーチやプレゼンをするときは、緊張してどうしても早口になってしまうものです。聴衆には神経質でせわしない印象を与えてしまい、話の内容も伝わりにくく、またそんな会場の雰囲気を過敏に感じ取ってますます緊張してしまう……。落ち着いて、ゆっくり話すにはどうすればいいのでしょうか。ロミオ・ロドリゲス Jr.さんは、『メンタリズム 最強の講義』の著書を持つメンタリスト。堂々とした心理術パフォーマンスで聴衆を驚かせる、話術のスペシャリストでもあります。ロミオさんは同書で「大勢の前でも緊張せずに話す、唯一の方法」を紹介しています。早速見てみましょう。
あらゆる試験を突破する「暗記のすごいコツ」
ペーパー試験は暗記が明暗を分ける
春からの新生活にむけて勉強を始めたものの、覚えることが多くてすぐに忘れてしまう……そんな悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。資格試験・大学入試・社内の昇進試験など、いわゆるペーパー試験の合格のカギは「暗記」にあります。勉強した内容を暗記して、試験会場で答案用紙に適切に吐き出すことができれば、どんな試験にだって受かるのです。難しいのは、どうやって暗記したらいいのか――。この一点に尽きるといえます。ここでは『図解でわかる 暗記のすごいコツ』の著者・碓井孝介氏が、有効で効率的な「暗記のコツ」を紹介します。すぐに真似できる方法ですので、ぜひあなたの勉強生活に取り入れてください。
元テレ朝アナウンサーが教える「噛まないトークの下準備」
噛まずに話すコツは「30 秒のラ行」にあり!
プレゼンをはじめとするビジネストークから愛の告白まで、話のなかの「ここぞ」という場面で噛んでしまい、あとで恥ずかしさに悶える人は数多くいます。噛むのを防ぐには滑舌をよくするのが一番ですが、どうすればいいのでしょうか。元テレ朝アナウンサー・渡辺由佳さんの著書から見てみましょう(参考文献:『どんなに緊張してもうまく話せる!』)話すときに噛んでしまうのは、「緊張からくるストレス」のせいだと思っていませんか? じつは、そうではありません。「舌の筋肉が半分寝ている」ことが原因なのです。そこで話し出す前に、ウォーミングアップをして舌の筋肉を動かしましょう。そうすれば、噛まなくなります。
「だから、何?」と上司がイラつく説明下手な部下の特徴と改善策
仕事のできる人が絶対やらない説明の仕方
上司への報告がイマイチ上手く伝わっていない気がする……。その原因はあなたの「説明の仕方」にあるのではないでしょうか。ここでは、研修講師として活躍する車塚元章さんの新著『仕事のできる人が絶対やらない説明の仕方』の第2章「職場で上司から評価される説明の仕方」から、伝わりにくいダメな報告にありがちな特徴とその改善例を紹介します。
2020年こそ「目標達成」したい!と思った人が挫折しない6つのポイント
その目標に「ワクワク感」はありますか?
皆さんは、昨年に立てた目標を達成できたでしょうか。残念ながらあと一歩届かなかったり、途中で挫折してしまった人は、「今年こそはいい年にしよう!」と新しい目標に向かい始めていることでしょう。2020年こそ絶対に目標を達成したい──。挫折を繰り返さないためにはどうすればいいのでしょうか。弁護士として多くの経営者、成功者を間近に見てきた三谷淳さんは著書、『最高の結果を出す 目標達成の全技術』で 「達成できる目標を設定するためのポイント」を6つ挙げています。 良いスタート切るための参考に、それぞれ紹介していきましょう。
まとまらない会議や打ち合わせの3大原因は?
「思考整理」で仕事のスピードも質もアップする
時間を浪費するばかりで議論がまとまらず、何も決められない会議に参加していませんか。そんな「ダメ会議」には原因があります。ここでは、コンサルタントで、情報活用術や仮説思考に関する著書も多い生方正也さんの新著『結果を出す人がやっている「思考整理」の習慣』の第4章「生産性の高い会議・打ち合わせを行うための思考整理」から、ダメな会議にありがちな特徴と、それらを改善する方法を紹介します。
トップ営業マンが「売れる部下」を育てられない決定的な理由
「営業の6ステップ」で無意識の行動を可視化する
「名選手は名監督にあらず」は、スポーツ界だけでなくビジネスの世界にもあてはまります。とくに「営業」にその傾向は強く、売りまくっていた営業マンが部下を指導する立場になると、思っていたような成果を出せなくなる、といったケースは多いようです。
「服」でなりたい自分を実現、目標を達成するビジネスコーデ
印象は「言語化」できる
芸能人ではなく、一般人のスタイリストとして今まで4500人以上の買い物に同行してきた森井良行氏のもとには、「服」を変えたことで、仕事や恋愛がうまくいったという嬉しい報告が続々と寄せられています。目的や目標に合った服を着ることで、まわりからの評価が高まり、自信も湧いてきます。それは、服選びの大きな醍醐味です。ここでは、新著『38歳からのビジネスコーデ図鑑』から、ビジネスからプライベートまで、「評価される見た目」をつくる服装術を紹介します。
「規則だから無理」では時代に取り残される?失敗できない人は「出世」もできない
出世とは「井の中の蛙」が外に出ることだ
「さんまのスーパーからくりTV」や「中居正広の金曜日のスマたちへ」など、数々のバラエティ番組をプロデュースした角田陽一郎氏は、2016年12月にTBSを退社しました。角田氏は、会社を辞める頃、業界や組織の在り方に違和感を抱いていたそうです。本来、マスコミは不特定多数の人に向けて「開かれた情報」をアウトプットする媒体なのに、むしろ閉鎖的な「井戸の中の理論」で動き、「閉じた情報」を提供しているように感じたからでした。そこで角田氏は、井戸の「中の人」をやめて「外の人」になることを決意。いわく、「これこそが僕なりの出世です。つまり、既存のフレームから『世に出る』ことが出世なのです」。現在、角田氏はフリーランスの「バラエティプロデューサー」として活躍しており、常に10個のプロジェクトのプロデュースを同時にしているそうです。案件の中には「自分自身」も含まれているようで、様々なプロジェクトを通じて出会ったヒト・モノ・コトを、セルフプロデュースにも活かしているとか。角田氏は、日々どのような発想で「ヒト・モノ・コト」を捉え、セルフプロデュースのヒントにしているのか――。新著『出世のススメ』から、その一部
AI革命を生き抜くためにビジネスマンが知っておくべき「3つの逆説」
田坂広志氏が考える、AI時代に必要なもの
5月27日、丸善丸の内本店セミナールームにて、多摩大学大学院の名誉教授である田坂広志氏の講演会が開催されました。新著、『能力を磨く ─ AI時代に活躍する人材「3つの能力」』の内容をもとにしたその講演のダイジェストをお届けします。
ダイエット外来の医師に聞く、頑張らなくてもお腹が凹む「やせる食べ方」
10万人以上にダイエット指導をした先生の指導とは
減量外来を開設する医師、工藤孝文先生はこれまでのべ10万人以上にダイエット指導をし、自身も25キロのダイエットに成功しています。その工藤先生が提唱しているのが「内臓脂肪」を減らす生活習慣。無理せず、我慢しないでやせることができるコツを、工藤先生にうかがいました。
自分のことを話さないリーダーは成功しない
「OPENNESS」こそがゴールへのカギだ
国内外で数多くのプロジェクトを成功に導き、現在は企業や教育機関におけるプロジェクトリーダーの育成に力を入れる伊藤大輔さんは、著書『プロジェクトリーダー実践教本』で次のように述べています。「多くのリーダーは“OPENNESS(オープンネス)”を重要視しています。これはあらゆる国のビジネスにおいて共通の概念といっても良いでしょう」「オープンであること」が大事なのは想像がつきますが、具体的にどう振る舞えばいいのかと考えると人それぞれに違うイメージを持つのではないでしょうか。ここでは、リーダーたちが重要視するという「OPENNESS」について、『プロジェクトリーダー実践教本』第1章を中心に見ていきましょう。
目標を達成できる人とできない人。一体何が違うのか
達成することが最終目的ではない
弁護士法人や税理士法人、コンサルティング会社の代表を務める弁護士の三谷淳さんは、多くの企業の事業発展や新規上場をサポートしてきました。そのなかで、「目標を達成できる人」と「できない人」との大きな違いを実感するようになったそうです。その違いと、達成している人の手法をまとめたのが『目標達成の全技術』です。ここでは同書の第5章「一生使える『目標達成脳』の作り方」を中心に、高い目標を達成できる人の考え方や行動習慣を見ていきましょう。