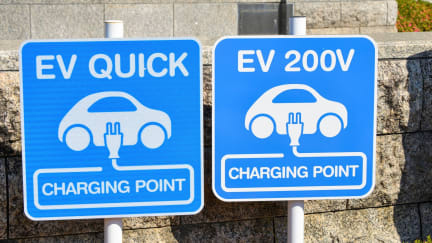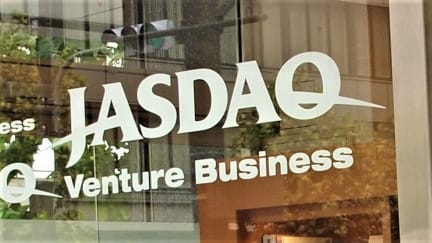株式市場におけるオミクロン株の影響、ワーストケースを考えてみる
半導体など成長分野については好機となる可能性も
株式市場では、値動きの激しい日々が続いています。南アフリカで発生されたとする新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」は、その感染力、毒性、既存ワクチンの有効性等はまだはっきりとわかっていません。どの程度の危険性なのか見極め中として、今後の世界経済へのリスク等、市場の不透明感が増していることが背景のひとつとして考えられます。
首位ヤマト運輸に包囲網?好調が続く宅配便業界の最新動向をレポート
社会構造の変化で宅配は生活のインフラへ
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、多くの業界が苦戦を強いられています。こうした状況下でも、巣ごもり消費など新常態に対応して好調を維持しているのが宅配便業界です。足元では緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の効果に加え、ワクチン接種が進んだこともあり国内では新型コロナの新規感染者数が減少傾向にあります。一方、海外では新型コロナの変異株により感染が再拡大している国もあることから、国内ではコロナの感染対策として新常態が維持されるとみられ、宅配便業界の好調は続くと思われます。<写真:ロイター/アフロ>
日本株に年末ラリーの可能性高まる、株高を予想する5つのポイントを解説
衆院選は10月31日投開票
自民党の岸田文雄新総裁は、10月4日召集の臨時国会で首相指名選挙を経て第100代首相に選出されました。所信表明演説と各党の代表質問を終えた後、衆院を解散し、衆院選に臨むことになります。今後の注目は岸田新政権が次期衆院選挙で勝利し、安定政権を築くことができるかです。
日経平均株価3万円突破も上昇余地はまだまだあると読む理由
市場参加者のセンチメントが改善、日本株反攻の展開
9月3日の午後、菅首相が自民党総裁選に不出馬の意向が伝わったことを機に相場は上昇ピッチを速め、あっという間に日経平均株価が3万円の水準まで駆け上がりました。しかし、相場の潮目が変わったのは少しさかのぼる8月31日の後場だと筆者は考えています。日経平均株価は前月の7月まで11カ月連続で月末日がマイナスとなっていました。8月31日の前引けが前日比53円安の2万7,736円と、下げ幅が小幅にとどまり、12カ月連続の月末安を意識していた投資家の買戻しを誘ったとみられ、後場は上げ幅を広げる展開でした。市場関係者が注目していた8月27日の米ジャクソンホール会議では、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長がオンライン講演し、米量的金融緩和の縮小の示唆と早期利上げを牽制する発言がありました。市場が求める回答をもって無事通過したかたちです。国内では新型コロナウイルス感染者数の増加がピークアウトの様相を呈しつつあり、日本株を売る動機が次第に希薄になりつつある中、支持率低迷に苦しんでいた菅首相不出馬のニュースが飛び込んできたことで相場は一段高の反応を示しました。日本株の頭を抑えていた様々な不安要素という名の
2021年後半の日経平均株価はどうなる?月間騰落率と週足終値の相関分析から予想してみた
1950年以降の市場データで徹底分析
今年後半の日経平均株価はどうなるのでしょうか?今回は、月間騰落率と週足終値の相関分析から考察してみます。
Twitter CEOや「大阪なおみの色」も!様々な分野に普及するNFTで大変革が予想される業界は?
国内市場で注目の各社を紹介
2021年3月、Twitterの共同創設者でありCEOを務めるジャック・ドーシー氏は、最初のツイートを291万ドルで販売しました。また同年4月にはプロテニス選手の大坂なおみ氏とその姉の大坂まり氏が、6枚のカード(デジタルデータ)をオークションに出品。まり氏がなおみ氏をデザインした「大阪なおみの色」というタイトルで、サイングッズなどが付与され、落札総額は58万ドルを超えています。上述のツイート、カードは、ともにデジタルデータです。そのデータに価値を付与したものがNFT(Non-Fungible Token=非代替性トークン)です。今、NFTは様々な分野へ広がりを見せています。
EV普及で恩恵をうける企業と淘汰される企業…群雄割拠の自動車業界で日本企業の現況を探る
環境対応に対する開発が激化
コロナ禍では、感染拡大を防ぐため、多くの国や地域で人の移動が制限されました。中国やインドでは自動車の利用が一時的に少なくなったことで、都市部では綺麗な空が広がったとも言われたそうです。環境問題については、従来から各国で様々な取り組みは掲げられていましたが、近年は企業単位でも明確に環境に対する対外的な目標が掲げられています。各国がガソリン車から環境対策に適したEVや燃料電池車(FCV)へシフトしていく目標が掲げられたことで、従来のガソリン車販売は各国で規制が始まるでしょう。各国の完成車メーカーの開発競争がより一層激しくなっていくことが予想されます。今回は、転換期を迎える自動車業界の今を様々な観点から解説するとともに、日本企業の動きを紹介します。
コロナ禍で苦境のコンビニ3社、徹底比較で見えてきた“差”
新しい生活様式への対応力と海外展開
新型コロナウイルスの感染拡大は人々の生活様式を変化させました。その結果、人々の生活に寄り添う形で成長を続けてきたコンビニエンスストア(CVS)業界も大きな変化を余儀なくされています。特に歓楽街やオフィス街などの店舗は、外出自粛の考え方が浸透したことにより苦戦を強いられています。一方で、住宅地に位置する店舗はおうちごはんや家飲みといった、新しく定着した生活様式の恩恵を受けています。コロナ禍を約1年間経験したCVS業界のこれまでを振り返り、これからの展望を考えてみたいと思います。
3月は日経平均よりジャスダック平均が好調だった理由
中小型銘柄の中長期投資はアナリストレポートを活用
3月は日経ジャスダック平均株価の値動きの好調さが目立ちました。3月9日から22日まで12営業日続伸し、2020年1月以来、約1年2か月ぶりの高値水準となりました。12営業日続伸は、2020年5月15日から6月2日の13営業日続伸以来の記録です。一方、日経平均株価は30年半ぶりに3万円の大台を回復してからは上値の重い展開でした。今回は3月のJASDAQ市場を振り返りながら、中小型銘柄の分析に役立つ情報をご紹介します。
脱炭素で注目の「銅」先物価格が史上最高値へ、強みを持つ総合商社はどこ?
資源・エネルギー市況の回復続く
新型コロナウイルス感染拡大の影響で急落した、原油や銅など資源・エネルギー市況が回復傾向にあります。これは、コロナ禍で急速に落ち込んだ世界景気の回復が継続すると想定していることが背景にあります。また、米国や欧州、日本など主要国の中央銀行による金融緩和が長期化する見通しであることに加え、米国のバイデン政権による追加経済対策の実施や中国の第14次5ヶ年計画によるインフラ投資の実行など主要国の財政出動のほか、新型コロナのワクチン接種が世界的に進展していることから、今後も資源・エネルギー市況の回復が続くとみられます。
日経平均は2万9000円台を回復!世界景気とワクチンから考える今後の展開
海外投資家が日本株買いをけん引か
年明け以降の世界の株式相場は騰勢が強まりましたが、1月の月末にかけて米国株式市場の混乱が波及、日本株市場も調整色が強まり、日経平均株価は25日移動平均線を割り込む場面もありました。政府は2月2日の新型コロナウイルス感染症対策本部で、11都府県に発令中の緊急事態宣言について、栃木県以外の10都府県で3月7日まで延長しました。しかし、相場の基調が大きく崩れることなさそうです。昨年11月以降の急ピッチの上昇も反動もあり、しばらくはボラティリティーの高まる場面もありそうです。一方で、世界的な金融緩和の継続と世界経済の回復見通しを背景に相場は強い地合いが続くと予想されます。<写真:つのだよしお/アフロ>
前回の緊急事態宣言と何が違うのか?宣言後も株価が続伸するワケ
30年ぶりの高値更新
1月7日に緊急事態宣言が発令され、首都圏の1都3県を対象に、飲食店への時短営業や夜8時以降の不要不急な外出の自粛が要請されました。注目された株価の反応は、8日の日経平均株価の終値が前日比648.90円高の2万8,139.03円と大幅続伸し、1990年8月8日以来およそ30年ぶりの高値を更新。株価の反応を見る限りでは、今回の緊急事態宣言が株式相場に与える影響を過度に悲観視する市場参加者は少なそうです。その理由を解説します。
2021年丑年の株価はどうなる?過去の丑年パターンから来年の相場を予測
今年と最も相関係数が高かった年は
2020年も残り1カ月を切りました。今年の干支となる子年は1950年以降では過去5回ありました。それぞれ、子年はどんな相場だったのでしょうか。過去の株価を分析してみたいと思います。さらに、来年の干支である丑年との相関も考察してみます。
2020年IPO市場が過熱 初値平均2.4倍と高騰する魅力はどこに?
投資家は参加すべきか
2020年の新規上場(IPO)の初値が好調です。2020年は直近、10月30日に東証マザーズへIPOしたRetty(7356)までの62銘柄をみますと、公開価格に対する平均初値上昇率は2.4倍となっています。2010年以降の最高値は2013年の2.2倍ですから、人気の高さがうかがえるでしょう。なぜ、IPOが好調なのでしょうか。
酒税法改正、真の狙いは6年後の税収増?人気の新ジャンルは最終的に1缶26円アップ
ビールは値下げ
今年の10月から酒税法改正の第1弾がスタートしました。同法は2026年10月にビール類の税制を一本化するための段階的な措置として行われました。税法上、ビール類はビール、発泡酒、新ジャンル(第3のビール)に分類され、それぞれ税金が異なります。税金が一番高いのがビール、次いで発泡酒、新ジャンルという順番です。改正により、ビールの価格は1缶(350ml)あたり7円下がり、第3のビールは9.8円上がります。
5Gスマホ競争、トラブル続きの楽天モバイルが実は優勢?コロナ禍で加速する全国展開
総務省は基地局整備前倒しを要求
第5世代移動通信システム「5G」は、これまでの4Gと比べて約100倍の速度で通信が可能になり、なおかつ低遅延である高速通信です。高画質の動画配信や大多数の同時接続などが可能となるほか、ビジネスの分野でも遠隔医療や自動運転などに活用されることが期待されています。この5Gを活用した商用サービスは、今年3月25日のNTTドコモを皮切りにKDDI、ソフトバンクが相次いでスタートさせています。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の中、思惑通りにいかないことが多々あるようです。各社の5G戦略を解説します。
ユニクロを買っていたら68倍に!コロナショックを乗り越え、盛り上がるIPO市場
再開後、15銘柄すべてで初値を上回る
新型コロナウイルスの影響で、一時は休止していた新規株式公開(IPO)が好調です。銘柄の動きを示すIPOインデックス(加重平均)が堅調に推移しています。これは対象銘柄の騰落率を時価総額で加重平均したもので、国内株式市場のIPO銘柄の上場後1年間の平均的な動きを表す指数です。QUICKが算出、公表しています。
改正道路交通法で注目のドライブレコーダー、有望な投資先は?
出荷台数は3年で330%の伸び
あおり運転は、重大な事故を発生させる可能性のある危険な行為です。これを取り締まるため、6月30日にあおり運転罪を新設した改正道路交通法(道交法)が施行されました。他の車の通行を妨害する幅寄せや急ブレーキなどの行為が対象で、実際に事故に至らなくても適用されます。あおり運転の厳罰化を受けて、自分を守るためにドライブレコーダー(DR)を車に搭載する人が増えるとみられます。