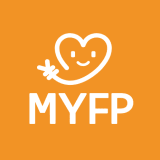ビジネス
経済、投資の最新情報、仕事の給与や稼げる副業情報などを紹介します。
東京は“世界で最も客室の多い都市”だった?「ホテル不足問題」の虚実
最新「世界の都市総合力ランキング」を読み解く
来年に迫った東京オリンピック・パラリンピックの開催。大勢の外国人観戦客の来日が想定され、五輪開催決定の直後から東京の「ホテル不足」を指摘する声が聞かれるようになりました。しかし、一般社団法人森記念財団の都市戦略研究所が11月19日に発表した「世界の都市総合力ランキング 2019」によると、上記のような世間一般の認識とは異なる現状が明らかになりました。世界の主要48都市の中で、東京はホテルの客室数が最も多い都市だというのです。なぜ、客室数が最多であるにもかかわらず、五輪開催時のホテル不足が指摘されているのでしょうか。その理由を深掘りしてみると、東京が都市として再び活性化していくためのヒントが見えてきました。
“泥沼化”必至なコクヨの敵対的買収、ぺんてる「次の一手」を予想する
「白馬の騎士」と「毒薬」が登場?
オフィス用品大手のコクヨが11月15日に表明した文具大手・ぺんてるに対する買収が、泥沼化の様相を呈し始めています。オフィス用品大手のプラスがぺんてる側に立って買収防衛策を講じており、膠着状態に陥っているのです。文具だけでなく、オフィス家具でも大手シェアを誇るコクヨの売上高は約3,150億円と、ぺんてるの10倍近い水準。その圧倒的な資金力の差をみると、ぺんてるに勝ち目はないように思われます。しかし今回、コクヨはぺんてるの買収にかなり手こずっているように思われます。確かに、ぺんてるは非上場企業ということもあり、取引所を通じた買収が進められないという制約もあります。しかし、コクヨにとって最大の障壁は、やはりぺんてる側で買収防衛策を講じる企業たちの存在でしょう。ぺんてるはこの先、どのようにしてコクヨと渡り合って行くのでしょうか。筆者個人の観点から予想してみたいと思います。
利益35億円突破、勝ち続ける個人投資家の「損切り」と「買い増し」のルール
勝っているときに買い、負けているときに売る
「貯まるから増やすへ」。投資に挑戦したいが、何から手を付けてよいのかわからないという初心者から、腕に自信がある中上級者までを対象に、わかりやすく投資を語り合う連載「みんなの投資広場」。 前回に引き続き、デイトレードから投資を始め、10数年で利益35億円を稼ぎ出した、テスタ氏に話を聞きました。
これから伸びる投資先は?初心者のための決算書の読み解き方
どのようにして投資先の事業を理解するのか
決算書というと、細かい数字や文字の羅列で、それだけで拒否反応を起こしてしまう人も少なくないのではないでしょうか。 しかし、これから伸びる投資先を見つけるためには、決算書ほど有効なツールはなかなかないことも事実です。 投資の初心者でも基礎からわかる、伸びる投資先を見つけるための決算書の読み解き方を考えてみます。
オワコンと思われた「国内パソコン市場」が新成長期に入った理由
恩恵を受けそうな企業はどこ?
スマートフォンやタブレット端末の高性能化に伴い、一時は「オワコン」(終わったコンテンツ)扱いされたこともあるパソコン。ですが足元では、国内出荷台数の伸びが加速しています。なぜ今、国内のパソコン市場が新たな成長期に入っているのでしょうか。そして活性化する市場の中で、活躍しそうな企業はどこなのでしょうか。
潰れるラーメン店はどこに問題があるのか、ラーメン店経営のプロが明かす「裏側」
「味」や「こだわり」だけではビジネスにならない
「国民食」といわれ老若男女に親しまれているラーメン。電話帳に登録されているだけでも全国で3万軒超という数のラーメン店があるそうです。全国にある郵便局の数が2万4,000店弱ということから考えても、これはかなりの数。私たち日本人はラーメンを「食べる」のも大好きですが、逆の見方をすればこれはラーメン店を「やる」人が多いということもあります。なぜこんなにも人はラーメン店をやりたがるのか。そこにはどんな魅力とビジネスとしての「うまみ」があるのか。「経営」という側面からラーメン店について考えると、日常的に食べているラーメンの味も少し新鮮に感じるかもしれません。今回お話を伺ったのは、ラーメンプロデューサーとして独自の方法論をもとに400店以上のラーメン店をプロデュースしてきた藏本猛Jrさん。藏本さんが今年10月に上梓した書籍『誰も知らなかったラーメン店投資家になって成功する方法』(合同フォレスト)にはラーメン店の「オ―ナ―」として資金を投資して稼ぐノウハウが示されています。「味」や「こだわり」だけではないラーメンビジネスの奥深さについて、数々のラーメン店を見てきた同氏ならではの経験を交えて語ってい
「2020年の投資先」としてベトナムが注目に値する3つの理由
“漁夫の利”だけじゃない投資妙味
米中間で貿易協議が続いていますが、2018年7月の第1弾の関税発動から1年以上が経ち、その影響は顕在化しています。米国は中国からの輸入を減らす一方、ベトナムや台湾などからの輸入を増やしています。ベトナムから米国への輸出は今年1~10月に前年同期比+28%と増加し、米国は全体の約23%を占める最大の輸出相手国に躍り出ました。また、同国の実質GDP(国内総生産)成長率は2019年7~9月期に同+7.3%へ加速しました。世界全体の景気が米中摩擦の影響で停滞気味な状況において、その健闘ぶりがうかがわれます。まさに「漁夫の利」を得た格好で、ベトナムは2020年の注目市場の1つと言っても過言ではないでしょう。しかし、注目の理由は「漁夫の利」だけではありません。
フリーターから投資で利益35億円、テスタ氏が培った「デイトレードの勝ち筋」
自分の勝ちパターンを見つける
「貯まるから増やすへ」。投資に挑戦したいが、何から手を付けてよいのかわからないという初心者から、腕に自信がある中上級者までを対象に、わかりやすく投資を語り合う連載「みんなの投資広場」。今回はデイトレードから投資を始め、10数年で利益35億円を稼ぎ出した、テスタ氏に話を聞きました。
世界経済の“夜明け”は近い?「年末株高」の期待度を探る
最新マクロ指標を徹底分析
経済協力開発機構(OECD)が11月12日に発表した9月の景気先行指数は、前月からほぼ横ばいにとどまり、世界経済の夜明けが間近に迫っていることを示す結果となりました。米中通商協議の進展期待が維持される下、半導体をはじめとするハイテク分野の在庫調整が進展。政策期待も残存していることなどが背景にあり、世界的な株高傾向が強まりをみせています。
東西統一から30年、ドイツはなぜ再び“袋小路”に入ろうとしているのか
欧州屈指の経済大国で何が?
ベルリンの壁が崩壊してから、今年で30年。統一を果たしたドイツは、旧東ドイツ地域が抱えていた低成長や高い失業率といった“負の遺産”を見事に克服し、欧州屈指の経済大国へ飛躍を遂げました。1990年代から2000年代初頭にかけては「欧州の病人」などと揶揄される存在でしたが、ゲアハルト・シュレーダー前首相時代に大胆な労働市場改革に取り組んだことなどが奏功。後継のアンゲラ・メルケル首相の時代になって、「奇跡の回復」を実現しました。そのドイツが今、試練に直面しています。同国の変調は欧州連合(EU)圏、ひいては世界全体の経済にも影響を及ぼしかねません。ドイツで何が起きているのでしょうか。
貯めるより増やした方がいい?手取りの3割を投資にまわす29歳女性
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、「貯めるよりも増やした方がいい」というアラサー独身女性。手取りの3割を投資に回し、家計は毎月赤字です。家計再生コンサルタントの横山光昭氏が運営する『マイエフピー』のFPがお答えします。社会人8年目の独身女性です。お金は貯めるよりも増やしたほうがよいと考えています。今も、貯金よりも会社の持ち株と株式投資にお金を回しています。投資は分散投資がよいと思いながらも、持ち株だと投資額に10%上乗せをして買ってもらえるので、これでいいかと思っています。また、株式投資では、30万円ほどマイナスになっていますが、損切りできないで保有したままです。今、働きながら大学院に通い、キャリアアップを図っています。終了まで、あと130万円ほどかかる見込みです。それとともに、結婚も考え始めました。私の年収は約550万円、彼は400万円ほどのようですが、今後に向けお金に対する考え方や家計状況など見直していく必要はあるでしょうか。お稽古は絶対やめられないので支出を減らす対象には
「もう1回やってみよう!」という気分の源、脳の"報酬系回路"を活性化させる
依存症を作ってしまう脳の仕組みが、プラスに変わる⁉︎
最近、芸能人の薬物依存の話が世をにぎわせています。なぜダメだと知っていてもやめられないのでしょうか。脳のメカニズムから読み解いてみると、依存症を引き起こす報酬系回路には、マイナス面だけではなく、私たちを成長させるプラス面も併せ持っていることが分かります。
脱「箱根の通過点」 刺身食べ放題のテーマパークが小田原にできた理由
イクラやマグロなど約30種類のビュッフェ
神奈川県小田原市が、海産物に特化した施設「漁港の駅」をオープンしました。地元でとれた魚介類を使った、刺身食べ放題の店もあり、海鮮好きにたまらない内容となっています。この施設には小田原市が抱える、ある課題を解消する狙いが隠されていました。メディア向けに開かれた内覧会の内容から探ります。
渋谷パルコ「日本初」スニーカー洗濯専門店は何がスゴイのか
盛り上がるスニーカー市場
11月22日にリニューアルオープンする「渋谷パルコ」。ファッションや飲食店など193のテナントの中で、目を引いたのが「日本初」というスニーカーウォッシュ専門ブランドの店舗です。商業施設の中で提供されるスニーカー洗濯サービスとは、どのような内容でしょうか。メディア向けに開かれた内覧会の様子から探ります。 【写真20枚】新生「渋谷パルコ」の内部を公開
訪日客「5.5%減」よりも深刻、日本経済をむしばむ“病巣”の正体
2020年の経済・株式市場はどこに向かう?
11月20日に発表された10月分の訪日外客数は前年同月比-5.5%と、8月分と同様に昨年の実績を下回りました。7月まで訪日客は順調に伸びていましたが、8月から日韓関係の悪化で韓国からの訪日客が前年から半分程度に激減したことが、訪日客数全体を押し下げました。また10月は、大型台風が到来したことも大きく影響したとみられます。一方で、ラグビーワールドカップ開催の効果でイギリスなどからの訪日客は伸びました。訪日客数は2012年には年間853万人でしたが、安倍政権が繰り出したさまざまな政策対応で2013年から年々増え、2018年には3,119万人まで急拡大。2019年に入っても、7月まで同約+5%のペースで順調に伸びていました。しかし、8月から2018年平均を下回る水準に減少しています。10月の訪日客減少には大型台風の悪影響があったため、11月以降はやや持ち直すとみられますが、2019年年間の訪日客数は+2〜3%程度の緩やかな伸びにとどまりそうです。
イオン、4年目の「ブラックフライデー」が過去最大級に大盤振る舞いなワケ
半額商品は過去最大の160企画に
今年で4年目を迎えた、イオンの「ブラックフライデー セール」。これまでの3回は本場・米国のブラックフライデーにならって11月の第4金曜日から開催していましたが、今年は第3金曜日の22日から、開催期間も従来の3日間から2日拡大して5日間の日程で開催します。前夜祭ということで他店舗に先駆けてセールが始まった、東京のイオンスタイル品川シーサイド店を訪れると、消費増税の直後にもかかわらず、例年に勝るとも劣らない数の買い物客が集まっていました。過去3年の蓄積を踏まえて、今年はどこまで進化したのでしょうか。 【写真15枚】イオン「ブラックフライデー」今年の見どころは?
投資初級者が見落としがち、「減益決算なのに株価上昇」のカラクリ
景気敏感株・コマツの最新決算から考える
10月下旬から11月中旬にかけて、日本企業の2019年7~9月期決算が発表されました。全体としては厳しい内容でしたが、業種別に見ると“まだら模様”の様相でした。一般的に、業績が芳しくなければ、その後の株価の動きも冴えない展開になりがち。しかし、11月に入ってからの日経平均株価は2万3,000円台を回復し、年初来高値を更新しています。いったい、どんなカラクリが潜んでいるのでしょうか。景気敏感株の代名詞である小松製作所(コマツ、証券コード:6301)を例に、考えてみます。
新生「渋谷パルコ」の飲食フロアが想像以上にカオスな理由
昆虫食、女装、避妊具まで…
商業施設の集客に重要な役割を果たすレストランフロア。近年は大人の利用者をターゲットとした「フードホール」形式を導入する商業施設が増えていますが、11月22日に開業する渋谷パルコは、まったく別のベクトルを打ち出してきました。「食・音楽・カルチャー」をコンセプトとする地下1階のレストランフロアの名前は「CHASOS KITCHEN(カオスキッチン)」。昆虫食のレストランがあると思えば、女装ウェイトレスが接客するバーもあり、文字通り混沌とした空間になっています。異色なレストランフロアを作り出したパルコの狙いは、どこにあるのでしょうか。11月19日に開かれたメディア向け内覧会の内容から探ります。