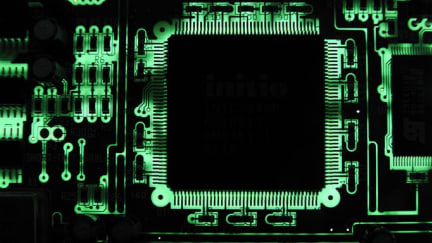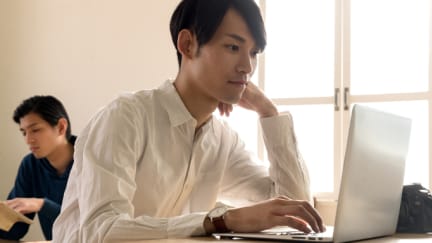ビジネス
経済、投資の最新情報、仕事の給与や稼げる副業情報などを紹介します。
上昇続いた「原油価格」、これから先の適正水準は?
一時、3年半ぶりの高値に
世界的な指標となっているWTI原油価格は2017年6月の1バレル=40ドル台前半から、ほぼ一貫して上昇基調を歩み、5月上旬には70ドルを超えました。私たちの身の周りでも、ガソリン価格が顕著な上昇を見せるなど、原油高を実感する場面が増えてきているように思います。ここまで原油相場を押し上げてきた原動力とは、いったい何だったのでしょうか。また、この先の原油相場はどのような展開を見せるのでしょうか。原油価格上昇の背景を整理するとともに、今後の原油価格の見通しについて考えてみます。
インテルも開発を急ぐ「人工知能チップ」って何?
“ITの巨人”に忍び寄る脅威
半導体大手の米インテルが5月23日、新しいプロセッサーを2019年に市場投入すると発表しました。この商品、実は“業界の巨人”が起死回生を狙って発売する商品です。というのも、インテルはある成長分野で後れを取っているのです。それが人工知能(AI)チップです。盤石と思われた同社は何につまずいているのでしょうか。解説してみたいと思います。
米金利上昇は日本株にプラスか?マイナスか?
約7年ぶりの水準にざわつく市場
米国で長期金利の上昇が続いています。3月16日には一時3.1%を超えるなど、約6年10ヵ月ぶりの高い水準に上昇しました。トランプ政権が昨年 12 月に成立させた減税規模は、10 年間で 1.5兆ドルにも及ぶ大規模なものだったほか、1.5 兆ドルのインフラ投資計画も打ち出されており、国債増発懸念から金利が上昇しているのです。この米金利上昇は、今後のマーケットにどのような影響を与える可能性があるのでしょうか。
「ブロックチェーン・ウィーク」に見る仮想通貨の今後
昨年はイベント前後で価格が急騰
5月14日から16日にかけて、仮想通貨の情報サイト「CoinDesk」が運営する年次イベントがニューヨークで開催されました。「ブロックチェーン・ウィーク」とも呼ばれ、全体では昨年の2倍強の8,500人もの投資家や個人が参加しました。勢いづいたCoinDesk は、さらに9月にシンガポールでも初めてのフォーラムを開催すると発表しました。同イベントでは、金融当局者の講演や、技術系の若手実力者と金融関係者によるデジタル決済の将来に関する討論など、143のセッションが行われました。開催場所のニューヨークヒルトンホテルの周辺では、高級車のランボルギーニがプロモーションとして車を走らせたことも話題になりました。
イオン株主総会に潜入取材、どんな質問が飛び出た?
岡田社長が語った変革への誓い
「グループを大きく変えながら、基本理念は変えず、新しい時代の流通を実現できるような企業群になっていきたい。ご支援をよろしくお願いします」――。イオンの岡田元也社長が自らの発言をこう締めくくると、一部の株主から拍手が沸き起こりました。5月23日午前10時から千葉市の幕張メッセで開かれた、イオンの株主総会。昨年よりも200人ほど多い、約1,900人の株主が出席しました。1時間30分強に及んだ今年の株主総会。多くの時間が割かれたのは、岡田社長による経営方針の説明と、それらを受けた株主との質疑応答でした。一体どんなやり取りが繰り広げられたのでしょうか。
開花する「異端」技術、実用化段階を迎えた遺伝子治療
有望な日本企業は存在する?
遺伝子治療がいよいよ実用化の段階を迎えています。これは従来の医薬品の代わりに、治療用の遺伝子を使う技術です。製薬業界で長らく「異端」扱いされてきましたが、昨年、米国で承認が相次ぎ、大きな話題となりました。最近は欧米大手製薬会社による遺伝子療ベンチャーの大型買収も目立ちます。7~8年前まで遺伝子治療が低迷していたことを考えると、隔世の感があります。従来の医薬品では考えられないような治療成績を示したことが背景にあり、今後、本格的な普及と市場の拡大が見込まれます。はたして、日本にもこの分野で活躍が期待できる企業が存在するのでしょうか。
1ドル=111円台、具現化しつつある麻生財務相の発言
日米金利差は節目の3%を突破
5月に入り、ドル円相場は一時1ドル=111円台まで円安ドル高が進んでいます。この動きは円ではなく、ドル主導といってよいでしょう。つまり、ドル全面高という環境下で他の通貨同様、円が売られたという解釈が腑に落ちます。では、ドルが買われた理由ですが、単純に“金利差”と見るべきでしょう。3月29日、麻生太郎財務相は国会の答弁で、「これまでの歴史を見ると、米国との金利差が3%に達すると、必ずドル高円安に振れる。例外は1つもない」との見解を示しました。そうした状況が具現化しつつあるようです。
iDeCoよりもまず企業型確定拠出年金を利用した方がいい理由
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回は横山光昭氏がお答えします。将来に向けて、最近話題の「つみたてNISA」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」を始めようと思います。というのも、老後資金や子どもの教育費、マイホーム資金を貯めるのに、複利の効果を利用して増やすのが一番良いのではないかと思ったからです。この2つは運用益も非課税でとてもお得だと思います。ただ、利用するのは初めてなので少し不安があります。メリット、デメリット、商品選びなどを含め、どのように活用していくとよいのか教えてください。ちなみに、会社に企業型確定拠出年金制度がありますが、選択制ということでしたので自分は利用していません。〈相談者プロフィール〉・男性、36歳、既婚(妻:35歳・専業主婦)、子ども2人・手取りの世帯年収:約465万円・貯蓄:180万円
暑い日に冷たく栄養補給、「缶入り冷製スープ」に商機あり
市場規模は2年で5倍に
5月も半ばを過ぎ、最高気温が25度を超える「夏日」が増えてきました。暑い日が続くと、どうしても食欲は落ちてしまいがち。そんな時に重宝するのが、冷やしてスッと飲める冷製スープです。毎年、猛暑に関するニュースが増えるにつれて、冷製スープの市場規模も右肩上がり。中でも成長著しいのが、缶入りタイプの商品です。そして、今年この分野でこれまで以上に力を注ごうとしているのが、ポッカサッポロ フード&ビバレッジです。どんな戦略で市場を拡大しようとしているのでしょうか。
“株主優待+配当利回り”で魅力の「厳選2銘柄」を診断
JTとKDDIを深掘りする
日本の株式市場には、世界的に見ても珍しい制度が存在します。上場企業が株主に感謝の意を込めて贈り物をする「株主優待制度」。株主に「お中元」や「お歳暮」を贈るようなものです。本来であれば、企業は株主に対して配当金を支払うことで利益還元するのが筋です。ところが、日本の個人株主の一部に、お金をもらう以上に贈り物(株主優待)を喜ぶ傾向があることから、この制度が存続・発展しています。とても魅力的な制度なので、積極的に活用したほうがいいでしょう。と言いつつ、優待大好き投資家の中には、優待内容しか見ないで銘柄を選ぶ傾向があるので注意が必要です。
REIT投信の資金流出問題は終わったか
構造的問題の整理と検証
昨年のREIT(不動産投資信託)市場は、好調なファンダメンタルズにも関わらず株価は低迷しました。この最大の背景は、J-REITで運用する投資信託(REIT投信)からの資金流出でした。資金流出は最近やや沈静化しています。この問題はでに過去のものとなったのでしょうか。
10年後の仕事はどうなる?今売れているビジネス書ランキング
ビジネスパーソンにとって大切な基礎知識
4月5日(木)発売の新刊『10年後の仕事図鑑』が首位を獲得しました。『10年後の仕事図鑑』は、落合陽一さんと堀江貴文さんによる共著。「10年後どころが5年先すら予期できない今、仕事は、会社は、社会は、キャリアはどうなるのか?」という不安に対して、時代の先端をいく2人が、今考えられる社会の姿を語り尽くした一冊です。タイトルに「仕事図鑑」とあるとおり、本書には〈消える職業〉や〈生まれる職業〉を含めた50近くの“職業の未来”をイラスト・解説付きで掲載。また「そういった社会の動きを希望ととるか絶望ととるかは、すべて自分次第である」といい、経営者ですら職を奪われる時代にどうポジションを取るのか、生き方のヒントも与えてくれる内容となっています。
初の政権交代、「マレーシア経済」の行方はどうなる?
マハティール氏が返り咲き
5月9日、マレーシアでは下院(代議院)選挙が行われ、マハティール元首相率いる野党連合の希望連盟(PH)が与党連合の国民戦線(BN)を破り、総議席数の過半数(222議席のうち122議席)を獲得しました。下院選挙の結果を受けて、マレーシア独立後初となる政権交代が実現し、マハティール氏は2003年以来15年ぶりに首相の座に返り咲きました。今回は、マレーシアの政権交代後の経済見通しについて考えてみたいと思います。
50代は老後準備のラストスパート!「100-自分の年齢」の法則
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回は花輪陽子氏がお答えします。夫と、あと少しで教育費が終わる子供2人と、義母で暮らしています。現在、資産が2,400万円ほどあります。内訳としては1,800万円が証券会社の投資、その他600万円が定期になっています。日経平均が7,000円台の時に4割近く目減りした時代もありましたが、最近は戻ってきました。その経験からか、老後資金として考えているため、少々投資に充てる資金が多過ぎるかな思っている次第です。プロの目から見てアドバイスいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。〈相談者プロフィール〉・女性、52歳、既婚(夫:52歳・会社員)、子供2人・職業:会社員・居住形態:持ち家(戸建て)・手取りの世帯月収:50万円・毎月の支出目安:50万円
結果を出すリーダーは部下を評価しない?相手を安心させる秘訣
チームを動かすために必要なこと
社員20名のベンチャー企業を皮切りに、ミスミやリクルートでキャリアを積み、現在は人材育成や組織活性化を中心に数々の大手企業をコンサルティングしている中村一浩さんは、自らの経験から、ビジネスリーダーの “理想像”に行き着いたそうです。それは、「メンバーの言動に対し、すぐに評価を下さない」ということ。リーダーの役割は部下を指導し、評価することのはず。中村さんの真意はどこにあるのでしょうか。著書『なぜ、「すぐに決めない」リーダーが結果を出し続けるのか』の第1章「メンバーのパフォーマンスを最大化する」から、その一端をピックアップしました。
貿易摩擦問題は“オオカミ少年”で終わる?
米中の貿易摩擦問題を考える
米中の貿易摩擦問題をめぐるドナルド・トランプ米大統領の発言を振り返ると、イソップ寓話に出てくる「オオカミ少年」を思い起こさせます。貿易戦争(注1) への進展を連想させる発言を繰り返しながらも、一方で、深刻な事態には至らないような動きも垣間見えます。当初はこの問題に衝撃を受けた市場関係者も、実際には深刻な事態にならないのではと思い始め、次第に過激な発言に慣れていく状況が「オオカミ少年」と類似しているようです。トランプ大統領の当面の目標は、11月6日の米中間選挙(注2) で勝つ(共和党が勝利する)ことでしょう。そのため、「中国によって米国内産業が痛めつけられ、貿易赤字が膨らんでいるほか、知的財産権なども侵害されている。よって、国内産業を保護する姿勢を強めれば、共和党支持が増えるだろう」と目論んでいる可能性はあります。3月1日には、中国製品を念頭に鉄鋼とアルミに追加関税を課す方針を表明。3月22日には、最大600億ドル相当の中国製品に制裁関税を課す大統領令に署名。4月5日には、1,000億ドル相当の中国製品への追加関税の検討を米通商代表部(USTR)に指示するなど次々と強硬策を打ち出し、中国
総額6.8兆円、武田薬品はなぜ巨額買収に踏み切った?
シャイアー買収の戦略的意義
かつてないほどの巨額買収のニュースが飛び込んできました。日本最大の製薬会社の武田薬品工業がアイルランドの製薬会社シャイアーを620億ドル(約6.8兆円)で買収するというのです。製薬業界では世界の大手による寡占化が進んでいて、このままでは日本勢はその流れから取り残されてしまうのではないかと懸念されていました。今回の買収発表で、武田薬品工業の世界の中でのポジションはどう変わるのでしょうか。
社会人1年目「給与だけでは不安。第2第3の収入源がほしい」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回は花輪陽子氏がお答えします。社会人1年目で、どのように資産形成していけばいいのか分かりません。支出は個人的には多くない方だと思います。まずは目標100万円を貯めて、それをすべて株式投資に回そうと思っています。また株以外の投資知識があまりなく、投資信託やNISAなど名前は聞くものの、どこから手をつけていいかわかりません。社会人1年目が言うことではないかもしれませんが、今のお給料だけでは正直将来が不安です。給料以外に第2、第3の収入がほしいと思っています。30歳になるまでに、給料に加えて第2、第3の収入で、年間収入1,000万円を達成したいのですが不可能でしょうか(株は得したり損したりすることもあるので一概には言えないかもしれませんが…)。また、もし、達成できる可能性があるのなら、株、FX、不動産など、何をいつから始めるのか、始めるまでにどれくらいの資金を用意すればよいのか教えてください。〈相談者プロフィール〉・男性、23歳、未婚・職業:会社員・居住形態:賃貸