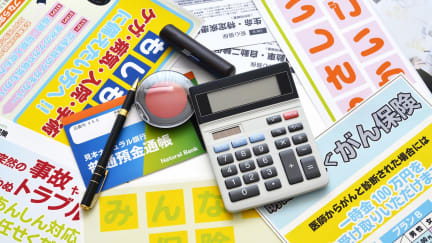家計改善は、保険の見直しが効果的。保険料0円から2000円までのコスパ保険5選
ピンポイントで入りたい保険
2022年は食料品、日常品などをはじめ、いろんな物が値上げラッシュ、これが2023年も続くと予想されています。しかし、肝心の給与があまり変わらないのでは、生活はどんどん厳しくなります。家計の防衛のためにもどこかで節約をしていかないとならないでしょう。節約するには、たとえば保険の見直しが有効です。今回は、ゼロ円から2000円までの家計にやさしい保険料の保険を紹介してみます。とはいえ保険料が安いだけで、保障がイマイチでは元も子もありません。もしもの時には役に立つ、そして、コスパに優れている保険を紹介してみたいと思います。
年金生活への移行時期60代の生き方が、老後生活を決めるワケ
働く意義が変わる
「60代の生き方が、その後の老後生活を決定づける」なんていわれても、ピンッとこないかもしれません。「なぜ?」と思ってしまいますね。しかし、60代というのは、現役生活から年金生活への大切な移行時期にあたります。人生が大きく変わっていくターニングポイントといっていいでしょう。この時期をどのように過ごすか、そしてどうやって過ごしたかが、その後の生活を決めるといってもいい大事な時期なのです。(60歳以降も働いている人は、現役といえますが、ここでいう現役生活というのは、一般的に収入が多くある時期として便宜的に使っています。また年金生活というのも、収入の多くが年金になっている時期を便宜的に使っています)
キャッシュバックや旅行の割引も。知らないと損な生命保険のタダで利用できる「付帯サービス」
介護や税務の相談も
日本人の約8割の人は、なんらかの生命保険に加入しています(生命保険文化センター「生活保障に関する調査」)。じつは、その加入している生命保険には、さまざまな付帯サービスが付いているのです。付帯サービスとは、生命保険会社が提供している無料で使うことができるサービスです(有料のものもあります)。しかも何度使っても大丈夫なのです。付帯サービスの中には、かなり便利で役に立つものもあり、ショッピングや旅行などの割引に使えるサービスや、なんとキャッシュバックでお金が戻ってくるものまであります。こんな便利なサービスがタダで使えるのに、利用しないのは損。でも、「どんなサービスがあるのか、よくわからない!」という人が多いと思います。今回は便利で役に立つ生命保険の付帯サービスを紹介します。
一時金、年金、併用…iDeCoはどのように受け取るのが正解か? 出口戦略をお金のプロが解説
退職金と同タイミングで受け取るときは要注意
iDeCoはいつから始めればいいのかというと、いつでもOKです。長期の積み立てになるので、始める時期はそれほど気にする必要はありません。しかし、早いに越したことはありません。なぜなら早く始めれば、より長期で積み立てることができ、その分金額も多くなるからです。では、iDeCoの受け取りは、どうすればいいのでしょうか?iDeCoは、60歳から75歳までの間に受け取ることができ、「一時金」「年金」「一時金と年金の併用」の3つの受け取り方から選ぶことができます。つまり、タイミングや受け取り方法を自分で選択できるのです。では、受け取るタイミングと受け取り方は、どう選べばもっとも有利になるのでしょうか?今回は、iDeCoの出口戦略、受け取り方について解説をしてみましょう。
退職する人は必見!任意継続か国保か、保険料が安くなるのはどっち?
任意継続から国保の切り替えが可能に
会社員を辞めてフリーランスになろうと考えている人、または定年退職で仕事を辞める人など、退職してすぐに次の会社に勤めない場合には、重要な手続きが3つあります。まず、「雇用保険の手続き」で、失業給付の申請です。次の仕事が決まっていない場合には、とくに重要です。次に60歳未満の人は「年金の手続き」が必要です。第3号被保険者から、第1号被保険者へ変わります。企業年金も手続きが必要ですので、人事部などに確認してください。最後に、忘れていけないのが、「健康保険の手続き」です。会社の健康保険を継続するか、別の健康保険に入るか、どちらにしても手続きが必要です。2022年1月から少し改正があり、加入する健康保険によってはお得になります。今回は、2022年の改正を含め、退職したときの健康保険の手続きについて説明したいと思います。
定年後の時間は思った以上に長い。老後生活をイメージするためのお金の見直し方と「定年活動」のススメ
お金もキャリアも先のことを想定するのが重要
それまでの人生を振り返ってみてください。会社や仕事を中心に物事が回っていませんでしたか? 多くの人は日常の時間の中心に「仕事」があります。それが60歳で定年を迎え、仕事の第一線から外れることになります。ここで、一度立ち止まって、生き方の総括をしてみませんか? この時期に定年後のプランニングを考えることは、とても大切です。定年後の選択肢は、いくつも用意されています。リタイア、再雇用、転職、起業、フリーランス、ボランティア、学び直し、……などなど。のんびりした人生を過ごすのか? または、仕事の第一線として働き続けるのか? それとも、いままでとは違った新たな道に進むのか? すべて、あなた次第です。その重大な分かれ目になるのが、定年です。自分のお金のプランニングはもちろんのこと、キャリアについても見つめ直して、さらに人とのつながりも再構築していく必要があります。それを整理するために「定活」=定年活動があります。今回は「定活」のススメということで、解説していきます。
40%以上が「樹木葬」を選ぶ時代に。一般墓と比べて費用はどの程度違う?
価格は一般墓と比べて控えめ
私がもつ樹木葬のイメージは、西行の詠んだ「願わくは 花の下にて 春死なん その如月の 望月の頃」というところでしょうか。なんとなく桜の木の下に埋葬されるのもいいのかな?なんて漠然と思っています。桜は満開よりも、散り際の桜を見るのが好きというのも、人生の散り際のイメージがあるからでしょう。この西行の歌のイメージが好きだからかも知れません。自分のお墓について、まだ具体的にイメージを持っているわけではありませんが、遠からず自分のお墓についても考える時期がくるのでしょう。ということで、今回は樹木葬について解説をしてみます。
不妊治療が健康保険適用に。医療保険でも給付金を受け取れる可能性も
医療費以外の問題もあり
日本では、不妊について心配したことがある夫婦は35%いるそうです。また、実際に不妊の検査や治療を受けたことがある夫婦は18.2%で、夫婦全体からみると5.5組に1組の割合です。それだけ多くの方が、不妊についての悩みを持っています。いままでの不妊治療は、体外受精などの診療は自費だったので、高額な費用がかかっていました。自治体などの助成金もありましたが、それでも立て替える必要や所得制限などの条件がありました。そのため、高額な治療費が負担になり、あきらめる方も多かったと思います。でも、2022年4月から不妊治療が保険適用になりました。これは、じつに朗報です。一般の治療と同じように、病院の窓口では3割負担で受診できることになり、かなりハードルが下がったといえます。さらに高額な費用がかかったとしても、高額療養費制度があるので負担額に上限があります。つまりお金の心配をあまりせずに治療に専念することができるようになったのです。今回は、不妊治療の現状と医療保険について説明していきましょう。
2022年10月からパート・アルバイトの手取りが減ってしまう? じつはそんなに悪い話でもない社会保険の適用拡大の話
長い目で見ると、とてもお得
現在、事業所規模が500人超の会社で働くパート・アルバイト(短時間労働者)は、厚生年金への加入義務がありますが、2022年10月からは事業所規模100人超の会社にも適用が拡大されます。これによって、パートやアルバイトで働いてきた人は、厚生年金と会社の健康保険に入ることができますが、専業主婦(夫)は、手取り金額が減ってしまうことになります。「えっ大変!手取りが減ってしまうの?」「そうでなくても、値上げラッシュで家計はピンチなのに!」なんて思う人が多いかも知れません。あわてないでください。今回の改正で、「損をする人」「得する人」がいます。でも今回の改正をよく理解してみれば「損をする人」も「得をする人」に変われます。じつは、そんなに悪い話でもありません。今回の改正で何が変わったのか? そして、どうすれば「得をする人」になれるのかを解説してみましょう。
トイレ修理390円〜の業者に修理依頼も、55万円の請求! 悪徳業者に引っかからない方法とは
火災保険の付帯サービスを上手に使おう
「トイレ修理で〈390円〜〉というネット広告を見て修理を依頼したら、なんと55万円請求を受けた」(40代・女性)。「解錠で、高額請求をされて個人情報を知っていると脅されて、その場で支払った」(20代・女性)これは、国民生活センターに寄せられた実際の事例です。近年、日常のトラブルに事業者が対応する「暮らしのレスキューサービス」で、高額請求を受けたという相談が急増していると、国民生活センターが注意喚起を行っています。ネット検索で上位に表示されていた広告がきっかけという相談事例が急増しています。そこで、今回は、水回り・カギ開けのトラブルの対処法と便利な火災保険の付帯サービスについて紹介します。
年金の受取開始が75歳まで延長に。何歳から受け取るのがもっとも得する?
70歳を目標にしてみる
2022年4月に年金の大きな改正がありました。その中でも話題になったのが、年金の受給開始を75歳まで延長できることです。それまでは、60歳から70歳までに年金を受け取ることができましたが、5年延長になり75歳までの受け取りが可能になったのです。60歳から75歳までの15年間であれば、どの時点で年金の受け取りを開始するかは自分で決められます。つまり選択肢が広がったといえます。そこで考えたいのは「いったい、いつ受け取るのがもっとも得をするの?」ということです。年金の受け取るベストタイミングっていつなのか?を解説してみます。
ポイントがもうすぐ期限切れ…。有効に使うなら「ポイント募金」も手
消滅か寄付か
SDGsとは、国連で決まった「持続可能な開発目標」のことで、17のゴール、169のターゲットを定めています。「SDGsに関する意識調査」(セレス「モッピー」調べ)によると、約8割の人がSDGsについて知っていると答えていて、かなり浸透してきたのがわかります。しかし、実際に行動している人はわずか1割です。ただ、4割の人が行動を起こしたいと思っているそうです。興味はあるけれど、なかなか行動に起こせない、どんな行動を起こせばいいのかもわからないひとも多いはずです。それに、最近の値上げラッシュ。家計がどんどん厳しくなるのも無視できません。SDGsにも協力はしたいけど、家計のことを考えると、すぐには踏み切れないところもあります。そこで、家計にそれほど影響を与えずに、SDGsに協力する方法を考えてみましょう。
フリーランス・自営業者は必見! 国民年金保険料の支払いで1万円以上得する方法
前納とクレジットカードのコンボ
日本は、国民皆年金制度なので、原則全員が国民年金に加入しています。そのうち、1,449万人が国民年金の第1号被保険者で、全体の約21%です(「厚生年金保険・国民年金事業の概況」令和2年度より)。第1号被保険者は、自営業・フリーランスのひとたちです。第2号被保険者は、会社員・公務員のひとで、厚生年金に加入しています(4,513万人、全体の67%)。第3号被保険者は、専業主婦(夫)のひとです(793万人、全体の12%)。第1号被保険者の国民年金に加入している人は、月額1万6,590円の保険料を支払っています。この保険料を安くしたいと思いませんか?今回は、国民年金の保険料が得になる話をしてみます。
ミュージカルや歌舞伎のチケットが半額に!あまり知られていないお得な制度、美術館も安くなる?
実はお得な都民半額観劇会や友の会
新型コロナウィルスの影響が少しずつ収まり、普段の生活に戻してきた感じがあります。コンサートや演劇などのイベントでの人数制限も徐々になくなってきています。コロナ禍で中止になっていた歌舞伎とかミュージカルの公演も、予定通りに開催されるようなりました。まだ人数制限などもありますが、美術館に訪れる人も増えてきているようです。久しぶりに、歌舞伎見物とかミュージカルを楽しみたいと思う人も多いでしょう。しかし、そんな気持ちに暗い影を落とすのが「値上げラッシュ」。「6月からは2ヵ月間で3,000品目の値上げをする」、「今年の累計の値上げは、1万品目を突破する公算が大きい」などのニュースを聞くと、節約をしなければ……とも感じてしまいます。「ミュージカルや歌舞伎に行くのは贅沢かな?」と思い留まってしまうかもしれません。でも、チケットが半額で観られるとなると、行ってもいいかな?なんて思いませんか。今回は、超お得なチケットの入手方法を解説します。
「介護離職」をすると自分の老後は破綻する?悲劇にならないために使える制度やサービスでの対策方法
誰にでもおこりうる介護生活
厚生労働省の「雇用動向調査」によると2019年に介護・看護を理由に退職した人は約10万人、そのうち男性は約2万人、女性は8万人です。女性の方が圧倒的に多く、負担が女性に片寄っていることがわかります。介護離職者の年代を見てみると男性は、50~54歳、女性は60~64歳がもっとも多くなっています。人それぞれですが、人生の中で、介護は「自分の両親」「配偶者の両親」「配偶者」と、5人の対象者が考えられます。介護は、誰にでも起こる問題の一つかもしれません。親の面倒は自分がみたいとか、兄弟がいなくて自分しか面倒をみる人がいないこともあるでしょう。その場合、仕事をやめて介護に専念したい気持ちもわかります。しかし、「介護離職」をしてしまうと親子共倒れになってしまう可能性があります。また介護が終わって、気がつくと自分の老後の生活が破綻となりかねません。今回は、実例をもとに「介護離職」してしまったことで起こりうる悲劇や対策についてお話します。
保険は見直すのが「正解」? それとも見直さないのが「得」なのか?
見直しをしたら損になるケースも
「一度入った保険を見直す必要はない」「保険を見直さなくてもずっと同じでいい」「保険を見直すと損する」なんて、思っていませんか?これは、間違いです(一部あっているところもありますが)。ずっと同じ保険に入っていると保障が足りなかったり、多すぎたりすることがあります。定期的に見直すことで、ムダのない保険に入ることができるのです。今回は、保険の見直しが必要な理由、保険の見直しのタイミングとその注意点について考えていきます。
「得な保険」はないけれど「保険の得な入り方」はある?支払い方や控除、お得な使い方
意外と使える活用方法
「得な保険は何でしょう?」という質問を受けることがあるのですが、とても答えに困ってしまいます。というのは、「保険には得」はないからです。えっ?と思ってしまう人もいるかもしれません。毎年出版している保険ランキング本の「いい保険・悪い保険」の監修者だからこそ聞いたのに……と。でも、事実です。そもそも保険金・給付金を受け取るというのは、何らかの不幸な出来事やトラブルが起こったからにほかならないのです。できることならば、保険金を受け取るような事態が起こらないことが、いちばんいいことなのでしょう。とはいえ、そんな事態になったときに、経済的に助けるのが保険の役割です。ですから、「得な保険」というのは存在しません。しかし、「得な保険の入り方」というのはあります。今回は、得な保険の入り方についてお話しをしましょう。
非正規の女性の年収は平均197万円、35歳から正社員になった場合に年金額はどのくらい増やせる?
ロスジェネ世代の老後
40歳前後の人たちは「ロスジェネ」世代と呼ばれています。1990年代後半から2000年代前半の「就職氷河期」に社会に出た世代のことを指します。バブル崩壊によって「失われた10年」の時です。ロストジェネレーション、略してロスジェネです。景気が低迷していた時期に新卒として社会に出た人たちです。そのため希望通りの職業に就くことができないばかりか、非正規社員や、なかには無職などとなった若者の世代です。とくに損をしたのは、女性で、男性に比べても非正規雇用が多く、現在も低賃金での生活を強いられています。非正規雇用だと、収入が安定しないなどの理由から未婚率も高くなります。低賃金で、親と同居し、生活を親に依存しなければ生活が送れない独身者も多くいます。また70代の親に40代の子の「7040問題」など、この世代はさまざまな問題を抱えています。では、このロスジェネの世代の人が、高齢になるとどんな老後になるのでしょうか?国際医療福祉大学の稲垣誠一教授によると、約40年後、未婚だったり離別した65歳以上の女性の約半数290万人が生活保護より低い収入になるという予測があります。かなり衝撃的なデータです。女性が将