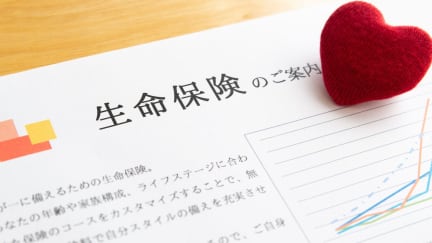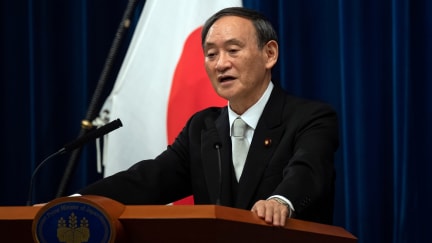ビジネス
経済、投資の最新情報、仕事の給与や稼げる副業情報などを紹介します。
「日銀が買っているからETFを買え」というアドバイスは正しいか?投資信託との違い
まずは自分で全てを理解しよう
投資を始めて情報収集の一環として経済紙を読んだり、ニュースサイトを見ていたりすると、「日銀によるETF買いの観測が広がり、相場の下値が支えられている」や、「日銀は今日の東京株式市場で、通常のETFを〇〇億円買い入れた。」といった記事を目にすることがあると思います。私の知人も投資をしている友人から「日銀も買ってるしETFを買ったら?」とアドバイスを受けたそうですが、「ETFが何か分からない」とのことでした。今回はETFについて学んでいきましょう。
「現地を見ずに買う」のは言語道断、不動産投資初心者が見落としがちなこととは?
現地には時間を変えて4回行く
物件探し、融資の手続き、賃貸管理など、不動産オーナーはやることが多そうに見えます。これから不動産投資を始める人はどんなことに注意すれば良いのでしょうか。2008年から不動産投資をはじめ、分譲マンション23戸を持つ依田泰典さんにポイントを聞きました。
転職に本当に役立つ「資格トップ3」資格自体には価値はない?
「サラリーマンでも取得可能」な範囲で厳選
コロナの影響で、日本経済が大打撃を受け雇用が激減をしています。不景気になると、”自己研鑽”する人が多くなり、資格取得に勤しむ人が多くなりがちです。しかし現実には、転職に有利にならない資格もたくさんで、無駄な時間とお金を使っている人が多くいます。面談人数2000人以上、300社以上の転職支援をしている転職コンサルタントの池田佑樹が、転職で本当に役に立つ「汎用性の高い資格」を厳選して3つ紹介をします。
年内に米大統領が決まらない可能性も?トランプ劇場に一喜一憂する株式市場
新型コロナ感染というオクトーバーサプライズ
米国の大統領選挙投票日まで1ヶ月弱となった9月末から、接戦だった選挙情勢に変化が生じています。
株で3000万円の損失も、分譲マンション23戸オーナーの「投資遍歴」
不動産は「交渉」ができる
株などの投資経験がある人でも、意外と知らないのが不動産投資の世界です。2008年から不動産投資を始め、東京23区内に分譲マンションを23戸保有する依田泰典さんに、株と不動産の違いについて伺いました。
“ラニーニャ現象発生”で株価はどう動くか
寒い冬に向けての株価の動き
先月、気象庁から世界的な異常気象の原因となる“ラニーニャが発生したとみられる”との発表がありました。ラニーニャは南米ペルー沖の海面水温が低くなる現象です。この冬にかけてラニーニャが続く可能性は70%と高い確率になるとのことです。ラニーニャが発生すると、日本の気候はどのように変化するのでしょうか。南米ペルー沖の海面水温が下がるのと対照的に、フィリピン近海の海面水温が上昇します。すると水蒸気が増えて雲が多く発生し、日本では雨の日が多い秋となります。さらに冬にはシベリアからの冷たい空気が流れ込みやすく、寒冬の傾向があります。気象の変動は人々の生活に影響を与えるものですから、このラニーニャも経済、そして株価の動きを左右するようです。今回はラニーニャと株価の関係を取り上げます。
GoTo “錬金術”が話題、抜け穴だらけの問題点はどこにある?
飲食や旅館に恩恵ある制度設計を
「合宿免許が半額で、通学よりも安く取得可」、「ご飯を食べてお金ももらえる」--。このような政府発「GoTo」キャンペーン関連の”裏技”が話題となっています。今月から都民にも解放された「GoToトラベル」。そして、同じく今月から全国で順次開始される「GoToイート」キャンペーンで、これらの制度を使った”錬金術”が巷で物議をかもしています。そもそも”GoTo錬金術”とは何なのでしょうか。そして、その問題点はどこにあるといえるのでしょうか。
精神科医が教える「怒りをコントロールする技術」
まずは、「最初の6秒」をやりすごせ
ついイラッとして暴言を吐いたり、怒りのメッセージを送ったりしたことは、誰にでもあるのではないでしょうか。怒りの感情は、人間関係のトラブルを巻き起こしたり、後になって大きな後悔をしたりするので、取扱注意です。では、「怒り」はどうコントロールしたら、いいのでしょうか? 精神科医の樺沢紫苑さんの著書『ストレスフリー超大全 人生のあらゆる「悩み・不安・疲れ」をなくすためのリスト』から抜粋して紹介します。
「クレジットカードの色」はどこまで大事? “固定費削減”はセミリタイアへの近道
「見栄を張らない」人生の気楽さ
最近クレジットカード会社の「デフレ」化が進んでいるように感じます。15年ほど前まで「黒いカード」というものは、選ばれし者だけが持てるもので、今から1時間後に○○航空のファーストクラスを突如として確保できる、的な都市伝説まであったほどです(いや、本当かもしれないけど)。しかし、今、新興のカード会社が次々と「黒いカード」を出しており、それらがそこまで年会費が高くないんです。
酒税法改正、真の狙いは6年後の税収増?人気の新ジャンルは最終的に1缶26円アップ
ビールは値下げ
今年の10月から酒税法改正の第1弾がスタートしました。同法は2026年10月にビール類の税制を一本化するための段階的な措置として行われました。税法上、ビール類はビール、発泡酒、新ジャンル(第3のビール)に分類され、それぞれ税金が異なります。税金が一番高いのがビール、次いで発泡酒、新ジャンルという順番です。改正により、ビールの価格は1缶(350ml)あたり7円下がり、第3のビールは9.8円上がります。
トランプ大統領の新型コロナ感染で日経平均は下落。今後の為替市場の見通しは
11月3日米大統領選
結果論として、マスクを拒否し、マスクをつけないことを推奨し続け、マスク無しでの遊説を各地で続けていたトランプ米大統領が新型コロナウイルスに感染することは必然であったのかもしれません。トランプ大統領の感染は、市場にどんな影響を与えるのでしょうか。<写真:アフロ>
クリーニング必要なし!ワイシャツ1枚440円、サブスク戦国時代に登場した5つの特化型商品を追う
どこまでおトクに利用できるか
定額料金を支払うことで、一定期間のサービスが保証されるサブスクリプション(以下、サブスク)。日本では古くから新聞購読、雑誌の年間購読などがありましたが、ここ数年であらゆる業態が取り入れはじめ、各社より様々なサブスク商品がリリースされています。もはや「サブスク戦国時代」とも呼べる今ですが、ここでは、それまでには想像できなかった特化型サブスク商品をここで5つご紹介。利用者目線で細かく見ていきたいと思います。
米のファーウェイ制裁強化始まる、世界シェア変動で投資妙味のある銘柄3選
当面は半導体関連の銘柄選択が重要に
米商務省によるファーウェイへの制裁強化の猶予期間が9月14日に終了しました。今後はファーウェイに半導体を販売する場合、ファーウェイが設計した特注品であれ、スポット市場で取引される汎用品であれ、少しでも米国の技術が使われていれば事前の許可が必要になります。2020年4~6月期にファーウェイは、中国国内スマホ市場での圧倒的なシェアを武器に世界で5,000万台半ばのスマホを販売し、世界シェアがトップとなりました。今後、急速にシェアを失うことは明らかで、漁夫の利を狙った競争が激しくなりそうです。<写真:ロイター/アフロ>
うつを再発させないために、上司や労務担当者はどうフォローすべきか
「復職後再発率ゼロ」の心療内科医に聞く
こころの不調で休職した従業員が職場に復帰するとき、いかに病気を再発させないようにフォローすべきか。職場担当者が果たすべき役割について考えます。(本稿は月刊『企業実務』2020年9月号の記事を転載したものです)うつ病などのこころの病による休職からの職場復帰はなかなかむずかしいとされています。しかし、職域の気分障害治療とリハビリテーションを専門に手掛ける心療内科医療機関のボーボット・メディカル・クリニックでは、これまで2000人近くの患者を診断し、復職後再発率がゼロだという。その経験をもとに、『復職後再発率ゼロの心療内科の先生に「薬に頼らず、うつを治す方法」を聞いてみました』を発刊した同クリニックの亀廣聡院長に、復職支援にあたって企業が押さえておくべきポイントを聞いてみました。
なぜ人は高値で株を買ってしまうのか
高値覚えと安値覚え
9月も終わりになり、さすがに朝晩は寒いくらいになってきました。新型コロナウイルスの感染拡大も続いていますが、株式市場は堅調な地合いが続いています。米国では先駆したハイテク銘柄などに調整となっているものも見られますが、世界的な金余りのなかで売り急ぐ動きも見られません。ナスダック指数も下がったとはいえ、10,000の大台はしっかりとキープしています。
そもそも保険ってなんのために入るのか?保険の基礎知識
保険の仕組みができた理由
日本人の約9割(88.7%)※が「生命保険」や「医療保険」など何かしらの保険に入っています。この数字は、諸外国と比較するとかなり高い割合です。にもかかわらず、保険に嫌悪感を抱かれている方、もしくはご自身の加入内容を理解されていない方が大半です。ではなぜこのような状況になってしまっているのか、「そもそも保険ってなんのために入るのか」の本題に入る前に、まずは時代背景から簡単にお話していきます。※生命保険文化センター「平成30年度 生命保険に関する全国実態調査(速報版)」参照
菅政権の規制改革は歴代政権と何が違うのか
シングルヒット量産型
今週29日は9月中間期末の配当権利落ち日でした。この日の日経平均は150円弱の配当落ちを受けて反落して始まりましたが、徐々に下げ幅を縮めると最後は小幅高で取引を終えました。配当落ち分を埋めきったということです。配当落ち分を即日埋めるのは相場が強い証拠といいます。背景にはやはり菅政権への期待があると考えられます。菅政権への期待とは規制改革が進むという期待です。
今すぐできる、「伝える力」がみるみる上がる3つのポイント
コミュニケーションは資質ではなくスキル
リモートワークなど多様な働き方が広まるなか、さまざまなツールを介しても、きちんと伝えられるコミュニケーション力が求められています。日本IBMや日本マイクロソフトで役員を務め、現在は様々な企業の取締役として経営アドバイスを行う佐々木順子さんは、コミュニケーションは「努力しだいで上達することができる」といいます。具体的にどのようなことを心がけたらよいのでしょうか。著書『「あなたにお願いしたい」と言われる仕事のコツ88』(ぱる出版)から一部抜粋して紹介します。