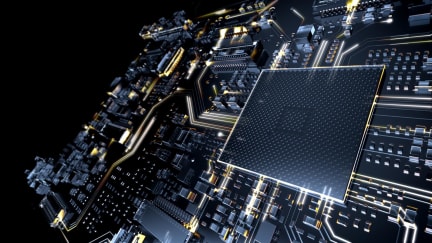ビジネス
経済、投資の最新情報、仕事の給与や稼げる副業情報などを紹介します。
時価総額1兆ドル超え!エヌビディアが急騰したのは何故なのか
日本市場復活の鍵は?
先週、5月29日週にアメリカの半導体メーカー・エヌビディアの時価総額が、一時1兆ドル(日本円で140兆円)に達した事が話題となりました。半導体メーカーでは、初めての1兆ドル企業です。これまで1兆ドルを超える企業は7社あり、アップル、サウジアラムコ、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン、テスラ、メタで、エヌビディアは8社目となります。皆さんもいくつかの企業は耳にした事があると思います。
トヨタやパナ、SBは選ばれず…優良銘柄を選定した【JPXプライム150指数】上位10銘柄は?
投資家が知っておくべき株価指数の意義
JPX総研が公表した新指数「JPXプライム150指数」の構成銘柄や算出要領が、5月26日(金)に発表となりました。今回は、株価指数の概要と代表的な各国の株価指数、投資家としての株価指数の意義、そしてJPXプライム150指数についてお伝えします。
森永製菓と江崎グリコにある【2倍の差】とは?好調お菓子メーカーの決算を分析
長期チャートで株価の変化を見ると…
夏の足音が次第に大きくなりつつある今日この頃、わが家の娘たちは毎日のようにアイスを食べています。彼女たちが選ぶアイスはだいたい決まっており、チョコモナカジャンボか、ジャイアントコーン。この2つは何年も変わらず、わが家の冷凍庫のイツメンです。チョコモナカジャンボは森永製菓、ジャイアントコーンは江崎グリコが製造しています。わたしの贔屓はジャイアントコーンですが、チョコモナカジャンボも捨て難い。アイスでは甲乙つけがたい対決ですが、じつは株価の上昇率も夏に向けて接戦を繰り広げています。お菓子メーカーは、コロナの巣篭もり需要で2021年、2022年は好調でしたが、2023年は原材料高に苦しめられ、業績は低迷していました。そこから価格転嫁をすすめ、徐々に業績が回復しつつあります。あらためて2社を比べてみましょう。画像:TradingViewより
上場する「日経225ミニオプション」、基本的な4つの取引方法
米国では活発なオプション取引
4月から、日経平均株価が非常に強い動きになっています。背景には、東証が上場企業に資本コストや株価を意識をするよう要請したことによるPBR(株価純資産倍率)の改善期待などから、海外投資家が大幅に買い越している事があげられます。4月末から5月上旬にかけ行われた決算発表と同時に、増配や自社株買いなど株主還元を発表する企業も多く見られました。
円安が進んだら、インフレが進行したら…投資家に必要な「連想力」を磨く方法
4つの事例から考える
株式投資は連想ゲーム−−多くの投資家が共感するこの言葉には、株式市場を理解するための重要な鍵が隠されています。経済の動向、社会の変化、業界の特性など、膨大な情報から一つの予測を導き出すためには、情報を結びつけ、連想する力が求められます。今回は、投資初心者や日本株に興味をお持ちの方々に向けて、連想ゲームと呼ばれる理由について、具体的な事例をもとに解説していきます。
日経平均が約33年ぶりに高値を更新したのはなぜ? 金利、企業業績、それ以外に考えられる要因
バフェット、PBR改善要請の影響か
日経平均がバブル崩壊後の高値を更新しました。その後も買いの勢いは衰えず3万1000円の大台も越え、1990年7月以来、約33年ぶりの水準まで上昇しました。日本株が急伸した背景として様々な要因を指摘できますが、まずはもっとも基本的なことを確認しましょう。
給与に休暇、懲戒も…職場で確認しておくべき【就業規則】のポイント
弁護士の視点からピックアップ
会社員の方は、お勤めになっている会社の就業規則をご覧になったことはありますか?私は就業初日に、「今日はこれを読んでおくように」と就業規則を渡されたので、何が重要かなど特に意識もせずに、パラパラと紙をめくって読んだ記憶があります。内容については、それほどしっかり把握していなかっただろうな、といまでは思います。それでも一読しているだけ、まだいいのかもしれません。なかには、就業規則を配布されたり社員専用サイトから確認しておくようにと言われてはいても、目を通していない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか?確かに、就職した後でないと見る機会のない就業規則ですから、「もう入社したし、いまさら確認してもな……」と思ってしまうのもわからなくはないです。私が退職手続きの代理業務を行っている際、就業規則の内容を把握していなかったり、何処にあるかもわかっていなかったり、という方が実は少なくないです。就業規則の中には、給料に関すること、休日に関すること、賞罰に関することといった、ご自身が会社に対して守らないといけない事、ご自身の会社に対する権利など、知っておくべき事が記載されていますから、その内容は入
メイク需要が追い風に!進む“脱マスク”で恩恵を受ける黒子企業とは
日本を代表するビューティー企業の決算は?
日経平均株価は、バブル後の高値を33年ぶりに上抜けて31,000円台に乗せてきました。上昇の要因は、下記が考えられます。カリスマ投資家であるバフェット氏が日本株に好意的な発言をしたことPBR1倍割れ銘柄に対する東証の改善要求により、日本企業が株価上昇を意識し始めたことしばらくは日本の金融緩和政策が続きそうであること期待以上に日本の存在感をアピールできた広島サミットインフレ高止まり、金融不安を抱えた欧米に比べて安心感があること国内外から半導体関連に関する投資が活発化していることこれらに加えて、各国に遅れてやってきた“脱マスク”の効果もかなり大きいと思っています。というのも、マスク着用が個人の判断に委ねられてから、しばらくはまだまだマスク着用者が圧倒的に多かったものの、ゴールデンウィークを挟んだのちは、徐々にノーマスク派が増加しています。わたしは真っ先にマスクなしの生活を堪能しておりますが、なんと清々しいことか。制限なしに行きたいところへ外出できる開放感を存分に味わえる−−そんな気持ちの昂揚が、日本景気を明るくしていることは間違いありません。うっかりお財布のヒモもゆるくなっていることでしょ
投資をまったくせずに老後資金2000万円を貯めるのは難しい?お金のプロがシミュレーション
老後資金“だけ”なら難易度はそこまで高くはない
「お金を貯めるには投資が必要」とよく言われます。株・債券・投資信託・不動産など、金融商品はいろいろありますし、iDeCoやNISAといった老後資金づくりに役立つしくみも整備されています。こうした金融商品やしくみを利用した投資をまったくせずに老後資金2000万円を貯めるのはそもそも難しいのでしょうか。皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
日本は「最も悲観的な国」を脱出も…。漠然としたお金の心配をする人が多いという調査結果
世界17か国2万人のウェルビーイングや金融行動を比較
今回はフィデリティが毎年実施している人々の心理や金融行動に関するグローバル調査についてご紹介したいと思います 。ウェルビーイングの国際比較もわかる調査になっています。調査結果を一言でいえば、「インフレがすべてを動かした」といったところでしょうか。日本では過去20年間デフレの時代が続き、私たちは物価が上がらない世界に慣れきっていました。ところがコロナ禍を契機に、2022年、突如としてインフレが始まり、私たちの生活は大きな影響を受けました。対抗措置として大企業では賃金の引上げが行われましたが、日本の労働者の7割が働く中小企業では、まだまだこの動きは広がっていません。世界的にはインフレの影響はもっと深刻です。インフレによる生活水準の低下は、人々の心理・行動を玉突きのように動かしています。その様子を調査結果から見ていきましょう。
SNSの流行で価格が高騰する暗号資産「ミームコイン」。一攫千金かハイリスクか、投資家はどう扱うべきか
SNSが金融市場におよぼす影響は大きくなる
最近になって「ミームコイン」というSNSでの流行などによって価格が高騰する暗号資産が再び注目を集めています。2021年には柴犬をモチーフとした「ドージコイン」がイーロン・マスク氏の支持を受けて大きく値上がりしましたが、今回は「ペペコイン」というカエルのキャラクターに代表される銘柄が人気となっています。ペペコインは2023年4月に発行が始まり、5月6日にはスタートから約50倍以上の価格まで高騰しました。しかし、そこから約60%下落し、まさにジェットコースターのような値動きを見せています。このような投機色の強いミームコインの盛り上がりを見て、一攫千金を狙えると考えるか、投資リスクが大きいと考えるかは人によって異なるでしょう。ミームコインブームはこれまでも暗号資産市場で度々起きており、今後も定期的に発生するでしょう。そこで今回は、投資家の立場としてミームコインをどのように捉えるべきか、ミームコインが暗号資産全体の相場に与える影響についてお話します。
楽天グループの株価急落はなぜ起きたのか?焦点となるのはモバイル事業
カギは6月から実施する新プラン
5月15日(月)の取引終了時間近くに、楽天グループ(4755)の株価が急落しました。私はラジオNIKKIの生番組に出演するため、電車に乗っていて、スマホで株価を見ていたのですが、14時50分頃に740円超えで推移していた同社の株価が、あっという間に一時625円まで売られました。一部報道機関から、公募増資や第三者割当増資などを検討していると発表されたことで大幅下落となりました。
日経平均3万円超えも市場では降格ラッシュ?上場している企業が降格するとどうなるのか
東証フォローアップ会議の影響とは
2023年5月17日(水)、日経平均株価は3万93円59銭となり2021年9月以来、約1年8ヵ月ぶりに3万円台を回復しました。要因として4月から、海外投資家の買いが継続していると見込まれいます。日本株への先高期待感や為替市場での円安進行、5月17日(水)に内閣府が発表した2023年1-3月期GDP速報値が前期比0.4%増、年率換算で1.6%増と3四半期ぶりのプラス成長で、先進国では遅れてのコロナ禍からの経済回復で個人消費も伸びていることに加えて、インバウンド期待もある……と、理由はいくつか考えられますが、東証のPBR1倍割れ企業に対しての取り組みもその一因となっているのではないかと感じています。今回は東証のPBR1倍割れの企業に対しての取り組みを、投資家はどう捉えるべきなのか−−仮に上場維持基準を満たせず、プライム市場からスタンダード市場に降格した場合、どのような影響があるのかを考えていきましょう。
相次ぐ米銀行の破綻、債務上限問題、インフレ…。米国への投資はいまどうするべきか
個別銘柄や債券に投資している人は要注意
シリコンバレー銀行の経営破綻からはじまり、シグネチャー銀行、ファースト・リパブリック銀行などここ数ヶ月で複数の銀行が経営破綻しました。一部の有識者やメディアは「リーマンショックの再来」と表現しています。日本では米国株に投資する投資信託や米国の個別銘柄、債券などに投資をしている個人投資家も多くいるため、今後の米国経済や株式市場の行方に不安に感じている方も多いかと思います。今回は不安を小さくするために、まずは米国が抱えている問題点を整理したうえで、どのような投資行動をとればいいかを書いていきます。
コクヨの株価が決算発表後に右肩上がり、その裏で伸びた銘柄とは?
“二匹目のドジョウ”を狙う方法
日々発表される決算のチェック作業は、投資家にとっては重要なイベントです。決算発表をきっかけに株価が上昇し始めることも多いため、その初動を捉えたいなら、発表当日にチェックするのがベストです。とはいえ、1日で何百社、混み合う日には千社以上の発表が重なりますから、すべてに目を通すのはきついもの。専業投資家ならまだしも、会社員として働いている個人投資家の方でしたら睡眠不足で日中の仕事に差し障りがでます。そこで、効率よく当たり銘柄を見つける方法として、好決算で株価の反応がよかった銘柄の“二匹目のドジョウ”を狙う作戦を紹介します。
NTTが異例の大型株式分割、狙いは新NISA?個人投資家にとってのメリットとデメリット
想起される1987年の上場
先週、5月12日(金)のザラ場に驚きの開示がありました。NTT(9432)が2024年3月期の決算と同時に、1株につき25株を割り当てる株式分割を発表しました。時価総額が14兆円を超える同社が25分割とは考えつかず、開示情報をもう一度見返すほどの出来事でした。
分散は地域や商品だけじゃない−−分散投資で考えたい【時間】を分ける優位性
代表的な方法「ドルコスト平均法」とは
分散投資はリスクを軽減し、ポートフォリオ全体の安定性を高める投資戦略です。株式における分散投資の考え方として、前回は「地域」と「銘柄」について見ていきました。今回もう1つ、「時間」について解説していきます。
決算発表の翌日に爆上げ!投資家が反応した3つの銘柄の共通点とは?
3月決算企業が本決算を発表するタイミング
ゴールデンウィーク前後は毎年、決算発表が集中するため、休みボケなどとは言ってられません。とくにこの時期は、3月決算企業が本決算を発表するため、投資家からの注目度がもっとも高く、寝る間を惜しんで決算チェックをしている強者もいることでしょう。わたし自身は、すべての決算内容に目を通すほどのマニアとは言えず、決算発表後に株価の反応がよかったものだけを、どれどれとチェックする、後出し投資法を実践しています。決算発表後の株価の動きは、よくても下げたり、悪くても上げたりチグハグな動きをすることが多々あり、一筋縄ではいきません。好決算を期待した先回り買いで、被曝したこともしばしば。そういった悲劇を避けるため、決算後の株価の反応を見てから参戦するのが良策です。今回も、決算発表の翌日に暴騰した銘柄を物色していたところ、いつもとは少し違った傾向に気づきました。