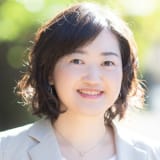住まい
賃貸の家賃やマンション相場、住宅ローンなど、役立つ不動産情報を紹介。
日頃から掃除している? 汚部屋? 家の状態別6時間で終わらせる大掃除リスト
「掃除」より「片付け」を優先したほうがいいケースも
年末の恒例家事「大掃除」。月末ギリギリまで仕事があって、ようやくのお休みだからゆっくりしたいという気持ちがある反面、大掃除をやらないと…という罪悪感にかられている人もいるのではないでしょうか。モヤモヤしているならば、時間を決めてその時間だけ大掃除をすることをおすすめします。しかし、大掃除というと換気扇、窓磨きなど定番の作業が浮かびますが、「そこをやっている場合じゃない」というケースの家もあります。今回は家の状態にあわせて6時間でやる大掃除のリストをご紹介します。
憂鬱な大掃除を楽にする! 家事アドバイザーが使い続けるお掃除アイテム6選
水回りで大活躍
年末が近づいてくると「大掃除しなくちゃ…」と憂鬱な気分になる方もいるのではないでしょうか。日頃やっていないところの掃除は、手間がかかるものです。しかし、近年は技術の進歩で便利な掃除グッズが多く発売されています。筆者は仕事柄、数多くの掃除グッズを試していますが、今回はその中でも高い効果を実感して使い続けているアイテムをご紹介します。
家計に占める家賃の適正は何%? 割合をさらに減らしたほうがいいケースとは
目先の生活を重視しすぎないことが大切
家賃は、家計において大きな割合を占める固定費となります。そのため、家賃を決める際には、無理のない範囲で設定することが大切です。ここでは、家計に占める家賃の相場について解説します。
増えつつある「固定資産税0円」の不動産とは? あまり知られていない”負”動産の活かし方
活用策を見い出せば、高値で売却・賃貸ができる可能性も
不動産の所有者にかかる費用の一つに、「固定資産税」があります。土地、建物にかかわらず、不動産にはすべて、市町村役場が定めた固定資産評価額が決められています。この評価額とは、不動産鑑定士などの有識者の意見も交え、客観的な立場から不動産の価値(時価)を鑑定して算出されたものです。たとえば、建物の築年数が経過すれば、その分だけ価値は下がり、他方、都市開発などによって土地の相場が高騰した場合には、そのぶんだけ価値が上がるわけですが、これらを評価額として反映させているのです。この評価額に所定の税率をかけたものが「固定資産税」であり、すべての不動産に評価額がある以上、不動産の所有者は固定資産税を毎年納める義務があるのです。不動産の規模や地域性によって大きく異なりますが、たとえば一軒家やマンションをマイホームで所有している場合には年間数万~十数万程度、投資用のアパートやマンション経営をしている場合には、年間数十万近い納税をしていることもあります。 しかし、なかには「固定資産税が0円の不動産」というものがあります。しかし、これは認知度が低いため、なかには「一向に納税書類が届かないが、もしかして自分の手
エアコン、電気カーペット、こたつ…冬物家電を節電しながら使う方法
冷気の遮断と熱を逃さないことがポイント
暑い夏も終わり、そろそろ寒い冬に向けて暖房機器の準備が必要な時期となってきました。エアコンやファンヒーターなどの暖房機器は多種多様ですが、冬本番を前にそれぞれの節電方法を考えてみましょう。
変動金利型住宅ローンを契約した人は必見!金利上昇の影響が大きい人の特徴3つ
注意点と対策をFPが解説
10月31日、日銀は長期金利の上限のめどを1%とすることなどを決定、大手三行は10年固定金利型住宅ローンの基準金利を引き上げました。日本の金利は低い水準にありますし、短期金利に大きな動きはありませんが、変動金利型住宅ローンを利用する方は、来年以降の基準金利は上がることを想定したご家庭の対策を確認しておきましょう。とはいえ、なかなか重い腰が上がらない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は変動金利型住宅ローンを利用している方のうち、金利上昇への備えを早めにすすめておきたい方の特徴を3つ挙げ解説します。
「夫が働けなくなった時に住宅ローンの返済が続くのが心配…」どうすればいい?
団体信用生命保険、福利厚生制度、そして…
住宅ローンの借り入れをしている方は、万が一働けなくなったらどうしようと頭をよぎったことはないでしょうか。夫婦の場合、働き方や金融資産など状況によって対処方法は変わってきますが、どのように考えていくのが良いのかを解説します。
築古戸建は不動産投資の対象としてアリかナシか。気をつけるべきマンションとの決定的な違いとは?
築古戸建てならではのメリットとは?
前回の寄稿記事では、「築古マンションは投資対象としてアリか」というテーマをお話ししました。公開後、「では、築古戸建はどうか?」という質問をいただきましたので、今回は築古戸建に絞って、不動産投資の対象としてアリかナシか、筆者の経験も交えてご紹介したいと思います。
野菜を使い切ることも節約のひとつ! 食費節約に役立つ使い切りレシピ
最強のお助けメニューはキーマカレー?
連日のように値上げのニュースが続く中、2023年の猛暑が野菜に影響し、さらなる値上げとなっています。このような中で食費を節約したいとなると、少しでも安いお店を探したり、安価で買える食材に置き換えたりする方向へ考えがいきがちです。しかし、日本の一般家庭の食料廃棄率は低くなく、農林水産省「食品ロス統計調査 平成26年度 」によると、世帯食の一人1日当たりの食品ロス量は40.9gで、その約半分の19.5gが「野菜類」というデータが出ています。何かを我慢するよりも、買ったものをしっかり食べきることも食費の節約につながるのです。今回は野菜を食べきるということを考えてみたいと思います。
45歳でマンションを購入した独身女性 完済は80歳「老後資金を確保できるか不安」
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、45歳会社員の女性。73歳の母との同居を視野に入れ、34年ローンで新築マンションを購入した相談者。ローンを返済しつつ老後資金を確保できるか不安だといいます。FPの渡邊裕介氏がお答えします。
住宅ローン、返済比率20%でも赤字に転落…住宅購入を進める前に知っておくべき予算の立て方
住宅ローン借入可能額の落とし穴
住宅購入を予定しているAさん(39歳)。住宅メーカーへ相談する際、どれくらいの予算を想定すればいいのかを相談しに、ファイナンシャルプランナーの筆者のもとに相談に来られました。住宅ローンの借入額がいくら位までであれば、無理なく返済できるのかが気になっているそうです。Aさんのご家庭の家計状況と今後の対策についてみていきましょう。
「最寄駅は自転車15分で不便…」マンションを住み替えたい共働き4人一家 教育費との両立は成り立つ?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、38歳、共働き4人家族の女性。中古マンションを購入したけれど、利便性が悪く住み替えを考えていますが、教育費も含めいくら貯めたらいいかわからないと言います。FPの横田健一氏がお答えします。
【新NISA】活用前に要チェック!ありがちな「誤解」5選
失敗しないために押さえるべきポイントとは
2024年から始まる「新NISA」。投資の利益にかかる税金(通常、約20%)が無期限で非課税にできるとあって、注目が集まっています。しかし、家計や運用について筆者のもとに相談に来る人から話を聞いてみると、「制度内容を誤解している」「制度を使うことばかりに目を向けていて、資産形成の目的であるライフプランを無視している」といったケースが散見されます。新NISAの制度を正しく理解して、「自分はどうやって活用するとよさそうか」を考えてみましょう!
「子どもも500万の新車も欲しい」29歳夫 共働きアラサー新婚夫婦の家計は車を買っても回る?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、まもなく結婚するという29歳、会社員の男性。これから子どもも欲しいけれど、500万円の新車も欲しいと悩んでいます。FPのシミュレーションの結果は?FPの秋山芳生氏がお答えします。
40代が加入する生命保険、年間払込保険料はいくら?
生命保険への関心が高まる時期
30代で婚姻し子どもにお金がかかり始める40代。少子化対策で高校無償化や子ども手当の拡充など、子育て世代への優遇は進んでいるものの、学費以外の費用も想像以上にかかります。切詰めたいのが民間生命保険の保険料ですが、万一の際、頼りになるのも民間保険です。40代が加入しておきたい保険を考えます。
都内で暮らす60代夫婦の平均年収や貯蓄額、生活費はいくら?【2023年版】
勤労世帯と無職世帯で大きな差
60代は、現役で働く人もいれば、リタイアする人もいて、その生活スタイルは多様です。仕事だけではなく、家庭の状況も多様で、子どもに教育費がかかる家庭もあれば、子どもが就職して家にお金を入れる家庭もあるでしょう。また、医療費や介護費がかかる家庭もあります。今回は、都内で暮らす60代夫婦の平均年収や貯蓄額、生活費について見ていきます。60代夫婦の暮らしは多様ですから、どの家庭も平均値のとおりとはいきません。ただ、平均値との違いから、家庭ごとのバランスが見えてくるのではないでしょうか。
「ふるさと納税」2023年10月から何が変わる? お得な返礼品を見逃さない方法
ポイ活も有効
毎年12月末が近づくと慌てて「ふるさと納税」の手続きをする人も多いかと思います。筆者もその一人ですが、2023年は9月末までがお得な場合もあるので早めのチェックが必要です。2023年10月1日から「ふるさと納税」のルールが変更されるので、今までと同じ返礼品でも寄付額が高くなったり、返礼品の量が少なくなったりすることも予想されます。現時点でも「ふるさと納税」のポータルサイトでは「9月30日受付終了」と明記されている返礼品もあるので、狙っているものがある場合は、早めに行動しましょう。
該当したら即検討!直ちに処分すべき不動産4選
使い道がない不動産は要注意
不動産は、銀行預金、保険商品、株式、外貨など、さまざまな金融資産の中でも、比較的安定的な資産として位置づけられ、特に高度経済成長期には「土地神話」と呼ばれる”不動産は値上がりし続ける”と信じられていたほどでした。しかし、バブル崩壊や人口減少といった要因によって、今日では「不動産=安定資産」とは必ずしもいえない意識の方が常識になりつつあります。もちろん、都市部の不動産は高止まりが続き、不動産投資やマイホーム購入のいずれも、物価低迷期に比べると信じられないような高値になっている側面もあります。その一方で、特に地方の不動産を中心に、需要と供給のバランスが崩れ、資産価値がどんどん目減りしている不動産も増えており、こういった不動産の方が圧倒的多数といっても過言ではないほどになってきています。そこで、この記事では「直ちに処分すべき不動産」を4つご紹介したいと思います。該当する不動産をお持ちの方は、ぜひ早期処分を検討することをお勧めします。