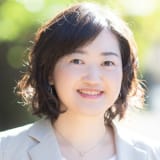約2,000万人が糖尿病&予備軍…。年間治療費は? 発病したら保険加入できる?
受診の中断が年間8%も
「尿の泡立ちがよくて、甘い匂いがする!」あなたにも、経験がありませんか?その他にも、「喉が渇きやすく、いつも何かを飲んでいる」「運動不足」「トイレによく行く」ということが当てはまる人は、糖尿病に注意が必要かも知れません。じつは、糖尿病というのは、日本人にとっては身近な病気なのです。「国民健康・栄養調査」(2016年)によると、糖尿病、糖尿病予備軍をあわせると約2000万人と言われています。日本人の6人に1人は糖尿病または糖尿病予備軍ということになります。糖尿病が強く疑われる人は、男性の5人に1人、女性は10人に1人です(「国民健康・栄養調査」2019年)。男性はとくに気をつけたい病気です。糖尿病の自覚症状は少なく、健康診断などで発見されることが多いです。糖尿病は、それ自体が直接命に関わることはないのですが、放っておくと恐い病気です。
自転車利用者のヘルメット着用義務化。不着用で事故が起きたら保険金の支払いはどうなる?
ヘルメット着用していますか?
改正道交法により自転車を利用する場合、全年齢でヘルメット着用が努力義務となりました。罰則はないものの警察では、事業所や自治体、学校などを中心に働きかけをしています。万一事故にあった場合、ヘルメット着用していなかったら、保険は支払われるのか検証してみました。
よゐこ有野がぶっちゃける【保険】への不満「損してる気分になる」
損しない保険のイロハ(1)
お笑い芸人・よゐこの有野晋哉さんが、毎月さまざまな専門家をゲストに迎えて、お金の知識を身に付けていく「お金の知りたいを解決!お金の学園〜学級委員・よゐこ有野晋哉〜」。2023年5月はファイナンシャルプランナーの塚越菜々子先生に、保険について伺いました。
旅行先で突然の病気…クレジットカード付帯の海外旅行傷害保険だけで補償は万全? 自動付帯と利用付帯の違いも解説
入院になると思わぬ高額になることも
旅行シーズンになると、気になるのが海外旅行傷害保険。盗難、預けた荷物が届かない、水が合わず腹痛で入院など、旅行先ではどんなアクシデントが起きるかわかりません。「でも、クレジットカードに付帯されている傷害保険があるし…」なんて思っていませんか? クレジットカード付帯の海外旅行傷害保険の補償は万全なのか、検証してみます。
1億円近い賠償事例も…。自転車保険選びのポイントと加入しなくてもよい人とは?
民間保険会社以外の選択肢もあり
自転車は、子どもから高齢者まで手軽に活用できる交通手段として、重宝されています。その反面、自転車事故による、高額損害賠償請求が後を絶ちません。条例により自転車保険加入が義務化されている地域が多い中で、どのような保険を選べばいいのか、詳しく説明します。
契約者が保険金請求できるとは限らない? 意外と知らない手続きの仕方と注意点
死亡の場合は要注意
じっくり内容説明を聞いて加入した保険商品。「保険金請求の仕方は何か起こってからで大丈夫」と考えていませんか?保険商品によって請求する人が違うことがあります。いざ保険金請求をする際に困らないよう、注意すべき点を解説します。
その保険不要かも。結婚・出産・定年退職…ライフイベント別に保険を見直すポイントをFPが解説
ポイントをチェックし保険を考える
よく「保険はライフイベントごとに見直しましょう」と言われます。「見直し=加入し直す」と考えられがちです。これはある意味正しくもあり、誤りでもあります。見直すことは決して加入し直すことばかりではなく、加入中の保険が、ライフスタイルに合っているかどうかを見極めることが大切です。今回は、ライフイベントに対し適切な保険に加入しているか、その見極めるポイントについて解説いたします。
年金のギモン、繰上げと繰下げはどちらを選ぶべき?よゐこ有野「破綻してもらえなくなるって聞くけど…」
資産運用と家計(4)
お笑い芸人・よゐこの有野晋哉さんが、毎月さまざまな専門家をゲストに迎えて、お金の知識を身に付けていく「お金の知りたいを解決!お金の学園〜学級委員・よゐこ有野晋哉〜」。2023年3月はファイナンシャルプランナーの岩城みずほ先生に、資産運用と家計について、弁護士でタレントの三輪記子さんと一緒に伺いました。今回は、「公的年金制度」について伺いました。「年金は破綻する」と言われているのは、本当なのでしょうか?
がんになったらすべてを保障してくれるわけではない?知っておきたいがん保険の保障範囲
合併症は保障されない保険も
がん保険の契約件数は、2527万件(生命保険協会調べ2020年度)で、かなり多くの方が契約をしています。そもそも「がん保険」とは、どんな保険でしょうか?「がん保険」とは、「医療保険」の一種ですが、がんという病気しか保障しない保険です。逆にいうと「がん」になったときには保障してくれますが、がん以外の保障はありません。では、「がん」になったら、すべてを保障してくれるのでしょうか?じつは、そうでもありません。どんな「がん」に対して保障してくれるのか? または、どんな場合には「保障」してくれないのか? 再度確認してみましょう。
保険料はどちらが安い?割戻金がある? 共済と保険の違いとどちらを選べばよいかポイントを解説
「簡単に加入」に注意、必要な時に払えない可能性も。
共済と保険、TV・Web・新聞折込など広告宣伝が頻繁に行われ目にしない日はない商品です。いずれも家・車・ひとのリスクを保障する商品ですが、違いは何か理解せず加入しているひとも多いのではないでしょうか? 値段の違いだけではない、共済と保険の違いを解説します。
火災保険で地震の被害は補償される? 知っておきたい地震保険の基本
地震保険の加入のススメ
2023年、東日本大震災から12年を迎えます。マグニチュード9.0という巨大規模の地震により甚大な被害を受けました。「地震があったときのために備えておきたい」と考える方も多いでしょう。ただし、火災保険だけでは、地震による災害は補償されません。今回、地震保険とはそもそも何か、そして保険料や加入率について解説します。
保険の重複加入、何がよくない? かぶりやすい保険とお金を無駄にしない入り方
重複補償に注意!加入中の保険を事前チェック
自動車保険、火災保険などの申込時、他に同じ目的の保険に入っていませんか?というチェック項目があります。1台の車に保険をふたつ掛ける人はいないかもしれませんが、細かい項目の重複は見逃しがち。家族で違う保険会社に加入していると、重複している補償に気づかないことも。どのような点に注意すれば無駄が省けるか、チェックポイントを解説します。
それiDeCoとNISAのほうがメリットありますよ−−FPが出会った勘違い事例3つ
貯金や保険を使った時との違い
iDeCoとNISAの認知度も高まり、ご自身でも活用しようという方が増えてきました。さまざまな活用法がありますが、用途が限定的だと勘違いしていて、「それ、iDeCoやNISAを使ったほうがメリットありますよ!」というケースも。ファイナンシャルプランナーの筆者が、実際に出会った事例を3つ、具体的な金額を交えて紹介します。
保険でよく聞く「先進医療特約」、保険なしで受けると費用はどの程度かかる?
可能性は低いが、該当したら大きな力に
「先進医療特約」は、最近の医療保険やがん保険に加入する際には、もれなくと言っていいほど付帯して提案されています。必ず入らなければいけないわけではありませんが、月額100円程度の保険料のため、万一のお守りとして付けている方がほとんどです。先進医療とは何か? 実際に先進医療を受けるひとはどの程度いるのか?など、必要性を考えてみます。
会社員とフリーランスの社会保険料はどう決まる? 仕組みと保険料を抑える方法を解説
フリーランスは支払い方で抑えることも
給与所得者であれば、毎月の給与から差し引かれて支払っている社会保険料。毎月の明細をみるたびに「結構引かれてるなあ・・・」と感じている人も多いのではないでしょうか。もちろん、社会保険料を払うことで、さまざまな給付を受けられるわけですが、少しでも抑える方法があるなら実践してみたいと思うでしょう。今回は社会保険料が決まる仕組みと、保険料を抑える方法についてご紹介します。
大学生活に潜むリスクを守る「共済保険」、加入したほうがよい? 保障内容を詳しく解説
重複保障に注意!
受験シーズンを迎えています。合格発表になると、待ったなしに入学準備をすすめなければなりません。大学入学でひとり暮らしを始めるお子さんをお持ちの親御さんにとっては、暮らしの様々なリスクは心配の種です。どのようなリスクに備えればいいのか考えてみます。
生命保険はどこで契約をするのが得? 気になる疑問と保険料を少しでも安くする方法をFPが解説
長期で差がつく支払い方法
「生命保険はどこで契約をするのがお得ですか?」と聞かれることがあります。じつは、生命保険の場合、同じ商品で同じ契約ならば、保険の営業員からでもネットからでも、どこで契約をしても保険料は同じなのです。保険料の割引をしてはいけないと、法律で決まっているからです。とはいっても、保険料がお得になる契約の仕方はあります。物価上昇が続いている2023年も物価上昇が続く見通しで、家計にとっては厳しい時代になってきています。少しでも保険料を安くする方法を解説していきましょう。
65歳から介護保険料が大幅増で驚きの事例も…介護保険の仕組みを解説
地域によって保険料に大きな差
65歳の誕生日を迎えると、健康保険証の様な紙の介護被保険者証が届きます。介護保険があることは認識しているものの、受けられる介護サービスや、支払わなければならない介護保険料について、くわしく知っているひとは多くないでしょう。65歳を境にサービスの内容も保険料の負担額も大きく変わります。老後のライフプランに影響を与える介護保険について検証します。