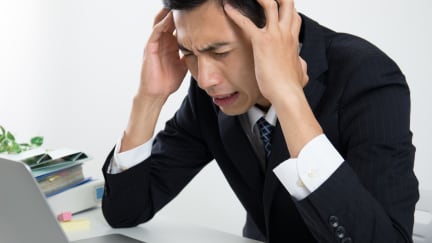生活
食事や買い物、通信、交通など、日々の生活全般のお金の話を紹介します。
薬味ソースで食べる「ぶりの唐揚げ」レシピ
冬の魚の代表格“ぶり”
冬の魚の代表格“ぶり”、この時期スーパーでもよく見かけます。ぶり大根、ぶりの照り焼きなど美味しい料理がたくさんありますが、今日は気分を変えて唐揚げにしてみませんか?ニラ、生姜、にんにくたっぷりの薬味ダレをかければ身体もポカポカ。外はからっと、中はふわっとした食感のぶりをたっぷり召し上がれ。
フリマアプリとキャッシュレス決済うまく使いこなすには?メルカリ、PayPayフリマ、ラクマを比較
お得な使い方や注意点
昨年の10月に消費増税があり、国がキャッシュレス決済を推すようになりました。実際に使っている人も多いのではないでしょうか。リアルなお店だけではなく、フリマアプリでもキャッシュレス決済が使えます。そこで今回の記事では、フリマとキャッシュレス決済についてお得な使い方や注意点を紹介していきます。
タイで給料18万円の食事情 、和食のランチや居酒屋にはどれだけ行ける?
現地料理だと一食180円
生活の大きな基本のひとつ「食」。海外で暮らすとなると、食事が心配になるものです。日本食はあるのか、現地の食事はおいしいのか、値段は、衛生面は……。しかしタイでは、日本と同様かそれ以上に、満ち足りた食生活を送ることができます。というのも、タイはいまや世界でも有数の「日本食が充実した国」なのです。
バッテリーの寿命はどれくらい?意外と知らない電動アシスト自転車の使い方
乗る際の注意点や、バッテリー充電でやってはいけないことも
最近街中で見かけることの増えた電動アシスト自転車、通称"電動自転車"。子どもの送迎や、荷物が増えるお買い物、長距離の通勤や移動などにとても便利ですよね。普段乗りこなしつつも、意外と知らない電動アシスト自転車のアレコレについて、「ここが進化していた!」や「乗る際の注意点」、「バッテリーの寿命や注意点」までお話しします。
源泉徴収票で何がわかる?押さえるべき1行からキホンの見方まで解説
自分の年収・所得・税額を確認しよう
年末か、年明け早々に勤め先から受け取る「給与所得の源泉徴収票」。1年間の給与に関する書類ということはわかっていても、数字の羅列で、なかなか見る気になれないかもしれません。今回は、細かいことはさておき、まずは「給与所得の源泉徴収票」のキホン、どこに何が書いてあるか、大枠をざっくり押さえていきましょう。
所得税・住民税はどうなる? 2020年から施行される税制改正のポイント
年収850万円以上の会社員は負担増に
2018年には配偶者控除、2019年10月には消費税率アップがありました。2020年は税金の計算にあたって差し引かれる「控除」が変わります。会社にお勤めの給与所得者なら年収850万円を超える方など、収入が多い方には負担増となります。一方、フリーランスや起業、在宅で仕事を請け負う方は、負担が減ることがあります。今回は、2020年の税制改正が家計にどのように影響するのかお話しします。
ダメだとわかっているのに…ストレスによる浪費が止まらない
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、母親を亡くした喪失感やストレスから、爆買いや暴飲暴食が止まらないという26歳の独身男性。ボーナス補填が続く生活に不安を感じているといいますが……。FPの氏家祥美氏がお答えします。26歳、独身です。夏に母親が亡くなったことや仕事のストレスもあって、爆買いや暴飲暴食が止まらず、食費や交際費などがかさんでいます。出費が激しく毎月赤字で、ボーナスで補填しています。このままではいけないと数年後の生活に不安を感じていますが、どうしたらいいのかわかりません。アドバイスよろしくお願いします。 <相談者プロフィール>・男性、26歳、未婚・職業:会社員・居住形態:賃貸(一人暮らし)・毎月の世帯の手取り金額:18万円・年間の手取りボーナス額:54万円・毎月の世帯の支出目安:20万円【支出の内訳】・住居費:5万円・食費:4万円・水道光熱費:2万円・教育費:なし・生命保険料:1万円・通信費:3万円・車両費:なし・その他:5万円(交際費、お小遣い含む)【資産状況】・毎月の
冷蔵庫にあるもので「春巻き」をつくろう
食卓の一皿にオススメ
人が集まることの多い季節。気のおける人たちと囲む食卓は至福以外の何物でもありませんね。そんな食卓の一皿にオススメなのが、春巻き。中の具材はお好きなもので。冷蔵庫の余り物でも構いません。火が通っているか心配することもなく、スティック状なので食べやすく、パーティーにはオススメな一皿ですよ。
2020年税制改正で扶養内パート妻の働き方はどうなる?
給与所得控除の引き下げと基礎控除の引き上げ
妻がパート扶養内で働いている人は、制度変更が行われるたびに不安に思われることでしょう。そこで今回は2020年税制改正で扶養に関わる変更点についてお伝えしたいと思います。
高額商品を売りつける”悪”の電話マニュアル、「トリセツ詐欺」の手口
数十倍の値段で仏像を購入させる
詐欺や悪徳業者を摘発すると、たいがい騙しのマニュアルが出てきます。これは、詐欺のターゲットになった人を騙すための取扱説明書ともいえます。電話では「どういう言葉で騙すのか」などが書かれています。今、取説(トリセツ)を使った騙しが跋扈しており、注意が必要です。今回は、悪徳商法の手口についてみていきます。
米国産牛肉はどれだけ安くなった? 「イオン」が関税引き下げで価格改定
人気の2品目が値下げに
1月1日から発効した日米貿易協定。日本は米国産の牛肉やワイン、チーズなど8,000億円規模の農産物に関して、関税の引き下げを実施しました。これを受けて、流通各社も販売価格の改定に踏み切り始めています。大手スーパーのイオンも、その中の1社。1月9日から、全国の約540店舗で米国産牛肉の販売価格を改定しています。今回の価格改定によって、牛肉の価格はどの程度、安くなったのでしょうか。価格改定に合わせて報道陣に公開された販売現場を取材しました。
発達障害の特性を強みとして活かす、1000回開催されたワークショップ
社会適応ではなく、社会活用を目指す
サービス業などの人間相手の産業が主流となった現代の日本では、発達障害と診断される人の数が増えています。発達障害の当事者であり、コミュニケーション力向上のためのワークショップを1000回以上開催してきた冠地情さんの初めての著書が今回発売されました。その本「発達障害の人の会話力がぐんぐん伸びる アイスブレイク&ワークショップ」(講談社)には、発達障害の特性を強みとして活かすための技法が詰まっています。
お金を貯めるためにすべきこと、今年のカギは「節税」と「備え」
ファイナンシャルプランナーに聞くお金の貯め方
いよいよ2020年の幕開けですね。今年の国内のビッグイベントといえば、東京オリンピックですが、海外にも目を向けると、アメリカ大統領選などもあり、国内外で世界経済に影響を及ぼしそうなイベントが目白押しです。また、国内では昨年からの消費税増税の影響もありそうです。そんな中、今年こそ、お金を貯めるぞ!と意気込んでいる方も少なくないことでしょう。今回は、2020年にお金を貯めるためにやるべきことについてお話します。キーワードは「節税」と「備え」です。
「目標があっても毎月赤字で貯められない」42歳シングルマザー
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、万が一に備えて生活費1年分を貯めたいという42歳シングルマザー。ですが家計は毎月赤字、ボーナスで補てんする日々だといいます。FPの渡邊裕介氏がお答えします。中2の子どもがいる、シングルマザーです。固定費にかかるのか、毎月赤字です。足りない分はボーナスで補てんしています。まずは、生活費1年分くらい貯蓄して万が一に備えたいと考えています。ただ、今の支出でどう貯めたらいいのかわかりません。家計が黒字になったら、つみたてNISAを始めたいですし、ゆくゆくは家を建てたいとも思っています。<相談者プロフィール>・女性、42歳、バツイチ・子ども1人:14歳(中2)・職業:会社員・居住形態:賃貸・毎月の手取り金額:24万円前後・年間の手取りボーナス額:70万円・毎月の世帯の支出目安:24万円【支出の内訳】・住居費:6.5万円・食費:4万円・水道光熱費:2.5万円・教育費:3.5万円・保険料:1.3万円・通信費:1.5万円・車両費:1万円・お小遣い:1.5万円・
夫亡き後、未成年の子どもがいるとマイホームを売却するのに時間がかかる理由
相続人の権利は未成年の子どもにも平等
不慮の事故で亡くなった夫。遺された妻は悲しみに暮れる暇もなく、ひとりで3人の子どもを養っていかなければなりません。妻は、夫が遺してくれたマイホームを売却する決心をしますが、マイホームの名義を亡くなった夫から相続人である妻に変えるのは簡単なことではありませんでした。なぜなら、未成年の子どもたちにも相続権があるからです。自分が亡くなった後に大切な家族が困らないように、子どもが生まれたら、自分名義の住宅を購入をしたら、遺言書の作成をしておいた方がいいといいます。
タイに移住した日本人、銀行口座やクレジットカードはどう扱っている?
タイ暮らしのマネー管理・基礎編
タイに十年以上定住した経験のある筆者が、タイ移住へのステップを紹介する当連載、今回のテーマは「移住の資金」についてです。タイに暮らす7万人超の日本人はどうやってお金を管理し、使っているのでしょうか。口座はどうしているのでしょうか。皆さんの実例から見ていきます。
情報商材の“あり得ない”儲け話、どんな人が引っかかりやすい?
騙されやすいタイミングや時間帯がある
「1カ月で〇百万・〇千万稼げます」……。投資や副業などで儲かるノウハウやシステムを教えると称し、高額のお金を要求する情報商材のトラブルがネット上にあふれています。業者はFXや仮想通貨、転売などと手を変え品を変え、甘い言葉で消費者を誘惑してきます。しかしうたい文句ほど儲からないばかりか、多数の被害者を出して集団訴訟が起きたり、詐欺などの悪質な刑事事件に発展したりするケースも少なくありません。ただ、こういった一見荒唐無稽な儲け話に対しては、「私なら絶対引っかからない」と思う人が実際は大半ではないでしょうか。危険なネット上の情報商材の「引っ掛けるメカニズム」を分析した前編に続き、今回迫るのは「どんな人がどんな心理状態で商材のワナに引っかかるのか」、加えて「引っかからない対策」。情報商材のトラブルに詳しいあまた法律事務所(東京・文京)の豊川祐行代表弁護士に話を聞きました。
年始めに「固定費」を見直して、貯まる人になろう!
お金の見直し計画
ほんの少しゆとりができる年明け。実は、自分のお金まわりを確認する大チャンスです。特に、「固定費」といって毎月一定額かかるお金について確認すれば、気づかなかった無駄を減らすことにつながり、その分お金が貯まるようになるのです。今回は、年始めにぜひ取り組みたい、「固定費」の確認方法についてお伝えします。