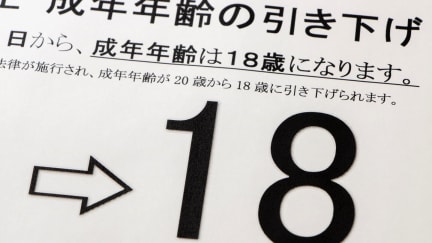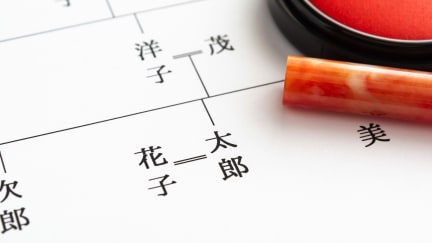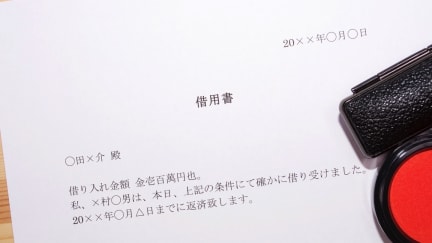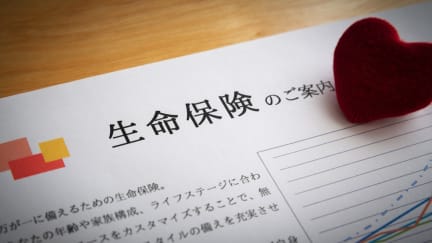4月からの成年年齢の引き下げが相続に与える影響は?相続診断士が解説
押さえておきたい7つの影響
2022年4月から、成年の年齢が20歳から18歳に引き下げられました。社会生活における様々な場面への影響が取り沙汰されていますが、相続の場面でも多くの影響があるのです。7つの影響を相続診断士が解説します。
養子縁組で相続が複雑になってしまうことも?2つの事例でプロが解説
養子縁組をする前に必ず理解しておきたい法律と相続
血縁関係がない親子関係という家族の形も少なからずあります。そんな場合、「養子縁組」を行うことで、様々な相続上のメリットがありますが、思わぬ法律の落とし穴もあるのです。今回は、相続対策として養子縁組という選択肢をとった場合に気をつけてほしい2つの事例を紹介します。
疎遠だった父親が亡くなり手続きに困る娘。遺言の有無を確認する方法とは?
遺言書の保管方法と探し方
遺言書の保管の仕方を指南する情報は増えてきましたが、意外と知られていないのが「遺言書の探し方」です。自筆証書遺言と公正証書遺言、それぞれどのような方法があるのでしょうか。
自分に万が一の時、これを書いておけば家族も安心。「エンディングノート」の使い方
終活のプロが教える必須の10項目
「終活」が浸透し、存在が知られるようになった「エンディングノート」。何を書けばいいのか、どのように活用すれば効果を発揮できるのでしょうか? 終活のプロが解説します。
亡くなった父に認知した子がいることが相続で発覚!戸籍の落とし穴とは?
戸籍の編製や改製に注意
親が亡くなった時、相続の手続きをするためには戸籍を取り寄せて相続人を確定することが必要です。この時に初めて父親に認知した子がいたということを知るケースがあります。認知した子がいることを知らずに来てしまう戸籍の落とし穴とは……。
家族が認知症になる前に理解したい「成年後見制度」のしくみ。メリット・デメリットは?
「法定後見制度」と「任意後見制度」の違いも理解しよう
介護などの場面でたまに耳にする「成年後見制度」という言葉。判断力のない人に代わって代理人が契約などをできるようにできるみたいだけど、詳しいことはよく知らない……という人は多いのではないでしょうか。この制度では何ができて何ができないのか。利用することによるメリット、デメリットは? 行政書士が解説します。
生命保険金の受取人を孫にしたことで思わぬ相続税が発生してしまう!?
勘違いしやすい生命保険と生前贈与の注意点
孫ができれば、あの手この手で財産を残してあげたいと思うもの。生前贈与を利用してなるべく節税したいところですが、制度を知らないとそれが裏目に出てしまう場合も。今回は、孫を生命保険金の受取人にしてしまったために、生前贈与した分まで税金がかかる結果になってしまったケースから、間違いやすいポイントを紹介します。
認知症で親族が預金を引き出せなくなる問題。新指針でルールが緩和されるかも?
成年後見人がいなくても預金が引き出せるケースも
認知症になると、当事者の親族であっても預金が引き出せなくなってしまうことが問題となっています。このルールが、2020年に出された新指針によって緩和される可能性が出てきました。現状の制度と実際のポイントを解説します。
知らないと相続手続きがこじれることも!遺言書を書く前に確認すべき2つのこと
「相続人」と「財産状況」を知る重要性
自分にもしものことがあったときのために準備しておきたい遺言書。しかし、書き始める前に、確認しておくべきことが2つあります。もし、確認しないまま不完全な遺言書を作ってしまった場合、かえって相続争いが起こったり、手続きが煩雑になってしまったりすることもあるのです。
せっかく用意した遺言書が無駄に!?知らないと無効になる書き方のルール
知っておきたい5つのポイント
遺言書は、自分が亡くなった時、大切な誰かに想いを伝え財産を引き継いでもらうために重要なものです。遺言書を法律上で有効なものとするためには、いくつかの注意点があります。これを知らないと、せっかくの遺言書が無効になってしまうのです。
親が認知症になった時に心強い制度「家族信託」ってどんなもの?
いざという時に困る「お金」と「家」に備える
親が認知症になった時に困るのが、銀行口座の凍結により生活費が引き出せなくなったり、不動産売買ができなくなってしまうことなどです。そんな法律の落とし穴に備えるために今注目されているのが、「家族信託」です。どんな制度なのでしょうか? 相続の専門家集団「アクセス相続センター」の税理士が解説します。
中小企業経営者に「もしも」が起こる前に対策しておきたい「お金と人」の問題
事業継承が進まない理由と解決のヒント
中小企業の経営者の高齢化が進んでいます。経営者に「もしも」があった時にどんな問題が起こるのでしょうか。また、事業継承の際にはどんな問題があり、どんな対策が有効なのでしょうか? 相続に精通する専門家集団、アクセス相続センターの相続診断士が解説します。
障がいを持つ子の相続に潜むリスクとは?「親なきあと」に備えるために
「この子のために」が裏目になることも
障がいのある子を持つ親にとって悩ましいのは「親なきあと」のこと。相続対策にどのような準備が必要なのでしょうか。
生前贈与による相続税対策ができなくなる!?今からできる対策は?
税制改正で生前贈与の課税システムが変わる
昨年末の「税制改正大綱」の発表で、生前贈与の場合でも相続と同様に課税されるように、税制改正を積極的に進めていく方針が示されました。詳細やタイミングはまだ不明ですが、今から対策できることはあるのでしょうか。
おひとりさま・一人暮らしの終活。どんな備えが必要?
認知症や孤独死への備えや葬儀・相続で困らないために
自分の意思にかかわらず、誰でも「おひとりさま」になる可能性があります。「おひとりさま」になったとき、いずれ直面する課題が「終活」です。認知症や孤独死、自分が亡くなったあとの葬儀や相続で周りの人が困らないために、どのような備えが必要なのでしょうか。
「内縁の妻に家を残したい」遺言でカバーできない不安を解決する「死因贈与契約」
「契約」とは異なる遺言の「弱点」
遺言は、遺言する人の気が変われば書き換えることができます。一方で、受け取るほうにも受け取らない自由があります。つまり、確実に意志が実行されるわけではありません。このような弱点をカバーするために活用を検討するべき「死因贈与契約」をご存知でしょうか?
子どもの「相続放棄」で親の借金が親族にスライドしてしまう!?
安易に相続放棄してはいけない理由とトラブル回避の知恵
「相続放棄」と聞いて、皆さんは何を連想されるでしょうか? 相続放棄を検討する理由としては、大きく2つが考えられます。1)「被相続人が残した借金の支払から逃れるため」2)「相続財産を引き継ぎたくない」今回は、相続放棄することによって、どのような問題が起こるのか、またトラブルにならないための知識を解説します。
受取人の選択を誤ると悲劇!生命保険金を遺産争いの火種にしないために
生命保険は「お金の遺言」。うまい活用方法とは
現在、生命保険の加入率は男女ともに約8割。年齢層によっては約9割にもなります。しかし、生命保険と密接に関係するはずである相続の相談をしていると、保険の内容を把握していない方も多くいらっしゃいます。また、内容は把握していたが、相続における知識が少なかったがために、ご自身の想いや願いを叶えることができないこともあります。今回は、そんな事例をご紹介します。