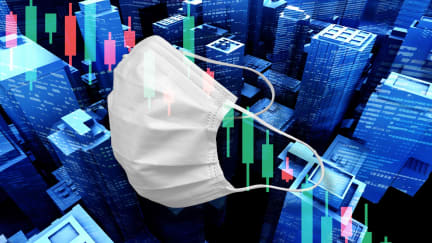辞意表明で”支持率爆上げ”、次期政権で株価は”大幅プラス”になるのか
内閣支持率と株価の関連性
安倍首相の電撃辞意表明により、内閣支持率が異例の急上昇を示しています。最新のJNNにおける世論調査によれば、9月時点の安倍政権の内閣支持率は62.4%となりました。コロナ禍において持病が悪化する中、職務を継続していたという辞任理由が明らかとなった後の世論調査ということもあり、前月比では+27.0%と大幅な上昇を記録しています。政権末期は通常、徐々に国民の支持を失い、最終的には低い支持率での首相交代が行われるのがこれまでの傾向でした。そして、新しい首相に代替わりするタイミングで、再び高い内閣支持率となる、いわゆる「ハネムーン効果」が発生していました。このハネムーン効果に近い現象は、金融市場において「ご祝儀相場」と呼ばれる現象として現れます。首相交代のタイミングで、「一時的に株価が上昇しやすくなる」という経験則です。アベノミクスを承継する姿勢を見せる菅氏が次期首相として半ば確実視されていることもあり、次期政権が高い支持率で幕引きを迎えた安倍政権を承継する形となれば、足元の支持率が短期で大幅に下落する環境とは言いがたいかもしれません。このように考えていくと、次期政権のスタート時にはハネムーン
野菜高騰がデリバリーの追い風に!?外食産業で好調な銘柄・厳しい銘柄
業態によって明暗分かれる
5月25日に緊急事態宣言が解除され、落ち着きが見えたかのように思えた新型コロナウイルスの感染拡大ですが、7月以降は第2波が到来し、消費の回復にもブレーキがかかっています。引き続き外出を控える動きが目立つ中、人々の食生活も外食が減少し自炊やデリバリーを利用する機会が増えてきています。新型コロナウイルスを受けた食生活の変化を追いながら、外食産業の注目銘柄についても見ていきたいと思います。
コロナ禍で「SNSを最も賑わせた投資銘柄」ランキング
1位は普段日の目を見ないあの銘柄?
コロナ禍では、オンラインミーティングツールを提供するIT企業等が思わぬ恩恵を受けた反面、旅行業界や航空業界が大きな打撃を受けるなど、セクターによって明暗が別れる展開となりました。各国の金融緩和の甲斐もあって、日経平均株価はコロナ禍前とほぼ同水準の22,000円代まで戻しています。しかし、新型コロナウイルスの第二波が再び日本経済に悪影響をもたらす懸念もあり、油断できない状況が継続しているといえるでしょう。業績見通しを非開示とする企業も出現するほど不確実性の高い相場環境では、第三者の投資家目線も投資判断のひと要素として取り入れる余地があるでしょう。
コロナ禍でも「夏枯れ」到来、今年前半の相場を振り返る
8月以降も個別銘柄は荒い値動きが続く?
新型コロナウイルスの大流行により、株式市場は年初から値動きの激しい動きが続きました。日経平均株価は3月に16,000円台をつけるなど大暴落しましたが、その後、世界的な大規模金融緩和を背景に急速に回復。一時23,000円台を付けるまでに値を戻し、現在は22,500円付近でレンジ相場を形成しています。個別銘柄を見ると、ソニー(6758)、ソフトバンクグループ(9984)が約20年ぶりの高値を更新するなど、日本を代表する大型株にも資金の流入が見られています。この相場の勢いは夏以降も続くのでしょうか?
“ファミマ完全子会社化”が伊藤忠を真の総合商社トップにする?
コロナ禍で「非資源ビジネス」が光った
コンビニ業界と総合商社がここ数年で連携を強化しています。日本を代表する「五大商社」の一角である伊藤忠商事は8日、子会社であったファミリーマートに対し株式の公開買い付け(TOB)を実施しました。伊藤忠は総額5808.81億円でファミリーマートを完全子会社化し、同社は上場廃止となる予定です。近年では、総合商社とコンビニをはじめとした小売企業の連携強化の例が目立ちますが、これによってどのような効果が得られるのでしょうか。
旅行代の半額補助だけじゃない「Go to Travelキャンペーン」活用法
投資の面でもチャンス?
新型コロナウイルスの世界的流行はとどまることを知らず、世界の感染者は1,000万人を突破しました。日本でも感染第2波が警戒されているものの、世界的にみると感染の程度は緩やかであり、少しずつ日常を取り戻しています。そんな中、さらなる消費の回復を後押しするべく、8月から政府主導の観光支援策「Go to Travelキャンペーン」が実施されます。このキャンペーンを投資で活用するにはどうすればよいでしょうか?
上場企業の業績予想「コロナのせいで未定」は言い訳になるのか
市場は「減益」以上に厳しく評価
東京証券取引所が6月上旬にまとめた「2020年3月期決算発表状況」によれば、株式上場している3月期決算会社の約6割に相当する1,216社が、コロナ禍を理由として業績予想を「未定」または「非開示」としました。特に、外出自粛の影響が大きかった「陸運業」や、海外需要の低減による業績への悪影響が懸念される「輸送用機器」が業績予想を明らかにしない傾向があるようです。一方で、医薬品や食料品といった需要の高まりが一部で見られた業界については業績予想を積極的に開示する傾向があることもわかりました。たしかに、今後のコロナ禍による影響がどれほど長期化するか明らかでない以上、予想の精度が低下することはやむを得ないといえるでしょう。
クレカ購買データで見る消費回復「早い業種」「遅い業種」
コロナで変わる消費スタイル
日経平均株価は一時1万6,000円台をつけたものの、現在は2万2,000円台に回復するなど、新型コロナウイルスの影響からの急速な切り返しを見せています。一方で実際の経済状況は深刻さが日に日に増しています。感染第2波への警戒が続く中、我々は徐々にコロナ前の生活へと戻っていくことになりますが、完全に元に戻るには時間がかかるでしょう。今回は4月以降の消費動向を踏まえて今後の消費動向を検討していきます。
「オンライン飲み会」需要で酒屋が人気?クレカ購買データでわかるコロナ消費
コロナ禍で変わった消費者の行動
5月17日現在、日本における新型コロナの新規感染者数はピーク時からおよそ35分の1程度の20人となりました。落ち着きを取り戻しつつある感染者数の動向を受けて、政府は本日21日にも緊急事態宣言の解除を全国に拡大するかの判断を行うとみられています。コロナ禍においては、旅館やフィットネスジムなどが大きな打撃を受けた反面、ECやオンラインコンテンツを取り扱う企業が株価を伸ばす場面もみられました。それでは、コロナ禍で意外な恩恵や打撃を受けた業種はあるのでしょうか。今回は、4月後半以降のクレジットカードの購買ビッグデータ(現金含めた総支出の推計値)を用いて、4月7日の緊急事態宣言以降に私たちの消費行動がどのような変化をたどったのかを確認していきたいと思います。
コロナ相場の「勝ち組」「負け組」はどの業種?
伸びそうなセクターを探す
新型コロナウイルスの世界的流行は止まることを知らず、世界の感染者は250万人を突破しました。また、WTIの原油先物が歴史的な大暴落を続けるなど、世界的には不安定な状況が続いています。この混乱を先取りする形で世界の株式市場も2月の後半から急激な調整を強いられ、3月中旬に日経平均株価は高値から一時8,000円を超える暴落を記録しました。しかし、3月23日からの3営業日で約3,000円の上昇を記録するなど急激なリバウンドをみせ、現在は1万9,000円台に位置しています。この期間のセクター別の騰落率はどうだったのでしょうか。東証業種別株価指数(33業種)の3月18日から4月17日までの騰落率から、セクター別の強弱を見ていこうと思います。
タピオカブームはやっぱり新型コロナによる「株価暴落の前兆」だったのか
不思議な一致を読み解く
「タピオカブームは株価暴落の前兆ではないか」――。昨年6月、このような書き出しで始まる記事「タピオカブームは本当に『株価暴落の前兆』なのか」で取り上げた「タピオカブームと株価の暴落」が当てはまる形となってしまいました。2019年は「第3次タピオカブーム」ともよばれ、SNSで映えるタピオカドリンクが流行した年でもあります。たとえば、「業務スーパー」で冷凍タピオカを取り扱っていた神戸物産はブームの助けもあって、1年前の株価2,112円から、一時は2.17倍の4,600円まで値を伸ばすなど、思わぬ快進撃もみられました。それでは、第3次タピオカブームが相場にもたらした顛末はどのようなものだったのでしょうか。
金融緩和が“効かない”?コロナ暴落で株を買うタイミングはいつなのか
財政出動と原油動向がカギ?
世界的に流行が広がっている新型コロナウイルスの影響で、世界の株式市場は混乱の渦中にあります。2月中旬まで高値圏に位置していた世界各国の株価指数は、軒並み30%程度の下落となりました。今回のコロナショックによる株価の下落は「世界的な感染拡大懸念」「原油価格暴落」「WHOによるパンデミック宣言」「欧米での感染爆発」という4つの局面に分けられます。現在は特に「世界各国で渡航制限や外出禁止令」など、実体経済が停滞するという副作用の伴う対応を各国が余儀無くされた結果、景気判断の見直しが相次いでいます。市場関係者の間では、リセッション入りを先取りした相場展開とみる者もいるようです。
相場急落時こそ考えたい、「積立投資」に潜む大きな落とし穴
長期投資との上手な付き合い方
新型コロナウィルスの感染拡大により、世界同時株安が進行しています。今年の2月には2万3,995円の高値をつけた日経平均株価。達成すれば3度目となる2万4,000円の大台突破が期待されていましたが、それは今や遠い目標となってしまいました。感染拡大に伴うサプライチェーンの停滞懸念などを背景に、日経平均は3月10日に一時1万9,000円割れとなるなど、パニックとなる場面もありました。11日には反発しましたが、それでもまだ2万円には届かない水準です。日銀が2日に買い入れたとされる1,000億円以上のETF(上場投資信託)は、すでに含み損という厳しい段階に入っています。そんな状況で考えたいのが、積立投資とのうまい付き合い方です。金融機関は「暴落した時こそチャンス!」というセールストークをよく使いますが、はたして本当にそうでしょうか。
日経平均の下落は1000円安で収まる? 日本経済が直面する不都合な真実
コロナショックの影響度はいかほどか
1月17日に2万4,115円の高値をつけた日経平均株価。1月末から世界的に流行している新型コロナウイルスの影響を受け、2月初旬に2万3,000円を割り込む場面もありましたが、大きく崩れることなく2万3,000円台で推移していました。しかし2月24日は世界的な株安となり、3連休明けの25日の日本市場も一時1,000円安と大幅下落。翌26日も179円安となり、2日間で約960円も下落しました。これからの株価はどう動いていくのでしょうか。新型コロナウイルスの影響と現在の日本が置かれている景気情勢からみていこうと思います。
時価総額400億超のオリガミをタダ同然で買収、メルカリは本当にトクしたのか
タダより高いものはない?
1月23日、QRコード決済の老舗であるOrigamiが、フリマアプリ大手のメルカリの傘下に入ることがわかりました。for Startups,inc.が昨年12月に公表した情報によれば、Origamiは国内スタートアップの推定時価総額ランキングのうち16位にランクインし、その額は417億円にもなっていました。出資者によるOrigamiの価値は、スタートアップ界隈で例えれば「FiNCより下、ウェルスナビより上」という位置付けだったようです。しかし、この時価総額ランキング発表からわずか1ヵ月半後、Origamiはメルカリに“タダ同然”で買収されることになるのです。買収額はメディアによってゼロ円であったり、数百万円であったりとバラツキがあるものの、とても低い値段である点ではおおむね一致しています。つい最近まで400億円以上の時価総額があったOrigamiを、なぜメルカリは“タダ同然”で買収できたのでしょうか。
1年で50%上昇、日本の投資家は「ナスダック」にどう向き合うべきか
買うとしても、どういう買い方がベスト?
短期的な下落を伴いながら高値を更新し続けた、2019年の米国株式市場。2020年に入っても勢いは衰えず、NYダウ平均は3万ドル、ナスダック総合指数は1万ポイントをうかがう流れとなっています。中でも、ハイテク銘柄で構成されるナスダック総合指数は、米国を代表する株価指数であるNYダウやS&P500と比べても強さが際立っており、2019年1月につけた直近安値に比べて約50%の上昇となっています。停滞感の漂う日本株に比べて、米国株、特にナスダックはなぜここまで力強い値動きとなっているのでしょうか。日本の投資家が考えておくべき、ナスダックとの向き合い方を検討してみます。
イラン情勢を機に考えたい、投資における「地政学リスク」の備え方
“戦争リスク”の特徴と対策
大規模な軍事衝突の可能性は低いといわれているものの、ウクライナ機撃墜による反政府デモの勃発など、いまだ火種がくすぶっているイラン情勢。株式などのリスク資産で資産運用している人は、これを機に、軍事衝突のリスクに強い資産構成について確認し、いざという時のための備えをしておくことが大切です。そこで今回は、戦争や軍事衝突の懸念が生じた際にニュースでよく言及される、「地政学リスク」に強い資産構成について検討していきたいと思います。
「人の行く裏に道あり花の山」だった昨年の株式相場、2020年はどうなる?
相場格言と日経平均を徹底比較
2020年の株式市場は本日1月6日に大発会を迎えます。昨年は大発会から一時700円安を記録するなど、大荒れのスタートになりました。しかし、年間を通じた最安値は、この大発会の1万9,241円でした。2019年の日経平均株価は米中貿易摩擦や各国の金融政策に大きく反応し、値幅が上下約4,500円と変動が大きく、難しい相場となりました。しかし、9月以降は上げ基調となり、12月には一時2万4,000円を突破。終わってみれば、バブル崩壊以来の高値圏に位置するという結果となりました。今回は、そんな2019年の相場を、先人の経験則である相場格言で振り返り、2020年にはどうなるかを展望していきたいと思います