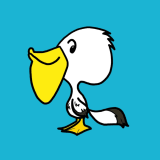ビジネス
経済、投資の最新情報、仕事の給与や稼げる副業情報などを紹介します。
2030年に向けて起こるメガトレンド−−予想される新たな巨大市場とは?
MBA 2030年の基礎知識(1)
現代のビジネスパーソンにとってITリテラシーが必須となったように、求められるスキルや知識は時代によって変わっていきます。この先の時代に向け、どのようなことを身につけていくべきなのでしょうか?ビジネススクール「グロービス」による著書『MBA 2030年の基礎知識100』(PHP研究所)より、一部を抜粋・編集して2030年に向けて起こるメガトレンドについて解説します。
インボイス制度によって仕事は減る? 税理士・小島孝子氏×お笑い芸人・かじがや卓哉氏に聞く「インボイスが始まった未来」
大切なのはルールの模索
個人事業主だけでなく企業の対応も問われるインボイス制度。税理士として企業の顧問や実務家へのセミナーなどを手掛ける小島孝子氏と、お笑い芸人であり税理士として事務所を開業している個人事業主の一面も持つかじがや卓哉氏に、実際にインボイス制度がスタートした後の業務負担などの疑問点をお聞きしました。インボイス制度はなぜ生まれたのか、個人事業主はどう対応するべきなのか、3本連載でお届けします。Vol.1:インボイス制度はなぜ生まれた? どんなひとが影響を受ける? 税理士・小島孝子氏×お笑い芸人・かじがや卓哉氏に聞く2022年以降の消費税の姿Vol.3:課税事業者になるべきか、免税事業者のままか…税理士・小島孝子氏×お笑い芸人・かじがや卓哉氏に聞く「今後取るべきインボイス制度対策」小島孝子神奈川県生まれ、税理士。ミライコンサル株式会社代表取締役。1999 年早稲田大学社会科学部卒、2019 年青山学院大学会計プロフェッション研究科修了。大学在学中から地元会計事務所に勤務した後、都内税理士法人、大手税理士受験対策校講師、一般経理職に従事したのち2010 年に小島孝子税理士事務所を設立。税務や経理業務に
インボイス制度はなぜ生まれた? どんなひとが影響を受ける? 税理士・小島孝子氏×お笑い芸人・かじがや卓哉氏に聞く2023年以降の消費税の姿
そもそもは払うべき税金です
個人事業主だけでなく企業の対応も問われるインボイス制度。税理士として企業の顧問や実務家へのセミナーなどを手掛ける小島孝子氏と、お笑い芸人であり税理士として事務所を開業している個人事業主の一面も持つかじがや卓哉氏に、2023年10月1日の導入開始に向けて、正しい知識や心構えについて伺いました。インボイスがスタートしたらどうなるのか、個人事業主はどう対応するべきなのか、3本連載でお届けします。Vol.2:インボイス制度によって仕事は減る? 税理士・小島孝子氏×お笑い芸人・かじがや卓哉氏に聞く「インボイスが始まった未来」Vol.3:課税事業者になるべきか、免税事業者のままか…税理士・小島孝子氏×お笑い芸人・かじがや卓哉氏に聞く「今後取るべきインボイス制度対策」小島孝子神奈川県生まれ、税理士。ミライコンサル株式会社代表取締役。1999 年早稲田大学社会科学部卒、2019 年青山学院大学会計プロフェッション研究科修了。大学在学中から地元会計事務所に勤務した後、都内税理士法人、大手税理士受験対策校講師、一般経理職に従事したのち2010 年に小島孝子税理士事務所を設立。税務や経理業務に関する執筆やセ
サッカーワールドカップの関連銘柄、日本に代わりFIFAスポンサー企業が増加傾向の国とは
日本企業の関連銘柄も
11月1日(火)に、11月20日(日)~12月18日(日)の日程で中東のカタールで開催されるサッカーのFIFAワールドカップ(W杯)カタール大会の日本代表メンバーが発表されました。32カ国が出場する今大会は新型コロナの影響もあり、代表メンバーも通常の23名から3名多い26名が選出されました。大方の予想通りの選出となったものの、これまで日本代表のFWとして活躍された大迫勇也選手や前回大会で大活躍された原口元気選手が落選となりました。過去の選出においても三浦知良選手や中村俊輔選手が代表から落選するなど、非情な決断が行われました。何はともあれ、選出された日本代表のメンバーには過去最高の成績が残せるよう応援しています。
ホテル宿泊無料カードも!年300以上株主優待を取得するペリカンが11月に絶対に取得したい銘柄3選
「隠れ優待」をもらう条件とは?
株主優待制度は日本独特の制度と言うことで、外国人投資家や機関投資家から公平性の観点から批判もあるものの個人株主が多い企業は廃止するどころか拡充する企業も少なくありません。さて、11月は権利日を迎える実施企業数が少ない月ですが、その中でもキラリと光る、筆者が絶対に取得したい株主優待を紹介します!
円安が「日銀の金融緩和のせい」は本当なのか?アナリストが指摘する論理的な矛盾
金融緩和と為替介入の関係性
10月28日(金)、日銀の金融政策決定会合で金融緩和の継続が決定され、その後、黒田日銀総裁の記者会見が始まると、それまで146円半ばで推移していた米ドル/円は米ドル高・円安へ大きく動き出しました。これは、最近の黒田日銀総裁会見後の「お決まりパターン」のようになっていますが、実は「間違う」リスクがあるということを、今回は説明したいと思います。
S&P 500、知っておきたい構成銘柄と注意点−−円安の資産防衛手段になるのか
バフェットも魅力があると考えている!?
S&P 500に関連する投資信託やETFに投資されている方、または投資を検討されている方は、日本にも多くいると思います。ではS&P 500が、どのような指数なのかご存知でしょうか?アメリカの500銘柄に分散投資している……というくらいでしたら、もう少し知っておくと投資の役に立つかもしれません。
「紹介キャンペーン」は本当に有効なのか?ファンづくりに有効な手段とは
売れ続ける秘訣(3)
顧客がファンになり、新たな顧客を紹介してくれるのは営業にとって理想的な状態といえますが、どうすれば実現していけるのでしょうか?そこで、営業コンサルタント・和田裕美( @wadahiromi )氏の著書『ファンに愛され、売れ続ける秘訣』(かんき出版)より、一部を抜粋・編集してファンづくりのテクニックについて解説します。
プレゼン資料に他社比較が不要になる−−中長期的な関係をつくる方法とは
売れ続ける秘訣(2)
近年の営業スタイルにおいて、新規顧客の開拓を優先するのではなく、既存顧客を大切にする=ファンをつくることで中長期的な関係性を築いていく「ファンベース」という考え方が注目されています。そこで、営業コンサルタント・和田裕美( @wadahiromi )氏の著書『ファンに愛され、売れ続ける秘訣』(かんき出版)より、一部を抜粋・編集してファンづくりに必要なことについて解説します。
新規顧客の開拓は非効率?「買ってもらってからが始まり」の営業戦略とは
売れ続ける秘訣(1)
少子高齢化でお客様は減り、さらに物価高で財布のひもは固くなる……消費の傾向が大きく変わっる中、営業活動を成果につなげるには、どうすればよいのでしょうか?そこで、営業コンサルタント・和田裕美( @wadahiromi )氏の著書『ファンに愛され、売れ続ける秘訣』(かんき出版)より、一部を抜粋・編集して営業スタイルの変化について解説します。
株主優待が目的の銘柄はNG?一般NISAで買うべきなのはどんな銘柄なのか
ロールオーバーすべき人は?
秋といえば、紅葉・読書・美味しい食べ物……色々ありますが、私にとっては株主優待の季節です。ピンとこない? お得な上に楽しいのに知らないなんて、なんて……嘆かわしい!今回もお笑い芸人で本当の税理士である税理士りーなが、少し知るだけで簡単にできる、NISAや投資を楽しむコツを分かりやすく解説します。
銀行も対応に追われるデジタル給与払い解禁、注目される「資金移動業者」とは?
導入のきっかけは2018年
労働者にとって給料日は少し特別な日だと思います。ほとんどの方が銀行振込による給与の受け取りをしていらっしゃると思いますが、今後はその受け取り方が少し変化していきそうな気配も感じます。
投資総額4億円の不動産投資家が明かす、物件を購入する前に考えるべき4つのポイント
家賃保証・サブリースはあてにしない?
もふもふ不動産のもふです。第1回は不動産投資とは投資ではなく事業であること、第2回はまず勉強するべきことを解説しました。今回は、不動産投資で失敗しないように、初心者が騙されやすい注意点について解説します。不動産投資は失敗すると取り返しがつかないことが多いです。これまでに、多くの失敗事例や、最悪のケースですと自己破産になってしまったケースなども見てきました……。私は2018年からメディアやYouTubeを通じてずっと注意喚起を行っていますが、詐欺に引っかからずに済んだというお声もよくいただきます。失敗しないためにも、ぜひ最後までお付き合いください。
リクルート、日立、ヤマダ電機が実施する「自社株買い」が買い材料になるのはなぜか?
2022年に過去最高を更新した背景とは
10月17日(月)にリクルートHD(6098)が1,500億円を上限に自社株買いを実施すると発表しました。2022年は、上場企業の自社株買いが急激に増えているのです。背景として株主還元強化の一環として、自社株買いをしている模様です。2022年9月末時点で自社株買いの実施企業数は、過去最高だった2019年の843社をすでに超えており、まだ3ヵ月を残していますが実施額も6兆6,245億円超と過去最高を更新しています。実施する企業数も1社あたりの金額も増えている状況です。2022年の市場のテーマの一つ言っていい注目ワードの自社株買いについて、「自社株買いを実施すると発表しており買い材料となった」とニュースで言われるのはなぜなのか、メリットデメリットや企業動向などをお伝えします。
ユニクロやドトールが業績好調も…小売企業の決算速報から見る、コロナ禍から復活を遂げた企業、苦戦する企業
小売業が好調な理由
世界的に株価はなんともスッキリしない値動きが続いています。10月21日時点で米国のダウ平均は31,082ドル、日経平均は26,890円となっていますがこれらは昨年末と比べてそれぞれ15%、7%程度値下がりしています。
ユニクロ、NETFLIX、マクドナルド−−創業者に共通する「お金を増やす思考法」とは
お金を増やす思考法(3)
世界の大富豪はどんな哲学を持ち、その考え方や生き方に共通点はあるのでしょうか?ジャーナリスト・桑原晃弥 氏の著書『世界の大富豪から学ぶ、お金を増やす思考法』(ぱる出版)より、一部を抜粋・編集して似鳥昭雄、ジェシー・リバモア、レイ・クロック、ジョン・ポールソン、柳井正、リード・ヘイスティングスについて紹介します。
孫正義とスティーブ・ジョブズの共通点「自分の得意なことに集中する」
お金を増やす思考法(2)
世界の大富豪はどんな哲学を持ち、その考え方や生き方に共通点はあるのでしょうか?ジャーナリスト・桑原晃弥 氏の著書『世界の大富豪から学ぶ、お金を増やす思考法』(ぱる出版)より、一部を抜粋・編集して孫正義、J・K・ローリング、スティーブ・ジョブズ、マーク・ザッカーバーグ、ピーター・リンチについて紹介します。
投資が注目されるいまだからこそ増える「資産運用詐欺」。若い人の被害相談事例が増えている原因
資産運用詐欺から自分の資産を守る法(1)
投資、資産形成が注目される時には、必ずといって良いほど「資産運用詐欺」が増えます。たとえば1980年代のバブル経済。NTT株の上場を機に投資ブームが起こり、「財テク」などと称して、個人マネーが株式市場に流れ込みました。この時、「投資ジャーナル事件」や「豊田商事事件」が社会問題になりました。恐らく今、50~60代の方は記憶にあるでしょう。