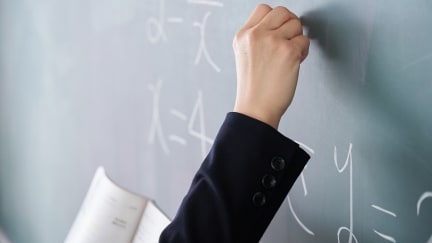高校数学を楽しいと思える人に共通する2つの考え方
「計算力」だけでは理解しきれない数学の世界
中学までは数学が得意だったはずなのに、高校に入った途端についていけなくなった……そんな経験を持つ人は少なくありません。『そういうことだったのか!高校数学』の著者であり、Z会進学教室の数学講師も務める石原泉先生は、高校数学を理解するには「論理力」と「読解力」が必要だといいます。高校数学の苦手克服のコツをお聞きしました。
テレアポ営業上級者直伝「責任者に必ずたどり着く簡単テクニック」
営業でテレアポの壁を突破するには?
テレアポ営業で責任者や決裁者にたどり着くまでにはいくつか壁があります。『テレアポ&リモート営業の基本』の著者でコンサルタントの伊庭正康さんが、壁を突破して成約につなげる誰でもできる簡単なテクニックを紹介します。
ビジネスメールに使える便利な表現6選
汎用性の高い使えるフレーズ
「文章を書くことがストレスです」「文章を書くことが苦手で……」「文章を書くのに時間がかかります」そんな「文章アレルギー」の人は多いのではないでしょうか? しかし、文章を書けるかどうかは、仕事の成果や周囲の評価に大きく関わります。『そもそも文章ってどう書けばいいんですか?』を著書にもつ、山口拓朗さんが、これまでライターとして3000件以上の取材・インタビューを経験した中から導き出した、「書くことが嫌い」を「書くことが好き」へと変える、文章作成のコツを教えてもらいます。
“自己評価が高い人”ほど陥りがちな「心の罠」
ビジネスで遠回り・空回りしないための原理原則
物事を成り立たせる根本的な決まりである「原理原則」。時代が変わっても変わらないもの。流行に振り回されずに光り続けるもの。解釈はいろいろありますが、この漢字4文字の意味するものは、実は広くて深いのです。名だたる企業を率いて国内外のビジネスの第一線で活躍してきた新 将命(あたらし まさみ)氏は「ビジネスで成功するのにも『原理原則』がある。にもかかわらず、多くの人がそれを知らず、我流で動いて遠回り・空回りしている」と言います。ここでは、そんな“自己評価が高い人”ほど陥りがちな「心の罠」から免れるための原理原則を紹介します。
2021年に民法と不動産登記法が改正、「相続登記の義務化」知っておきたいポイントは?
「なぜ義務化?」「いつから?」「罰則は?」がわかる
2021年4月、民法と不動産登記法が改正されました。今回の改正の目玉といわれるのが「相続登記の義務化」です。法改正にいたった背景とポイントをまとめました。
「文章を書く」ことの苦手を好きにかえる方法、もう1度確認したい文章の基本「5W3H」
一生モノのスキル
伝える力【話す・書く】研究所を主宰し、「文章の書き方」に関する著書も多い山口拓朗さんに書き方のコツを教わります。今回は、文章を書くのに欠かせない「5W3H」についてです。
多くの人が誤解している「論理的」の本当の意味
論理的思考を身につければ、「伝わる」に変わる
日常よく使われる「論理的」という言葉。そもそも、どんな意味なのか——。論理パズルや論理思考力に関する著作を多くもつ論理のエキスパート・小野田博一氏によれば、「実は、多くの人がその意味を正しく理解しないまま、なんとなく使っている」といいます。「自分の考えをうまく説明できない」「相手に伝わらない」とお悩みなら、まず「論理」とはなにかを考えることから始めてみましょう
多様化時代は“カメレオン”タイプが営業を制す?営業力が上がる処方箋
成果を出す人はどこが違うのか
働き方が多様化しているように、「営業スタイル」も人それぞれ。営業を生業とする人が皆、それを得意としているわけではなく、多くは「短所」も「苦手」も抱えているもの。ならば、成果を出す人はどこが違うのでしょうか。リクルート黄金期を支えた営業経験をもとに人気オンライン講座「営業サプリ」の総合監修を務める大塚寿氏が、あなたの営業力がいますぐアップする処方箋を提示します。
40歳以上の“おとな女子”が幸せであるための5つの心得
人生100年時代を、元気に楽しく過ごすために大切なこと
将来の自分がどうなっているのか、考えてみたことはありますか? 40代、50代、60代、70代……酸いも甘いも噛み分けた“おとな女子(R40≒40代以上)”であっても、具体的に思い描くのは、なかなか難しいもの。とはいえ、未来は1日1日の積み重ね。毎日をどう過ごすかで、人生は大きく変わります。未来のあなたがハッピーでいるために欠かせない「5つの心得」をお教えしましょう。
テレワークで「やるべき業務」がわからない部下に上司がすべきフォロー
監視ではなく、個人を尊重した進捗確認を
緊急事態宣言が延長され、政府はますます企業へテレワークを推奨しています。新型コロナ感染拡大に伴い、徐々に導入されていったテレワークですが、慣れとともに「なんとなく目の前の業務をこなす」ことがルーティン化してきた人もいるのではないでしょうか?職場のメンバー一人ひとりが「やるべき業務」を意識するにはどうすればいいのか、上司はどのように部下へ仕事を割り振っていくべきなのか――今回は『リーダーシップがなくてもできる「職場の問題」30の解決法』の著者であり、コンサルタントとして1200名以上に職場の問題をヒアリングしてきた大橋高広氏にテレワークの業務改善法を聞いてみました。
「仕事のやる気」はどこから生まれるのか
やる気を左右する三つの欲求の正体
「給料が安いからやる気が出ない」とよく言われるが、果たして「やる気を生む源」となるのはそれだけなのでしょうか。その疑問に対する答えの一つを、経営コンサルタントである池本克之氏の著書『出社しなくても最高に評価される人がやっていること』からみてみてみましょう。
「有望な若手が辞めていく会社」は、まず就業規則を見直すべき
「管理・強制」から「パートナー関係の構築」へ
働く人の意識が多様化する現在、「会社のルール=就業規則」にも変化が求められています。従業員の管理を目的とした“上から目線のルール”では人材が定着しないからです。これからの時代の就業規則にはどんな視点が必要なのでしょうか。社労士として1000社を超える企業の経営問題を解決してきた、下田直人さんに聞きました。
暴落で心が折れそうな株初心者がラクになる話
日経平均と一緒にメンタル下降中の人は必読
「3万円台回復」に沸いた春先の雰囲気もどこへやら、ゴールデンウィーク開けの日経平均は2日で1000円以上も下落、昨日の落下でも心が折れそうになっている人もいるかもしれません。とりわけ、この落下に一番こたえているのが、年初の好調をみて新たに株取引を始めた人ではないでしょうか。今回はそうした人にこそ読んで欲しい「プロディーラーが大損したときのメンタルマネジメント」の実例を紹介します。※本記事は『「株式ディーラー」プロの実践教本』より一部を抜粋・編集したものです
“ポイ活”しながら効率的に資産を増やすには?
損はしたくない…と思っている人の最初の一歩
国を挙げて取り組んでいるキャッシュレス化。商品やサービスの利用時に発行されるポイントの付与率や還元率だけでなく、そのポイントの使い勝手が気になる人も多いでしょう。昨今は、ポイントを元手(原資)に株や投資信託など金融商品を購入できるサービスも増えています。「投資ってどうやるの?」「興味はあるけど損したくない」……そんな方のために、ファイナンシャルプランナーの野原亮氏が、誰でも手軽にできる「0円投資」の方法を紹介します。※本稿は『貯金がなくても資産を増やせる「0円投資」』(野原 亮・著)をもとに再編集しています。
え、これって労働時間?あいまいなオン・オフの境界線
実務上、労使トラブルになりがちな3つのケース
新型コロナ感染症を機に、時差出勤やテレワーク導入など勤務形態を見直す企業が増えています。働き方が多様化し、働く人の意識も変わりつつあるなか、これまであいまいにされてきた「労働(オン)と休憩(オフ)の境界線」についても目が向けられるようになってきました。実務上「これって労働時間?」と判断に迷ったり、労使トラブルになりがちな3つのケースについて解説しましょう。
就活に成功するために不可欠な戦略と努力とは?内定を勝ち取る「近未来分析」
『「正しい努力」で結果を出す 図解 戦略就活メソッド』から
就活に成功するために不可欠な「正しい戦略」と「正しい努力」を解説した『図解 戦略就活メソッド』の著者、林晃佑さんは、京都大学在学中に「京大生向け就職支援サービス」で起業して以来、リクルートのグループ会社の代表などを歴任しながら、これまでに1万人以上の就活生を支援してきました。林さんはその経験から、「これからの時代の就活に成功するためには『近未来分析』が欠かせない」と指摘しています。『図解 戦略就活メソッド』の一部を要約しながら、具体的に解説していきましょう。
私たちの選択が「自分の意思によるもの」と言い切れない科学的理由
遺伝子はどこまで「行動」に干渉するのか?
私たちが自分の意思で「選択している」と思い込んでいるものは、実は「遺伝子」によって先天的に決められているのかもしれない。人間は遺伝子によるコントロールから逃れられないのだろうか――。『「運命」と「選択」の科学』では、注目の若手脳神経科学者・ハナー・クリッチロウが、そうした疑問の解明に挑みました。同書のポイントを紹介します。文:日本実業出版社WEB編集部
小さな会社が生き残るための条件は?満たすべき4つの条件
「変わり者」は放っておいてもらえる
ドラッカーの「生態的ニッチ戦略」とは、ひと言でいうと「競争のない市場で事業を展開すること」です。そんな市場はなかなか見つからないと思ってしまいますが、「藤屋式ニッチ戦略塾」の主宰者として中小企業経営を支援する藤屋伸二氏は、「非競争市場には4つの条件があり、うち2つの条件を満たすことができれば創り出せる」といいます。それらはどんな条件なのか、事例をもとに見ていきましょう。