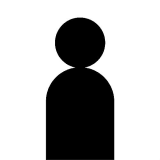生活
食事や買い物、通信、交通など、日々の生活全般のお金の話を紹介します。
妻「夫の死後、自宅が売れない?」住宅購入時に考えておきたい相続の盲点とは
三井住友信託銀行が住宅ローンと相続の一体サービスを提供開始
コロナ禍で働き方やライフスタイルが変化し、マンションや戸建ての購入を検討している人も多いのではないでしょうか。注文住宅の情報を発信するメディア「おうちパレット」が2021年4月に男女3,000人を対象に行った調査では、将来は「持ち家」に住みたいと答えた人は80.9%という結果でした。住宅購入の際には多くの人が住宅ローンを利用します。その住宅ローンに今年6月、新しいサービスが誕生しました。三井住友信託銀行の「ハウジングウィル」です。注目すべきは、“住宅ローンから相続までをワンストップで提供する金融業界初のサービス”という点です。なぜ、住宅ローンに相続なのでしょうか。三井住友信託銀行審議役の江面文朗さんに話を聞くと、住宅購入で起こる相続の注意点が見えてきました。
夏に食べたい!簡単「さっぱりチヂミ」のレシピ
ミョウガや大葉をたっぷり
暑くなるこの時期。簡単に作れてさっぱり食べられる一品を紹介します。スーパーでよく見かけるミョウガや大葉をたっぷり使った爽やかなチヂミ。下味をつけているのでそのまま食べても美味しいです。
本格「手作り中華ちまき」の作り方
竹皮で包んで蒸した出来立てちまき
竹皮で包んで蒸した出来立てちまきの味は、子供達に食べさせてあげたい素朴で、優しくて、昔ながらの美味しさです。準備しやすいように豚肉はブロックではなく薄切り肉、銀杏の代わりに蒸し大豆で代用しました。ぜひ挑戦してみてください。
経費と生活費がごちゃまぜの自営業夫婦の家計。管理のコツと万が一への備えは?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、夫婦ともに自営業の41歳の女性。月により収入に波があるためやりくりが難しく、赤字が出ることも。家計改善のポイントは? FPの横山光昭氏がお答えします。 夫婦それぞれで自営業をしています。夫の方は自営業の収入がそう多くないため、アルバイトをして収入を維持することを助けてくれており、毎月の手取り収入は夫婦で45万円ほどが平均です。ただ、月により波があるため、安定せず困っています。家計は時々赤字になってしまい、貯金から補てんをする月もあります。子どもはまだ小学生ですし、私たちの老後のこともありますから、お金を貯められるやりくりを身に着けたいです。銀行でつみたてNISAはしています。また、それとは別に転居を考えています。今より5,000円高い家賃の物件に住みたいと思っているのですが、家賃は半分を経費にしているので、家計にはあまり影響がないと思っているのですが、大丈夫でしょうか。アドバイスをお願いできたらと思います。【相談者プロフィール】・相談者:女性、
手取り20万円の暮らし「〇〇するのがキツイ」ランキング1位は?理想の手取りは?
アンケートで暮らしぶりが浮き彫りに
手取り20万円と聞いて、どのような生活を思い浮かべますか。ひとり暮らしか、実家暮らしか。未婚か既婚か。子供の有無によっても、暮らし向きはだいぶ異なります。株式会社ビズヒッツが、手取り20万円の男女500名を対象に「手取り20万円できついと思うことに関する意識調査」を実施。調査結果をひも解くと、手取り20万円で生活している人たちの暮らしぶりが浮き彫りとなりました。
「外出と外食が減っているのに貯金ゼロ」30代4人家族の破綻寸前の家計は再生なるか?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、2人の子どもと公務員の夫をもつ33歳パートの女性。コロナ禍で外食や外出が減っているのに、貯金がまったくできないという相談者。家計の内訳を見てFPが指摘する問題点とは? FPの秋山芳生氏がお答えします。 コロナで外出、外食が減っているのに一向に貯金が出来ません。支出は少ないと思っているのに、給料が残らないのはなぜでしょうか。上手な貯金の方法が分からず、家計の計算も苦手です。コツを教えてください。【相談者プロフィール】・女性、33歳、パート、既婚・同居家族について:夫/33歳、公務員月収25万円、妻/パート平均月収7万円 子ども2人(4歳、6歳)・住居の形態:賃貸(愛知県)・毎月の世帯の手取り金額:32万円・年間の世帯の手取りボーナス額:130万円・毎月の世帯の支出の目安:25万円【毎月の支出の内訳】・住居費:7万円・食費:5万円・水道光熱費:2万3,000円・教育費:3万円・保険料:4万5,000円・通信費:2万円・お小遣い:2万円・その他:10
自然災害が増え2022年に火災保険がまた値上がり?保険料は最大36.6%上がるところも
過去最大の上げ幅に
突然の激しい雨や、雷雨が発生する「ゲリラ豪雨」のシーズンは、7月から9月です。ウェザーニュースによると2021年の発生回数は昨年の1.2倍になる見込みだそうです。火災保険での水災の備えは大丈夫でしょうか?じつは、2022年に、またまた火災保険の値上げが実施されます。昨年(2020年)には、2021年に火災保険は値上がりをするという記事を書きました。このときの値上がりは、2017年〜2018年に起こった大規模な自然災害をもとに損害保険料率算出機構が出した「参考純率」によって保険料が見直されました。2022年の保険料の値上げは、2019年〜2020年に起こった自然災害をもとに同じく損害保険料算出機構による改定です。各損害保険会社は、この「参考純率」の改定を踏まえて2022年には保険料が値上がりする見通しです。では、どのくらい値上がりをするのかというと、全国平均で10.9%です。この平均で約1割以上というのは、過去最大の上げ幅になります。それ以外にも長期契約がさらに短縮されることになります。これも実質の値上げになります。火災保険を検討中の方は、年内に契約または契約更新をすると得になりますね。
今さら聞けない所得税と住民税って何?どう計算すればよいか解説
なんとなく引かれる税金を理解しよう
私たちの身の回りには、買い物やサービスを受けるときに支払う消費税をはじめ、いろいろな税金があります。身近な税金である所得税や住民税は、毎月お給料の中から何となく大きな額の税金が引かれるけれど、実際よくわからないという人が多いかもしれません。今回は、所得税と住民税の計算の仕方について、わかりやすく解説していきます。
暑い日に食べたい!「ささみの揚げないチキン南蛮」
タルタルソースでご飯がススム
毎日暑い日が続き、食欲も落ちがちになるこの時期。さっぱりしたもので、しっかりしたおかずをご紹介します。ミョウガを入れた爽やかなタルタルソースに甘酸っぱいささみでご飯がすすみます。ささみを揚げ焼きすることで、暑い時期でも簡単に作れます。
猫の治療費は1日4万円?かかりやすい病気は?飼う前に知っておきたい猫にかかるお金のこと
病院選びのポイントも解説
コロナ禍でおうち時間が長くなり、ペットを飼う人が増えたと言われています。その中でも人気が高まっているのが猫です。現在、国内で買われているペットのなかで飼育頭数のトップに君臨しています。そんなペット猫の現状について、「猫を飼った後に『思っていたよりも大変だった』と感じる方が少なくありません」と話すのは、猫を泌尿器疾患から守るIoTトイレ「Toletta (トレッタ) 」を提供するトレッタキャッツの代表・堀宏治さんです。今回は堀さんに、猫を飼う上で想定しておきたいお世話代や猫がかかりやすい病気、そして病気になったときの治療費などについて詳しく聞きました。
作り置き常備菜「ししとうの牛脂炒め」とアレンジレシピ
今が旬の野菜を食べよう
お弁当にあると嬉しい緑のおかず、ししとう。そんなししとうも今が旬です。ししとうだけをたっぷり使って、作り置きおかず始めませんか?スーパーに置いてある牛脂と一緒に炒めてあげるだけで、まるで焼肉のような旨みたっぷりな炒め物に。シンプルなのに、ご飯も進むがっつりおかずに変身です。
お出かけ不要!自宅に優待品が届く9月の株主優待銘柄5選
商品やカタログが届くので便利
届くのが待ち遠しくなる株主優待ですが、内容によっては外出を控えていてなかなか優待を使えずにいるという方もいらっしゃるかもしれません。そこで、今回は9月権利確定の優待銘柄の中から、自宅に商品やカタログ等の優待が届く銘柄を5つご紹介します。コロナ禍ではこのような優待が嬉しいですよね。ぜひ参考にしてみてください。
30代世帯年収1000万、退職金なしの夫婦。住宅ローン・教育費・老後資金の貯蓄プランは?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。 今回の相談者は、36歳、会社員の男性。退職金がないため、老後資金が心配な相談者。住宅ローンの完済予定は71歳、これから子どもも欲しいといいますが、どんなマネープランを立てればいいでしょうか? FPの高山一惠氏がお答えします。 今の会社は退職金制度がないため、老後の資金が心配です。また、36歳にして住宅を購入し、住宅ローンを35年(変動)で組みました。完済予定が71歳になるため、65歳定年時までに完済したいと思っています。今は共働きで世帯年収は1,000万円程度のため、貯蓄もできていますが、今後子どもも最低1人は欲しいと思っていますので、老後資金がどのくらい必要で、どのくらい貯められるのか心配です。【相談者プロフィール】・男性、36歳、会社員、既婚・同居家族について: 夫(相談者)/会社員(SE)、年収570万円 妻/31歳、会社員(SE)、年収420万円・住居の形態:持ち家(戸建て・千葉県)・毎月の世帯の手取り金額:49万円・年間の世帯の手取りボーナス額:
素材の持ち味が活きる「鶏肉と夏野菜の炊き合わせ」レシピ
煮物じゃないよ、炊き合わせ
全部一緒に煮てしまう煮物も良いけれど、たまには別々で煮てみませんか?それぞれの持ち味を生かしたお出汁を吸ってより食材の味が活きてきます。たくさん作ってお弁当のおかずにするのもいいですね。
ピーマンと調味料だけで完成!食べる手が止まらない「ピーマンのはちみつ醤油炒め」
食べる手が止まらなくなるレシピ
スーパーで手軽に買うことができ、栄養豊富なピーマン。今回はピーマンと調味料だけで作る「ピーマンのはちみつ醤油炒め」をご紹介します。材料はシンプル、作り方もとても簡単ですが、1人でピーマン2個分をペロっと食べてしまう、食べる手が止まらなくなるレシピです。ぜひ作ってみて下さい。
食費、日用品、趣味娯楽費…使いすぎを家計簿の機能を使って改善
Web版「マネーフォワード ME」を賢く使ってみよう
家計簿を使い始めたら、支出が多い…と気がつく人も多いでしょう。自分の支出がわかったら、次は何をすればいいでしょうか。今回は、パソコンで「マネーフォワード ME」のweb版をより使いこなして、支出を改善する方法を解説していきます。
月10万の保険料と13万の食費で大幅赤字の家計。FPが指摘する見直しのポイントは?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、50歳、会社員の女性。高額の保険料と食費が家計を圧迫し、毎月赤字。老後資金はおろか、娘と息子の教育費の準備もおぼつかないと言います。保険料と食費の見直しのポイントは? FPの横山光昭氏がお答えします。毎月大幅な赤字です。家計簿をつけているのですが、必要だと納得して入った生命保険の掛け金が多すぎて、負担になっていると思っています。長女があと1年ちょっとで大学受験となるので、教育費も確保しなくてはいけませんし、その後に長男も続きます。私たち夫婦も50代で、老後資金も気にかけなくてはいけないと思っているのですが、今のままでは貯めることもできません。保険については、夫は給与天引きで会社のグループ保険に入っていますので、減らせるものもあるのではないかと思っています。ただ、中には将来に備えお金が貯まる保険もあるので、解約してしまってはもったいないような気もしています。悪いのは保険料の支払いだけではないかもしれません。家計全体を見ていただき、どの支出をカット
自己破産した義父に代わりローン返済中。2世帯同居で3人の教育費をどう準備する?
FPの家計相談シリーズ
読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、36歳、公務員の女性。自己破産した義父のローンを返済しながら義両親と同居中の相談者夫婦。3人の子どもの教育費が足りるか不安だと言います。FPの氏家祥美氏がお答えします。子ども3人の教育費を貯めているが足りるかどうか不安です。5年前に義父が自己破産し、夫が不動産担保ローンを組む形で家のローンやその他を引き継ぎ、義両親と同居になりました。築30年の二世帯住宅の水道光熱費は異様に高く、これでも見直して安くなった方です。電気代だけは義両親と別にしてあります。同居にあたって、ボロボロだった箇所をリフォームした結果、貯蓄はほぼなくなりました。その後、子どもがさらに2人生まれ、収入が激減した時期もありましたが、やっとぼちぼち貯められるようになってきました。今は児童手当を預金、月収から3万円をつみたてNISAに回しています。ボーナスは特別支出を引いた20万円を預金に回しています。それと妻のiDeCoを月5,000円かけています。上2人だけ学資保険をかけています